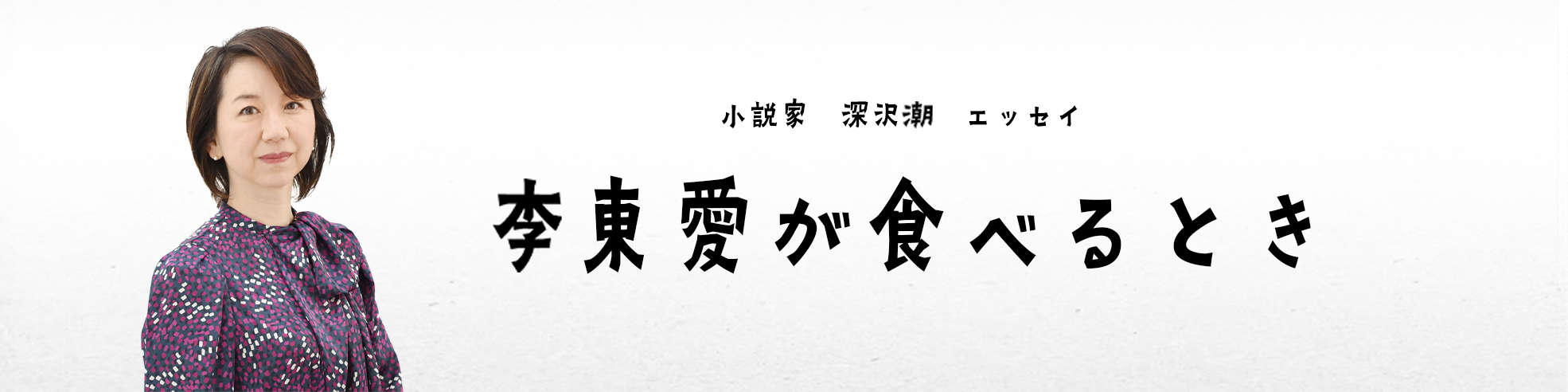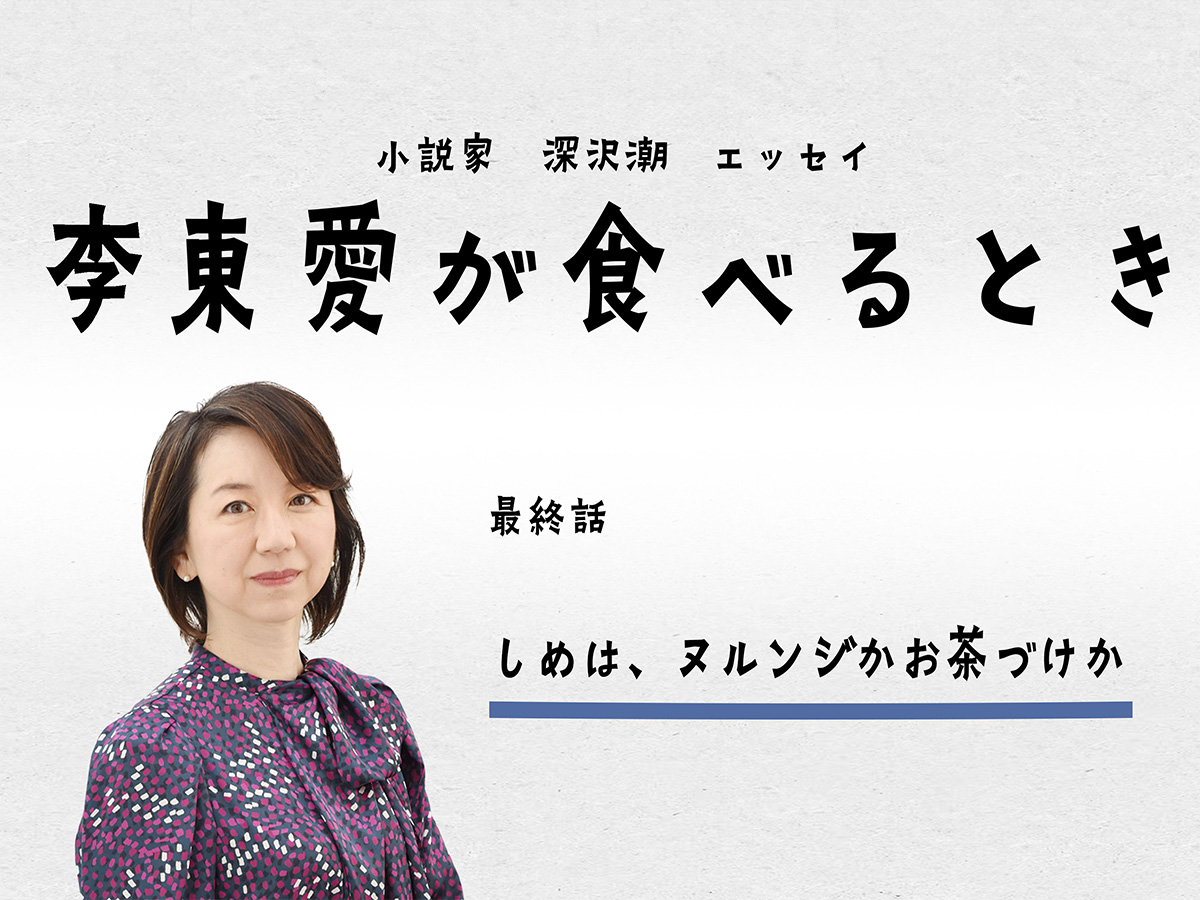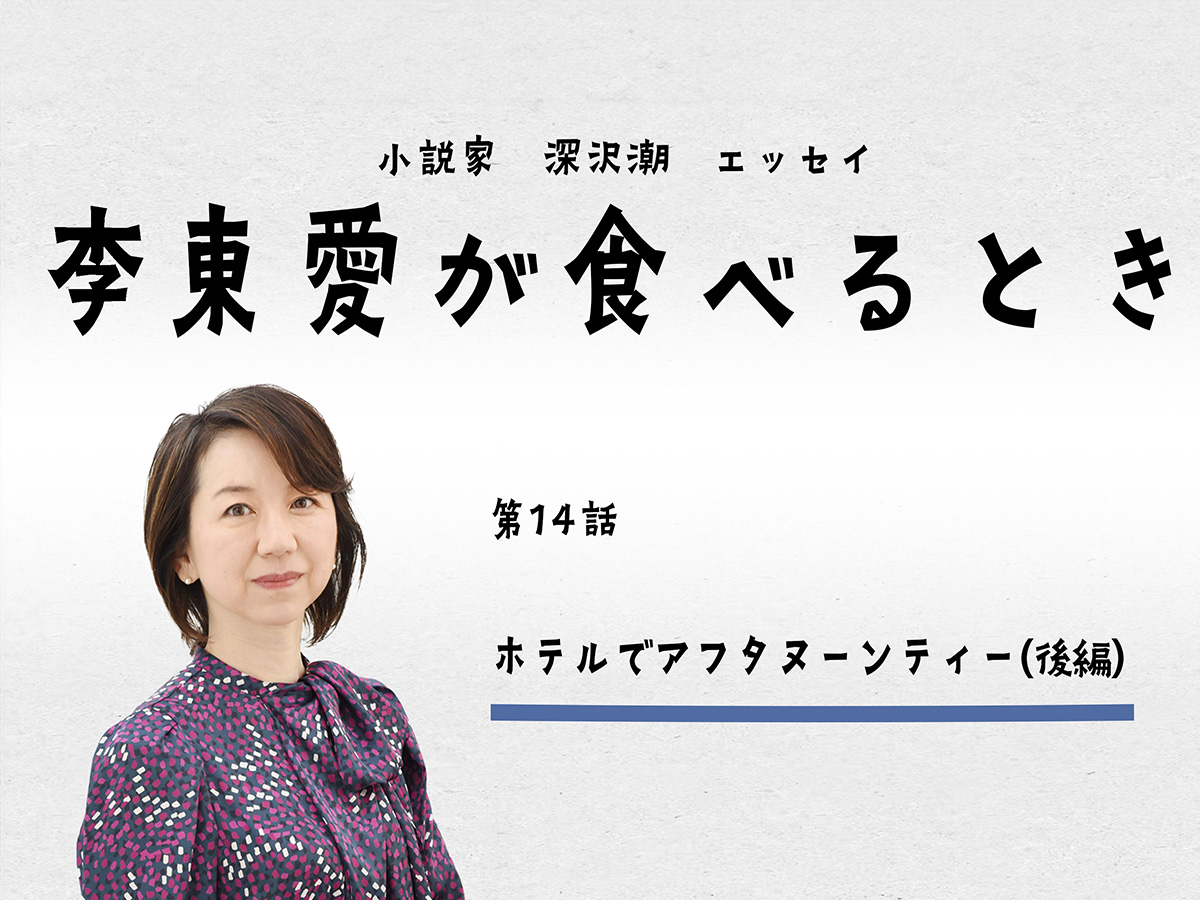第3話 寿司におもう。
好きな料理のランキングに必ず入る寿司だが、私にとっては、長らく避けていた料理のひとつだった。鮮魚が苦手というわけではない。むしろ、刺身は好物だったりする。つまり、寿司そのものの味が嫌いというわけではない。
だとしても、海外で、国内で、「日本に暮らしているんだから(あるいは日本人なんだから)寿司は好きなはず」という言葉を投げられると、ちょっとむっとしてしまう。朝鮮人だからキムチが好きだろうと同様、ステレオタイプの押しつけにうんざりする。寿司への想いはさまざまであっていいはずだ。
ごく幼いころは寿司など、日常的に食べていなかった。いまのように安い寿司チェーン店もなかったし、外食はめったにしなかった。「お寿司をとろう」となるのは、祝い事があるか、大事なお客さんが来たときかに限られた。つまり、寿司はもっぱら特別なときに出前でとるものであった。
7月の初旬のその日は、良く晴れ、暑かった。小学校では水泳の授業があり、いつも見学だった姉が5年生にして初めて学校でプールに入ることができて、姉本人も母もとても喜んでいた。「みんなと一緒にプールに入る」ことを姉は切望していたのだ。
いま考えるとあの日はもしかしたら土曜日だったのかもしれない。我が家には、歳の近い母方のいとこ三人が遊びに来ており、大好きな叔父(サンちゃんアジェ)も来ていた。当時3年生の私は無邪気にはしゃいでいた。しかも、めったに食べない寿司の出前まで取ったわけで、子ども心に、こういうのを幸せというのだろうかと漠然とながらも感じ取っていたような気がする。
普段は食の細い姉もさびぬきの寿司をほぼ一人前平らげ、これには母がことのほか驚いていた。その日にプールに入ったのは、だいぶ病状が良かったからだった。プールに入れたし、元気なのだから、「もしかしたらこのまま快方に向かうのでは」という希望を母は持ったに違いない。
私の姉は、生まれつき心臓の病を患っていた。正式な病名はファロー四徴症という。左右の心室を分ける心室中隔という仕切りの壁に大きな穴がある、全身へ血液を送る大動脈が左右の心室にまたがってしまっている、肺へ血液を送る肺動脈の右室の出口が肺動脈弁と一緒に狭くなる、左右の心室の圧が等しくなり右室が肥大する、という四つの特徴を持つ先天性の難病だ。
症状としては、静脈の血液が大動脈に流れ込んでしまうため、血液中の酸素が不足してチアノーゼ状態となり、息切れや呼吸困難、けいれんなどの発作がたびたび起きる。
心臓外科の領域においては当時最先端をいく東京女子医大病院で姉は治療をうけてきた。この病気には姑息手術と根治手術という大手術が必要で、姉はその二つをすでに受けていた。
手術だけでなく、発作のたびに姉は入院をくりかえしており、我が家は、姉を中心に生活が営まれていた。私と姉は三歳違いで、私は生後すぐに乳児院に入れられた。姉の入院に母が付き添うため、私の面倒が見られなかったからだ。父は民族団体の仲間とともに韓国の民主化運動と金大中氏の支援、そして後ほどは実業で忙しく(父のことは文春文庫の「海を抱いて月に眠る」という小説に描いている)、私は母の実家や、同級生の家、父の知人の家など、さまざまなところに預けられた。大人ばかりのなかでランドセルをしょってひとりで電車に乗るのが嫌でたまらなかったこと、同級生や父の知人の家ではどう振舞っていいかわからず戸惑ったこと、母の実家で精神疾患のある叔父(てろうアジェ)から怒鳴られるのがものすごく怖かったことなどが鮮明に記憶に残っている。
姉は一年遅れて小学校に入学したが、通院や入院、病状悪化のために学校を休みがちで、しかもふだんから体力がなく、学習についていくのが難しかった。さらに体育の授業は常に見学だった。そんな、ほかの子どもたちとは明らかに違う姉は、かっこうのいじめの対象となった。チアノーゼになると発作が起きて命の危険があるから走ってはいけないのにわざと走らされる、給食の牛乳のストローの紙を食べさせられる、開胸手術による胸の傷跡を見られて「フランケンシュタイン」と呼ばれ「気持ち悪い」とからかわれるなど、いま思い出しても胸がしめつけられるようなことがしょっちゅうあった。そんな仕打ちが発覚すると母が激怒して担任の先生に抗議したが、あまりとりあってもらえず、いじめた当人の家に乗りこんで行ったこともあった。そのときに、通名を使い周囲に隠しているのにもかかわらず、「朝鮮人のくせに」と言われて言い返せずに家に戻り、母が悔し泣きをしていたこともはっきりと覚えている。それらの出来事に父の介入がなかったのはなぜなのか、詳しいことは不明だが、姉を守って闘っていたのはいつも母だった。
2学年下だった私も、姉がいじめられている場面に遭遇したことがある。休み時間の校庭で、ある女の子が姉の筆箱を持って走り、姉に追いかけさせていたところを目撃したのだ。私は1年生だったが、姉を助けずに咄嗟にその場から逃げてしまった。
実は、私は、つねづね家庭が姉中心で自分がないがしろにされているように感じていた。「お姉ちゃんばっかり」とひがみ根性のかたまりだった。そして、「走ってはいけない」ことは知っていたが、命の危険があるとまでは理解していなかったから、ちょっとだけ、「いい気味だ」とまで思っていたのだ。
姉は私にとても優しくて、姉自身を嫌いということはまったくなく、自分が姉にひどい態度をとることはしなかった。けれどもいつも大事にされている姉が羨ましくてたまらなかった。姉が入院した際、東京女子医大に見舞いに行くと、すぐそばにあったフジテレビの子ども向け番組「ピンポンパン」のスタッフがボランティアで小児病棟に来ているのを見て嫉妬した。また、高価な果物や花、おもちゃやぬいぐるみ、ぴかぴかの文房具、面白そうな本などを見舞い品としてもらっているのを見て、代わりたい、と思ったりもした。
私は、けがをしていないのに包帯を巻いたり、すこぶる健康なのに水銀の体温計を細工して熱のあるふりをしたり、足をひきずったり、ふだんからそういった詐病をしては母にアピールした。そのたびにひどく叱られたが、私は必死だった。憎たらしい、というか、扱いにくい子どもだったのは明らかだ。
さらに私は韓国人っぽい「東愛」なのに、姉はいじめられないようにと日本人っぽい「麻由美」と名付けられていたことも、根に持っていた。○○子ばかりのなかで名前が目立つのは嫌なのに、なにかにつけて注目を浴びたり、自分が優先されないと機嫌が悪くなるようなところもあった。
姉は走らされたその日、チアノーゼから発作を起こして入院したため、私は母の実家に行かされた。また預けられるのかと、がっかりし、「あのとき止めていればよかった」と心から後悔した。
翌年、退院して間もなかった頃(おそらく手術だった)、姉はしばらく車いすで通学し、私はつきそっていた。ある日下校時、車いすが珍しいのか、何人かの姉のクラスメートが姉のまわりにいた。そのなかには、姉を走らせた女の子もまじっていた。車いすを押していたのは姉と親しくしてくれていた数少ないクラスメートのひとりだった。姉に好意的で、面倒をみてくれる上級生がいることに気を大きくした私は、姉を走らせた子に向かって、唐突に怒鳴った。
「お姉ちゃんをいじめないでっ!!」
私は、前述のとおり、決して「いい子」ではなかった。むしろ、性格がひねくれていて、意地悪で、気が強く、クラスでも嫌われていた。好きな子同士でなにかをやらされるときは、いつも余っていた。このときも、正義感からの言葉ではなかったと思う。
さて、寿司の出前を取ったあの日。姉は叔父(サンちゃんアジェ)とレコード店に行って、EPレコードを買ってきた。姉が家に帰ってきたとき、私はいとこと遊ぶのに夢中だった。なんの遊びだったか覚えていないのだが、走り回る遊びだったと思う。そういう遊びはふだん(走れない姉とは)できないので、楽しくて、興奮していた。だから、姉が「東愛の好きな秀樹のレコードも買ってきたよ」とレコードを渡してきたことで遊びが中断したことに、いらっとしてしまった。それだけでなく、私にはレコードを買うようなことを許さない母が、姉が買ってもらって帰っても、何も言わなかったことを「ずるい」と思っていた。
私は受け取ったレコードをその辺に置いて、母の目を盗んで足で蹴った。姉が悲しそうにそのレコードを拾ったとき、さすがの私も胸がチクリと痛んだ。だが、すぐに遊びに戻り、ふたたび思い切り動きまわった。
寿司を食べるまで、姉がどうしていたか覚えていない。食卓の様子も記憶にない。
だが、姉が食後に勢いよく寿司桶に嘔吐した光景は、スローモーションで頭に焼き付いている。それから姉は呼吸困難に陥り、意識不明となった。救急車が来て、担架に乗せられ運ばれていった。私はまるでドラマを観ているように、目の前で起きていることを現実感なく眺めていた。
姉は集中治療室に入り、母は病院に泊まりこんだ。私はいとこの家に行った。いとこの家に預けられるのは初めてで、毎日遊びまわった。制限ばかりの我が家やそれまで預けられた先と違い、いとこの家では遠慮もいらないし、あまり叱られないし、自由だった。ずっといとこの家にいたいとすら思った。姉がこのまま長く入院していてくれたら、とまで願った。
姉が入院したまま一学期の終業式を迎えた。私は母に言われて姉の代わりに5年生の教室に行って姉の席に座り、成績表をもらった。姉の担任の先生は「東愛ちゃんはえらい」と言っていたが、上級生のみんなに注目されて怖かった。私が怒鳴りつけた女の子が睨んでいるような気がして、顔をあげられなかった。
終業式の次の日、夏休みの初日、姉が救急車で運ばれて13日後、いとこの家で、なにかのごっこ遊びをしていたとき、電話がかかってきた。いつもは母がかけてきて伯母とだけ話すのに、珍しく「東愛ちゃん、電話に出なさい」と受話器を渡された。私は、そのときもまた、遊びを邪魔されて、面倒くさいな、と思ってしまった。
しぶしぶ受話器を耳に当てると、電話の向こうの声は、父だった。
「お姉ちゃんが死んだよ」
姉は意識不明のまま息をひきとったという。
私は、意味がわからなかった。姉が死ぬなんて、想像したこともなかった。両親も、姉が死ぬような病気だと話してくれなかった。いつものように、退院して戻ってくると信じて疑わなかった。
それから、通夜までの記憶が飛んでいる。電話のあとは、教会の聖堂でお棺のなかの姉に対面したことが思い出されるだけだ。姉の手を触ってみると恐ろしいほど冷たかった。目を閉じた顔は、姉とは違う人に見えた。人形みたいだ、とも思った。
私は、まったく泣かなかった。冷たい子だと周囲から思われたはずだ。いとこたちはおいおい声をあげて泣き、まわりの大人はすすり泣いている。父の慟哭する姿を初めて見た。母の涙は枯れることがなかった。
それなのに、私はなぜ泣けないのだろう。
まるで感情が氷ついてしまっていたかのようだった。
寿司は、姉が最後に食べたものだ。寿司を吐いている姿が、私が見た、動いている姉の最期の姿だ。
寿司は、姉のくれたレコードを蹴った自分の態度を思い出させる。ずっと入院していてほしいと願った自分が嫌でたまらない。
だから、私は、寿司を避けた。しかし、寿司と姉の死は、母にとっては結びついていないらしく、我が家ではその後も、なにかあると寿司の出前をとった。私が残すと、好き嫌いが多いと叱られた。なぜ食べないのか訊かれても、黙っていた。
なるべく寿司から距離をとるように努めて生きてきたが、息子が小学校1年生ぐらいの頃から、「回転ずし」に行きたいとねだるようになった。友だちから聞いて行ってみたくなったようだ。
私は、仕方なく、息子と娘を連れて回転ずしに行くようになった。得意げに「サーモンさびぬき!」「納豆巻き!」をひたすら繰り返す小学1年生の息子は、皿を重ねてご満悦だ。幼稚園児の娘は玉子や唐揚げを前ににこにこしている。
子どもたちの笑顔のおかげで、私の寿司の思い出が徐々に上書きされた。おかげでいまは、寿司に抵抗はないし、むしろ寿司は好きなくらいだ。
10年近く前、「緑と赤」(小学館文庫)の取材で韓国に行ったとき、「かっぱ寿司」を見つけて嬉しくなったことが懐かしい。長い韓国滞在で比較的からい食べ物が続いていたので、寿司を食べて、心が、胃が、ほっとしたのだ。
いまや、ソウルには手ごろな寿司店から高級店まで寿司屋はたくさんある。権力者が高級寿司を食べながら悪いたくらみをしていたり、買ってきた寿司を法律事務所で食べたりする弁護士の姿など、韓国ドラマや映画でも寿司はよく目にする。寿司は韓国でも大人気だ。釜山に住む父方の従妹も、コロナ禍前は、しょっちゅう福岡や大阪に来て寿司を楽しんでいた。
4月にソウルに行ったとき、働く若い女性のあいだでは寿司の「おまかせ」がはやっていると聞いた。日本に来て本場の「おまかせ」を食べたいという人達も多いという。せっせと働いたお金で、自分へのご褒美として食べるのだそうだ。自分へのご褒美は、ホテルのアフタヌーンティーや高級ブランド品購入といった消費行動にもなっているようだ。シャネルの店頭に長い行列があるのを目にした。学歴競争社会に勝ち抜くために血のにじむ努力をし続けた女性が疲れ果て、そういったことで自分を癒しているらしい。そしてブランド品の箱を開けてSNSで披露するUnboxingも日常的に目にする。だがそれが男性のミソジニー(女性嫌悪)に火が付く原因にもなっている。自分たちは軍隊に行って苦労した(している)のに、女ばかりがいい思いをして!という怒りが根底にあるらしい。
一方、いま韓国ではメルセデスベンツやBMWなどの高級外車や高価な大型SUV車を、ローンを組んで買う男性も(女性も)増えているという。たしかに、ソウルでは、外車やSUVがやけに多いと感じた。資本主義が極まり、人々が疲弊して、わかりやすく物質での満足に走っているのだろうか。日本でも同様の風景をバブルの頃に見たような気がするが、いまでも名残はある。格差は広がり、韓国も日本も、私たちはどこに向かっているのか、不安になる。
そんな懸念を持ちつつも、美味しいものをたまには、の誘惑には抗いがたい自分がいる。
このあいだ、ソウルに住む友人が東京に来て、寿司店で一緒に「おまかせ」コースを堪能した。私は、「おまかせ」をめったに食べない。ちょっと贅沢だったけれど、寿司は絶品の味だった。盛り付けも芸術的で、器も美しかった。友人とは、韓国のこと、日本のこと、さまざまな話をして、特別なひとときだった。
私の寿司の思い出が、素晴らしいものにさらに上書きされたと思う。
コロナ渦が落ち着いて、韓国から日本への観光客もかなり増えている。以前、韓国人のお客さんに対して故意にワサビを大量に入れて寿司を出したという事件があった。断じて許されないことだ。
寿司という料理の思い出が、レイシズムやヘイトの記憶につながるようなことが二度と起きないように、切に、切に、願う。
思い出の上書きには、長い時間がかかるのだから。

【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。