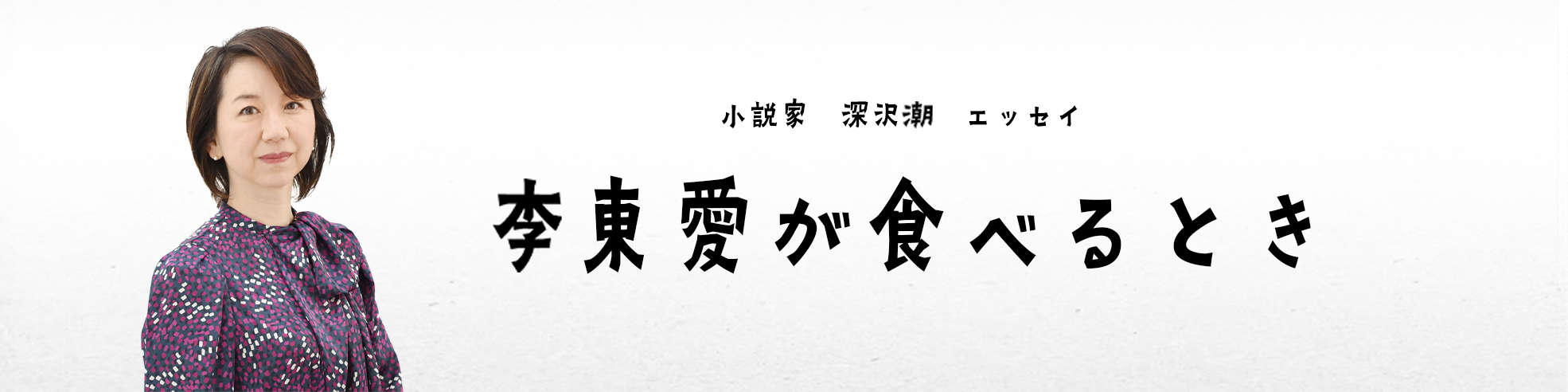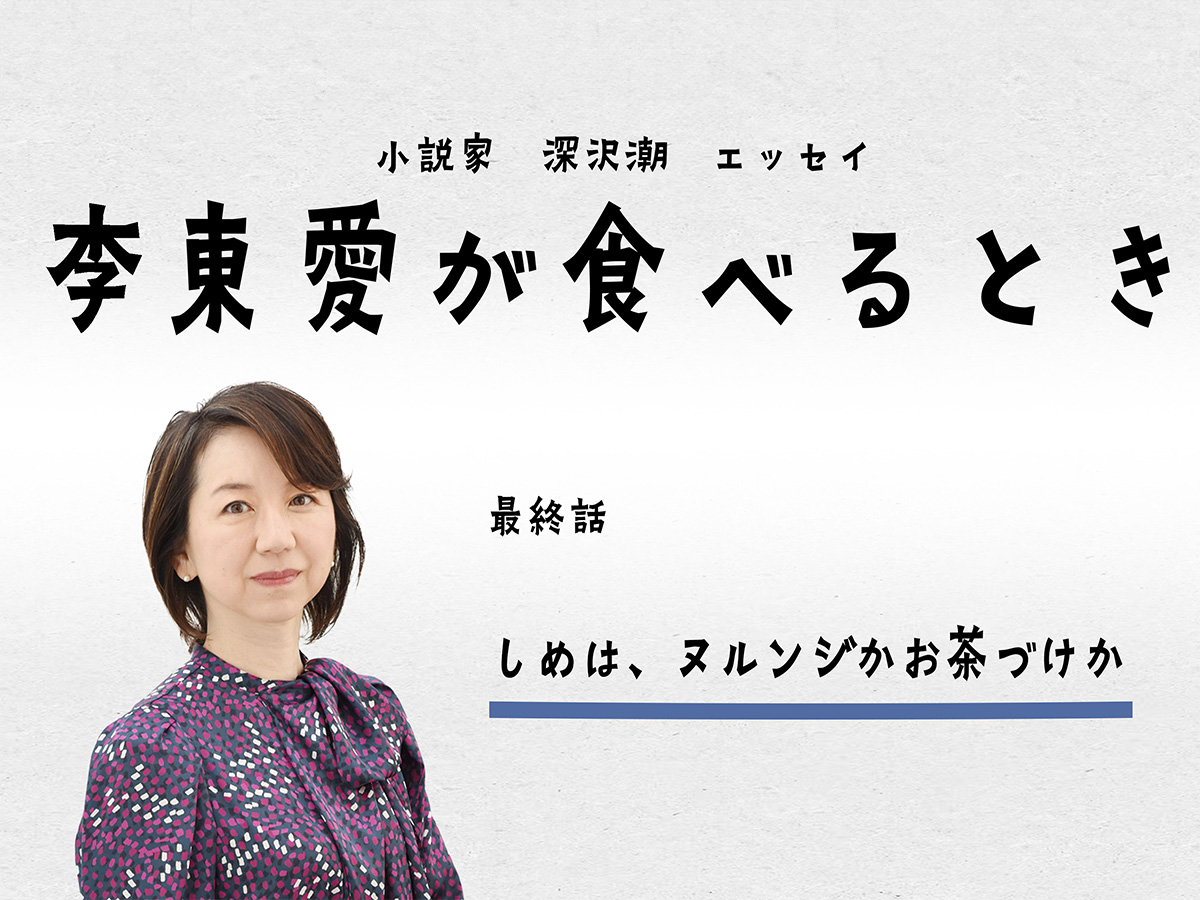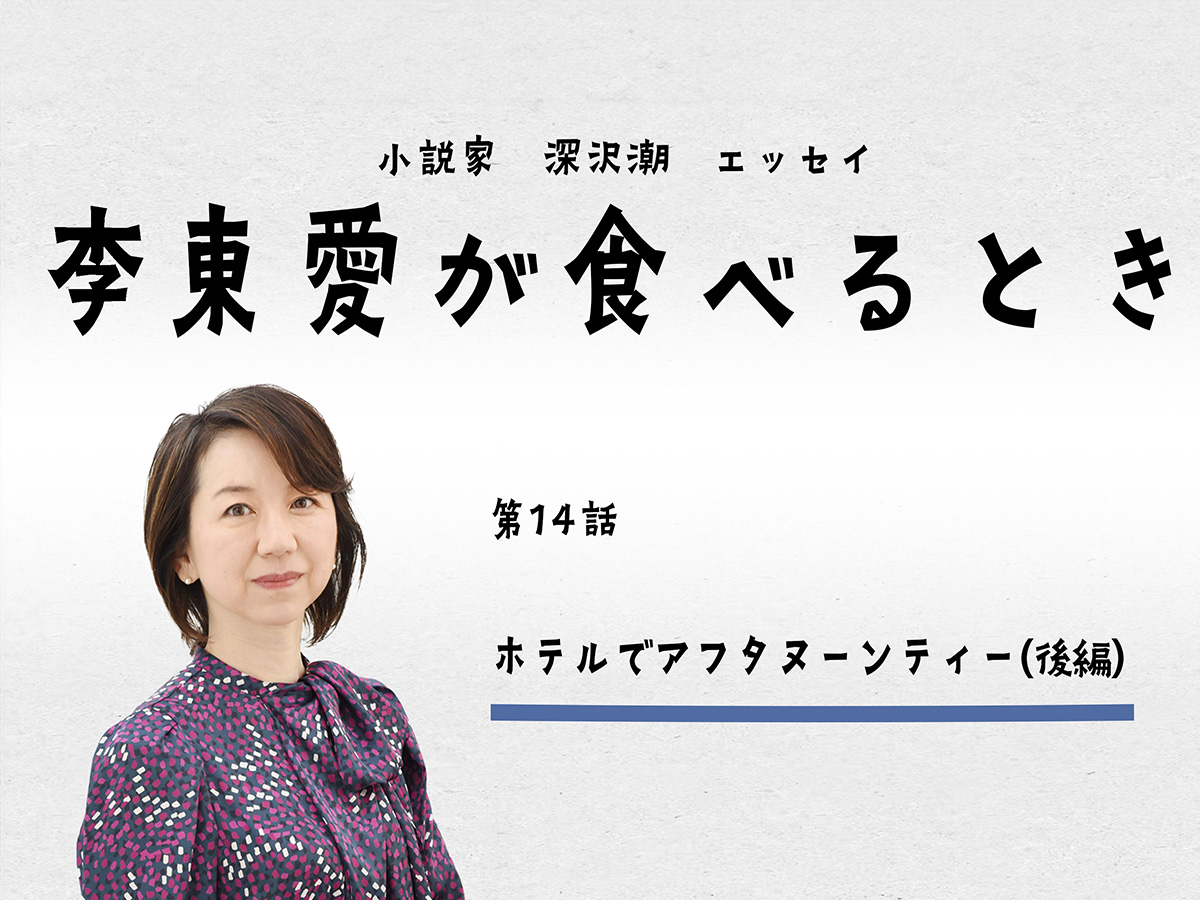第5話 酒とともにうたう
父が下戸なので、幼い頃にお酒を飲む大人を見たのは、たいがい母方の祖父の家だった。親族が集まるお正月や誰かの誕生会などに、上機嫌にまくしたてたり、喧嘩を始めたりするのを目にした。母方の親族は祖母をのぞき、母をふくめた6人きょうだい、その連れ合い、みなお酒が好きだった。
ときには、子どもたちを並べてひとりひとりうたわされたりもした。韓国ドラマなどでも、宴会で子どもに芸をさせるようなシーンがときどきあり、あのときのことがよみがえって嫌な気持ちになる。私は超音痴だったので、うたわされるのが大嫌いだった。しかも宴席では必ずいとこたちと競わされて、点数や順位をつけられた。そこで負けるのが悔しくてたまらなかった。
三歳下の従弟は、アニメや戦隊ヒーローの主題歌をうたい終わると必ず「トウガラシを見せろ!」と言われ、おどけた様子でズボンとパンツを下ろし、自分の“トウガラシ”を見せて、大人たちの喝采をさらっていた。優勝することも多かった。祖父にとっての孫たちは、女の子の比率が高くて、従弟が男の子であるというだけでちやほやされているのがあからさまだった。子どもごころに理不尽に思ったし、なんだかとても不愉快だった。一度母に「あんなものを人に見せるのはよくないのでは」というようなことを言ったら、「子どもだから」とか「かわいいじゃない」、「男の子はあれでいい」とか、「お酒の席だから」、といった答えが返ってきてよけいにモヤモヤしたのを覚えている。
子どもたちだけでなく、ビール一杯で真っ赤な顔になっている祖母も歌をうたうように強いられていた。祖母は、最初のうち頭を振ってかたくなに拒むのだが、周りの粘り強さに負けて、結局うたうことになる。そんなとき、祖母は小鳥のさえずるような小さな声で「はとぽっぽ」の歌をうたった。祖母のうたう「はとぽっぽ」は、言葉を覚えたての幼児がうたったようだった。あまりしゃべらないし、めったに笑わずかたい表情のことが多い祖母がはにかんでうたう様子を見て、「大人なのに幼稚だな」と思った。宴会でうたわれる歌は、いま思うと日本語の歌ばかりだったし、交わされる言葉も日本語だったが、当時はあまり気に留めていなかった。
私はよく祖父のところ、つまり母の実家に預けられた。祖父は毎晩、マグロの刺身をツマに、熱燗の日本酒を小さなやかんからガラスのコップについで飲んでいた。私と祖母、叔父ふたりは台所で祖父とは別に、焼き魚とみそ汁、たくあん、ときにはカレーなどを食べるのだが、祖父は居間で一人膳だった。だが、お酒がすすんでくると、私を呼び、うたいはじめる。
やかんに金属製のはしを軽くうちつけ、調子をとってうたうのは、かならずアリランだった。宴席では決してうたわない朝鮮の歌を自分の国の言葉で、目を閉じてごく小さな声でうたった。そもそも、宴席で祖父がなにかうたっていたかどうかは思い出せない。しかし、祖父がうたうアリランは忘れることができない。哀しく切ない調べに乗せていとおしむようにうたいながら、涙ぐんでいたからだ。
「東愛もいっしょにうたおう」と言われたことが何度かあるが、音痴であったこと、また、とくに思春期のころはアイデンティティの葛藤で、朝鮮の歌をうたうことなどとうていできなかった。だから私は、いつも、トイレに行くだの、宿題があるだのと理由をつけて居間から逃げた。隣の部屋で耳をふさいでうずくまっていたこともある。
約10年前、「ひとかどの父へ」という小説を執筆するにあたり、母に取材をした。そこで私は初めて、祖父が1923年の関東大震災時、自警団に殺されかけたということを知った。
祖父は1898年、慶尚南道の港街、鎮海に生まれた。日本にわたってくるまでは、小学校の教師だった。かつて地方代表のピッチャーで水泳も得意だった祖父は快活で友人も多かった。祖父は親しい友人のひとりであり、教員の同僚でもある、祖母の兄の家に呼ばれて遊びに行った。そのとき、ちらっと見た祖母を見そめて求婚した。婚約者のいた祖母は、すでに花嫁衣裳を手作りしていた段階で、結納品(のような、先方からいただいたもの)を返すのも大変で、故郷では大騒ぎの事件だったという。
1894年生まれで長女だった祖母は学校に通うことが許されなかったが、歳の離れた妹は日本植民地下の小学校に通っていたので、妹の教科書でハングル文字や漢字、九九を覚えたという。日本語の文字は来日後、教会に通うようになって聖書や祈祷書から覚えた。韓国語の祈祷書と照らし合わせたという。聖書が漢字とカタカナだったため、祖母はカタカナしか書けなかった。お年玉のポチ袋に「トウエ」といつも書かれていた。「なんでカタカナなのだろう、やっぱりハンメ(おばあちゃん)は幼いのかな」と当時は不思議だった。ただ祖母は、私が泊まると、隣に寝て、いつも聖人の話をしてくれた。そのときだけは言葉が滑らかだった。どれだけ繰り返し聖書や祈祷書を読んだのだろうかと思う。
祖母と結婚した祖父は、単身で日本に渡ってきた。祖父の家は、漁の権利を持ち、国から支給される米を配給する役割を担っていたので、経済的困窮での渡日ではなかったかもしれないし、小学校教師の職を失ったのかどうかは定かではないが、当時朝鮮人の職や土地が日本の植民者に奪われていったので、もしかしたら、日本に来ざるを得ない何らかの理由があったのかもしれない。鎮海が、日本海軍の軍港だったことを考えると、相当の日本人が早くから入植しただろうし、軍関係の日本人もあまたいただろう。
母によると、祖父は「日本で勉強したくて来た」という。もちろん、それがもっとも大きな理由に違いない。祖母を残してきたということは、朝鮮に帰るつもりだったのかもしれない。ともあれ祖父は、すでに渡日していた実兄が品川の星薬科大学の建築に携わっており、その兄を頼って来たそうだ。渡日の正確な月日はわからないが、関東大震災にあったとき、祖父は25歳だった。
品川にいた祖父は、「朝鮮人が暴動を起こした」「井戸に毒を入れた」などの流言を信じる自警団に囲まれ、「十銭五厘(じゅっせんごりん)」と言わされた。通説では十五円五十銭や五十円五十銭と言わせたことが多く伝わっているが、母が祖父から聞いたのは、「十銭五厘」だった。朝鮮人は単語のはじめの濁音がとくに発音できない。長音もなかなかうまく言えない。十(じゅう)や五十(ごじゅう)をちゅ、や、こじゅと言ってしまう。だから、濁音が最初にくる単語、長音が含まれた単語がいくつか使われたようだ。そして、正確に言えない人を、容赦なく殺した。祖父は、なまりのある地方の人も間違えられて犠牲になったのを見たという。
殺されそうになる寸前に、警官が制止して、祖父は命をつないだ。その後警察の留置所に入れられた。祖父の収容された警察署は幸い朝鮮人に危害を与えることはなかったが、警察署で殺されるような目にあった朝鮮人もいたので、ほんとうに紙一重で祖父は生き延びたのだった。震災において朝鮮人が亡くなったことは朝鮮でも新聞に報じられ、各警察署にいる朝鮮人の名簿が載ったそうだ。そこで祖母は祖父が生存していることを知った。この新聞掲載については、関東大震災の朝鮮人虐殺の事実を語り継ぎ、追悼の碑も立てた社団法人ほうせんかの方がその事実をあるシンポジウムで話していたので、母が祖父から聴いた話は信ぴょう性がある。ちなみに祖父は、(もちろん当時は慰安婦にされたとはわからなかったし、祖父も亡くなるまで知らなかったが)若い女性が強引にトラックにのせられて連れていかれるところも見たそうだ。
その後の祖父は、学業を諦め、祖母を日本に呼び、ひっそりと暮らし始めた。太平洋戦争中は工場を持ち、電球のガラスを作っていた。工場と住まいがあったのが、西大井で、そのあたりにも朝鮮人の小さなコミュニティがあったようだ。皮肉なことに、そこは伊藤博文の墓の近くだった。
差別や迫害、暴力にあうと、恐怖のあまり委縮して、権力や体制に追随してしまう。朝鮮人だから殺される、という震災で起きた出来事を経て、朝鮮人としての誇りを持ち続けることが難しくなる。自分の出自を呪い、日本社会に、日本人、体制に過剰適応しようとするようになってしまう。そしてそれは家族に継承される。その顕著な例が母の長兄だ。戦時中、明治大学の学生だった伯父は、自ら特攻隊に志願した。幸い新潟での訓練中に敗戦となったが、すっかり軍国青年だった。攻玉社出身の叔父は剣道の達人で、戦後も警察署で地域の子どもたちに剣道を教えるなどしていた。警察との良好な関係を築いていた方が生きやすい、というような生存戦略があったのかもしれない。
また、制度的、社会的差別を受けることで、精神を病んでしまう朝鮮人も多かった。母の弟もそのひとりだ。母の家族の来し方を知ると、朝鮮人が日本で生きることとはどれだけしんどいことかと、あらためて思い知らされる。
戦後、一家は大井町の仙台坂に越し、祖父はプラスチックの工場をかまえ、ブラウン管テレビの枠を作り、生計をまかなった。そのあたりにも朝鮮人が幾世帯か集まって暮らしていた。そしてここに大森教会からホルビス神父(母の記憶なので名前は正しいかわからない)が布教に来て、祖父の工場にも通ってきた。祖母がカトリック信者になったのは、この神父の影響だ。当時工場には朝鮮人の従業員ばかりで、家には韓国から勉強に来た人がいつもいたそうだ。そしてその多くが信者になった。従業員のひとりで、一番気障で遊び人だった沈さんはイエズス会の神父にまでなった。私も会ったことがあるが、彼は南米に赴任して日本に立ち寄ると我が家に必ず来た。「海を抱いて月に眠る」(文春文庫)や「ひとかどの父へ」(朝日文庫)には、これら母方の一家の歴史がエピソードのなかにちりばめられている。
朝鮮人同士で寄り添って暮らしていても、やはり震災の虐殺のトラウマは強く、祖父、祖母、そして母のきょうだいは、朝鮮人であることをなるべく隠して生きてきた。解放後、つかの間朝鮮人としての尊厳をとりもどし、母を含む学齢期のきょうだいはみな民族学校に通ったが、まもなく民族学校はつぶされた。5年生で日本の小学校に転校した母は、授業についていくのがそれは大変だったうえに、朝鮮人ということでずいぶんいじめられた。通称名を使っていたが、九九もなにも朝鮮の言葉で覚えていたから、すぐにばれてしまったのだ。
こどもたちへのいじめを目の当たりにして、また、学校がつぶされるという国家からの朝鮮人に対する迫害に、祖父も祖母もますます委縮してしまった。戦争が終わっても、差別は続く。だから祖父は、近所の人に聞こえないように、小さな声でしかアリランの歌をうたわなかったし、日本語の下手な祖母は口数が少なかったのだ。大井町から戸越銀座に越し、朝鮮人が周りにいなくなって日本人ばかりのなかで暮らしてからはなおさらだった。なにかの祝いなど、よほどのとき以外は、マグロと日本酒、酒とみそ汁、カレーなど、買い物の時点で朝鮮人とわからないようなメニューだったのだ。キムチもめったに食卓にのぼらなかったし、あってもニンニク抜きだった。
祖母がつねにこわばった表情だったのは、いつも「朝鮮人だとばれないだろうか」と不安だったからなのではないだろうか。また、叔父が精神を病んでいることも委縮する生活を助長した。祖母は「近所のひとがウチのことをどういっているか」と敏感すぎるほど気にしていたらしい。
祖父母は来日してから一度も自分の国に帰ることができずに、祖父は82歳、祖母は87歳で亡くなった。
私は、祖父と一緒にアリランをうたってあげるべきだった。祖父が故郷の歌をどんな想いでうたっていたか、想像もつかなかった。祖母のはとぽっぽは、唯一うたえた日本の歌だと知っていたら、幼稚だ、などというひどい感想を持たなかっただろう。朝鮮語の歌をうたうことなんてできなかったのだから。カタカナしか書けない環境だったのだから。私自身、朝鮮半島のルーツがあることを拒み、まわりに知られないように必死だったからとはいえ、祖父母にもっと寄り添えたはずだ。あのときにタイムスリップして、韓国語教室で習いたての祖国の言葉で祖父母と話したい。そして、祖父母の生きざまを聞きたい。キムチをつまに、焼酎(ソジュ)やマッコリを一緒に飲みたい。アリランを大声でともにうたいたい。「はとぽっぽ」に手拍子をつけてあげたい。
祖父母への贖罪の気持ちがあって、私は、小説のなかでアリランをうたい、おどる登場人物を描いた。「翡翠色の海へうたう」(KAOKAWA)だ。作中で、慰安婦とされた女性が沖縄の海に向かってアリランをうたい、酒に酔うとおどりうたう。慰安所近くの峠でも小声でうたう。のちに来た軍夫たちも峠でうたう。小説の舞台である阿嘉島の峠の名前はアリラン峠だ。
祖父はかつて小学校の教師だったのでオルガンが弾けて、母の実家にはオルガンがあった。祖父がよく弾いてくれたのは、日本で最初にできたワルツといわれる「天然の美」だったという。サーカスなどでよく流れる歌だそうだが、たぶんチンドン屋さんの音楽として覚えている人の方が多いだろう。やはり祖父が弾いたのは日本の歌なのだな、と思っていたら、聞き取り取材のしばらくあとに母と行った、在日コリアンのオペラ歌手田月仙さんが出演するコンサートで「故郷の春」という朝鮮の歌が流れたとき、母の目からわっと涙がこぼれ落ちた。
「小さい頃、お父さんがよくオルガンで弾いてくれた曲だった、忘れていた」
祖父は、歌詞を口ずさむことはなく、曲だけを弾いてくれたそうだ。私は、母の記憶と、祖父の想いを小説に残そうと、「海を抱いて月に眠る」に「故郷の春」のことを描いた。
さて、お酒に関する私自身のエピソードもいくつかある。初めてお酒を口にしたのは、高校生の頃、背伸びして行った渋谷のカフェバーで、グラスに塩がついているソルティドッグというカクテルを飲んだときだ。ジュースみたいでとくに感慨もなかった。
お酒は20歳からというのに、大学のテニスサークルでは、新入生が飲みまくっていた。正確に言うと、男子学生が飲まされていた。イッキ飲みという悪習がまだ根付いていたころだ。泥酔して叫び出したり、街を走り抜けたり、お酒というのは、人のタガを外してしまうものなのだな、と学んだ。そういえば、小学生の頃、船舶会社で機関士をしていたコモブ(父の妹の夫)が我が家に何度か立ち寄ったことがあった。コモブは世界各地で買ったお土産をくれたし、私を膝の上にのせて楽しそうにお酒を飲んでいた。私はコモブが大好きだったが、ときどき、お酒を飲みすぎて、おいおいと泣き出してしまう。航海で数か月も離れている、釜山の妻子が恋しくて、彼らの名前を叫びながらさらにお酒を飲んでいた。まさにタガが外れてしまっていた。
タガが外れると困る、自分の出自がばれたらまずい、と肝に銘じていた私は慎重に深酒を避けた。素の自分なんて出たら怖い。だから学生時代はお酒の失敗はない。
しかし社会人になると、酒席の機会はバラエティに富み、お酒を飲む機会自体も多く、すすめられたお酒を断りにくいという場面が増えた。それはおもに上司が一緒のときだった。若手の女子社員はお酌をさせられる、といったいまではほぼ消滅したような慣習もあった。
それまで私は、記憶がなくなるほど飲んだことはなかったが、とうとうそのときが訪れた。
外資系の化粧品メーカーのマーケティング部に勤めていたとき、出張でパリの本社に行き、本社社長との会食があった。直属の上司と本社社長、それ以外にも何人かいたと思う。瀟洒なフレンチレストランでのフルコースでは、皿が変わるごとに異なるワインが出てきて、すすめられる。緊張と興奮が入り混じって、私はひたすらワインを飲んだ。正直言うと、パリで本社の社長と食事をしていることが得意で、調子に乗ってもいた。
デザートのときのワインが甘くて美味しかったのは覚えている。そもそもあまりお酒は強くないのに、すでに10杯近くは飲んでいた。食前にレストラン併設のバーのようなところで一時間以上待たされカクテルも飲んでいたから、25歳だった私にとって、その日は人生で一番アルコールを摂取した日となった。ディナーの時間も日本と違って午後9時くらいに始まり、空腹な状態から立て続けにお酒を飲んだのもまずかった。
食事を終え、エレベーターに乗ってすぐに意識がなくなった。気づくと、私はフランス人の老紳士、つまり社長に抱えられて一階の玄関フロアーにいた。恥ずかしくて消えてしまいたかった。直属の女性上司が顔をしかめていた。この事件はすぐに会社内に知れ渡り、しばらく社員の顔をまともに見られなかった。
とにかく飲みすぎてはいけないと自省しても、ときどきはめをはずしてしまうことはある。私が会社勤めをしていた頃はカラオケと言ってもボックスではなく、店でみんなの前で順番にうたう、というスタイルがまだあったが、一時期はカラオケのある店で酔いに任せてうたうことが好きだった。音痴なのはさておき、そのとき楽しければいい、と刹那的だった。家に帰ると「(在日と見合い)結婚しろ」という圧がすごかったので、そこから逃げたかったのだと思う。家に遅く帰ると「娘が酔って夜にふらついているとはなにごとだ」と父から殴られたこともあったが、止めなかった。うたうとその瞬間はすっきりする、ということに味をしめていた。だが、しだいにカラオケボックスへ行くことが増えて、点数などが出始めると、当然低い点ばかりで気分は下がった。だから、お酒とともにうたうこと=お酒とカラオケという組み合わせとは別れを告げることにした。以来、ほとんど、子どもの付き添いぐらいでしかカラオケボックスには行かなかった。ふたりの子どもが成人したいまは、カラオケとはまったく縁がない。
お酒は、心を解放してくれるが、ときには抑制が効かなくなって、悪い方向に行くこともある。酒席というものにくみして四十年近く経つが、若い頃はとくに、セクハラをうけることが非常に多かった。身体を触られることもしばしばだ。「ふたりで酒を飲めばOKということ」とかたく信じていた男性もいた。しつこいセクハラ発言から逃げたくて、カウンター内の大将に必死に話しかけたこともある。
いまでこそ、私はそういうことがなくなったが、まだまだ酒席でのセクハラはなくなっていない。無礼講という言葉に甘えて、さまざまなハラスメントが起きている。男性が下半身を見せたり素っ裸になったりするのもどうかと思う。お酒の席が悪夢になるようなことはなくなってほしい。
お酒を飲むのは好きだ。
付き合いで仕方なく、というのはさすがに減り、心が通じあうひとたちと飲むお酒はこんなにも幸せなものなのかと思うことが増えた。作家になって、在日コリアンの友人や差別にともにあらがってくれる日本人の仲間も増え、韓国に行けば必ず酒席をともにする人たちがいる。彼らといると、酔って音程のはずれたアリランや故郷の春を口ずさんでも、あたたかいまなざしで聞いてくれるし、ときには一緒にうたってくれる。大合唱だ。周りに外に聞こえたってかまわない。
お酒とともにうたうのは、いとしい歌。そしてお酒を酌み交わすかけがえのないひとときを、大切な人たちとともに、これからも過ごしたい。

左から3番目奥が東愛さん。(筆者提供)
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。