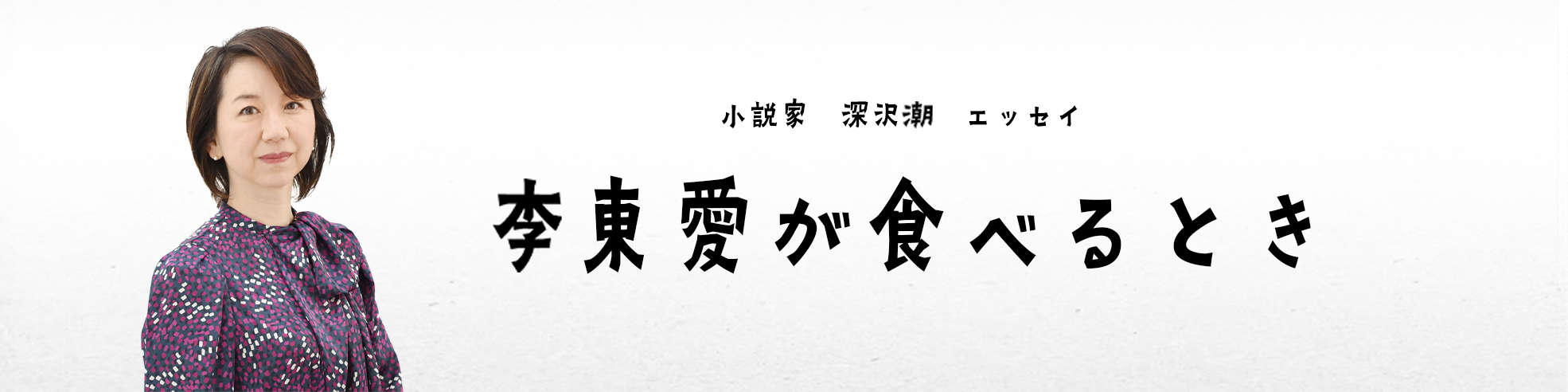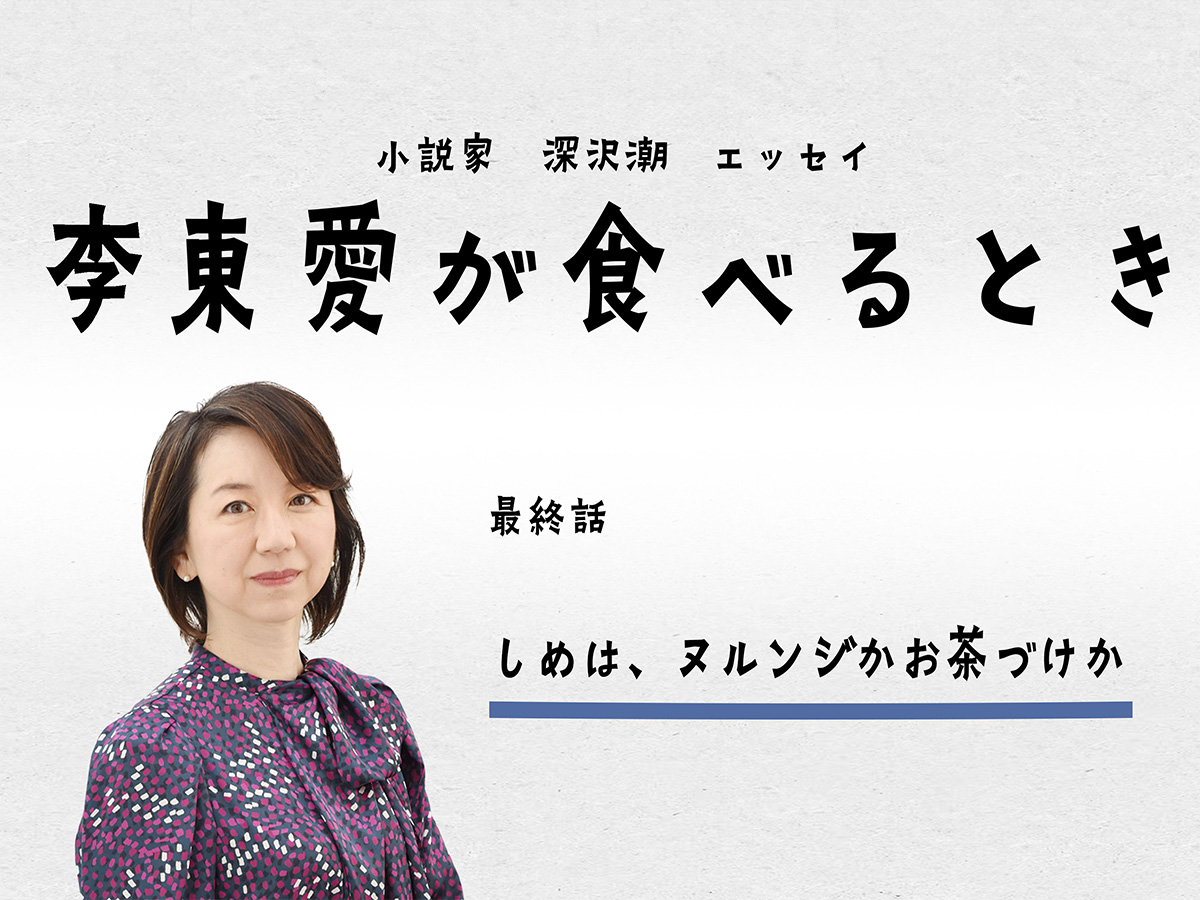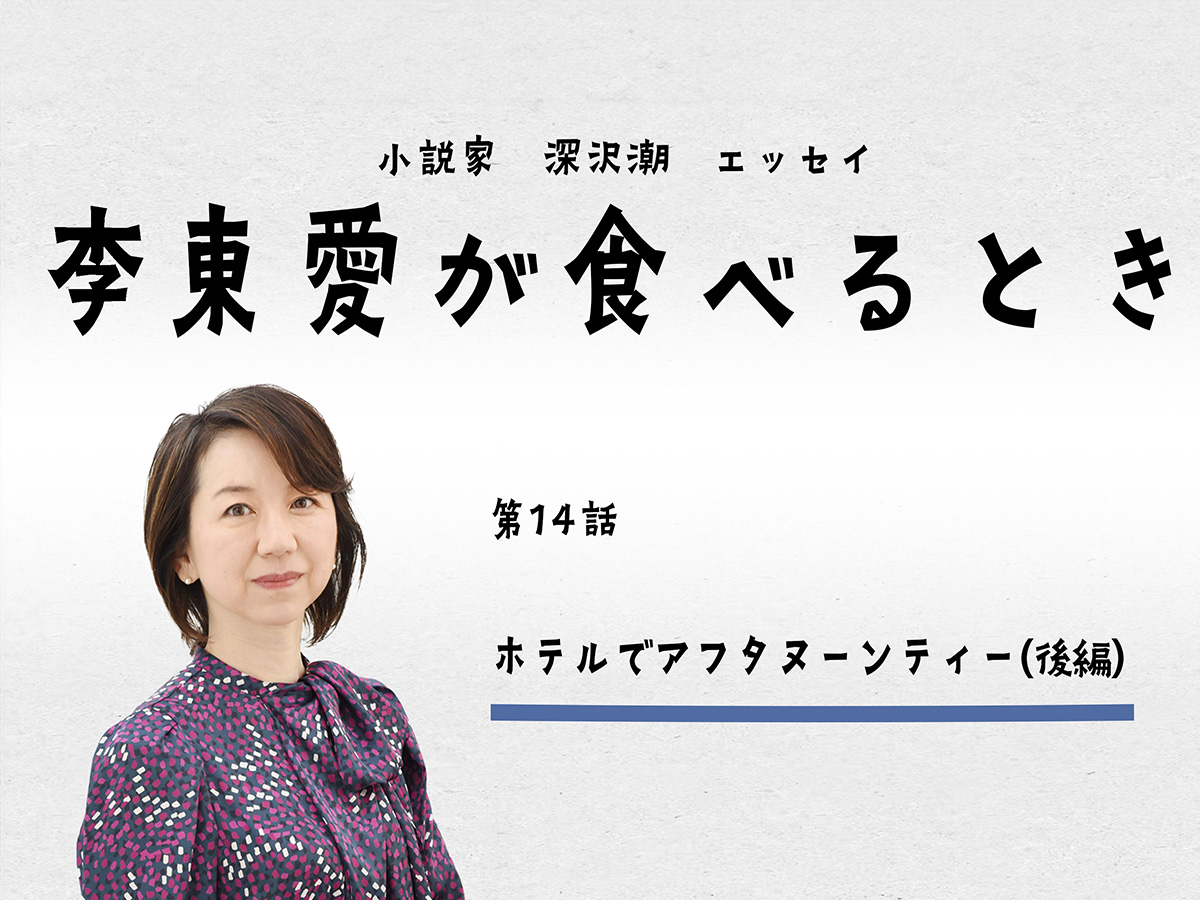第7話 肉をともに食べるひと
肉を食べる、と言ったとき、真っ先に思い浮かぶのは、私の場合、焼肉だ。加えて、焼肉といえば、かつては牛肉を焼いて食べることと同義であった。
焼肉の思い出は、家でのものではなく、焼肉店でのエピソードが印象深いので、いくつかを書いてみようと思う。
特に忘れられないのは、大使館のPさん一家と何度も赤坂の高級焼肉店に行ったことだ。なぜ大使館の人と父が接点を持つようになったかは、ちょっとした物語がある。
家族で焼肉店に行くことがたまにあったのだが、いつも行くのは、自宅から比較的近くにあった在日コリアンの家族が営む、価格も手ごろな小さな店だった。注文は父が決めてしまうし、せっかく外食するならもうちょっとしゃれたところ、たとえば洋食のレストランなどに行きたいと思うばかりで、実を言うと、私はその焼肉店に家族で行くのが、そんなに心躍ることではなかった。だが、大使館のPさん一家との食事はゴージャスな佇まいの焼肉店だったから、特別な感じがあって、まんざらでもなかった。
大使館のPさんと焼肉店に行くようになったのは、私が中学三年生のときからだ。全斗煥時代である。日記で確認したので、間違いない。Pさん一家とはあるときから突然付き合いが始まった。当時は父がどういう生き方をしているか知らず、興味もなかった私は、韓国大使館の人と父に接点があることを特に不思議に思うこともなく、赤坂の高級店ということに気圧されて緊張しつつも、正直、赤坂で焼肉を食べるというぜいたくは、好ましく思っていた。
Pさんは物腰のやわらかな紳士で、きれいな日本語を話した。これまで出会ったどの韓国人よりも静かで落ち着いた雰囲気の人だった。ご夫人も上品で優しい人だった。私よりも年下のお嬢さんふたりもおとなしかった。親族や知り合いがほぼ慶尚南道出身者ばかりで、Pさん一家が初めて知り合ったソウル出身の韓国人だという母は、「やはりソウルの人は違うわね、言葉から態度から」と会うたびに感慨深く言っていた。
私も「慶尚南道の人とソウルの人ってそんなに違うのか」と単純に思っていた。たしかにPさん一家は母方や父方の親戚たちや、在日コリアンの知人たちと著しく佇まいが異なっていた。Pさんは数年の駐在を経て韓国に戻ったが、私の両親はその後もずっとPさん夫婦と連絡をとって付き合っている。昨年もクリスマスカードのやりとりがあった。
「海を抱いて月に眠る」という小説を描くにあたって父に聞き取り取材を始め、父の来し方をあらかた聞き終えたとき、私はふとPさんのことを思い出して、父に「大使館のPさんとはどういう関係だったのか」と訊いた。すると父は「彼は情報部(安全企画部)の人間だった」と答えた。Pさんは駐日韓国大使館の公使だったという。そして、Pさんは父を尾行していたそうだ。
Pさんの尾行に気づいていた父は、ある日道端で立ち止まって振り返り、Pさんに近づいて行った。
「もう私はなにもしませんから、尾行しなくて大丈夫です。もうやめてください。わかりきった尾行は意味がないでしょう」
父はそうはっきり言い、それ以来親しくなったのだそうだ。「彼は良い人間だよ。立場が違っただけだった」と父は言うが、もしかしたら、親しくなったというのも、監視されていただけなのかもしれないし、父にとって、Pさん一家と付き合うことは、保険をかけるような意味合いがあったのかもしれないと邪推してしまう。あの赤坂の高級焼肉店での晩餐は、父にとっては命をつなぐ接待だったのではないだろうか。
金大中氏の支援や、日本での民主化運動を行わなくなったとはいえ、父はその後もつねに監視されていた。朴正煕時代のKCIAに続き、全斗煥政権の安全企画部の人間が韓国大使館に公使として、あるいは領事館の領事という体で、在日韓国人の動向を見張っていた。つまり、政治活動を止めた父にも普段から尾行がついていたのだ。
当時のPさんと父との関係の真相は不明だが、韓国が民主化し、父もPさんも年老いた現在は、ふたりが親しい友人であるのは事実だろう。それにしても、尾行とか、監視とか、実のところ現実味がなかった。
だが、四年前の春に釜山在住のコモ(叔母)から、父の日本での反政府活動のおかげで、韓国の父の一家がきびしく監視されていたことをはじめて聞いて、私は独裁政権や軍事政権下で生きる厳しさを思い知った。民主化するまで父の一家への監視は続き、そして当然ながら父には訪韓のたびに尾行がつき、きょうだいは連座で出世が妨げられたり、進学や就職が不利だったりと、いろいろなことがあったらしい。父が現役で反政府的な活動をしていた頃は家族への抑圧や弾圧はさらにひどく、北朝鮮に父の住所があると、当局から言われたことも明かしてくれた。反共のすさまじさは、日本に生まれ育った私の想像を越えている。
韓国の政府側といかなるやりとりがあり、どんな妥協や約束をしたかということを私が訊いても、父は話してくれないのだが、コモによると、父は韓国に暮らす自分のきょうだいが連座で不遇な目にあっていることを知り、ずいぶん苦悩していたということだった。つまり、妻や娘のことを考えて、あるいは危篤だった自分の母親に最後に会いに行くためだけでなく、韓国に住む家族のことも考えて、政権に抗う活動を断念したようだった。そして、それまで政府からパスポートを発行してもらえずに帰れなかった祖国に戻れるようになった。しかしそのつけとして、全斗煥政権の際には、父はかなりの額の寄付?賄賂?を要求され続けたともコモが嘆いていた。
父は祖母の臨終の際に訪韓して以来、ひとりで、あるいは家族をともなって、旧正月や秋夕、祭祀、夏休みや春休みなど頻繁に故郷の三千浦に行くようになるが、民主化以前は、相当の緊張感と覚悟をもって渡韓していたのだろう。その後父は、民主化以降に、やっと、なにも憂いなく、たびたびひとりで韓国に行くようになり、それは、つい四年前、80代後半になるまで続いた。
アイデンティティをだいぶこじらせた中高生時代を送った私は、祖国への想いも複雑なものがあった。そのことについてはこれまでの著作にも描いているが、私には小説に描いていない、韓国から来た青年との淡い思い出がある。
上智大学一年の初夏、大学の先輩が参加する英語のスピーチコンテストに先輩の応援に行った。会場は立教大学で、そこにはさまざまな国の学生が参加していた。たまたま私の席の近くには、韓国からの学生の集団が座っていた。
休憩時間になり、そのうちのある男子学生がひとりでいる私に英語で話しかけてきた。内容は忘れたが、たわいもないことだったと思う。ふだんは通称名を使い、韓国人であることを周囲にひた隠しにしていた私は、なぜだかそのときはごく自然に、彼に、「私は在日コリアンだ」と言っていた。すると彼は自分の仲間にそのことを告げ、それからは男女の韓国人学生たち数人が私を囲むようにして会話に加わってきた。なかには、妙に警戒するような態度を示して近づいてこない学生もいた。だが、話しかけてきた数人は、在日コリアンと接するのが初めてだとかで、興味津々で故郷はどこだとか、父親がなにをしているか、民団に所属しているのかなどを尋ねてきた。
私は、韓国人の学生たちと話すのがとても楽しくて、興奮していた。私も、韓国の現役の大学生と話すのは、韓国のいとこたち以外とは初めてだった。質問されて答えているのが、自分の嘘偽りのない素性であることも、新鮮だった。つねに隠していることを堂々と言えることも嬉しかった。
スピーチコンテストが終わったあとも、韓国の学生たちと離れがたく、しばらく会場の外で話していた。コンテスト出場を終えた日本人の先輩と、その先輩が親しくなったという在米コリアンの学生も加わった。それまで先輩には自分の出自を言えなかったが、そのときに勢いで話したら、「へえ、そうなんだー」とさらっと受け止めてくれた。小学校6年の三分間スピーチ以来のカミングアウトだ。とくに驚きもしない先輩の反応が意外だったが、ほっともしていた。大学のみならず中高の同窓生で、大学受験時に英語の家庭教師をしてくれた大好きな先輩に韓国人であることを隠していたことも、どこか後ろめたく思っていたからだ。私は、先輩に限らず、親しくなった友人に出自を隠していることが、嘘をついているような気がして、いつもなにか心の奥にひっかかっているような気持ちがしてしまっていた。けれども、在米コリアンの学生と親しくなるような先輩には、心おきなくカミングアウトができたし、帰国子女でもある先輩は、差別意識をまったく持ち合わせていなくて、こんな人もいるのか、と感激もしたのだった。
当時は携帯電話もなかったので、互いの自宅の住所と電話番号を書いたメモを交換し合った。最初に私に話しかけてきたのは、延世大学二年の金君で、なかなかの好青年だった。いまでいうイケメンで、韓国人俳優のコ・スに似ており、まあ、つまりは、とても好みのタイプだった。なによりさわやかな笑顔に魅かれた。私は彼とそこで別れてしまうのが寂しかった。もう次の日には、みな韓国に帰ってしまうという。
私は彼らに待ってもらって、公衆電話から自宅に電話をかけた。珍しく家にいた父が電話に出たので、「韓国の学生と会ったから彼らを家に食事に招きたい」と伝えた。すると受話器の向こうの父は、しばらく沈黙した。私は父が歓迎してくれると思い込んでいたので、その反応が不思議だった。もしかして私の行動は、父の怒りを買うようなことなのかもしれない、軽率だっただろうか、十人近い学生を家に呼ぶのは無理だということかと思い、がっかりしつつ、叱られたらどうしようと、びくびくして電話を切ろうとしたら、父が、低い声で「連れてきなさい」と言った。
急だったうえに、借家から持ち家になり多少広くなっていたとはいえ手狭だし、さすがに自宅に呼ぶのは、幼い妹たちもいて母の負担だということで、父の知人が経営する目黒の焼肉店に彼らを連れて行って、父のおごりで食事をすることになった。
父の知人の店は、あまり広くないので、貸し切り状態となった。だが、周りの目を気にせず英語や韓国語で話せることに安心した。韓国人の学生も在米コリアンの学生も、在日コリアンの営む焼肉店のような店は韓国や米国にはないので、珍しがっていた。父が気前よくロース肉を注文し、学生たちは「美味しい、美味しい」と次々に肉をほおばった。父の前では緊張しているようであまり話さないし、父もそれほど口数は多くなく、もっと盛り上がると思っていた私は拍子抜けした。先輩も父がいるからか、あまりしゃべらなかった。
私は金君の隣で、英語で会話をするのに一生懸命で、そのうちに、まわりのかたい雰囲気は気にならなくなっていた。胸の鼓動が終始高鳴っていたことはいまでも覚えているが、会話の内容はすっかり忘れてしまっている。
金君や学生たちとは目黒駅で名残惜しく別れた。私は彼らの姿、厳密に言うと、金君の姿が見えなくなるまで改札口で手を振った。
それから二週間ほどして、深夜に突然起こされ、父から応接間に呼ばれた。応接間に呼ばれるときは、たいがい説教と決まっていた。身に覚えがないものの、父が怒った時の恐怖が身に染みている私は、縮こまってソファに座った。手をあげられたらどうしようと、顔をあげる勇気はなく、うつむいて、なにか落ち度はなかったか、失敗はしていないか、近々で夜遅く帰った日があったか、男の子の友達から電話でもあったのだろうかと、猛スピードで思い巡らせていた。ちなみに我が家は門限も厳しく、恋愛もいっさい禁止だった。
父がテーブルになにかを置いたので視線をやると、白い封筒と便箋がある。促されて手に取ると、宛先には父の名が漢字で書いてある。裏の送り主が記されたところには、ハングルが並んでいる。便箋の方も、文面にはハングルしかない。私には何が書いてあるのかいっさいわからないし、これを見せる父の意図も読めないので、混乱した。
そこで父が口を開く。
「このあいだ焼肉に連れて行った延世大学の金君からだ。食事のお礼が書いてある」
「金君はなんて礼儀正しいのだろう」と感心しつつ、「だけど、お父さんにではなく、私に英語で手紙をくれればいいのに」「でも、きっと手紙を開けてしまうから、同じことか」などと考えていた。父も母も、男の子からの私宛の手紙を勝手に開けたことがあるのだ。
それから、と父が言葉を続ける。
「お前と交際したいので、文通を許してくれとあったから、『学生の本分は勉強なのだから、しっかりと勉強して、交際などと考えるのは止めなさい』と書いて返事を送っておいたからな」
父はそう言い終えると立ち上がり、応接間を出て行った。
そのときは、文通ぐらいいいじゃないか、私の意思など全く無視されるのだな、と父に支配されていることが悔しくて、悲しくて、しばらく無気力になってしまった。
だが、いま、金君のこの一件を思い返して気づくのは、別のことだ。
民主化前の1985年当時、旅行の自由化もまだで、特別な枠で来日し、スピーチコンテストに参加した学生は、韓国政府から「在日コリアンと接してはいけない」と言われていたに違いない。だから、警戒して私と話さない学生もいたのだ。民団に所属しているか訊いてきたのだ。1980年代、在日コリアンは北のスパイの可能性が高いと疑われた。韓国に留学した在日コリアンが、スパイの容疑で捕まり、刑務所に送られたという事実もある。学園浸透スパイ事件は有名だ。のちに無実となったが、在日コリアン社会において、その傷跡は深く残っている。
民主化後も保守政権のときは、来日する人たちにそうした注意喚起がつい最近まであったと聞いたことがあるくらいだから、当時はなおさらだろう。このように韓国から日本に来る人たちは、在日コリアンを警戒することが少なからずあるのだ。この事実を知って、私は、理不尽で切なくなってしまう。こちらがいくら祖国だと思っても、同胞だと思っても、向こうは色眼鏡で見るなんて。
あのとき、父が韓国から来た大学生との食事を承諾するのに躊躇したのは、反政府活動をかつてしていて、その後も監視対象だった自分と接したら、学生に被害が及ぶのではないかと考えたのだろう。娘の韓国人への同胞意識の目覚めが嬉しくて願いを受け入れ、また、学生を労いたい思いもあって焼肉店で食事はしたものの、それ以上のかかわりは避けるべきだと思ったのではないだろうか。
あるいは、もっとうがった目で見ることも可能だ。金君の手紙は、第三者のなんらかの意図があったのではないかとも父は考えたのかもしれない。安全企画部からの差し金とか……。そこまで考えるのは、韓国映画やドラマの見過ぎだろうか。
金君の手紙は、裏などないと思いたい。だって、彼の純粋そうな瞳は、私の脳裏にしっかりと焼き付いているのだから。金君との出会いをほろ苦くも大切な思い出としておきたい。
焼肉、の話。
私が社会人だった1990年代初め、焼肉はずいぶんとポピュラーになっていた。「焼肉を食べているカップルはもう関係がある」などというくだらない言説まで登場した。私も、会社の同僚たちと焼肉店に行くことが珍しくなかった。ホルモンも一般的となって、店も増えていって、いまでは、焼肉店も多様だ。
ホルモンといえば、実は私はホルモンが苦手でめったに食べなかったのだが、昨年京都の東九条で食べたホルモン焼きは格別に美味しかった。一緒にテーブルを囲んだのは、差別に抗う仲間たちで、肉も酒もおおいにすすんだ。それ以来、東九条でホルモンを食べることが、京都へ行くときの楽しみのひとつになっている。
東九条や鶴橋のような在日コリアンの集住地域にはとびきりの焼肉店があるし、在日朝鮮人や韓国人が営む焼肉店はいまでも各地で多いが、もはや、焼肉店といえば在日、といった時代は遠い日のことになりつつある。子どもたちが育ち盛りの頃は、手ごろな価格の焼肉チェーン店にお世話になった。息子は留学先の米国で牛角に行くのが楽しみのようだったが、牛角などは日本食レストランに分類されるだろう。
サムギョプサルも焼肉とするならば、案外、在日コリアンは、ことにオールドカマーと呼ばれるひとたちにとって、豚の三枚肉を焼くサムギョプサルは、最近まで馴染みのないものだった。私もサムギョプサルは、ママ友に連れられて行った新大久保で、2000年代の終わり頃に初めて食べた。1世の父や2世の母にいたっては、これまで食べたことすらない。私はいまでは好物で、とくに熟成肉のサムギョプサルが好きだ。そろそろ脂っぽい肉は避けなければならない年齢なので、たまにしか食べないが、とくに韓国に行ったときは外せないメニューだ。
日本では焼肉店というより、韓国料理店という名がふさわしい食堂が多くなってきていて、その人気は衰えていない。そして日本のみならず、世界中で韓国料理は人気が高い。
海外の韓国料理店で思いだすのはグアムの店だ。家族で行く海外旅行としては、韓国以外で初めての海外だった。1983年、高校二年の夏のことだ。飛行機を降り、空港でタクシーに乗ったら、30歳前後の運転手さんがアジア人で、ブロークンな英語だった。家族で唯一英語をかたことで話す私がどこの国の人ですかと訊いたら、韓国人だった。グアムに移住して間もないという。父にそのことを告げると、それから父がずっと彼と韓国語で話した。父は彼と意気投合して、レストランをすすめてもらい、そのまま連れて行ってもらった。
私たち一家は、初めての海外旅行での最初の食事が、韓国料理だった。しかも、韓国人の集住地域のなかの、韓国人しかいない小さな食堂に運転手さんの夫婦と一緒に行くことになってしまった。絶対権力者の父には逆らえなかったのだ。さすが、スーツケースにキムチを入れてこさせた父である。
「もう、本当に嫌だ、どこに行っても韓国がつきまとう。こういう店、いつもの焼肉屋と雰囲気が変わらないし、韓国の故郷で出てくる料理みたいで、珍しくもない。本場のハンバーガーが食べたかったのに!楽しみにしていたのに!生まれて初めての海外なのに!アメリカなのに!」
私はうんざりし、飛行機や車に酔ったと言って、ほとんど料理に口をつけなかった。運転手さんの夫婦はとてもいい人たちで、気を遣って私に英語で話しかけてくれたが、父がすぐに遮って韓国語に戻してしまった。非常に苦い思い出だ。
けれどもそんな私も数年前にアメリカのフロリダ州の地方都市に娘と行った際、空港から乗ったウーバーの運転手さんがコリアンだったことで意気投合し、コリアンレストランを教えてもらい、そこに真っ先に行ったというような、父と変わらない行動をしている。血は争えないものだとしみじみ思う。
とはいえ、40年近く経つと時代は変わり、子どもの方の反応がまったく異なる。娘はコリアンレストランに行くのをむしろ喜んでいたし、在米コリアン2世の若者の運転手さんとも英語で楽しく会話していた。レストランでは満足そうにジャージャー麺を食べた。とくにコリアンの集住地域でもなく、地元のひとが行き交う町の一角にある店には、アメリカ人や日本人のお客さんがいた。近くには、韓国系のスーパーがあり、韓国の食材がびっしりと並ぶ。スーパーの隣には韓国風のカフェまであり、パッピンス(かき氷)が食べられる。
92歳の父と86歳の母とともに、二か月に一回くらいの割合で焼肉店に行く。いまだにふたりとも肉を食べたいというのが、元気な証拠で何よりだと思う。食卓での話題は昔の話だ。最近の記憶は危ういが、だいぶ過去のことは覚えているので、私は両親に会うたびに、若い頃の話を訊くようにしている。
エッセイに金君の手紙のことを書くつもりでいたので、先日父に金君のことを訊いてみたら、覚えていなかった。とても残念だ。
「1987、ある闘いの真実」という、民主化闘争を描いた韓国映画を観ると、金君のことを思い出す。そして、映画を見終えると、身の置き所がないような気持ちになる。韓国で私と同世代の学生たちが闘っていたとき、私はバブルまっさかりの日本で、なにをのうのうと、自分のことだけを考えて暮らしていたのかと、やましさにさいなまれる。
私が延世大学二年の金君と出会ったのは、1985年。その二年後、金君は延世大学の正門前でイ・ハニョル君が催涙弾に当たったとき、どこでなにをしていたのだろうか。徴兵され、軍役に就いていただろうか。
あれから40年近くが過ぎ、金君はいまどんな人になっているのだろう。小説の世界ならば、私と金君はふたたび出会えるはずだ。果たして、いかなる物語が紡がれるだろうか。
向かい合って肉を焼きながら、お酒を酌み交わし、それぞれの生きてきた軌跡を語り合う、っていうのは、平凡すぎるだろうか。

(筆者提供)
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。