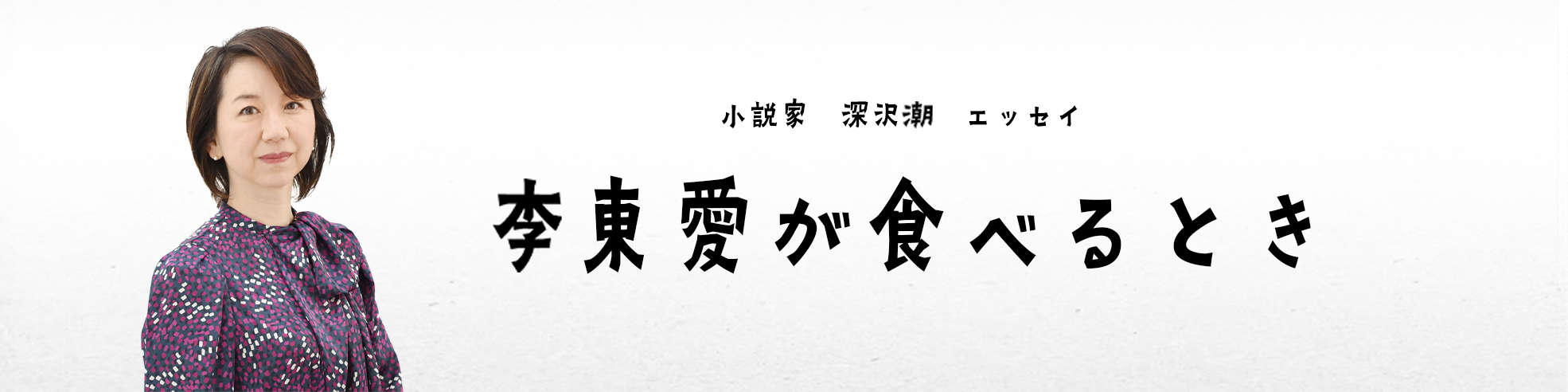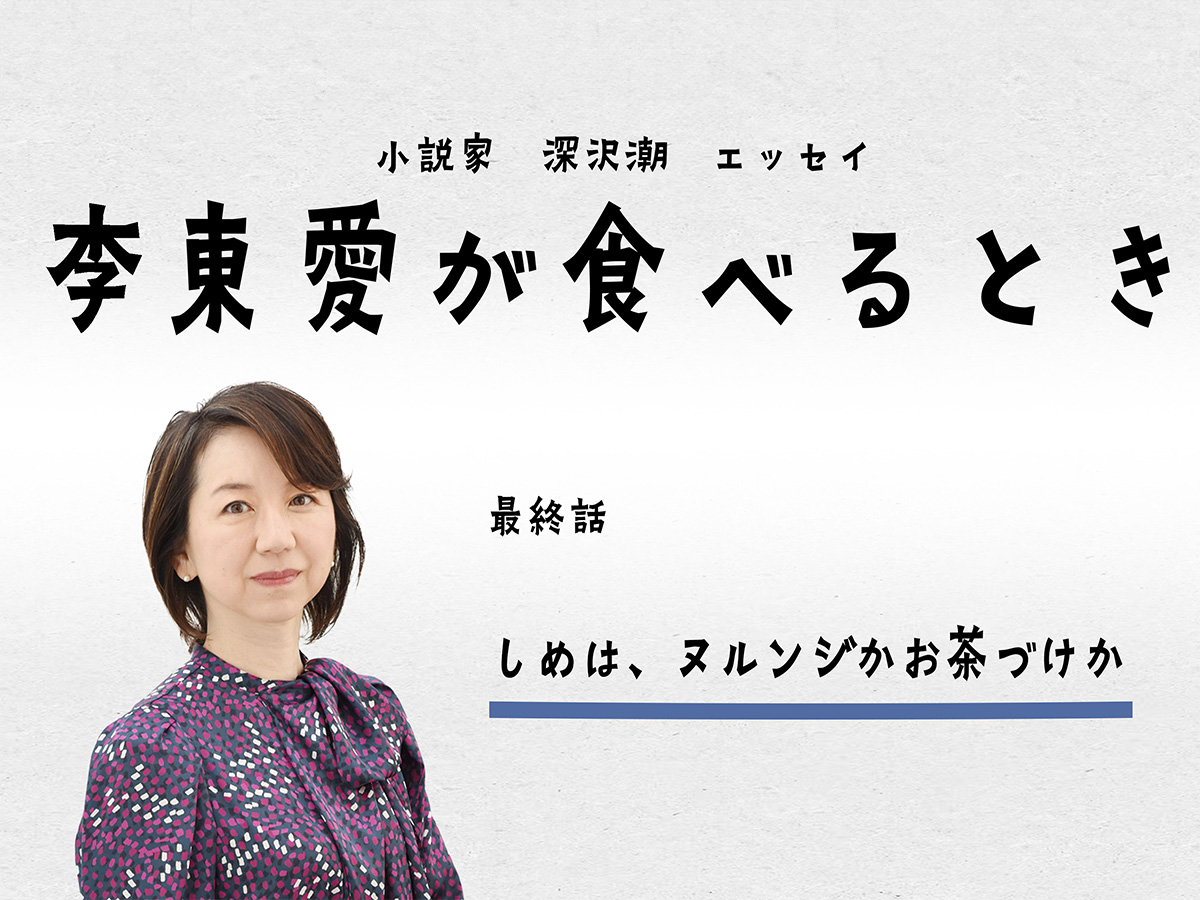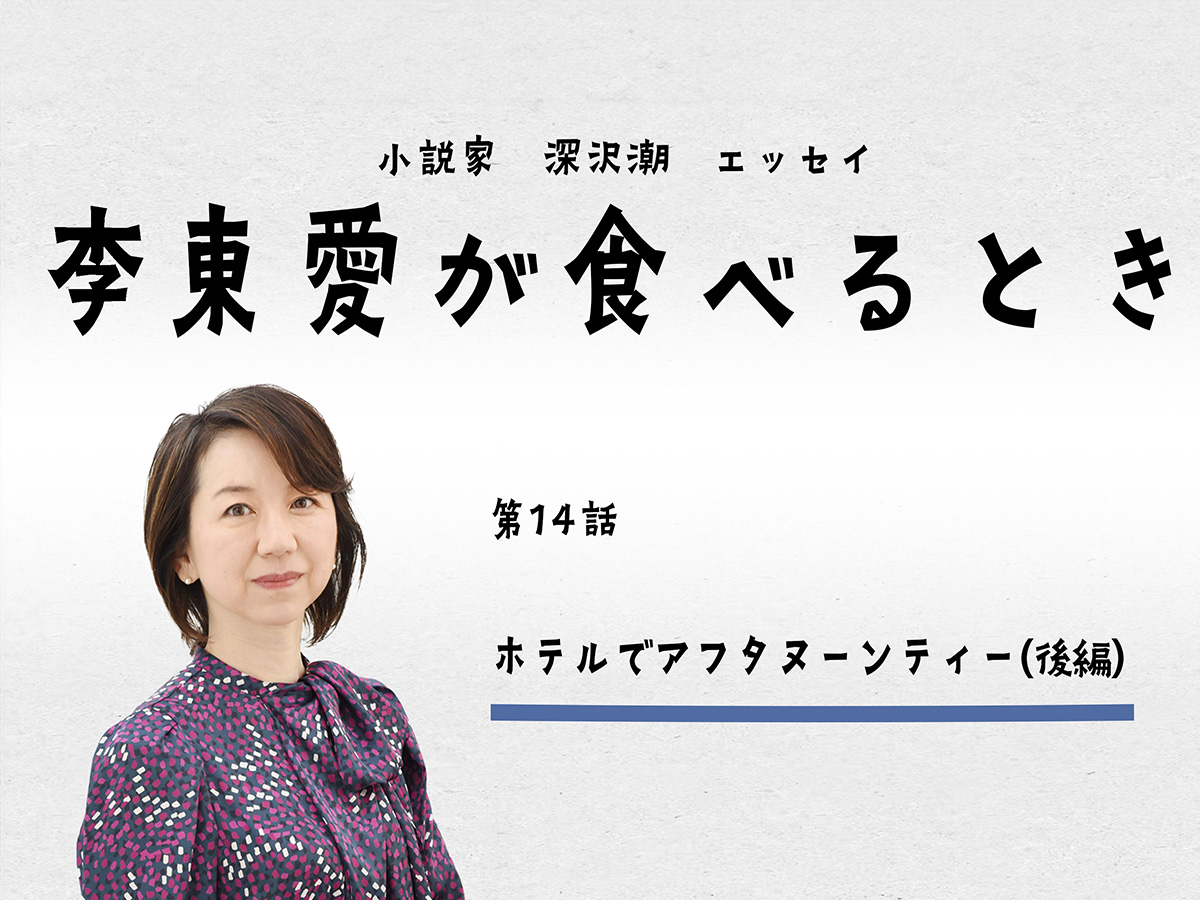第8話 ゆで豚(ポッサム)を前に
私には、歳の離れた妹がふたりいる。上の妹とは8歳、下の妹とは13歳も違う。中学に入学した年に下の妹が生まれ、私は三姉妹の長女になった。これだけ歳が違うと、喧嘩をすることなど、ありえなかった。もし喧嘩をしたら、小さな子相手にまったく、となるのは必然だったし、じっさい、妹たちと争うような動機もなかった。
妹ふたりが幼かったころは、世話をする、という場面が多かった。とくに下の妹は、母が高齢で産んだので、私がミニお母さんのような役割を果たしていたといえよう。
妹たちは、私にとって、かわいがる対象でもあった。上の妹には、人形のように、(母の留守中に)洋服をとっかえひっかえして着せてみたり、母の化粧品を拝借して三面鏡の前でメイクをしたりして遊んでいた。嫌がることもなく、妹も、たぶん楽しんでいたと思う。妹は母のワンピースを着て、ジュディオングの「魅せられて」を得意げに披露していた。このころには我が家にテレビが復活して、毎週「ザ・ベストテン」という音楽番組を観ることができていたので、その影響だ。
少し大きくなるとコスプレを嫌がったので、その遊びは止めたが、彼女らの世話は続いた。風呂に入れたりなどの細かいことだけでなく、13歳下の妹にいたっては、大学一年のときに、毎朝幼稚園に送っていったり、母の苦手な裁縫やアイロンをしたりして彼女の幼稚園生活を支えた。幼稚園バッグに施した刺繍はディズニーキャラクターのダンボで、あれはなかなかいい出来だった。私は案外針仕事が好きだったし、手作りも楽しんだ。母が、「この刺繍は、姉が作った」と自慢していたこともあって、妹の幼稚園ママたちに、「偉いわねー」「いいお姉さんがいて羨ましい」と声をかけられることが、まんざらでもなかった。なにより母に認められることも、私にとっては重要なことだった。
のちに自分の子どもたちの手作りものも頑張って作ったが、それでも離婚後働き始めたうえにワンオペ育児の私には作りきれなくて、業者や友人に頼んだりしたことがあった。仕方がなかったとはいえ、後ろめたさはぬぐえなかった。しかし、果たして、後ろめたく思う必要などあったのだろうか。いまだに親の手作り品や手作業を強要する幼稚園や小学校が結構あるらしいが、あのシステムはやめるべきだと思う。同様に、手をかけたお弁当ばかりを評価する風潮もあまりよろしくないのではないか。もちろん、早朝からお弁当を作ることは大変だし、その労力は褒められるべきことだとは思うし、それが苦にならない人もいるだろうが、手作りをできない人が愛情不足だというわけではないのだから。物理的にできないだけでなく、料理や裁縫が得意でない人もいる。私も、長い間、早朝からお弁当を作って子どもたちに持たせるといった生活をしていたが、本当につらかった。冷凍食品を入れたことで、ママ友から嫌味を言われたこともある。
できるだけ家事や育児の負担を軽くするという方向に社会の空気が変わってほしい。
話がそれた。
妹たちは、私によく手紙をくれたり、絵を描いてくれたりした。一時期、断捨離にはまって、潔くものを捨てた私も、妹たちからもらったものは、いくつか大事にとってある。もちろん、自分の子どもたちからのものも厳選して残してある。それらを眺めるのを老後の楽しみにしたい。
下の妹が小学校低学年になると、「ちびまる子ちゃん」の漫画を貸してくれるようになり、私は妹から本を借りる、ということが凄くうれしかった。双方向の気持ちの行き交いを感じたのだ。ストレートに好意を示してくれる幼い妹たちが愛おしくてたまらなかった。
このように書くと、立派なお姉ちゃん、ということになるし、実際、そうであったと思う。妹の幼稚園ママのなかには、「あなたはシスターになったらいいんじゃないかしら」とまでいう人がいたくらいだ。そして一瞬だが、私は「シスターになるのも悪くないかも」と思ったことがある。究極の奉仕、神に仕えるって素敵じゃないかと。神に仕えたら、これまでの私のさまざまな罪や性格の悪さも、許されるのではないかと。
しかし、私が当時、根っから犠牲と奉仕を最上のよろこびとしていたかといえば、もちろん、そうではない。私としては、いいお姉ちゃんでいるしか、選択肢はなかったのだ。そして、妹たちから好かれている、求められている、ということが心の支えでもあったのだ。そして私は、誰かの世話をして好かれたい、という考えが強く身についていく。世話ならまだいいが、尽くす、ということに意義を見出してしまうようになった。これが、のちに男性との交際にも負の面をもたらすのだが、このことを書くのは、またにしよう。
犠牲と奉仕をよしとするのは、母の思考と重なっている。母も、誰かの世話をすること、尽くすことが、生きがいで、86歳になったいまも、92歳の父をこまやかに世話している。長い間、老人ホームや児童館でのボランティアをしていた。母は熱心なカトリック信者だが、母とカトリックの信仰は親和性がある。
さて、ゆで豚がなかなか出てこない、とお思いでしょうが、もうちょっとだけお付き合いいただきたい。
すこし時間をさかのぼる。
中学受験を終えて、晴れてセーラー服を着るようになった。真新しい制服とともに、すべてをリセットしようという思いは、前に述べたように、親友へのひどい仕打ちとなって表れた。それだけでなく、学校生活においても、新しい友人を得ることに必死だったが、うまく友達と接することができなかった私がとったのは、媚びる、尽くす、という行為だった。たとえば、席が近くなり話すようになった子に、好かれたくて、別に誕生日というわけでもないのにプレゼント攻勢をかけるというような迷走をした。たいしたお小遣いをもらっていなかったので、母の財布から紙幣をくすねて彼女が好きなミュージシャンのLPレコードを買って贈った。しかし、結局その子とはあまり親しくなれなかったうえに、盗難がばれて、母から嘆かれ、父からこっぴどく叱られ手をあげられた。
もう、最低だ。私は、根性の悪さが治っていなかったのだ。自分が一番、自分を嫌だった。そして私は深く反省した。挽回をはかって、こんどは、模範的なカトリック信者になるべく、教会のミサに熱心に通い、学校のカトリック信者向けの教えのクラスにもまじめに参加した。善良な人間になりたい、という気持ちは私の中で肥大していた。そう見られたい、というだけでなく、本当に善良になりたい、と思っていた。そうならなければ、このままでは、地獄に落ちると信じていた。
ハイソな生徒たちには戸惑ったけれど、私の入学した私立学校の、カトリックの精神が基になった道徳的、倫理的価値観は、私の心の隙間を埋めて、生きる上での軸を与えてくれた。信者の生徒向けの「教え」の課外クラスのシスターは優しくて、大好きになった。つねに弱きものに寄り添いたいと思うようになった。
在日コリアンという出自だったこともあって、差別、ということに敏感だった私は、小学校の頃に「アンネの日記」の読書感想文を書いたり、夏休みの自由研究でナチスのホロコーストについて調べたりしていた。そして、差別される人、社会的に弱い立場にいる人たちについて書かれた書籍を積極的に読んでいた。題名は忘れたが、朝日新聞が子ども向けに出した書籍で知った部落問題や障がい者差別の現実に衝撃をうけ、強い関心を持っていた。
だから、英語を教えてくれたシスターが授業の始まりに必ず、世界の貧しい人たち、困っている人たち、弱き人たちのために祈りましょう、と手を合わせることに感動した。また、クリスマス前に乳児院にプレゼントを届ける役回りをクラスで募った時も、期末テスト前にもかかわらず、率先して手を挙げた。自分も預けられたことがあるからぜひ行きたいと思って、乳児院を訪ねた。
だが、そこにいたのは、暴れまわる子どもたちだった。私にとって幼い子どものサンプルは妹たちだったので、比較的おとなしかったふたりとはまったく異なるギャングたちに驚いた。ある5歳児は、おもちゃの自動車をぶんぶん振り回して投げていた。幸い誰にも当たらなかったが、想像していた「かわいそうな、けなげな子どもたち」とは程遠かった。
いまなら、あの子たちが理解できる。たぶん、見知らぬお姉さんたちの来訪に興奮してしまったのだ。気を引きたかったのもあるだろう。私も、授業参観をかねたお楽しみ会が小学校であったとき、母子のドッジボール大会で、大声で叫びまわり、騒いだことがあった。周りの人たちが唖然として自分を見ていたのを覚えている。姉の死後それほど経っておらず、母は姉が通っていた小学校に来られるような心境ではなく、その場にいなかった。寂しかった私は、誰かの気を引きたかったに違いない。
そもそも、乳児院にいた子どもたちを、かわいそうな、けなげな子たちと思い込んでいることがおかしいのだが、当時はそんなことには気づけず、私は、乳児院の子どもたちの姿にひたすら落胆したのだった。幼かったとはいえ、傲慢だった。
だが、中学生の私は、まだまだ純粋で、24時間テレビに感動して涙を流し、近くのコンビニに募金をしに走っていくようなことをしていた。
それでもしだいに、友だちづきあい、卓球部のクラブ活動、それなりの勉強、欧米のミュージックシーンを追うことなど、つまりは日々の生活に忙しくなって、信仰を深めることと善良になることへの歩みは滞っていく。さらに、韓国人であることに悩み、友達からアウティングされた上に仲間外れにあうといったこともあった。あまりにもショックで、自殺しようかと思いつめたぐらいだ。弱い立場の人たちのことよりも、自分のことに精一杯だった。
「善良になったって、結局は韓国人だと嫌われるじゃないか」と投げやりになっていた部分もあっただろう。勉強もおろそかに、部活も不真面目に、妹たちの面倒もおっくうになっていた。妹の習い事の発表会に行かなかったことで、母から責められても、開き直っていた。
高校一年生になると、なにもかもがうんざり、といった気持ちで日々を過ごしていたうえに、体重が増え続けていて、容姿のコンプレックスも最大にふくれあがっていた。
そのころ、3歳になった下の妹をはじめて連れて、夏休みに父の故郷に行った。日本では在日コリアンであることの葛藤は大きかったが、韓国に行ったら行ったで、いつもお客さん扱いで、そして日本人として見られることも多くて、さらに自分もいまひとつ韓国を祖国とは思えず、居心地が悪い。アイデンティティは、自分の国に帰ってさらにさまよってしまっていた。本当は、韓国に行きたくなかったが、逆らうような真似はとうていできない独裁政権は、祖国だけでなく、我が家でも同様だった。
私たち家族が故郷に行くと、親族のもてなしが次々に続く。歓迎する気持ちが汲み取れてそれはそれで嬉しいと同時に、言葉がわからずにそこにいるしんどさもあった。父がいると、会話はほぼ韓国語になった。私たち子どもに気遣うような空気はなかった。日本語のできるおじやおばがいればときにはごくまれに日本語で話しかけてくれたが、家父長制色濃い1980年代の韓国慶尚南道の田舎町では、子どもはひたすら忍耐だ。ぶすっとしていると母に叱られるので、表情にも気を遣う。
父は9人きょうだいで、そのうち半分くらいが故郷に残っていた。それぞれが結婚していて、私には、覚えきれないくらいのいとこがいて、そのうちのひとりが、家に招待してくれた。おじやおば、いとこたちの家で食事をごちそうになったのは、何度もあったが、あまり詳しく覚えていない場合が多い。けれども、このいとこの家に行ったことは、情景が頭に浮かぶくらい、鮮明に覚えている。そのとき両親はほかの家に呼ばれていて、私は妹ふたりとともに、いとこの家に行った。
いとこは成人した男性で、結婚して間もないと聞いていたから、「新婚カップル」ということに興味があった。イチャイチャしている様子が見られるのか、いや、親族の前だとそんなことはないかな、でも、親たちはいないし、と高校生の想像力を駆使し、珍しくわくわくしていた。
行ってみると、いとこは、脳性麻痺を患っていて、連れ合いの方も同様だった。まったく知らなくて驚いたけれど、感情を表に出してはいけないと戒め、ポーカーフェイスでいるように努めた。私は、脳性麻痺の人に会ったのは初めてだった。家に通されて、食卓を囲んだが、言葉も通じない。なにより、どういう態度で接するのがのぞましいのかもわからない。
日本から来た私たちをもてなそうと、いとこ夫婦は、食卓にこぼれんばかりの料理を並べてくれていた。ちょうど私の目の前には、ゆでた豚が皿に山盛りになっていた。
私は、食べることと妹たちの世話をすることに専念することにした。それ以上太るのが嫌で、食べることに恐怖すら抱いていた当時の私だったが、食べることに逃げるしか、その場を切り抜けることを思いつかなかった。8歳の妹を隣に、3歳の妹を膝の上におき、ひたすら皿にゆで豚をとって、口にしていった。8歳の妹の皿にも置いていく。3歳の妹には、小さくちぎって口に入れてやった。みっしりと肉厚のゆで豚は適度に水分もあって美味しくて、調味料をつけなくても抵抗なく食べられた。私たち三姉妹は、ゆで豚をずっと食べていた。おそらく果物なんかも食べたと思うが、ゆで豚を大量に食べたことしか覚えていない。そして、その日の晩、3歳の妹が夜中に下痢と嘔吐をもよおし、大変なことになってしまった。
私は、罰が当たったのだと思った。そして、猛省した。妹に無理をさせてしまったことが悔やまれ、もてなしてくれたいとこに対しても申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
私にとって、つまりは、障がいのある人は他者であり、あわれむ対象であったのだろう。いとこという身近な存在だったことに戸惑ったのだ。まったく、あわれむなんてどれだけ上から目線だったのか。
それからの私はさぼりがちだった教会のミサにもふたたびしっかり通うようになり、学校では、信者の生徒たちの行く「宗教合宿」といったものにまで参加するようになった。そして、妹たちのことも、もっと気にかけようと心に誓った。癌で入院していた母方の祖父の病院にもまめに看病に行くようにした。
私はつねに、自分が偽善者なのでは、という疑いを拭うことができない。なぜなら、善良になりたい動機は、私の場合、そうあることで人に好かれたい、よく見られたい、地獄に行きたくない、というきわめてエゴイスティックなものであり、親切にしたり慮ったりする対象に純粋に心を寄せているわけではないような気がしてしまうからだ。ふと、このように客観的になってしまう瞬間は、自分という存在が張りぼての偽物ではないかと、嫌になってしまう。
生まれてすぐに洗礼を受けた、いわゆる幼児洗礼の私は、カトリックの教義とともに生きてきた。その結果、毎晩寝る前の祈りの時間にその日の出来事を思い返して反省するくせがついている。また、復活祭やクリスマスの前に罪を悔い改める告解(ざんげ)をする。だから内省をする習性が身に付いている。そして、罪を犯した人、悔い改めない人は天国に行かれず、地獄に行くという考えが染み付いている。
いまは、偽善であれ、露悪よりはよっぽどいいのでは、と思えるようにはなった。結果として善であることが大事なのではないか、と。こうなるまでは、長い時間がかかったが、善良であることを斜めに見て、冷笑する空気が色濃い昨今は、ますますそう思うようになった。さまざまな気持ちの変遷があって、カトリックの信仰からは離れているが、私はいまでも、善良でありたいし、一歩進んで、自分の生きる社会が、善き、良きものであってほしいと願っている。できるかぎりで、その一助にもなりたい。
ゆで豚は、いとこの家で食べてから、長らく口にすることはなかった。そもそもあまり豚肉を食べない家庭だったのもあって、我が家の食卓では、お目にかかったことがなかった。婚家でも見なかった。だから、ゆで豚にふたたび出会ったのは、2010年代の韓国料理店だった。ゆで豚は、ポッサムという名前の料理だともそこで知った。そして、しばらくぶりに食べたゆで豚は本当に美味しかった。それ以来、韓国料理店のメニューに見つけると、つい頼んでしまう。以前、韓国の媒体にインタビューをうけたとき、韓国料理ではなにが好きですか、と訊かれ、ポッサムと答えた。
火を通して甘みが増した白菜にゆでた豚を載せ、小魚の塩辛(アミ)と辛みそをつけ、キムチを重ねて、白菜で包む。大口をあけてほおばると、思わず、んーっと声が漏れる。
ポッサムは祝いの席やおもてなしの席によく出てくるメニューである。「李の花は散っても」の取材で、李方子さんと親しかったソウル在住の金順姫さんに何度かお話をうかがった。金さんは、私が訪ねて行くと、いつも大歓迎してくれて、ソウル市内の李方子さんゆかりのホテルのレストランや、金さん自身が気に入っている飲食店に連れて行ってごちそうしてくれた。取材しているのはこちらなのに、恐縮してしまうくらいだった。若者に人気だという南山のポッサムの店にも連れて行ってもらい、牛肉のポッサム、鴨肉のポッサム、そして豚肉のポッサムをごちそうになった。金さんは自ら白菜に肉を巻いて、私の口までもってきてくれた。幼い頃母の実家に預けられていたとき、祖母がよく私の口までスプーンをもってきて食べるように促したことを思い出した。ポッサムの味が秀逸だったのもさることながら、金さんの気持ちが嬉しくて、涙がこみあげてきた。「あなた、なんで泣いているの」と金さんは笑っていた。そんな金順姫さんは、2023年4月の刊行を待たずに亡くなってしまった。
ことし10月、ヘイトスピーチをめぐる裁判に大切な友人が勝利した。その祝いの席で食べたポッサムの味は、ことさら忘れられない。私にとって最高の韓国料理店で、素晴らしい人たちとともに、極上のしつらえのポッサムをいただいた。
私は、けっして立派な人間ではない。それでも、ポッサムを見るたび食べるたび、善き人でありたい、差別のない良い社会を望もうと思い続けるだろう。

(筆者提供)
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。