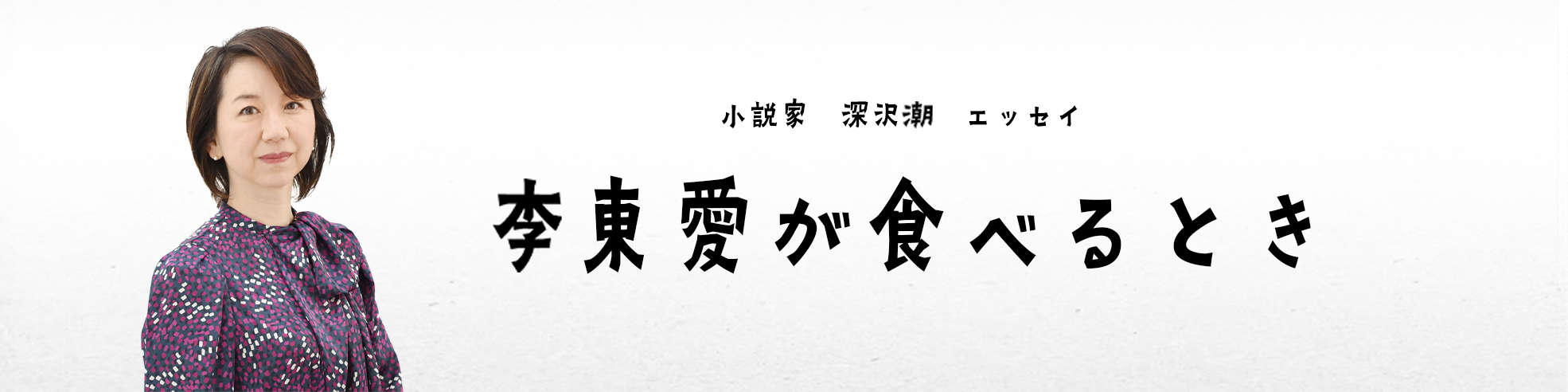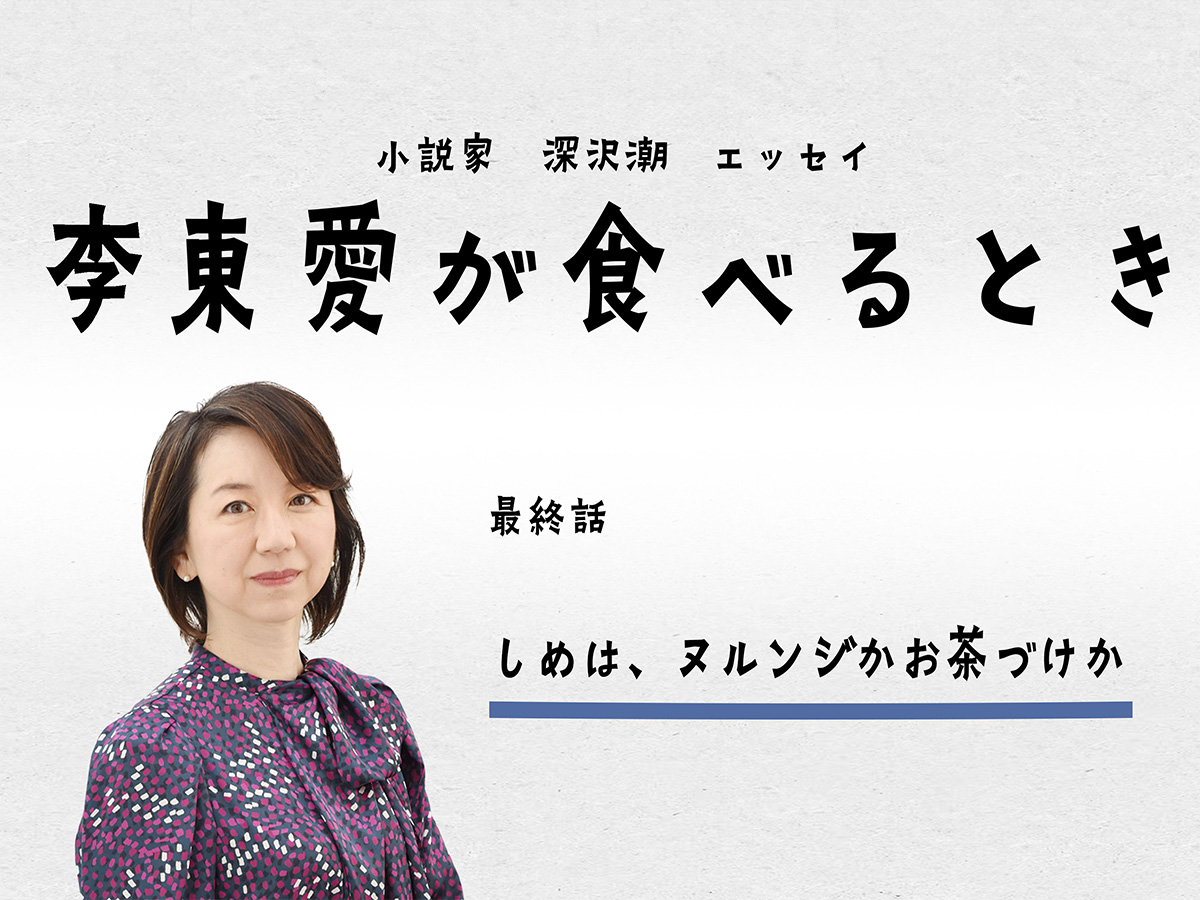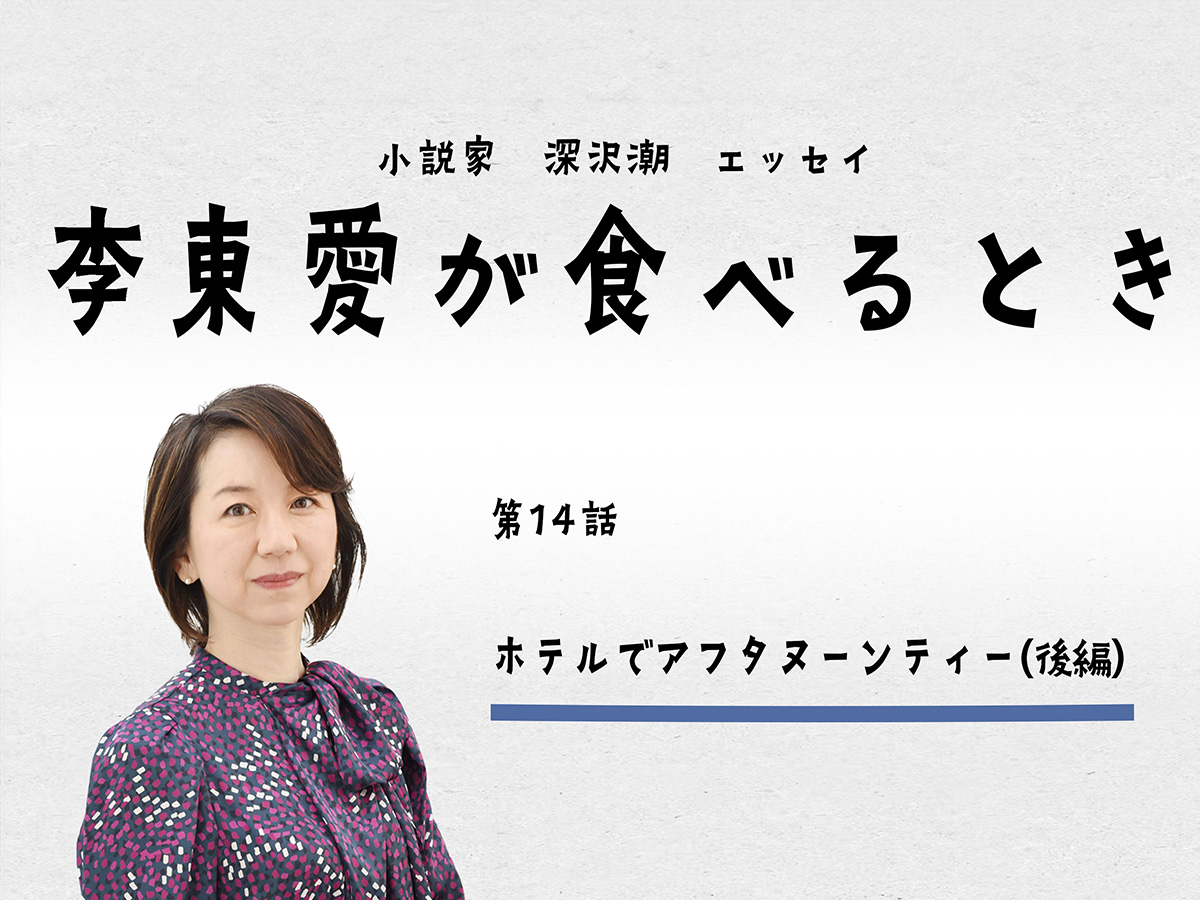第9話 ベーグルにクリームチーズたっぷりで
今年(2023年)4月にソウルに行った際、いま韓国ではどんなスイーツや食事がはやっているのかと興味津々で景福宮に近い三清洞を散策していると、ベーグルの専門店があり、入店を待つ長い列ができていた。三清洞は、若い世代も多く、韓国のファッションや食のトレンドがなんとなくつかめる場所だ。東京で言うと、表参道や青山あたりを想像していただければ近い感じだ。
ベーグルの店に並んで入ろうと思ったら、韓国の電話番号がないと順番待ちができないとのことだったので、店内で食べるのは諦めて、持ち帰りで買っていくことにした。テイクアウトは、それほど待たずにすんだのだ。店内には、生クリームがのっていたり、チョコレートコーティングを施されていたりする、装飾の美しいベーグルが豊富に展開されていた。私のイメージしていたシンプルな形のベーグルやサンドイッチになっているものもあったが、彩も華やかなベーグルの数々は、もはや、これらはベーグルと呼べるのだろうか、との疑問も抱かせる。日本のベーグル店でも、同じように感じることがある。
そういうアレンジも悪くない。食べ物がオリジナルを越えて独自に進化するのは、好ましいことだ。食が豊かになるってことだ。だから、私は、韓国で食べるトンカス(とんかつ)も、アメリカの日本食レストランで遭遇したタキビ焼き(炉端焼きのこと)も、カリフォルニアロールも、沖縄に行くたびに食べるスパムおにぎりも素晴らしいと思う。長年馴染んできた在日料理にいたっては、韓国在住の韓国人からしたら不思議に見えるものもあるが、かえってそれが愛おしくてたまらない。
食の原理主義は、偏狭なナショナリズムにもつながるし、そもそも、食べ物に国境などないのではないか。そんなことをひとりごちつつ、甘い味のベーグルに手が伸びそうになるのを、カロリー、カロリー、と自分に言い聞かせる。私は、代謝が悪くなっている年齢を考慮して、シナモンとレーズンが練り込まれた、比較的地味めの、オリジナルに近いベーグルを買った。そして、併売されているあまたのクリームチーズのなかから、これまたなんの変哲もないクリームチーズを選んだ。本当は、メープルシロップやチョコレート、きなこや抹茶の入ったものも魅力的だったのだが、こちらも胃もたれを危惧して、ぐっと我慢した。とはいえ、装飾のないシンプルなベーグルもつやつやとしていて、実に美味しそうである。明日の朝食が楽しみと、うきうきした心持ちになってくる。
店内はインスタ映え確実のしゃれたインテリアで、ロンドンのカフェをイメージしており、煉瓦の壁で、英語の文字にあふれていた。色彩豊かなトッピングのベーグルを前に、カップルが満面の笑みで写真を撮っている。幸せな空気が満ち溢れる心地のいい空間だった。次回の訪韓時にまた来てみて、イートインしてみたいと思ったが、なにしろ韓国の流行はあっという間に移り、店も数年でかわることが多いので、ふたたびソウルに来た時にこの店があるかどうかは不安だ。私は、なるべく早く再訪韓しようと誓った。食い意地というのは、人のフットワークを軽くする。
ベーグルは北米の東海岸で好まれてよく食べるもの、東欧系ユダヤ人が移住して広めたというくらいの知識しかなかったので、Wikipediaで調べてみた。抜粋を記してみる。
『小麦粉の生地をひも状にのばし、両端を合わせて輪の形にして発酵させ、茹でた後にオーブンで焼いて作られる。(中略)特性としては、通常パンの原料として使用される油脂(バターなど)、卵、牛乳を基本生地に使用していないことから、ほかの一般的な製法のパンに比べるとカロリーや脂肪分は低くタンパク質は多い』
『ベーグルは1880年代にユダヤ系ポーランド人移民によってニューヨークから広まった。1920年代までは、大規模な東欧系ユダヤ人社会のある都市を除いて、ベーグルはアメリカ合衆国内では珍しいものであったが、20世紀最後の20年ぐらいの間に、ベーグルは広く北アメリカで一般的なものになった。』
さらにWikipediaによると、日本に入ってきたのは、1990年代の終わりから2000年代のはじめにかけてだという。
私が、ベーグルという未知の食べ物に出会ったのは、1986年の春、アメリカに語学留学したときだった。つまり、まだ日本では手に入らなかった時期だ。そして、アメリカ全土にベーグルが広がり始めた頃でもある。当時、移民の食べ物だったと聞いて、コリアンルーツであり、移民のはしくれでもあった私にとっては、なにか、親しみを覚えるものであった。だが、なにより、クリームチーズをたっぷりと塗って食べたベーグルは、感激の味だった。そもそも、クリームチーズというものにもお目にかかったことがなかったので、なんだ、この悪魔のペーストは!と病みつきになったのだった。以来、私は、クリームチーズに目がない。キムチとも合わせてみたり、辛ラーメンに放り込んだり、生ハムで巻いたり、そのまま口にしたりする。つねに冷蔵庫にある食品のひとつだ。ベーグルが好きなのは、クリームチーズという存在があってこそ、とも言える。
さて、私が語学留学をしたのは、大学一年を終えた春休みだった。西海岸、サンフランシスコ近郊のオークランドの街にある、ミルズカレッジというカトリックの女子大の、English Center For International Women(ECIW)で3か月ほど学んだ。厳格な両親が留学をかろうじて許してくれたのは、カトリックの女子大付属の語学学校だったからだ。
中学生になると、欧米の音楽に夢中となり、影響をうけやすかった私は、当然のようにアメリカ文化が大好きになり、それはしばらく続き、大学生になってもアメリカ志向が強かった。部屋にバドワイザーの空き缶を並べたり、コカ・コーラのポスターを貼ったり(資本主義に染まりすぎ!)、星条旗にデザインされたノートをソニープラザ(いまはPLAZAと名称変更)で買い嬉々として使ったり、ラジオをFEN(Far East Network 米国基地の軍人向けの放送局)にチューニングして聴いていたりしていた。ハリウッドのみならず、米国の映画が公開されると、ひとりでも観に行った。バービー人形が好きで、ベティちゃんのグッズも集めていた。つまりは、いわゆる、アメリカかぶれだった。
たぶん、いまの中学生や高校生が、K-POPを好み、韓国のカルチャーに憧れたりするのも、同じような感じなのかもしれない。それともインターネットで情報が入手しやすいから、憧れとまではいかず、もっと身近な親しみだろうか。とにかく私にとって、アメリカは、情報もいまほど簡単には入って来ず、円が200円代半ばだったぐらいドル高だったというのもあって、物理的にも心理的にも遠いからこそ憧憬のまなざしが強くなったのだろう。
本場のアメリカに留学したい!と熱望していた私は、20歳(成人)の祝いなどいらないので、留学をさせてほしいと両親に懇願した。そもそも、周りの友人たちが、振袖を買うだの、母親のものを着るだのと聞くたびに、心が沈んでいた。私は振袖も着られないし、韓国籍だからどうせ区の成人式にも呼ばれないのだ、とくさってもいた。(当時は韓国籍などの外国人には住民票がなかったので、行政主催の成人式の案内は来なかった)かといって、チマチョゴリをしつらえて写真を撮るのが当然と言い放つ両親に対しても反発が強かった。日本でも韓国でもない、ましてや大好きな米国に行くのは、我ながらいいアイディアではないかと思ったのだ。
英語を学ぶ、という大義名分があったおかげと、カトリックの女子大の寮に入る、ということで、両親の許可を思いのほかすんなりともらえた私は、1986年の早春、成田空港からサンフランシスコに向けて、生まれて初めて単身で旅立ったのだった。
ここからは、日記を参照しながら続けたいと思う。当時の私は、ほぼ毎日、日記を記していて、留学中は大判のノートにびっしりと毎日の出来事をことこまかに書いていた。いま、ページをめくって読むと、自意識の過剰さと、自己肯定感の低さと、体重の増減について(つまりは太る、太らないについて)、さらには強烈なルッキズムとあまりの恋愛至上主義的価値観に染まっていることがつらつらと書かれている。「いや、ちょっとこれは」と19歳の自分にいろいろとツッコミを入れたくなるが、いったん、そこはスルーして、話を進めよう。
往路はロサンゼルスまで行き、サンフランシスコまでは国内線に乗り換えて行くということになっていたのだが、ロサンゼルスからサンフランシスコまでの国内便が欠航してしまい、途方に暮れてしまった。飛行機会社のカウンターに行ったが、社員が話す英語が早すぎてちんぷんかんぷんで、泣きそうになってしまう。それを見たひとりの社員が、私のパスポートが韓国のパスポートだということで、韓国語のわかる社員(おそらくコリア系アメリカ人)を呼んでくれたが、私は韓国語もまったくわからない。片言の英語で、日本に住んでいて、日本語しかわからない、と説明しても、要領を得ない。しまいには、韓国人なのに、なんで韓国語がわからないのかと、ゆっくりとした英語の詰問調(と感じただけかもしれないが)で言われた。弱り目に祟り目とはこういうことを言うのだろう。とうとう私はロサンゼルスの空港で、大粒の涙を流して泣いてしまった。
すると、たまたまカウンターにいた、日本の旅行会社のツアーガイドの人が、私に話しかけてくれた。ひっくひっくと泣き声交じりで事情を日本語で説明したら、その人が流暢な英語でカウンターの人にかけあい、私の手続きを助けてくれた。30代前後の男性だった。お礼をほとんど言う間もなく、彼は急いで立ち去ってしまったが、本当にありがたかった。風貌は覚えていないが、私にとって、あの人は、生涯忘れられない素敵なひとである。
サンフランシスコ空港で乗ったタクシー運転手さんも親切で(ガイドブックにタクシーに注意と書かれていたので、ぼられるかとびくびくしていた)なんとかミルズカレッジに到着した。寮は、ミルズカレッジの学部生や院生と一緒で、私の隣の部屋は、台湾からの留学生だった。挨拶だけで話はしなかったが、笑顔だったので、ほっとした。しかし、そこは、日本の家屋と違い間接照明しかなく、おまけに古い建物で、ひとり部屋で荷物を解いていると、むしょうに心細くなってきた。
シャワーでも浴びようとバスルームに行くと、男性がシャワー室から素っ裸で出てきてぎょっとした。
ここは、女子大ではなかったか?
なぜ男性が?
その後すぐにタオル一枚きりの女性も出てきた。あとから、男性の寮への出入りが特に禁じられていないことや、学内の寮には、男女混合の寮もあり、近くにあるUCバークレーの学生も住んでいると聞いて、かなり驚いた。男女交際を禁じていた私の両親が、女子大だから安心と思っていたことが滑稽に思えた。ミルズとバークレーの間には毎日シャトルバスが行き来していたのだ。
シャワーを終えて部屋に戻り、日記を書き始めたら、ノックがあった。もしかして、さっき会った隣の部屋の台湾人だろうかとドアを開けると、おそらく同世代くらいの色白のアジア人の女の子が笑みを浮かべて立っていて、私の手を握り、勢いのある韓国語で話しかけてきた。何を言っているかまったくわからないが、相手が興奮気味なのは伝わってきた。
私は、気圧されつつも、話が途切れた合間で、おそるおそる英語で、「韓国語が喋れない。日本に住んでいるから」と言った。すると、彼女の顔色がさっと変わって、振り切るように手を放すと、踵を返して行ってしまった。
その日の夜は、フライトの疲れや時差もあったが、ロサンゼルス空港での出来事や部屋に訪ねてきた韓国人の女の子のことが頭から離れず、ほとんど眠れなかった。
翌日、ECIWの登録をした。ここでは、移民してきた女性や難民女性への英語教育を州から依頼されて請け負っていたので、南米や中東など出身のさまざまな年齢層の女性がいた。だが、なんといっても多数派は日本人だった。現在アメリカの語学学校や大学では、圧倒的に中国人留学生が多く、日本人は少ないが、当時は、どこに行っても日本人がごろごろといた。
私は、日本人の学生たちと話せて、心からほっとした。ミルズカレッジに進学希望の人もいたし、結婚前に念願の留学に来た人もいた。また、台湾ルーツだが日本国籍を持っているという人もいた。彼女は大学院を受けると言っていた。日本のパスポートだが、名前は中華式で、その事実に、世間知らずだった私は驚いた。日本国籍なのに、日本っぽい名前じゃなくていいのか?と。すると、彼女は、台湾のルーツは大事にしているが、政情が不安定だから、日本国籍をとった、と答えた。そして、彼女の妹が宝塚音楽学校にいることも教えてくれた。将来の芸能活動の便宜上、日本国籍がいいのではという判断もあったという。
少し年上のその彼女とは、留学中、在日、ということで通じる感情もあって、親しく付き合った。彼女は世間知らずの私にいろんなことを教えてくれた。
私は、自然と日本人(厳密に言うと日本のパスポートを持つ人たち)とつるむようになった。ほかの日本人の学生は同じ寮で、私だけ違う寮だったのは、韓国のパスポートだからだったらしいが、スタッフに頼んで、寮も日本人の学生と一緒にしてもらった。彼女たちは、在日コリアンである私の事情に踏みこんでくる人もおらず、一緒にいて楽だった。
前の晩に私の部屋を訪ねた女の子は、大学、大学院、ECIWを通じて学内でたったひとりの韓国人で、以前からECIWにいる学生だとスタッフが教えてくれた。「彼女、韓国人が来るのをとても楽しみにしていたのよ。部屋番号を教えたけど、もう話した?」と訊かれ、はい、と小声で答えるしかなかった。その後、彼女とは、クラスが一緒になったのだが、目も合わせてくれず、避けられていた。一度だけ、勇気を奮い起こし話しかけたのだが、見事なまでに無視された。あとから、私が在日コリアンだったことにがっかりしたと言っていたと人づてに聞いて、ああ、私は人からがっかりされる存在なのかと落ち込んだ。
ただ、避けられていたのは、がっかりしたからだけではなく、1986年、民主化前の韓国人にとって、在日コリアンと接することは禁忌だったのかもしれないと、いまでは理解できる。旅行の自由化もまだだった時代にアメリカに留学が許可されたぐらいだから、彼女は、いいところのお嬢さんで、当然のように全斗煥政権を支持している家柄だったのかもしれないとも思う。政権を支持していなくとも、当時の韓国人が得体のしれない在日コリアンと親しくなろうなんて思わないだろう。言葉もしゃべれない、日本人と変わらない似非韓国人だった私なんかと……。
いけない、いけない。自分を卑下するのは、やめておこう。
在日コリアンのことをよくわかっていなかったということだってある。
考えてみると、ミンジンリーさんの「パチンコ」という小説がベストセラーになり、ドラマがヒットしたことで、zainichiという単語とその存在が、全米、全世界に知られたことはとても画期的で素晴らしいことだ。当時は、在日コリアン、それなに?という反応ばかりだった。
留学中、学生食堂で出会ったベーグルにすっかり恋した私は、毎朝、クリームチーズをたっぷりと塗って、サーモンやベーコンとともに、ベーグルを食べていた。ある日は、レーズンベーグルを3つも食べたと日記にある。言わずもがな、帰国する頃には、体重がどーんと増えていた。
食事はあまり美味しかったという記憶はないが、ベーグルに出会えたことと、しょっちゅうUCバークレーに遊びに行って、キャンパス内でフローズンヨーグルトを食べたことは、忘れられない。また、いくつか映画も観に行ったことを覚えている。字幕がなくてわからなかったけれど、楽しい思い出だ。
そのうち、生活に慣れてくると、余裕ができて、だんだんと日本人以外のクラスメートとも親しくなっていた。増えたのは、体重だけでなく、友人も、である。レバノン出身の女性や、コロンビアから来た女性、スタッフとして手伝ってくれたミルズの学部生のラテン系アメリカ人とも仲良くなった。マジョリティだった白人女性とは、ほとんど接することがなかったことは、アメリカ留学!と舞い上がって、白人の友人ができることしか想像していなかった私に、現実を思い知らせてくれた。そして、そのおかげで、自分がうっすらと差別的な考えを持っていたことにも気づいたのだ。名誉白人的な振る舞いと言えよう。
留学中、誘われてバークレーのアジア系学生主催のダンスパーティに何度か行ったが、帰国直前の日記には、「ダンスパーティなんてどこの国も同じようなもの。根本的にあまり好きじゃない」と書かれている。そう、バブルまっさかりのDisco全盛時代だったから、日本でも学生主催のダンスパーティはよくあったが、私は、そんな空気が苦手だった。日記には、「どうせ私はダサくて誰も相手にしてくれないし」とあるが、いやいや、別に、それでいいんだよ、とあの頃の自分に言ってあげたい。卑屈なその考え方がよくないよ、と。ダンスパーティーなのだから、楽しく踊っているだけでもいいじゃないと。それに、もともとダンスは苦手だったのだから、このツッコミも意味がない。ダンスパーティは、もちろん、出会いが目的という部分も大きいだろうが(当時はそれがほとんど目的だっただろうが)、それにしてもあまりにも男性からの視線を気にしすぎている。とにかく私はかなり暗かったし、ネガティブ思考の塊だった。だから日記は痛々しくて、精読はつらいぐらいだ。
そんな私も、アメリカに行ったことで、価値観の多様さに触れて、自分の見識も少しは広がったような気がする。在米中、レーガン政権はリビアに対して戦争を始め、ECIWのクラスではそのことについてディスカッションもした。アメリカは、他国に対して戦争を始める国なのだ、ということに、私は、自分がアメリカに対して良いことばかりを見ようとする色眼鏡を持っていたことに気づいた。オークランドという場所が、ミルズカレッジの門の外を出ると黒人の住む街だったこともあって、貧富の差、人種差別などを、肌で感じたことも大きい。大学では留学生以外の学生や教員は白人が多いのに、学内の清掃の人、市内のタクシー運転手はほぼ黒人だった。黒人は危ない、と堂々と言い放つ教員もいた。
一方、ジェンダーに関して、同性愛についての意識などは、ミルズカレッジはかなり進んでいたように思う。学内で、女学生同士が抱き合い、熱烈にキスをしている姿を見て、そして周りの人が自然にそのことを受け入れているのを見て、私はレズビアンに関する授業を大学で聴講させてもらった。LGBTQという言葉は知らなかった(なかった)けれど、中学、高校と女子校であったこともあって、異性愛だけが標準でないこと、感情の自由はある、ということは感覚的には理解していたが、難解な授業ながら、聴講したことによって、同性愛について、特別なもの、という意識はなくなった。もっと学びたくて、購買部でレズビアンについて社会学的に分析した本も買った。だけど、日本に戻ったら、日々の生活に忙しく、いつの間にか本棚の飾りになってしまった。あの本はいまどこにあるのだろう。あらためて読んでみたい。
3か月アメリカで寮生活をしてみて、それまで自分が世界一不幸だ、ぐらいに感じていたが、自分がいかに恵まれているかを悟った。難民として命からがら逃げてきたレバノン出身の女性は、子どもを母国に置いてきたと言っていた。カリフォルニア州だったこともあって、日本人以外のアジア人も多く、サンフランシスコの中華街にもよく行った。国境を越えた人びとは沢山いる。異国でたくましく生きるひとびとに、自分の祖父母や両親の姿が重なった。
チャイナタウンを歩いていると、緊張感がゆるむ。オークランドからサンフランシスコまでのバスに自分たちしかアジア人が乗っていなかったこともあり、同じような風貌のアジア人に紛れるとほっとした。ああ、私はアジア人なのだな、と楽になった。日本にいるときは通称名で暮していたから、パスポートと同じ本名でいることの解放感もかなりあった。アメリカで得た、この、日本人も中国人も韓国人もアジア人である、という感覚は、在日コリアンということに葛藤していた私には、大きな気づきだった。
日本に戻って、あのベーグルがまた食べたい、と何度か思ったが、いつの間にかベーグルの存在自体を忘れていた。しかし、それこそ、私が子育て真っ最中に、日本にベーグルが上陸した。私は喜び勇んで、ベビーカーを押して、近所に出来たベーグル店に入って行った。長男が幼稚園に行っている間で、まだ2歳に満たない娘と一緒だった。たまたま娘はすやすやと眠っていたし、店はベビーカーの子連れにやさしかった。
プレーンベーグルにクリームチーズを塗って口に入れると、ベーグルのほのかな甘みと、チーズの塩みが絶妙だった。すっかり忘れていたアメリカ留学の日々を思い出して、しばし、物思いにふけった。娘のやすらかな寝顔を眺めて、この子や長男にはアイデンティティに悩むことのない人生を歩んでほしい、そして、何人、ということにこだわらずに生きていける環境を与えたいと思った。幸い子どもたちは、アメリカ留学の機会を得て、さまざまな経験をすることで、属性に拘泥しない価値観を持つことができた。
昨年(2022年)、エブリシング・エブリウェア・オールアットワンスという映画を娘と観に行った。アカデミー作品賞をとったこの中国系移民の家族の物語は、エンタメ色が強いが、底辺には、母娘の葛藤も描かれている。母娘は永遠に闘うということも、映画のなかで暗示されていたように思った。母娘二人暮らしの私たちには身に染みるメッセージだった。もりだくさんの表象がつめこまれた映画では、複雑性の象徴として、黒いベーグルが出てきて、そのメタファーも、私と娘に強烈に響いた。黒々とした姿で回り続けるベーグルは、この世界の混沌を表しているような気がしたのだ。
ユダヤ系移民によって広まったベーグル。ゆえに、黒いベーグルは、ユダヤの国として在るイスラエルが戦争をしている現実を予言したかのように、いまとなっては思えるのは、考えすぎだろうか。

(筆者提供)
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。