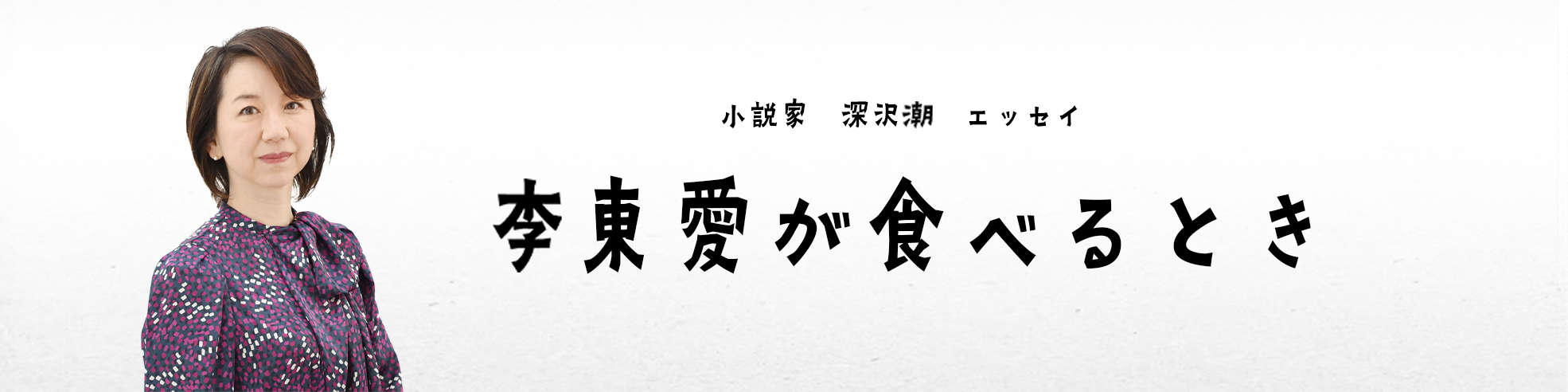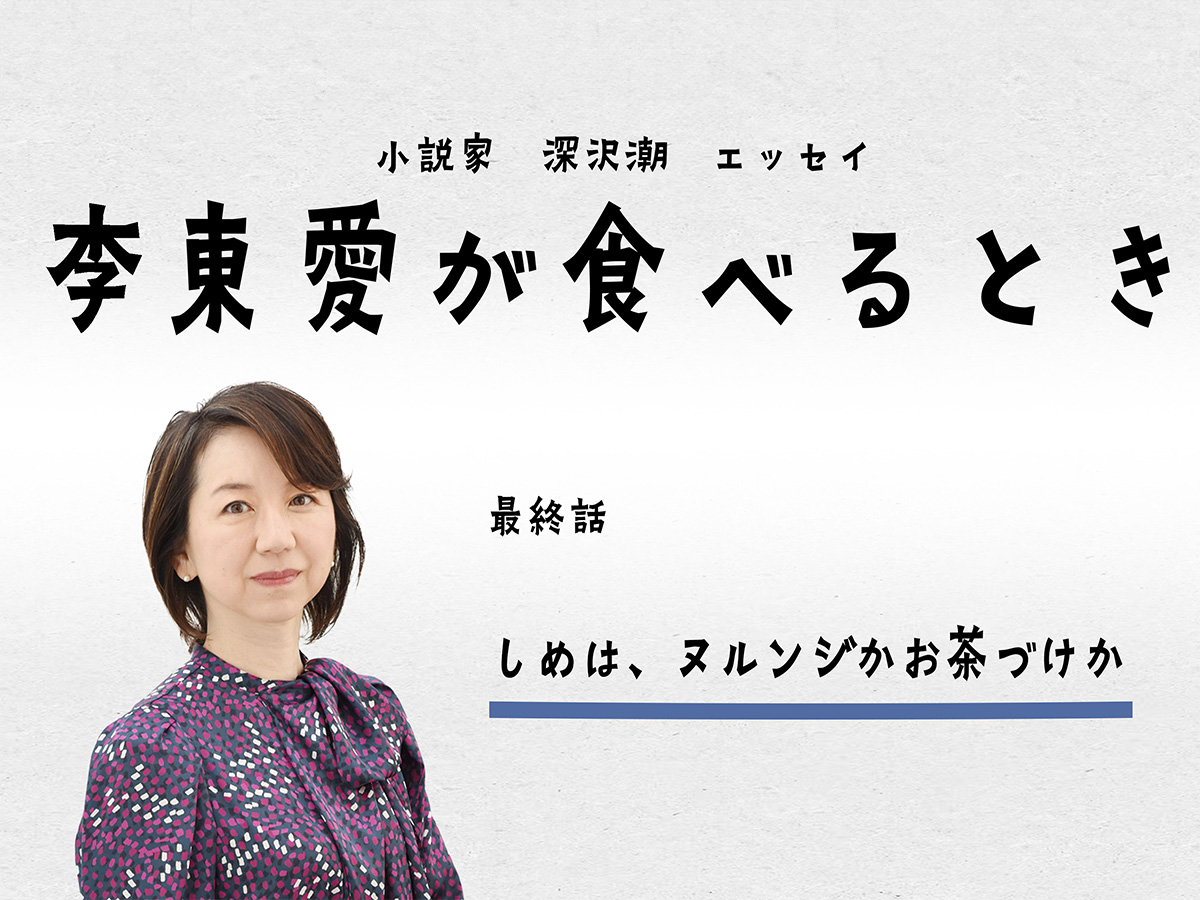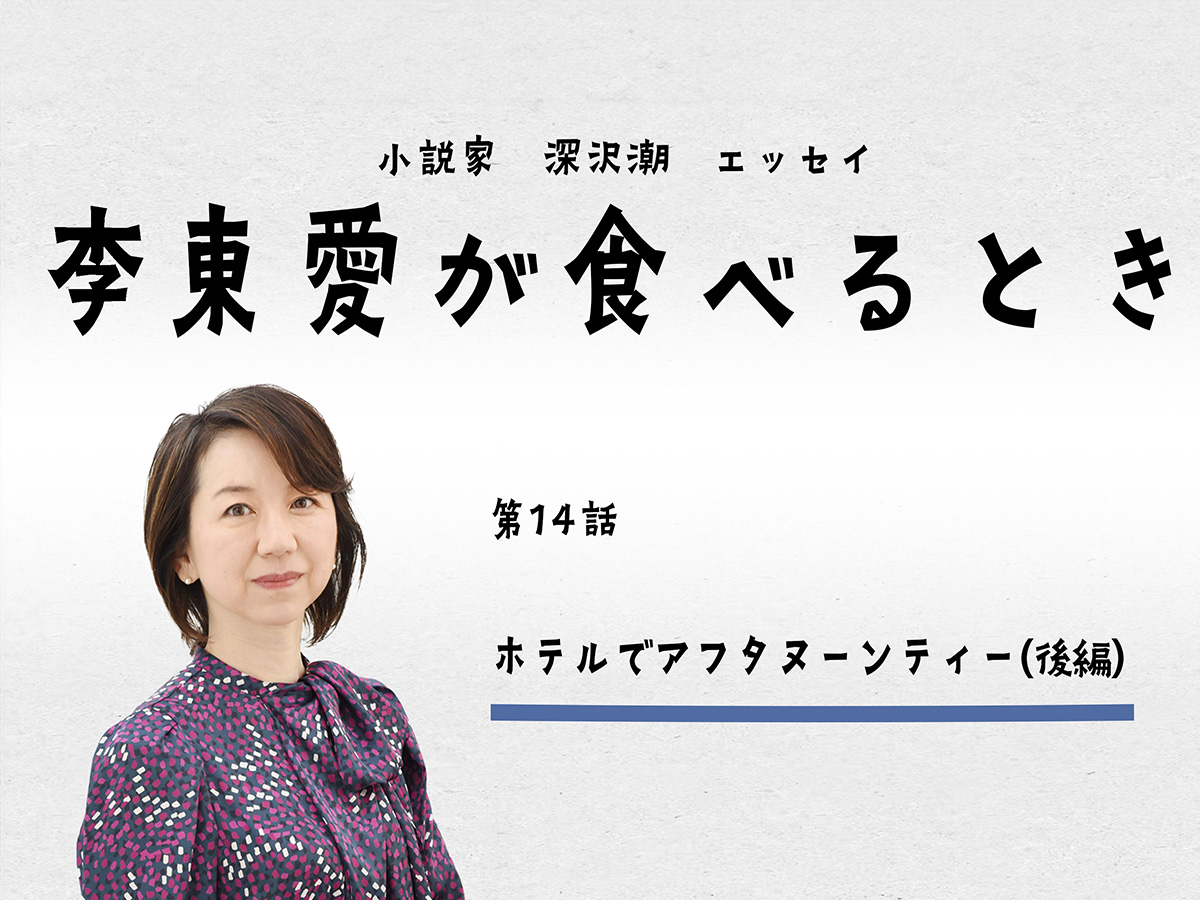第10話 手作り、のチョコレート
2月14日のバレンタインデーが近づくと、高級なものから手軽な感じのものまで、さまざまなチョコレートが店頭に並ぶ。そして、世間が、そわそわした空気を醸し出す。スイーツのなかではチョコレートがかなり好きな私も、この時期は、なんとなく浮かれた気分になる。商業主義に振り回されているといえばそれまでだが、華やかな商品展開が嫌いではない。ふだん、それほどなじみのないような種類のもの、たとえば、ルビーチョコレートや、オーガニック、フェアトレードのチョコレート、輸入ものの銘柄も多く目にすることができて、工夫を凝らした売り場やショーウィンドウを見ているだけでも楽しい。バッケージも可愛かったり美しかったり、思わず手にしたくなる。
だが、バレンタインデーに向けたチョコレート商戦を、こんなふうに穏やかに微笑ましく眺められるようになるまでには、長い時間がかかった。ものごころついた頃から、バレンタインデーというのが一大イベントで、しかも、男性が女性にアプローチするべきという考えが主流であったなか(特に昭和では)、その日は特別に「女性が男性に愛情を表現する日」で、「気持ちを託してチョコレートを贈る」ということがのぞましく、特別な行為として頭に刷り込まれていた。好きな男の子がいる、というのが女の子として自然なことで、バレンタインデーは女性から男性への告白の機会だったり、カップルだったら愛情の確認だったり、という認識だった。それゆえに、好きな人もいない、恋人もいない、失恋後、などは、バレンタインデーに寂しい気持ちを味わわざるを得ず、幸せそうなカップルを恨めしく思うことさえあった。
今でこそ私はバレンタインデーをむやみに男女の関係と結び付けなくなった。だが、つい最近まで、もしかしたら現在でも、世間ではそういう風潮は根強く残っていて、女性の心がざわつくだけでなく、バレンタインデーにチョコレートをもらえる見込みがない男性が、女性への嫌悪を募らせてしまうようなおかしな事態まで生じてしまっている。
つくられてしまった仕組みや価値観がおかしいのに、恨みつらみが直接的に向かうのは、女性の属性を持った人へというのがまさにミソジニー(女性嫌悪)の実態だ。ミソジニーについて考えるとき、韓国において、男子のみに兵役があることで、男性が女性を恨む、といったことが思い浮かんでしまう。2021年に日本で起こった、小田急線内での女性への無差別傷害事件も思い出される。ミソジニーによって起こった事件は、韓国でも2016年、江南で殺人事件があった。韓国でのMe Too運動、そしてフェミニズムが盛り上がるきっかけとなった事件だが、2024年現在、韓国のフェミニズムはバックラッシュがすさまじいようだ。声をあげることが恐ろしく、委縮してしまうといった事態が起きている。声をあげることで、おそろしいほど攻撃にあうという現象は、日本も同様で、そういう点では、日本と韓国は、あまりにも似すぎている。
恋愛至上主義的価値観および、異性からモテることが素晴らしいことという考え方は、そこから零れ落ちる人たちの呪詛を募らせ、男女だけでなく、同性同士でも、分断を生じさせてしまう。そして、交際や恋愛が女性と男性という二元論でしかいまだ語られにくく、さらには、恋愛そのものに関心のない人たちの声は届きにくい現実がある。エンタメにおいてBL作品などは増えたが、恋愛ありきのままの描写が多いし、LGBTQやアロマンティック(恋愛感情を抱かない)のことを描いてはいても、消費の域にとどまってしまっているように思う。少しずつ変わってきているとはいえ、日本や韓国のような家父長制が根強い社会においての恋愛至上主義や異性からのモテ礼賛は、恋愛の先に続くと刷り込まれた結婚への重圧を生じさせ続け、少子化を恋愛や結婚に安易に結び付ける風潮につながってしまう。もちろん、恋愛というプロセスを抜きに、マッチングアプリなどの出会いで(もちろん、マッチングアプリの出会いから恋愛というものもあるけれど)条件から入る結婚というパターンも増えている。いや、恋愛にしろ、結婚にしろ、スペックや条件というのは、多かれ少なかれついてくる。相性があう、ということは、価値観があうということで、その価値観のなかには、スペックや条件が作用する部分も大きいだろう。人を好きになったり、交際をしたりすること、結婚することについてだって、グラデーションがあり、多様なはずだ。簡単に定義できることではない。
いずれにせよ、結婚という制度(や恋愛)を過剰に肯定的に、幸せのひな型とするまなざしは、いまだに強い。
昨今の韓国の若い女性たちが、男性との交際を望まず、結婚も出産もごめん被りたいと思ってしまうのも当然だろうと思う。結婚や出産でキャリアが中断されてしまう、といった問題も含んでいるが、そもそも、結婚や出産によって女性の方により多くの負荷がかかる事実は、なかなか変わらない。それなのに、社会的に精神的に結婚を強いられてしまうのだから、たまったものではないだろう。結婚や恋愛を望む人がいてもいい、そうでない人もいていい、といった世の中には、日韓共に、まだまだ程遠いと感じる。両国とも独身女性が国外に移住を望みがちだというのも、うなずける話だ。
これまでの語りのように、多様な人の在り方、生き方を肯定したいし、社会がそうあるべきと考えている私だが、かつては、恋愛というものが、人生のうちで、かなり上位価値をしめていた。ロマンティック症候群という言葉も当てはまる。つまり、長いこと、恋愛至上主義であった。私の世代では、珍しくないことで、今でもそういう考え方が根強い人も少なくない。また、若い人でも、恋愛至上主義は一般的とさえいえるし、エンタメ作品などでも恋愛のエピソードが中心であったり、話の本筋に関係ないのに無理に恋愛要素を入れたりするようなものも少なくない。
それでも、恋愛がすべてという人は減ったと思う。私がこれまで描いた小説、「伴侶の偏差値」や「アグアをさがして」は、恋愛至上主義の女性が呪縛から解放される話だが、「なんでここまで男性との交際ばかり」という感想もあるので、変化は着実に訪れている。自分が書いた小説は、深層心理が出てしまうので、男性に振り回される主体性のない女性が出てくるのは、ある意味、過去の私の写し鏡のようなものだ。
もう一つ加えれば、私にとって恋愛というのは、つねに相手に尽くすことで成り立っていた。それについては、のちほど詳しく書く。
バレンタインデーに初めてチョコレートを男の子に渡したのは、小学校3年生のときだ。そして、その渡した相手が、いわゆる初恋の相手でもある。S君は足が速くて、明るい男の子だった。左利きだったことを覚えている。家も近くて、集団下校の際、同じグループだったことが嬉しかった。チョコレートを販売する菓子メーカーがバレンタインデーに注ぐエネルギーは並々ならぬもので、CMでもバレンタインデーの告白を煽っていたように記憶している。その影響と、ませた同級生の助言もあって、私は初恋の男の子の家のポストに、バレンタインデー当日の夕方、不二家のハートチョコレートを入れた。赤いパッケージでハートの形をした、昭和の人にはおなじみの50円のアレである。毎月のお小遣いはたぶん300円くらいだったから、値段的にも妥当だった。一週間前ぐらいに、近くのスーパーマーケットで買った。
直接渡す勇気がなかったので、家の前まで行き、まわりに人がいないのを見計らって、大慌てでポストに入れたのだが、愚かな私は、自分の名前をどこかに記すことはせずに、包装もせずにチョコレートを乱暴に放り込んだのだった。
3年生のバレンタインデーのころは、姉を亡くした半年ほどあとで、姉にまつわること以外は、そのころの強烈な記憶はバレンタインデーのことぐらいだ。それぐらい、私にとっては、大きな出来事だったのだろう。
翌日、学校で、割れたハートのチョコレートが郵便受けに入っていた、とS君がみんなに話していて、私はいまさら名乗り出ることもできずに、黙っていた。S君のことは、その後もずっと気になっていて、いよいよ卒業間近の6年生の3月に、思い出のサイン帳に記入してもらう時、「文通がしたい」と、勇気を振り絞って言った。しかし、あっさりと断られてしまった。学校も別々になり、私の淡い、幼い恋はこうして終わりを告げた。自分は否定される、受け入れられないという思いはしんどかったし、しばらくひきずった。3分間スピーチで自分が韓国人だと表明したあとだったから、それが原因だろうかと考えてしまったが、そもそも性格に難があったから当然と納得した。
次に、バレンタインデーにチョコレートを渡したのは、翌年だ。中学から私立の女子校に進学した私には、憧れの先輩というのができて、中学1年のころは、とにかくその先輩が大好きだった。卓球部の2学年上のFさんだ。運動部において、1年生にとっての3年生は(もちろん、どの学年の先輩も)、無条件に敬うべき存在で、廊下ですれ違うと、その場で立ち止まり、首を垂れて挨拶をしなければならない存在だった。中高一貫校だったので、高校2年生(高校3年生は大学受験に専念するため引退)にいたっては、雲の上の存在だった。怖い先輩も多い中、Fさんは、優しく、暖かい感じの人で、よく話しかけてくれた。親しみやすいけれど、卓球はとてもうまかった。だから、私は、Fさんにぞっこんだった。2学年上というのが、姉との学年差と同じだったから、もしかしたら姉のような存在を猛烈に欲していたという可能性もある。
私はFさんに贈るために、お菓子作りの雑誌を買ってきて、手作りの原料になるチョコレートであるクーベルチュールをわざわざアメ横まで行って手に入れた。試作を含めて、3日間くらい奮闘して、バレンタインデー直前には、ハート型のチョコレートが出来上がった。我が家のキッチンは母の独壇場だったが、チョコレートを友達と交換する、と言うと、母は快くキッチンを使わせてくれた。試作を食してみると、市販のものの方が美味しいような気もしたが、手作りが大事、と心の中で唱えた。すでに手作りへの幻想が芽生えていたのだと思う。
バレンタインデー当日だったのか、日付はいまとなっては定かではないが、私は、卓球部の練習を終えた帰り道、駅までの短いあいだに、先輩を呼び止め、チョコレートを渡した。サンリオで買ったカードも添えた。カードには、「交換日記をしてください」と書いた。当時、親しい友人や先輩との交換日記がはやっていたのだ。
先輩は、ちょっと恥ずかしそうに受け取ってくれて、交換日記にも承諾してくれた。私はさっそく渋谷のバラエティショップ(フルーツ店の雑貨屋の西村)に行って、ノートを探した。そして、ちょっと高いけれど、色味の綺麗な小ぶりのノートを見つけ、お小遣いで購入した。帰宅するとすぐに、自分の分の日記を記し始めた。まずは自己紹介を改めてした。小学校の卒業のときのサイン帳と同じようなことを書くと、次は何を書いていいのかわからなくなり、卓球の技術向上に関する質問などを連ねていった。そして、部活終わりにそのノートをFさんに渡すと、一週間ぐらいでノートが帰ってきた。中身はほとんど卓球の話だった。
その交換日記が続いたのは、おそらく三ヶ月くらいで、先輩からノートが戻って来なくて、終了となった。私は、1年生のなかで卓球がうまい方でもなかったから、あまり好かれていないのだろうと理解したけれど、あとから、Fさんが、卓球部にコーチとしてきていた大学生(男性)を好きだという噂を聞いて、私の行為はFさんに迷惑だったのだな、と悟った。こちらは気まずかったけれど、Fさんは交換日記のことなどなかったかのようにそれまでと同じく優しかったことが、かえって私の自尊心を削った。
それでも、卓球部のクラブ活動は、中学生の間は、わりとまじめに取り組んだ。しかし、Fさんの学年が引退し、高校生になると私自身が校外の男子に興味を持ち始めたり、友人と学校をさぼったりするようになり、卓球部をやめてしまった。私の通った学校において、運動部にいることがヒエラルキーの上位にいられることでもあって、それほど卓球が好きでもないのに、「属する集団の選択」を理由に卓球部に復帰したりもした。親しくなったグループに、私が韓国人だと知られて仲間はずれになったこともあって、自分の居場所を探していたのだ。戻ったものの、最後までレギュラーになることもなく、不真面目でへたくそな部員だった私は後輩にも侮られ、嫌な思いをずいぶんとした。まあ、今思うと、自業自得だ。とはいえ、自分たちのための「卒業生を送る会」で、後輩が私の卓球プレイのまねを面白おかしくおちょくって披露したときには、たいへん傷ついた。
卓球部では、先輩として、いや、部員としては最低だった私だが、高校2年のとき、後輩からバレンタインデーにチョコレートをもらったことが一度だけある。卓球部の後輩ではないことは確かだが、誰からもらったのか、その後、自分がどういう反応をしたのか、まったく思い出せない、けれども、ものすごくうれしかったと同時に、なぜ私に、と不思議だったことは覚えている。バレンタインデーの仕掛けをしたと言われる、メリーというブランドのチョコレートだった。ゴディバなどの輸入チョコレートはまだ容易に手に入らないころ、メリーはじゅうぶんに高級な、というか、特別な感じがあった。
高校1年のやさぐれていたとき、通学で利用する山手線に、ちょっと気になる男の子がいた。髪が長めで、軽くパーマをかけていて、当時のアイドル、竹本孝之に似ていた。私は、そのころ、竹本孝之のファンで、厳しい母の目を盗んで、友人の名義でファンクラブに入っているほどだった。同級生たちも、当時なんらかのアイドルに夢中になっている子たちがいて、しかも、クラスや学年でイケている(と私が思っていた)グループの子がアイドルの追っかけなどをしていたことにも影響されていた。アイドルを好きになることが、ださくて暗い自分の価値があがる要素のひとつのように思っていた節もある。そうしたよこしまなきっかけもありつつ、私が見つけたのは竹本孝之というアイドルで、実際、知り始めて好きになると、まさに沼に落ちるように夢中になっていった。推し、という言葉は存在しなかったが、アイドルを好きになることが、こんなに楽しいのか、と気づかされた。西城秀樹はずっと好きだったけれど、動向をおっかけたり、コンサートやファンの集いに行ったりするという発想はまったくなかったし、そのころにはすでに、秀樹が好き、ということすら忘れそうになっていた。だから、いまでいう推し活はすごく楽しかったし、当時の鬱々とした日々のなかで、生きる糧でもあったように思う。
ファンクラブの会報誌に「石鹸の匂いのする女の子が好き」と書いてあったので、一日に二回、朝晩シャワーを浴び、「習字が得意」と知って、自分も以前習っていた習字教室にふたたび通い始める、といったようなことをするぐらいだった。そして私は、電車の中の彼を、完全に竹本孝之と重ね合わせていた。
バレンタインデーは、勝負の日だった。
私はここでも、手作りチョコレートを選択した。もちろん、本物の竹本孝之の事務所にも同じものを贈った。作ったのは、クッキーにチョコレートをコーティングしたものだ。私は、そのころ、手作り菓子が好きで、non-noの製菓本をもとに、親しくなった友人の誕生日にシュークリームを作って渡したりしていた。気持ちを込めて、凝って白鳥の形にしたが、渡したとたん友人はひっくり返して持って帰ったので、ぐちゃぐちゃになり、悲しかった。私の気合と裏腹に、友人はあまり喜ばなかった。友人に対しても、こちらの気持ちが報われることはあまりなかったが、今思うと、すべてが重すぎる。
さて、チョコレートクッキー作り。妹たちに試作したパウンドケーキを食べさせたりもしていたので、私がチョコレートクッキーを作っていても、母は寛容だった。材料費を出してくれるぐらいだった。手作りが素晴らしいという価値観を強く持つ母は、私の作ったクッキーを自慢げに来客に振舞っていたりもした。
バレンタインデー当日の朝、乗り換えの代々木駅に到着する寸前に、気になっている男の子にチョコレートクッキーを押し付けて、逃げるように山手線から下りた。手紙を添えるか悩んだが、止めておいた。家の電話は親に管理されていたから連絡先も書けないし、どうせ毎朝同じ電車に乗るのだから、翌日に言葉でなにか伝えればいい、と思ったのだった。その当時親しくしていた友人のアドバイスもあって、ある意味煽られて、バレンタインデーに手作りチョコレートクッキーを渡したわけだが、結果は、端的に言って、失敗だった。
翌日、彼はいつもの車両にはおらず、その後、数日間ほかの車両に行ってみても、時間を早めてみても姿は見えなかった。まあ、そりゃそうだろうな、と思った。ニキビだらけで、太っていて(と自分では気にしていた)だっさい(自信がなかった)、身も知らない女の子に、突然チョコレートを渡されても、迷惑だろう。しかも、たくさんの人が乗っている電車の中で、押し付けられたのだから。
彼とは二度と合うことがなかった。
振り返ってみると、自己肯定感が低いわりには、積極的に男子にアプローチをしていた。その後も、憶えている限りにおいて、自分から好きになった人としか交際したくない、告白する、振られるとくりかえし、つまりは、片思いばかりの経験を積んでいく。数少ない、好きになってくれる人に目を向けようとは思わなかった。バレンタインデーにチョコレートを贈ったのは、その後も何人か思い当たるし、手作りセーターを渡すようなこともしたが、実らなかった。だから、私が初めて恋人と呼べる人ときちんと交際したのは、大学4年生になったときだ。このときは、自分から積極的にアプローチしたわけでもなく、友人から恋人へ、と進んだのだが、それも短い期間だった。けれども、楽しい思い出もそれなりにある。とはいえ、一貫して、相手に合わせすぎて、負担に思われていたのではないだろうか。当時、村上春樹の小説を読んだのも、アニエスベーのスナップカーディガンや、St.Jamesのボーダーカットソーを着るようになったのも、彼の影響だった。若いというのは、そういうことでもあるのだが、「こういう服を着る子がいい」との要望をそのまま受け入れていた。「長い髪の子がいい」と言うから、髪も伸ばした。母親が買ってきた服を着ていた私が、少し変わったきっかけににもなったから、そんなに嫌な思い出ではないし、結果としてダサさから抜け出せたからよかったけれど、こちらから、こういうふうにして、と言ったことはなかったから、やはり非対称だったと思う。呼ばれればすぐに駆け付け、予定も彼を最優先、というのが当然という感じであった。
社会人になったのは、平成元年で、世の中では、バブル全盛期であると同時に、バレンタインデーにおける義理チョコがさかんだったころだ。高級チョコレートも出てきて、バレンタインデーは、会社の同僚への義理チョコのために多大な出費を強いられた。さすがに義理チョコの手作りはしなかったけれど、好きでもない上司にまで買わなければならないし、女性社員同士でセンスを競わされているような部分もあって、うんざりしていた。もちろん、3月14日のホワイトデーにはお返しがあって、送った以上の金額のものをもらったりしたが、あまり嬉しくもなかった。いま、義理チョコの習慣がすたれたことは、本当に良かったと思う。
社会人になって交際した相手は何人かいるが、私は相変わらず奉仕ばかりしていた。自分からではなく、相手から交際を申し込まれたとしても、なぜか、付き合いはつねに非対称だった。
ある男性から家に呼ばれて、「肉じゃがかカレーを作れ」と命じられて作ると、「まずい」と言われて落ち込んだ。自分と付き合うには、肉じゃがとカレーがちゃんと作れなければためだと主張された。肉じゃがはもっと甘い味がいい、カレーは鶏肉じゃなくて豚肉じゃなきゃいやだ、ということで、次回はその言葉に従った。なぜに、日本で生まれ育った一部の(割と多くの)男性は、肉じゃがとカレーを女性へのジャッジの指標にしがちだったのだろうか。当時は、そういうものか、と疑問も持たずに受け入れていたけれど、料理を交際の条件にするなんて、女性が男性のケアーをするのが当然という価値観がはびこりすぎていた。その人は、不機嫌で人をコントロールする、今思うとモラハラ男性で、なにかで怒りを買って、車を降ろされ、東名高速道路の路側帯に置き去りにされたこともある。
他の交際相手だが、年末に「冷蔵庫の掃除をしに来て」と言われてそそくさと従い、「クリーニングをとってきて」と言われて取りに行くと代金を払うはめになり、しらばっくれてたてかえたお金をくれる気配もない、など、なぜそこまで相手の言いなりに尽くしていたのか、こうして思い返すと、自分が愚か、かつ痛々しくてたまらないし、腹もたってくる。いわゆる、都合のいい女ってやつだ。
尽くすことで好かれたかったのだろう。それしか考えられない。
それから、やはり、自分が韓国人であることで、否定されるのではないかという恐怖が常につきまとっていた。実際、韓国人だと打ち明けると「血が汚れている」「それは困る」と言われ付き合いが終わることも1度や2度ではなかった。だから、嫌われたくなくて、相手に尽くし、合わせるのが通常運転になってしまった。ありのままで好かれる自信がないのだ。
私は見合い結婚だが、婚約後、料理教室に通い、結婚後も長く料理を習っていた。そして、せっせと元夫に手作り料理をふるまい、子どもができれば離乳食もすべて手作り、その後もなるべく手料理で、という考えに縛られていた。料理を作るだけでなく、妊娠中にまで、請われるまま、元夫の送り迎えを車でしてもいた。
そして、いつしか、結婚生活は破綻した。
離婚という選択には、ここには書けないさまざまな理由があるが、私があまりにも自分を押し殺してきたことも原因の一つだと思っている。離婚の話が出るまで、大きな喧嘩はしたことがなかった。仕事を辞めろと言われれば、キャリアをいとも簡単にあきらめたし、夫や子どものため、という言葉で自分を縛ってもいた。子どものお弁当作りも、習い事も、家族の世話も、すべてのことをきちんとこなしたいという自分自身への枷は、相当強かった。夫の実家で行われる祭祀でも、まめまめしく働いた。本当は、不満があるのに、それをぐっとこらえていた。
尽くすことが悪いわけではない。手作りも素晴らしいし、否定したいわけではない。だが、そこに過剰な正しさを込めたとき、やはりひずみは生じる。
娘が小学生の頃(女子校)、バレンタインデーでは友チョコを贈るというのが、当然のようになっていて、娘は驚くほどの数のチョコレートを持って帰ってきた。微笑ましく思う一方、いや、これは、数の大小で、ヒエラルキーも生じるだろうな、と率直に心配にもなった。なかには、手作りのものも結構あり、衛生的にはどうなのか、と不安にもなった。そして、自分が贈った手作りチョコレートのことも、衛生的にはアウトだったよな、と思い出した。手作りは重い、という価値観もいまでは認知されていて、私は、あえて手作りを避けることも増えた。コロナ以降は、さらに、衛生概念のもとにおいては手作りに対しての過剰な意味付けも減っていくだろう。
また、男子校だった中学生の息子に、バレンタインデーにちょっといいチョコレートを渡したら、「お母さんから、とか、そういうのじゃないのが欲しいんだよね」と言われ、ああ思春期!難しい!と痛感した。
いまだ、バレンタインデーは、悲喜こもごもであることに変わりはないだろう。それでも、少なくとも私も私の家族も、いまは恋愛至上主義やロマンティック症候群からは距離があって、心は平穏だ。
チョコレートがとても好きだが、チョコレートという食品が、プランテーション、つまりは、植民地的作物であることも、ここ数年気にかかっている。大資本や、元宗主国の企業が、現地の人が飲み食いする作物ではなく、大規模な、資本主義的な営利のもとに、カカオを栽培する。搾取の構造がそこにはある。バナナやアボカド、パイナップル、珈琲もしかりである。
厳密にはできないけれど、私は、それらのことを知った以上、なるべくフェアトレードの企業のチョコレートを買うようにしている。高級チョコレートはもちろん極上の味だし、身近な価格のチョコレートも大好きだけれど、頭の片隅に、プランテーションのことを留めておきたいと思う。
2023年、韓国ソウルに行ったとき、フェアトレードの珈琲やチョコレートが以前より目に付くようになった。しゃれたカフェやチョコレートショップがフェアトレードの商品を扱っている、ということは、意識の先進性がファッションやトレンドに反映されていることで、それはとても好ましいことだと思う。
日本も韓国も、少しずつ、食を通じて、環境や社会構造への意識が更新されているのだな、ということがこれまた嬉しい。
今年のバレンタインデーは、チョコレートにこだわらず、自分に花でも買って、いたわろう。そもそも、キリスト教の聖人、St,バレンタインとチョコレートは全く関係ないのだから。バレンタインデーを、誰かを想う日だとするならば、殺伐した世相のなかで、まずは、自分を大事にすることが、必要だ。
あ、でも、やはりちょっとだけチョコレートも欲しいから探しにいこう。
最近のアンケートによると、バレンタインデーに深い意味を感じない人が増えているそうだ。良い傾向だと思う。そして、ようやく、私も、他人への奉仕に極度に意味を見出し、自己肯定のはかりとすることから、抜け出せるようになった。
バレンタインデーが楽しみである。

【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。