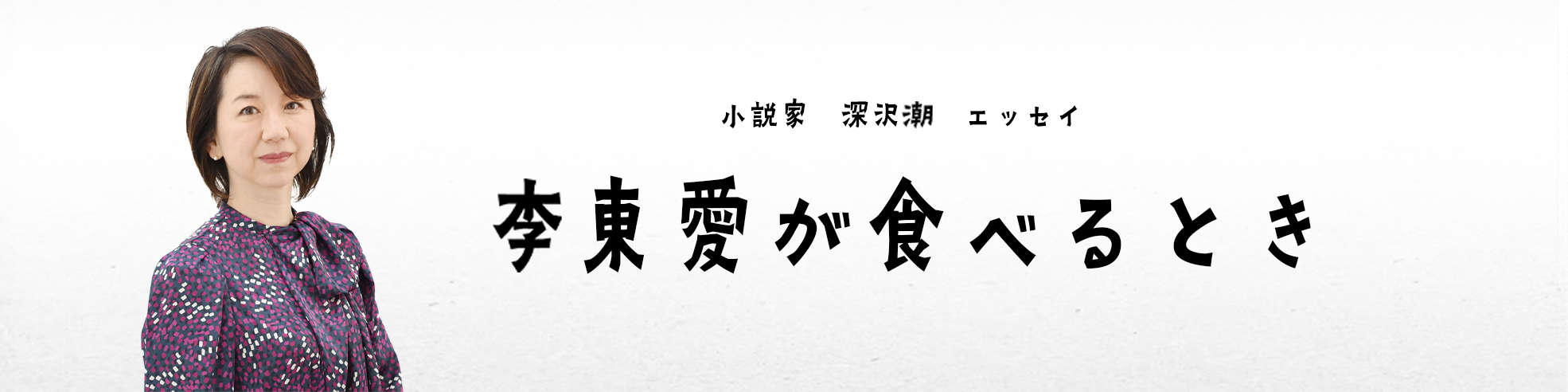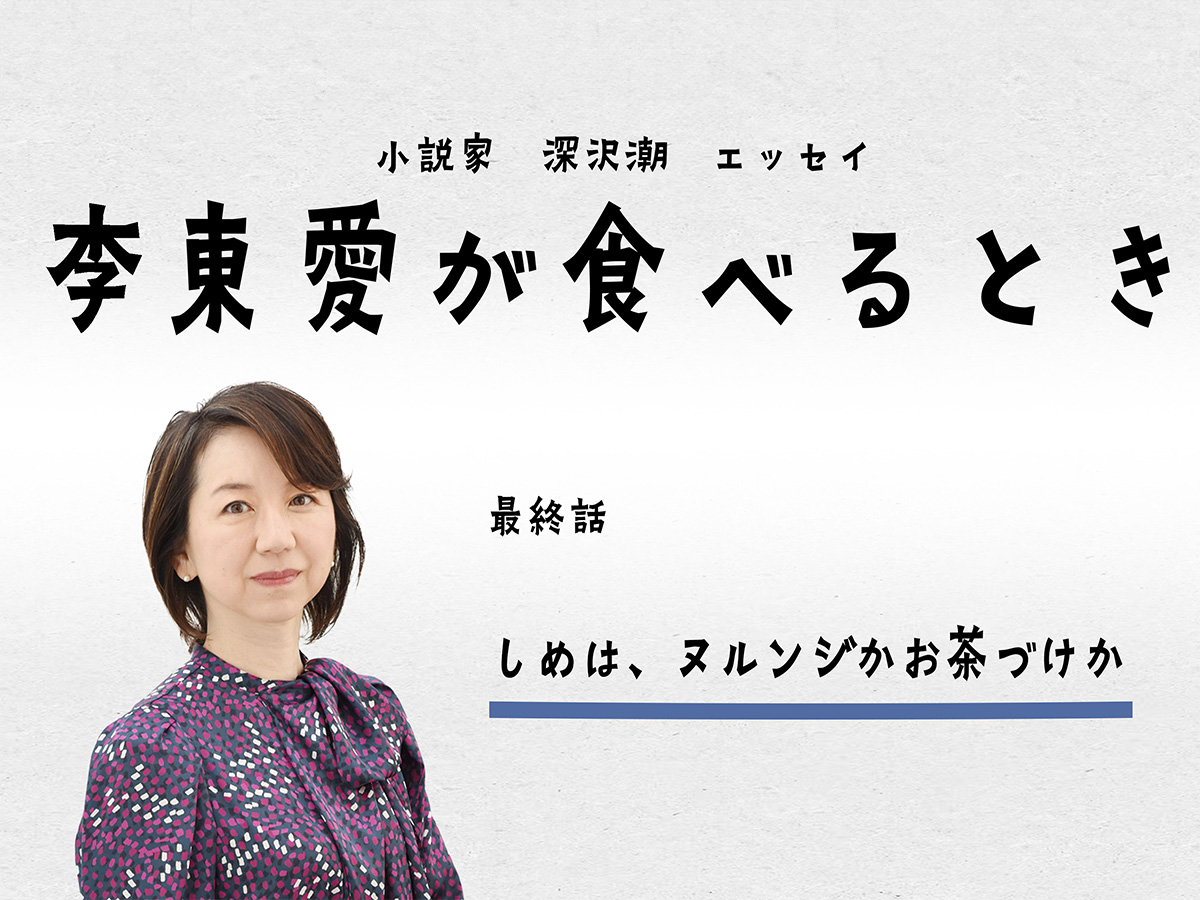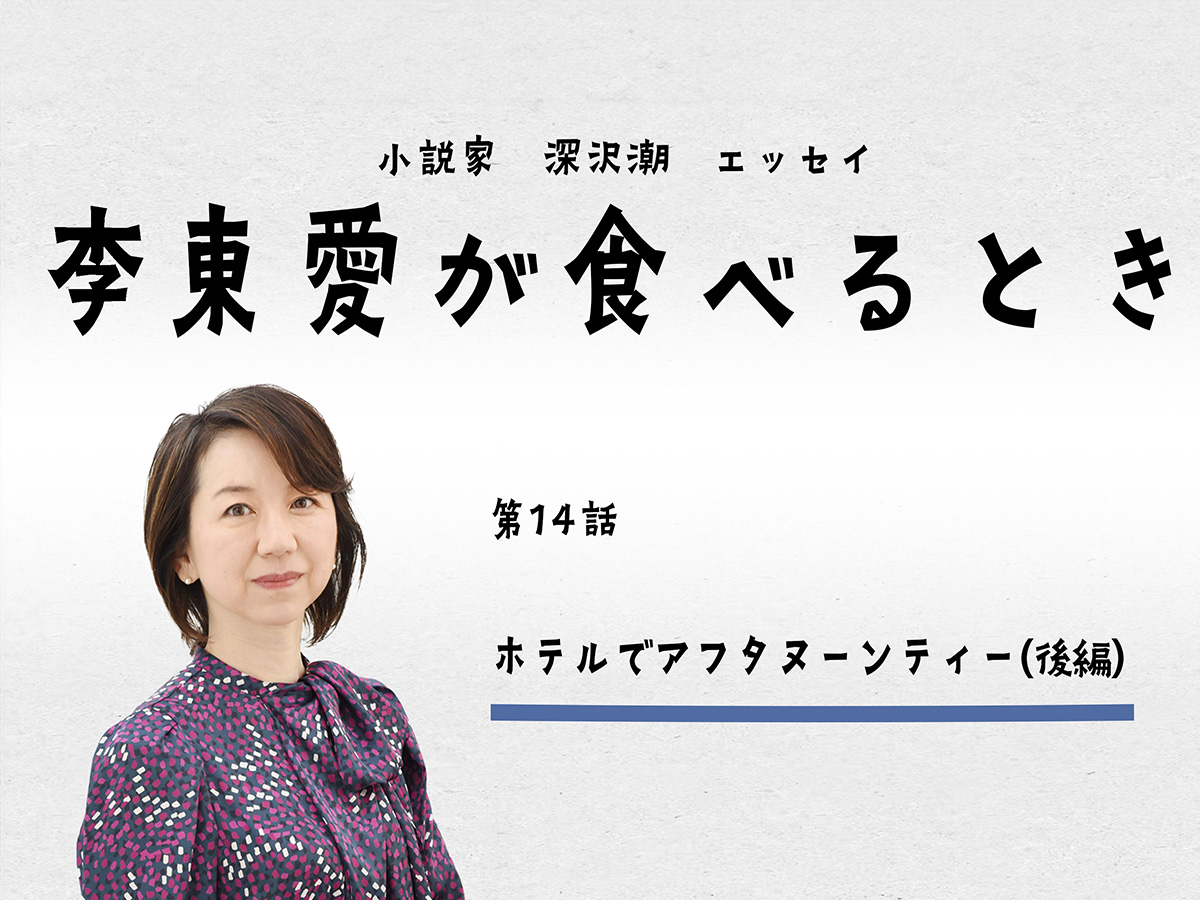第13話 ホテルでアフタヌーンティー(前編)
アフタヌーンティー。
その言葉から想起されるのは、優雅なひとときだ。場所は、高級ホテルのティールーム。プレートにのった美しい彩のスイーツや小ぶりのサンドイッチなどとともに、紅茶を飲んで談笑しているのは、ちょっとよそゆきの服に身を包んだひとびと。
幾重にもおよぶプレートに並ぶスイーツが象徴的な英国式アフタヌーンティーは、1990年代前半、日本においてそれほど一般的ではなかった。シンガポールや香港といった旧英国領に観光に行ったなかでも、ラグジュアリーホテルでお茶を飲めるようなごく少数の限られたひとたちぐらいしか経験していなかった。といっても、円高で景気もよく、トレンドに敏感なOLの海外旅行先として香港やシンガポールは人気が高かった。飲茶やアフタヌーンティーは、彼女たちにとっては、旅の目的のひとつでもあった。
私が当時勤めていた出版社からも「香港シンガポール辞典」というムック雑誌が刊行されていて、しかも広告部でその雑誌の進行業務をしていた私は、そのムックを読み込んで、アフタヌーンティーにあこがれ、夏季休暇に高校時代の友人とシンガポールに行って、ラッフルズホテルで生まれて初めて英国式アフタヌーンティーを経験した。焼きたてのスコーンがすごくおいしく、そして、ラッフルズホテルの格式のある豪華さに感動した。そういったことで、30年ほど前のシンガポール旅行は楽しい思い出として記憶されている。なにより、一時期かなり読んでいた村上龍の小説に出てきたラッフルズホテルに行けたことも嬉しかった。このころの私は、ミーハーで、ちょっと調子に乗っていたのかもしれない。私だけでなく、日本が、日本に暮らす人が、調子に乗っていた時代だった
しかしながら、そのころアフタヌーンティーという言葉は、まだまだ世間に広く浸透していなかった。私がシンガポールに行ったときも、アフタヌーンティーではなく、ハイティーと呼んでいたような気がするが、ハイティーなんて、知らない人が多かった。
アフタヌーンティーを単純に訳すと、午後のお茶、となり、つい、日本の清涼飲料水「午後の紅茶」を連想してしまう。するとたちまち、身近なイメージとなる。たしかに私の生活のなかで、午後のお茶の時間は、日常のひとときだ。執筆の合間に一息ついて飲む緑茶、友人とともにスイーツと一緒にいただく紅茶、担当さんとの打ち合わせでおかわりする珈琲。さまざまな午後のお茶の時間がある。珈琲も大好きだが、その他のお茶を飲む時間も、日々いつくしんでいる。
だが、ホテルでのアフタヌーンティーとなると、とたんに非日常のできごとになる。
そして、アフタヌーンティーの時間は、優雅どころか、案外、闘いや葛藤の現場だったりするのだ。少なくとも、私にとっては、そうであった。
ホテルで午後にお茶を飲んだ思い出として強く記憶に残っているのは、数々のお見合いの席だ。そして、そこは、神経戦がくりひろげられる場所でもあった。
私が大学3年生になったころから、母は、「卒業したら、お見合いをしなきゃね」と、ことあるごとに口にするようになった。その言葉は呪いとなって、私にのしかかり、私は勘弁してくれとばかりに、日本人との報われない恋愛にますます精を出した。就職活動でさんざん日本社会からはじかれる経験をしたが、日本人と交際して結婚すれば、私は社会に受け入れられるはずだ、と思っていた節もある。そのころは、恋愛のゴールは結婚だと信じて疑わなかったし、世間の空気もそうだった。結婚できないことに対する恐怖に近い感情もあった。いまは、まったくそんなことは思わないし、娘や息子にそんな考え方を強いるようなことは毛頭ないが、当時は、恋愛しなければ、結婚しなければ、というのが、強迫観念のよう自分の内に染みついていた。
だが、これまで書いてきたように、恋愛が結婚へと繋がることはなかった。私も、結局、在日の社会の中で生きていくしかないのだと観念してお見合いをすることにした。在日韓国人であることを必死に隠して生きてきて、その境遇から一生懸命逃れようともがいてきたけれど、逃れることはできないのだと悟ったのだ。在日コリアンの同胞とお見合いをすることは、私にとってとても重大な決断で、人生においてのひとつの転換点だったと思う。
お見合いのシステム化ともいえるマッチングアプリがさかんないまとは違い、当時は、お見合いをするような友人はまわりにほぼおらず、恋愛をうまくできない人がお見合いをするようなイメージがあった。恋愛を成就できないということは、ダメの烙印を押されたに等しく、恋愛結婚の方がよくて、お見合い結婚は妥協、という印象まであった。また、お見合いは、前近代的な産物だとも思っていた。したがって、なぜ時代錯誤なことをしなければならないのかと悔しかったが、私にとって結婚は、家から出る手段としては、最も現実的に可能だと考えられるものでもあった。だから、心を決めた。というか、諦めた。それほど、両親、特に母親の抑圧が辛かった。家から出たかった。
母は、「あなたはほっておいたらとんでもないことになるから、お見合いする気になってくれてよかった」と何度も言い、私は、そのたびに、親に屈服せざるを得ない無力な自分が嫌でたまらなかった。
当時の在日コリアンでも、日本人と恋愛結婚をしている人は多く、在日同士のお見合いに来る男性が、果たして在日コリアンとしてのアイデンティティが薄い、もっと言えば、在日コリアンであることに対してネガティブな気持ちを抱いてさえいる自分と話が合うだろうか、在日の嫁をとのぞむおそらく民族意識の高い家庭の雰囲気に私が馴染めるだろうかと不安も大きかった。とはいえ、もしかしたら、いい出会いもあるのではないか、という一縷の望みもあった。性格がよくてそれなりの容姿の人がいてくれたらいいなと淡い期待も持っていた。
まず、お見合い写真というものを撮った。
うきうきとはしゃぐ母とともに、お見合い写真が上手だと評判の写真館に行った。もちろん、撮影のために洋服も買ってもらった。母の見立てで、ちょっと地味なのでは?と思われる白い襟のついたグレーで無地のワンピースを選んだ。清楚に見えるといえば、そうなのだが、どうにも野暮ったい。私としてはもっと明るい色の服で写真を撮りたかったが、お見合いをすると承諾した時点で、主導権は完全に母の側にあった。いや、いつでも主導権は親の方にあったのだが。
仕方なく、という感じがにじみ出ているのか、その写真のなかの私の表情は、決して明るくはない。微笑んでと言われて作り笑いをしても、諦念が、漏れ出ている。のちに元夫が、「あのお見合い写真は地味で暗かったね」と言ったくらいだ。
私のお見合い写真は、ふたりのお見合いおばさんに手渡された。五反田のAさんと池上のBさんだ。
日本には、二つの在日コリアンの民族団体がある。在日本大韓民国民団(いわゆる民団)と在日本朝鮮人総聯合会(いわゆる総連)で、在日コリアンは、どちらかの組織の系統に分かれていた。現在は、どちらとも関係なく生きていけるが、マイノリティの互助組織でもあるので、以前は生きていくためにどちらかに属さざるを得ない在日コリアンがほとんどだった。
たとえば、我が家の場合、父が事業を営むのに、かつて日本の銀行は在日コリアンにお金を貸してくれなかったので、民団系の金融機関で資金調達をした。また、当時は民団を通して韓国のパスポートを発行していた。そして父は、民団の商工会で人脈を作っていた。
お見合いおばさんも、民団系のAさんと総連系のBさんになんとなくわかれていた。とはいえ、在日コリアンの世界は、ぱっきり二つに分かれてつねに対立しているわけではなく、親族のなかでも民団系と総連系が混在していたりしたし、友人同士でも同様だった。民族団体の幹部でもない限り、いや、たとえ幹部だったとしても、違う系統だからといっていがみあってばかりいるわけでもなかった。そもそも、在日コリアンの故郷は南の地域が多かったが、同郷の絆や親戚であるということの方がどちらかといえば大事だった。いがみあうことがあるとすれば、親族が集まる祭祀の席で酒が深くなって喧嘩になる、という感じだったりする。とはいえ、この喧嘩も、金銭問題が絡んでいたり、単に酒癖が悪いだけだったりということもあった。
もちろん、例外もあって、イデオロギーの強い人たち同士が犬猿の仲になることもあった。政治の話をして熱くなる、政治的立場の違いで対立するということもあっただろう。在日コリアンの集住地域では、朝鮮戦争の代理戦争が起きたこともあったし、朝鮮民主主義人民共和国への帰国事業をめぐっては暴力事件や抗争もあった。
だが、私がお見合いを始めた頃は、在日コリアン社会のなかで民団系も総連系も平和に共存していたように見えた。少なくとも、私の周りの在日コリアンたちはそうだった。東京で、集住地域に住んでいなかった在日コリアンであり、しかも通称名で暮らしていて、日本の学校にしか通っていなかったから、そう見えたのかもしれない。在日コリアンとひとことで言っても、その内情は、さまざまである。
そういったわけで、私自身は、民団だとか総連だとかをあまり意識したことはなかった。恥ずかしいことだが、実は、あまりよく朝鮮半島の事情も理解しておらず、民族団体の事情も詳しく知らなかった。親戚やごく少ない知人友人を通してしか、在日コリアンのことを知らなかったのだ。
お見合いおばさんも、総連系であっても民団の人の縁談があり、民団系でも民族学校を出た人の縁談があった。大事なのは、どれだけ「良縁」であるかであって、どちらかといえば、職業や家柄、金銭的にどうであるかが、お見合いおばさんたちの「良縁」であり勝負どころであったようだ。このあたりのことは拙作「縁を結うひと」(新潮文庫)に、自身の経験を交えておもしろおかしく小説にしているが、ここでは、私が実際に経験したことを思い返してみようと思う。
私のお見合い写真と釣り書きが二人のお見合いおばさんたちの手に渡ると、すぐに縁談が持ち込まれ、釣り書きが来た。25歳という年齢は、売り手市場のようだった。だが、そのとき、相手の写真を見た覚えがない。その後、数々のお見合いをしたが、こちらは写真館で撮った写真とさらに普段着に近いカジュアルな格好のスナップ写真、のちにはチマチョゴリを着て撮ったスナップ写真も見せていたが、男性の方は、写真はなく、釣り書きだけというのがけっこうあった。要するに女性の方がより容姿が重視され、男性は経歴や肩書が重視されているということなのだろう。写真をあらかじめ見たかったとは思ったが、女性が容姿を重視される非対称性をそれほど気にしなかった私の当時のジェンダー感覚は、権威主義とルッキズムとがあいまって、旧世代の感覚を完全に内面化していたと思う。
さて、記念すべき最初のお見合いは、五反田のAさんからの縁談で、品川区に住む歯科医の男性だった。8歳年上で長男であるということが釣り書きによる前情報だった。釣り書きには、氏名(本名と、あれば通称名)、両親の名前、きょうだいの有無(長男、次男なども明記)本貫、故郷がどこか(つまりは本籍地)、現在の住所、学歴、職業、趣味などが書かれていた。これは、私も同様の内容を書いた。
お見合いは、目黒の都ホテル(現在のウェスティン都ホテル)のティールームで、日曜日の午後に行われた。それぞれに母親が付き添うのだが、この構図は、その後のお見合いでも変わらなかった。そして、ホテルのラウンジやティールームで午後のティータイムにセッティングされることがほとんどだった。
歯科医の男性は、背が185センチくらいあって、都ホテルで会ったとき「大きいな」というのが最初の印象だった。まず、Aさんとその人と私、それぞれの母親の5人で席に着いた。朗らかそうな人で、母親の方も、優しそうに見えた。それぞれの紹介をAさんがして、次に母親たちが、釣り書きに書かれていない、父親の職業について説明などをした。そして、15分ほどすると、あの、ドラマなどでよく見た「あとは若いふたりで」というセリフがAさんの口から飛び出し、「あちらの席に行きなさい」と続く。
本当にそんなセリフがあって、お決まりのシチュエーションになるのだなと、私は半ば感動していた。芝居がかっているようにすら感じて、現実味がなかったが、言われるがまま、すこし離れた席に相手の男性とともに移動した。もはや、この状況を楽しんでさえいる自分がいて、緊張はなくなっていた。
どんな話をしたか今となっては全く覚えていないが、やはり歳の差を感じるな、と思った記憶がある。25歳の私からすると、30歳を越えている歯科医の先生は、落ち着きすぎていた。とても穏やかな人だったし、感じもよかったのだけれど、私は、このお見合いにおいてすら、少しは恋愛要素を求めていたのだと思う。胸がどきどきするとか、きゅんとなるとか、目や心が魅かれてどうしようもないという思いを、初見でも感じたかったのだろう。それは、私のこれまでの恋愛が一目ぼれかそれに近い感じで始まっていたからで、その感覚はどうしても捨てきれなかったのだ。つまり、ビビビッ、が欲しかったのだ。結婚と恋愛は違うと母がうるさく言うけれど、恋愛の先に結婚があってほしかった。私は、頭の中で、この人といちゃいちゃできるだろうか、子どもを作れるだろうか、と超現実的なことを考えていた。男性の職業や家のこと、母親の感じなどを思い出し、嫁いでその家の長男の嫁としてやっていけるかと、頭をフル回転させていた。
ふたりで向かい合ってお茶を飲んだが、そんなに話が弾んだわけではなかった。それでも嫌な空気ではなかったような気がする。私としては、とにかくおとなしく見られるようにという母の言葉を守っていた。その方がお見合いにはいいということだった。私としても、どうせお見合いをしなければならないなら、相手に気に入られた方がいいだろうと判断をしたのだった。もちろん、頭の中では饒舌だったのだけれど。
そんなわけで口数の少なかかった私に、その人は気遣っていろいろ話しかけてくれたのではなかったかと思う。30年以上前の記憶なので、はっきりはしないけれど、思いやりのある人だなと感じたことは覚えている。
ふたりでお茶を飲んでいる間に、Aさんと母親二人は別席で待っていて、しばらくしてそこに戻ってお開きとなった。
家に戻ると、母からどうだったかと訊かれた。私は、あまりピンとこないというような返答をした。すると母が怖い顔になって、「一度会ったくらいじゃわからないでしょう」と言った。私は、「でも……」と口ごもってしまった。
「どこか嫌なところがあったの? いい人だと私は思うわよ」
「別に嫌とかではなかったけど、歳が……」
「私とお父さんだって、7歳違うのよ。そんなのものよ。とにかく、断らずに一回はデートしなさい。それが礼儀だから」
「うん……わかった」
こんなような会話が交わされた。
夜になってAさんからかかってきた電話に、母は、前向きな返事をしていた。父は、母から話を聞いても、何も言わなかった。
翌週の土曜日に、私は青山の和風レストランで、お見合いした歯科医とデートをした。今回も母が高島屋で買ってくれた清楚なワンピースを着て行った。あまり好みのデザインではなかったけれど、仕方ない。唯一嬉しかったのは、欲しくても買えなかったフェラガモの靴を母が買ってくれたことだけだった。
カウンター席に並んでみると、彼は思いのほか痩身だった。だが、その足の大きさに驚いてしまった。30センチくらいあるから、靴がなかなか手に入らないとか、服も探すのが難しいなどという話をした。靴が好き、というところは、私と一緒だな、と思ったことを覚えている。それ以外には、私はどんな仕事をしているかなどを話したと思う。ときどき会話が途切れ、とても長い時間に感じた。この人と結婚したら、とあらためて考えてみるが、どうしても想像できなかった。いい人だし、嫌ではないが、好きになれそうな予感がしない、というのが、正直なところだった。私は、好きになれる人、なれそうな人と結婚したかった。
デートといっても、夕食を食べただけだったが、家に帰ると、母から根ほり葉ほり様子を聞かれた。私は適当に応えたが、あまりにもうるさいので、「もう、あの人とは会いたくないから聞かないで」と話を打ち切った。そこできっと母に叱られるのだろうと予想していたが、母は、案外あっさりと、「あらそう、じゃあお断りの電話をAさんにしなきゃね」と言ったのだった。
私は拍子抜けしてしまったが、すぐに、母が簡単に引き下がった理由がわかった。
一つは、父が、その歯科医の人の家が、済州島が故郷であることに難色を示したことだ。さらに、長男のところにはできれば嫁に行かせたくないということがあった。家父長制が根強い在日コリアンの家庭は、長男の嫁が苦労するのは、目に見えていた。年に数度はある祭祀の準備、まれにある両親との同居、男の子を産まなければならないなど、さまざまな抑圧がある。私の数少ない在日コリアンの友人のお姉さんが両班の家の長男に嫁ぎ、体重が10キロも減ってしまったと聞いていたので、私もできれば長男は避けたいと思っていた。だから、父が長男のところに行かせたくないと言ってくれたことにはほっとしていた。
だが、それまで、相手の故郷の地域が気に入らないなんてことがあるとは夢にも思わなかった。そして、在日コリアンとして差別を受けてきたはずの父が、同じ在日コリアンのことを、故郷によって、つまりは自分では避けられない属性によって、忌避することに驚いた。父は、慶尚南道が故郷だが、全羅道の人もできれば避けたいなどと言っていると母から聞いて、韓国人、在日コリアンの中に、地域差別が根強いことをはじめて知ったのだった。
私は、在日コリアンのことを本当によく知らないなと改めて思った。住んでいるわけでもない故郷がどこであろうと、あまり関係ないように思えたから、なぜ地域に拘泥するのかもわからなかった。そして、そんなことを言っていたら、ただでさえ、狭い世界の中で相手を探すのに、縁談なんかまとまるのだろうかとも思った。そんな理由で人を判断する父が嫌だった。日本人はダメ、というだけではなく、ほかにもダメな人がよりによって同胞のなかにいるなんて、父はいったい何様なのだろう。
母があっさりと引き下がったもう一つの理由は、Bさんから母のもとに連絡があって、いくつかいい縁談があると言われたからだった。
「すぐに決めなくても、もっといい人がいるかもしれないでしょ。Bさんによると、25ならまだまだ売れるって。間に合うそうよ」
母の言葉に、私は、自分がまるで商品、しかも生ものかなにかになったような気がして、不愉快だった。それこそ、クリスマスケーキだ。我が家の私に対する人権蹂躙は、お見合いにおいてすら顕在化した。そして、決定権は、私だけでなく、両親の方にもかなり、いや、相当あるということも思い知らされた。それでも、この、在日コリアンのお見合い市場に出たということ自体は認めざるを得ないことはわかっていた。だから、黙って言われることを受け入れた。いい人、という定義は両親と異なるかもしれないが、できれば私も、いい人、と出会いたいと願っていた。この市場で、自分をできるだけ高値で売って、釣り合う高値の人と結婚することしかないのだと考えた。
「それでね、さっそく、明日、あなたと一緒にBさんのところにご挨拶に行くからね。そこでお相手の釣り書きもいただけるそうよ」
母は瞳を輝かせている。
「Bさんは、日本一なのよ。条件の良い在日コリアンの縁談をたくさん持っているのよ」と笑顔まで見せた。
お見合いおばさんのBさんは、私が新人文学賞を受賞した短編「金江のおばさん」のモデルとなった人物だ。キャラの濃い、強烈な人だった。眼鏡のつるにルビーやダイヤがついていたことが、忘れられない。小説ではだいぶ脚色し、かつマイルドにしているが、実際のBさんは、小説の登場人物よりもかなり辛辣なことを言う人だった。
日曜日の午前に、私は母とともにBさんの家を訪ねた。午後にはお見合いがあるからと、早い時間を指定され、私は「なんで日曜日にこんな早く起きなければならないのか」と思いつつも、丁寧に、だが、ナチュラルに見える化粧をして母についていった。
応接室のような、ソファーとテーブルが置かれた部屋に通され、私は、Bさんからねっとりとした視線で、頭から足先まで値踏みするように見つめられた。そして、私の釣り書きと写真を確かめると、溜息を吐きながら頭を振った。
「東愛、あんたは、まず、会社をやめなさい。そして、花嫁学校に通いなさい」
??? 花嫁学校? ていうか、なんで、呼び捨てなのだろう……。
「いい大学だと、貰い手が減るんだよ。釣り合う男が少ないからね。男はね、自分より頭のいい女が嫌いなんだ。働いている女も嫌がるね」
??? ひどすぎる……。
「あんた、チマチョゴリの写真を撮りなさい。この写真じゃだめだ」
……。
私は、呆然としてしまった。このおばさんのもとにいい縁談があるのではなかったか。なぜ、私を全否定する言葉を浴びせられなければならないのだろうか。
母の方を見ると、うん、うん、と真剣な面持ちで頷いている。
かばってくれてもいいではないか。あれだけ教育熱心だった母は、せめて、いい大学のくだりや頭のいいうんぬんのところだけでも、なにか言い返してくれてもいいじゃないか。
涙がこみあげてきそうになるのを堪えていると、Bさんが、よっこらしょっと立ち上がり、隅に積まれた書類の束の中から、もったいぶって、一通の釣り書きを取り出し、私の横に座る母に渡した。あとから知ったことだが、釣り書きは、ランク順に積まれていたということだ。
「この人が、いまうちで一番いい話だよ。今見て、会うかどうか決めなさい」
私は、日曜日の午後、高輪プリンスホテルのロビーに母と出向いた。Bさんのアドバイスで、薄いピンクか白い服などの明るめの色を着てくるようにとのことだったので、私は、パステルイエローのスーツを前日に母と高島屋で買って、それを着て行った。
私がお見合いしたのは、ソウル大学を出た医師で、こんども5歳以上離れた人だった。高校までは民族学校に通っていたという。出身地は覚えていない。
最初のお見合いと同じように、互いの両親とBさん、私とその人がまずは同じ席につき、すぐにふたりきりでお茶を飲むことになった。やはり、どんな話をしたか、記憶にないが、前回同様、あまりしゃべらないようにした。というか、よく話す人だったので、話さずにすんだ。彼は、自分の仕事の話をしていたような気がする。長男というのが気になったが、清潔で、感じのいい人だった。しかし、30を越えているせいか、私には、大人すぎるように思えた。そして今回も、ときめくことはなかったのだ。
ふたりでのお茶を終えて席に戻り、会計を男性側がすませて解散となった。すると、Bさんが私に近づいてきて、「どうだったか? いい男だろう」とささやいた。
いい男とは? と思いつつも、はあ、とあいまいに答えると、Bさんは「向こうはあんたをものすごく気に入ったみたいだから、一回はデートしなさい」と、私の手を握った。
「あ、はい」
Bさんの刺すような視線に気圧されて、私はうなずいていた。いつの間に、向こうに確かめたのか、そして、この圧はすごい、とさすが日本一の辣腕だと驚いた。
後日、私がその医師とデートをしたのは、銀座のビルの上階にあるイタリアンレストランだった。ランチをしたのだが、そのときのことは、比較的しっかりと覚えている。彼は、東京大学の医局に勤めているとのことで、激務だと言っていたが、たしかにとても痩せていた。小柄なので、もしかしたら、私と体重が変わらなかったらどうしようと思ったくらいだ。
とても純粋な人だった。偉ぶることもなく、気さくでもあった。音楽はクラシックが好きとのことだったが、私がポップスを聴くというと、「松田聖子って案外いいですよね」と私に話を合わせてくれた。とはいえ、そのころは洋楽志向が強かったので、なんで松田聖子?とずれを感じてしまった。
彼は、恵まれない子どもたちの写真展(たぶんアフリカの飢餓の様子か何か)に行って、心が揺さぶられ、歌を作ったのだと言った。そして、「こんな歌なんです。タイトルは、『この子らに何を』」と言うと、その場で歌い始めた。静かなレストランに、歌は響いていた。というか、歌が始まると、あたりがしんとなったのだった。
自意識ばりばりの私が、まず思ったのは、周りの目が恥ずかしい、ということだった。「無理だ、この人」とも思った。
家に戻って、すぐに母に断ってほしいと伝えた。母はだいぶ粘って、嫌な理由を聞いてきたが、私はなにも答えなかった。無理、というのは、感覚的なものだったからだ。それに、歌が嫌だった、などと言えるわけがない。しかたなくひたすら首を振り続けていたら、母は、「仕方ないわね。でも、ご長男だったし、あちらのお母様、ご長男を大事に育てて来たでしょうから、嫁としては大変でしょうしね」と自分に言い聞かせるように納得してくれた。
いまの私だったら、「なんて、いい人なんだろう」と思うし、「この子らに何を」を聴いて、涙するかもしれない。そのころの自分に「この人と結婚したらいいんじゃないか」とアドバイスしたくなるだろう。
いや、本当に、若さというのは、傲慢であり、感覚的すぎるのだ。当然、感覚と言うのは大事だが、嫌になるポイントが、多すぎるし、自分の受け入れられる範囲が狭すぎる。考えてみたら、最初のお見合い相手の人だって、とてもいい人だった。
昨今、日本の若者たちが、カエル化現象と呼ぶものは、きっと、私が歌を聴いたときに感じたものなのだと思う。以降は、すべてが、無理、となってしまったから、よくわかる。
しかし、これも、すべて、いまとなっては、あの人はいい人だった、なのである。
その後もお見合いは続き、私は、ホテルのティールームで、闘い、いや、悩みつづけるのである。
(後編につづく)

(著者提供)
【プロフィール】 深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
■ 小説家 深沢潮 エッセイ「李東愛が食べるとき」
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、「無関心を関心に」「声なき声に光をあてる」ために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。