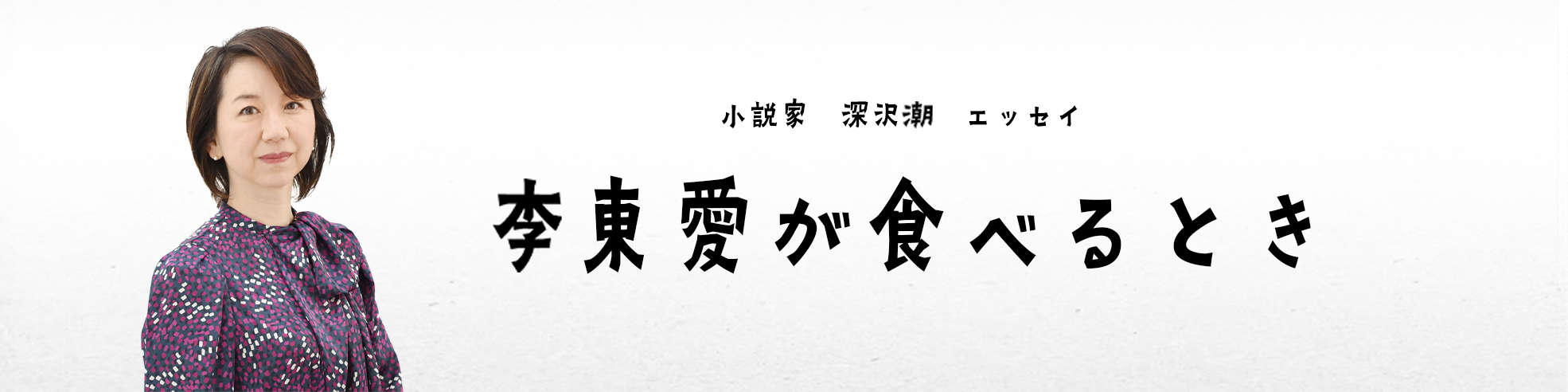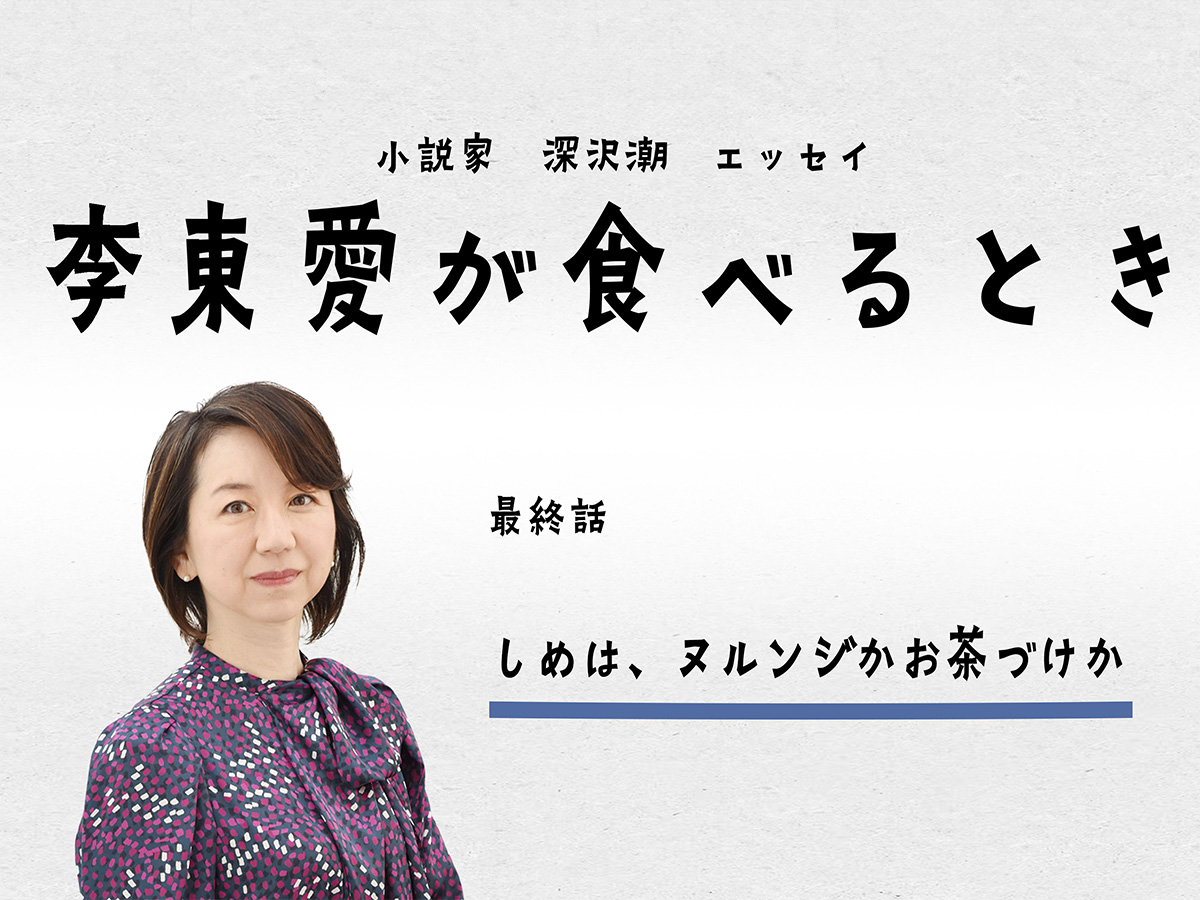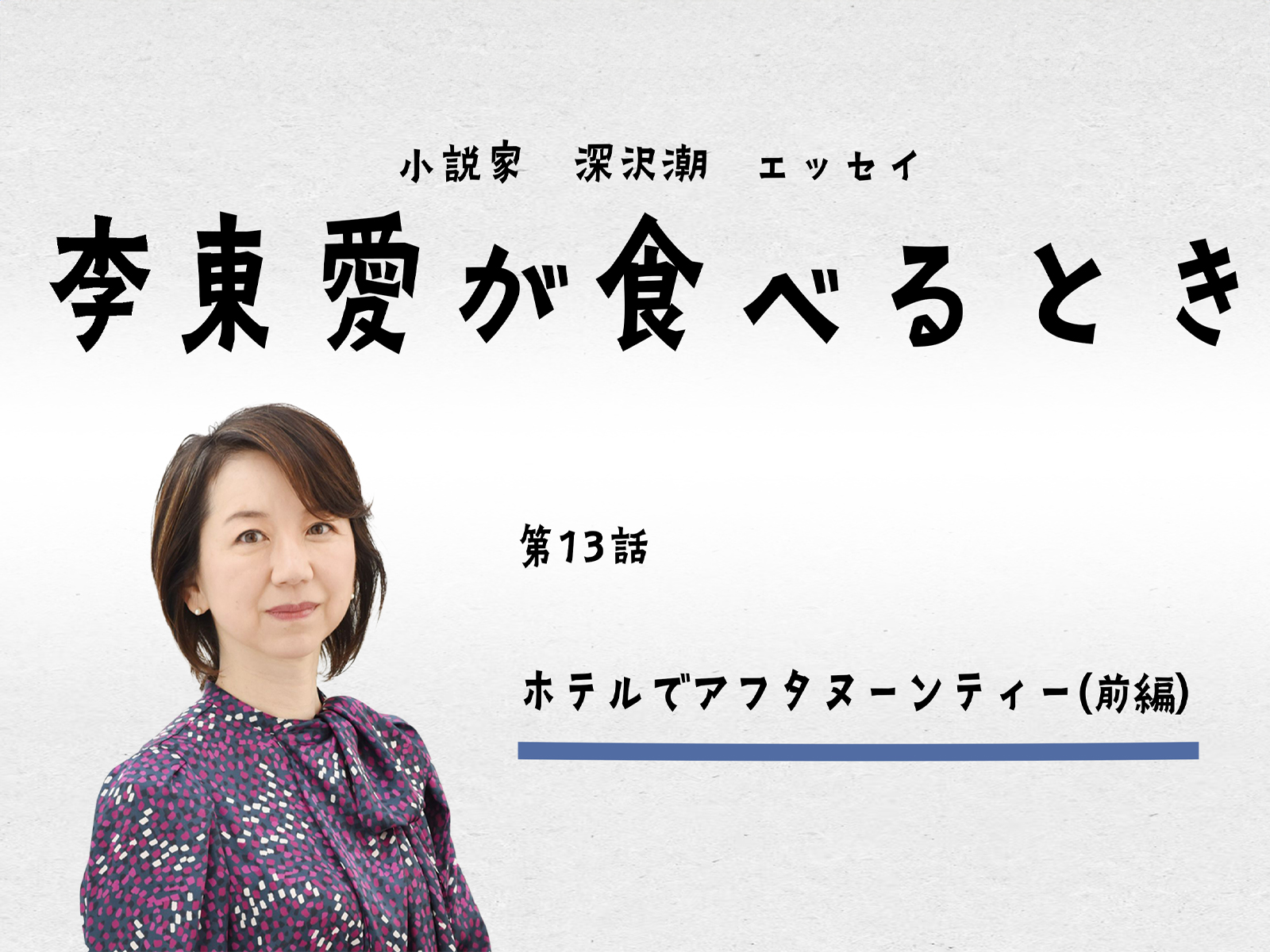第14話 ホテルでアフタヌーンティー(後編)
その後、池上のBさんの紹介で、次々にお見合いをした。相手は医師、弁護士、公認会計士など、士業の人をよく紹介された。なかでも圧倒的に医師が多かった。まれに、親の職業を手伝っているとか、特殊な技術者のような人もいた。サラリーマンが皆無だったのは、やはりまだそのころ在日コリアンの男性も一般企業への就職が厳しかったことを物語っているし、手に職がある人、専門職の人が、お見合いにおいて強かったということもあったと思う。
Bさんによると、私が4年制大学卒業であることで、士業の人が多くなったという。商売をやっていたりすると、嫁に高学歴を求めない、とはっきりと言われた。女子大の方が良かったのに、とも言われた。そこまで言い切るお見合いおばさんのBさんに私は終始圧倒された。
Bさんの紹介によるお見合いは、いつも高輪や新高輪、芝のプリンスホテルのティールームだった。成約するとそこで式や披露宴をあげることが薦められる、といった流れとなっていた。Bさんはホテルからバックマージンをもらっていたのだ。婚約指輪や、チマチョゴリをしつらえるのも、Bさんの紹介で、これもみなバックマージンがあるようだった。そして、Bさんは、一回の見合いで、当時10~30万円の紹介料をとり、成約すると50~100万円、あるいはそれ以上の報酬を得ていた。
我が家は、Bさんに結構な金額を払ったと思う。なぜなら、なかなか縁談がまとまらなかったからだ。10人以上の人と会った。デートも何人かの人と行った。
いまとなっては、忘れてしまった人もいるが、記憶に残っている人もいる。
ある医師は、最初のデートで、東名高速をフェアレディZでとばして、自分が大学時代によく通っていたという学校の近くの喫茶店に私を連れて行った。そこは常連しかいないような古い喫茶店で、インベーダーゲームがテーブルに組み込まれていて、コインを入れると占いができる灰皿が置いてあるような、「ザ・昭和」なところだった。
マスターは煙草を吸いながら、興味津々にこちらを見るし、出された珈琲は薄くてまずいし、その珈琲が入っていたカップはふちがかけていて、茶渋がこびりついていた。たぶん、ありのままの自分を見てもらいたいという気持ちでそこに連れて行ったのだろう。百歩譲って、もう結婚が決まったあとのデートならばわかるのだが、初手であの喫茶店はきつかった。レトロな喫茶店がいまでは流行っているが、そのときは、単に、古くて汚い喫茶店で嫌だ、としか思わなかった。
また、在日コリアンのなかで1、2を争うほど裕福で、自家用ヘリコプターを所有しているという実業家の息子さんともお見合いをした。歳が近くて、見た目もしゅっとしていたので、悪くないな、というのが第一印象だった。だが彼は、ホテルで二人きりでお茶を飲んだとき、ほとんどしゃべらなかった。仕方なく私の方から質問しても、話が続かない。30分ぐらいで、もうお手上げ、と思っていたら、「僕、こういう性格なんです。いつも喋らないから気にしないでください」と言われた。さすがにこの人とは、デートをすることもなかった。
「縁を結うひと」(新潮文庫)のなかに、エピソードとしてちらっと出てくる人だが、父親も医師で、数人いる兄弟もほとんど医師だという人(次男だか三男)を紹介された。彼は、10歳ぐらい上だった。この家も、在日コリアン社会のなかでは有名で、大きな病院を経営しており、父親は金日成の治療もしているとのことだった。(このときは金日成がまだ存命だった)さすがに歳が離れすぎていることと、私の父が、「北に行くことになったらさすがになあ……」と難色を示したことから、断ったところ、すぐに「じゃあ、弟はどうか」とBさんから話があり、本当に驚いた。弟も医師だった。
兄がだめなら、弟って、デリカシーがなさすぎるのではないか?
もちろん、私が弟さんと会うことはなかった。
ある弁護士さんとのお見合いでは、「僕は、弁護士として、同胞のために尽くしたい」と目を輝かせて言われた。そのころの私は、完全にしらけた人間だった。同胞のために、という言葉を聞いて、私とは合わない、と即座に思ってしまった。私は、在日コリアンの同胞のことなど、1ミリも考えたことがなかったし、正直言うと、考えたくなかった。自分のことしか考えない人間だった。むしろ、同胞と距離を置きたいぐらいだった。そもそもこんな人間が在日コリアン同士のお見合いに参加していることが矛盾していたのだが、お見合い相手のなかには、生活していくことだけに専心していると思われる人たちもいるだろうから問題ないだろうと甘く考えていた。やはり、私のような人間は、この一連のお見合いにはそぐわないと思い知らされもした。
最近は、在日コリアンの弁護士さんと知り合う機会も多々あるのだが、もしやあのときの人がいたらどうしようとドキドキしてしまう。同胞のために尽くす弁護士さんを、もちろん、いまは尊敬しているし、ともに差別と闘っていく仲間だと考えている。
さて、お見合い相手を断ってばかりだった私は、「ぜんぜんいい人がいない」とちょっと居丈高になっていた。
そんななか、10人を超えたあと紹介されたある医師はちょっと垢ぬけていて、いい感じだった。年齢も3歳ぐらいしか離れておらず、会話もはずんだし、この人なら、と前向きな返事をした。しかしながら、向こうから断られてしまった。私の母が大学を出ていないことと、私のことを興信所で調べて、「とうてい、うちの長男の嫁が務まるとは思えない」というのが断られた理由だった。
当時、私は、出版社の広告部に勤めていた。その見合い相手の家は、私の勤務していた会社の人にも、私のことを聞いたらしい。思うような仕事ではなく不満も多く、勤務態度もそれほど良くなかったから、それが伝わったに違いなかった。
断られた理由はほかにもきっとあっただろうが、ひとつ考えられるのは、私に交際相手がいたことがばれてしまったのではないかということだ。見合いをすると決めたが、実は、交際は細々と続けていた。彼は、私が韓国人と知っても態度を変えない人だった。
私は、見合いをする前に、その人に一応探りをいれた。だいぶ勇気がいることだったが、「結婚とか、いくつぐらいでするか、考えたことある?」といったようなニュアンスで遠回しに訊いたのだった。結婚を迫って嫌われたくないという思いもあったから、私との結婚ではなく、あくまで一般的な問いとして。
「まあ、30くらいかな」
当然といえば、当然の答えだったと思う。同い年だったから、男性としては、結婚なんてまだまだと思っていたはずだ。だが、私にとっては、由々しき事態だった。
30というと、あと5年はあるではないか。私は待てなかった。すぐにでも家から出たい。それに、30までその人と付き合い続ける自信もなかった。振られる可能性にいつも怯えていた。そして、すがりつくことに疲れてもいた。だから、曖昧な付き合いを続けながら、お見合いをした。それなのに、その人のことが好きだったので、きっぱりと別れることもできなかった。
付き合っている人がいる状態でお見合いをしたって、比較してしまうし、誠実とはいえない。ほかに好きな人がいるから、目の前の相手を気に入ることが少ないのも当然だった。お見合いの相手にもとても失礼だった。そして、交際相手にも。(当然ながらお見合いのことは秘密にしていた)
それでも、それまでのお見合いの相手がみな自分を気に入ってくれたので、いい気になっていた。いつもは日本人の交際相手に対して、自分が韓国人であることに気後れして卑屈になってしまうのに、同じ境遇の在日コリアンに対しては、上から目線で相手をジャッジしていた。謙虚さがなかった。
それが、この医師に、初めて断られたのだ。
ショックだった。
母も、だいぶこたえたようで、特に、母親も大卒でないと、と言われたことに、いたく傷ついていた。「どうせ私は高卒ですから」とBさんに何度も言っていて、そばで聞いていた私は胸が痛かった。母は、大学に行きたかったが、「女は行かなくていい」と許されなかったのだ。
自分たちが済州島や全羅道がどうのと言っていたけれど、母の学歴でこんどはこちらが難癖をつけられた。自分にかえってくるとは、まさにこのことだろう。
自分たちがやられてみないと、差別の愚かさにはなかなか気づけない。私も母も、断られたことにかなり落ち込んだ。そして、母は私の生活態度を厳しく叱責してきた。
私は、この時点で、お見合いはもうしたくない、と思ってしまった。在日コリアンにも受け入れてもらえないという事実がこの先も重なったら、自分を保てないと思った。自分が相手を受け入れなかったことは棚に上げて……。
お見合いをやめたいということを両親に伝えると、父はかなり不機嫌になり、母は感情的に私を責めた。しかし、私は考えを押し通した。とにかく、お見合いをまたするのが嫌でたまらなかったのだ。泣きながら訴えると、母は、「じゃあ、しばらくお休みってことにしましょう。本当は早い方がいい縁があるんだけどね」といつまでもぶつぶつと言っていたが、とりあえず尊重してくれた。父は、私に対して口をきかなくなった。
お見合いをしなくなった私は、まず転職をすることにした。大学を出て最初に働いた外資系金融会社は、仕事が合わな過ぎて半年ほどで辞め、転職して出版社に勤めたものの、その部署では女性はアシスタント的な仕事しか、させてもらえず、編集などへの異動も認められなかった。だから、私のキャリアへの不安、将来への不安は募るばかりだった。
家から出てひとりでも生きていけるように、もっと給料もよい会社に移りたかった。結婚できなくても、ひとりで生計をたてられたら、交際相手に期待することもなくなるのではないかと思った。私はもしかしたら結婚できないかもしれないという考えも湧き始めていたのだ。
転職活動は、外資系を中心に行った。案外すんなりといき、私は、フランス系の化粧品メーカーに総合職として勤めることができた。
仕事は充実していた。化粧品は好きだったし、海外出張や国内出張も多く、給料も比較的高かった。自分の足で立ち、歩いて行けるかもしれない、と希望が持てた。
交際相手に対しても、そこでようやく客観的になることができた。恋愛や結婚に大きな価値を見出していたが、この人との未来は難しいと、やっと認めることができた。なにより、仕事が楽しくてたまらなかったから、結婚にすがらなくても大丈夫かもしれないと初めて思うことができた。
国内の出張では、百貨店の外商の顧客との茶話会というのを経験した。ケーキとお茶を用意して、午後のひととき、つまりアフタヌーンティーの時間を過ごし、お客さんと化粧品の話で盛り上がる。当然、目的は自社の商品の紹介、つまりは宣伝なのだが、新色の口紅をつかってメイクのアドバイスをしたり、スキンケア商品の効能を説いたりすることは、面白い経験だった。仕事は多岐にわたり、手ごたえもあって、やりがいも感じていた。
百貨店の美容部員やホテルのサロンのエステティシャンに対して新商品の紹介と説明をするような仕事もしたので、全国各地に行った。仕事が終わって、その地の食をいただき、ひとびとと触れ合ったことで、視野が広がった。仕事の合間やあとに、ひとりで、評判のいい喫茶店やカフェに入って珈琲や紅茶をいただいく、つまり、アフタヌーンティーを自分だけのぜいたくな時間として過ごすということも楽しんだ。ひとりで旅行することも苦ではなくなり、むしろひとり旅が好きになった。
家にいると、結婚はどうするの? いつまたお見合いをするの? と母が嫌味っぽく、あるいは嘆くように言ってくるので、出張して家から、母から離れていると気が楽でもあった。交際相手とは、たまに連絡を取り合って会う、といった感じで、しっかりと向き合うことも避けていた。別れる勇気もなく、かといって、結婚したいと口にも出せなかった。けれども、仕事が順調で忙しかったから、目の前のことから目を背けていられた。
そんなある日、大阪に出張し、仕事を終えたのち、当地に住んでいた母方の従姉の家に遊びに行った。私よりも7歳上で、結婚してふたりの女の子がいた。こどもたちが寝付いたあと、従姉が私に悩みはないかと訊いてきた。私は、だれかに結婚のこととか、恋愛のことを相談したかったので、尋ねてくれたことが嬉しくて、自分の素直な気持ちを打ち明けた。結婚はしたいけれど、お見合いではない方がいいとか、父や母が抑圧的で辛いということも話した。交際相手がいて、本当はその人と結婚したいが難しそうだということも、隠すことなく吐露した。
話し終えたときは、深夜になっていた。従姉は相槌をうちながら、ひたすら聴いてくれた。紅茶を2回淹れてくれたことを覚えている。アフタヌーンティーではなく、ミッドナイトティーだ。
従姉は、日本人と恋愛結婚していたから、私の気持ちを理解してくれたと思っていた。だが、従姉は母の側の人間だった。私の話は、母にすべて筒抜けだったのだ。というか、母から頼まれて、私から話を聞き出したのだった。
大阪から戻ると、私は母の前に正座をさせられた。
「付き合っている人がいるんだってね」
「私やお父さんに対して、感謝ではなく、恨みがあるんですってね」
「○○お姉ちゃん(従姉)が、東愛は、ぜいたくなだけだね、って言ってたわよ」
「お見合いをするっていうから変わったと思ったけど、やっぱりあなたは、どうしようもない子ね」
私がそのときに、どれだけ絶望したかをうまく説明できる自信がない。
従姉は、DVや経済的な理由で離婚したイモ(母の姉)のもとで、奨学金で大学を出ていて、高校時代からアルバイトをして家計を手伝っていた。そんな従姉からしたら、私の話なんて、そりゃあぜいたくな悩みにしか聞こえなかっただろう。だけど、私は、切実だった。姉が亡くなって以来、従姉のことを実の姉のように慕っていたけれど、向こうは、私を「恵まれた従妹」としか見てくれていなかったのだ。そもそも最初から、母の味方でしかなかった。ミッドナイトティーは、最悪の思い出となってしまった。
私のことなんて、誰も理解してくれない。
ものごころついてからずっと感じてきたことがそのときはっきりとわかった。
それまでよりもさらに家に居づらくなった私は、ひとり暮らしをしようと決めて、物件巡りを始めた。だが、なかなか踏み切れなかった。自分が住みたいと思う場所は、家賃が高すぎた。従姉の言うように、私は恵まれていたのだろう。生活レベルが落ちることが、想像できず、怖かった。また、ひとりで暮らすことへの不安もあった。ちょっと前に、ある男性にストーカーをされたということがあったからだった。セキュリティのいい部屋は、どう考えても自分の給料で住むのは無理そうだった。
さらには、交際相手とも、うまくいかなくなっていた。そんな状態で、ひとりで生きていくなんてできるだろうかと不安はますます募るばかりだった。
悪いことは重なるもので、激務もあって、身体を壊して、入院をすることになってしまった。数日で退院できたが、私は入院中、海底に沈んでいるような気持ちだった。なにもかもがうまくいかない。せっかく仕事は順調だったのに、それも、身体が思うように動かなければ、元も子もない。身体だけでなく、心の状態がかなり危うくなっていた。
私は、社交的ではあったけれど、自分のすべてをさらけ出せるような友人はいなかった。だから、辛いときに連絡をできる人は思いあたらなかった。交際相手にも、入院したことは言えなかったし、友人にも伏せた。
私の身体を一番気遣ってくれたのは、母だった。心のうちは話せなかったけれど、病院に母が来てくれると、涙が止まらなくなってしまった。
私は、いったい、なにと闘っているのだろう。
先行きが見えないのに、頑張ってもしょうがないのではないか。
私は、根性もないから、覚悟もないのだ。だったら、親に従えばいいのかもしれない。
「いまの会社をやめなさい」という母に、私は黙ってうなずいていた。
私は、お見合いを再開した。Bさんの家をふたたび母とともに訪ね、みずから頭を下げた。そのときは、コンサルティング会社で秘書の仕事に就いていた。お見合いでも聞こえがいいと母も反対しなかったが、Bさんも「いいんじゃないか」と言った。最初のお見合いをしてから、2年近く、最後のお見合いをしてから、1年以上経っていた。
1994年の1月、雪が降った日曜日に、新高輪プリンスホテルのティールームで、お見合いをした。彼は、母親を同伴せず、ひとりで来ていた。一歳上の整形外科医で、次男だった。隣の区に住んでいて家も近く、屈託のない明るい人だった。なんとなく、育った環境も似ていた。我が家と同じ慶尚道が故郷で、父も母もかなり気に入ったようだった。
私は、この人と結婚することになった。医師の父親が癌の末期だということもあって、早く結婚した方がいいと言われ、3月には結納、4月には披露宴なしで教会での挙式だけをした。まさに、スピード婚だ。
結婚後、私は、母のすすめで、フィニッシングスクール(花嫁学校)と料理教室、お花の教室に通い始めた。つまりは、花嫁修業を遅ればせながらスタートしたということだ。仕事は結婚相手の父親が亡くなったり、地方の病院への転属などがあり、続けられなくて辞めた。
フィニッシングスクールでは、ひとりの在日コリアンの女性に出会った。彼女は地方在住で、新幹線で通ってきていた。結婚を控えており、やはり、お見合いで相手と知り合ったという。同じような境遇もあって、すぐに親しくなり、アフタヌーンティーをよくともにした。すると、彼女にもたらされた縁談のなかに、私にも勧められた人がいた。関西のお見合いおばさんからの縁談だったそうだが、あらためて、在日コリアン社会の狭さを実感した。
彼女とはなんでも話せていまでも親しく付き合っている。フィニッシングスクールでは、紅茶の淹れ方なども習い、ふたりとも紅茶が好きになったので、マリアージュフレールのティールームでアフタヌーンティーをすることもある。彼女もお見合いを何度かしているので、会うと、お見合いのエピソードは鉄板のネタであり、いまとなっては笑い話になっている。在日あるあるや、祭祀の話、語る言葉は尽きない。
同じような境遇が、そして似たような葛藤を持っていたことが、いかに心を通じさせるかということを痛感する。
英国式アフタヌーンティーといえば、スコーンが出てくるのが定番だ。クロテッドクリームをたっぷりと塗っていただく焼きたてのスコーンは本当に美味しいし、大好物である。
スコーンは、このようにアフタヌーンティーに出てくるもののほかに、アメリカ式のスコーンもある。こちらは、硬くてごつごつしているが、そっちも結構好きだ。
きっかけは、子育て中に食べたことだ。
大学病院勤務の元夫は、当直や呼び出しも多く、休日もアルバイトなどを入れていたので、子育てはほぼワンオペだった。
結婚して3年後に生まれた長男は、夜泣きがほとんど一時間おきで、母乳育児も加わって、私はぼろぼろだった。夜泣きは1歳で断乳するまで続いた。
ベビーカーや車のベビーシートではよく眠ってくれるので、寝かせたくて昼間に公園に行ったり、雨の日は車に乗せて、近所をぐるぐるとまわったりしていた。そのあいだはつかの間、私の自由な時間ができるからだ。
息子が8か月くらいのときだと思う。みぞれまじりの雨の降る寒い日、ぐずってばかりの息子を車に乗せた。寝不足でふらふらだったから、息子が寝たら、私も車の中で仮眠するつもりだった。家にいると、抱き癖もあって、なぜかすぐ目覚めてしまうから、最後の手段にすがる思いだった。
案のじょう、息子は車が走り出して10分もしないうちに眠りに落ちた。ファミリーレストランの駐車場に入ろうかと探していると、スターバックスを見つけた。スターバックスなんて、ずいぶん久しぶりだと嬉しくなって、車を路肩に停めて降り、急いでカフェインレス珈琲(母乳だったからカフェインは避けていた)と、ガラスケースの中で最初に目についたチョコレートスコーンを買った。息子を車に置いていたから、ひやひやだった。
運転席に戻り、チョコレートスコーンを口に入れると、むせてしまった。息子が起きたら大変と急いで珈琲で流し込むと、珈琲はまだ熱くて、口の中を火傷しそうになってしまった。あつっと大声が思わず出て振り向いてみると、息子はすやすやと寝息をたてて熟睡している。
私、なにやっているんだろう。
涙が零れ落ちて、しばらくハンドルに顔をうずめていたが、顔をあげて、スコーンを食べ続けた。甘くて、美味しくて、また頑張ろうと思えた。
スターバックスでチョコレートスコーンを見かけると、いつもこの日のことが思い出された。子育ても終わり、楽になったなあと、懐かしく、食べてみることもあった。
お茶をする、という機会は、子どもが幼稚園にあがってから、ママ友たちと持つことがとても多かった。そこでは、ぎこちないながらもお世辞を言いあったかと思えば、マウンティング合戦がくりひろげられたり、噂話に花が咲いたり、子育ての悩みを打ち明け合ったり、夫の愚痴をこぼしあったりする、喜怒哀楽さまざまが交錯する場だった。子どもがいて夜には出られないから、ママ同士の社交はどうしてもランチやアフタヌーンティーとなる。そんな様子は「ランチに行きましょう」(徳間文庫)に描いた。
最近の私のアフタヌーンティー、午後のお茶の時間、といえば版元の担当さんとの打ち合わせをすることも多い。そういうときは仕事モードである。閉所恐怖症なので、広々としたホテルのティールームだと嬉しい。珈琲のおかわりを何杯でも頼めるところがけっこうあるから、長い時間になっても、たくさんしゃべって喉が渇いても、安心である。
ホテルのティールームに行くと、自分のお見合いのことが蘇るが、いまでも、たまにホテルでそれらしき人達を見かける。そういうときは、つい耳をそばだてて、話を盗み聞きしてしまいそうになる。マッチングアプリで知り合ったのでは?と思われる男女の会話も聞こえてくる。盗み聞きはあまりいいことではないけれど、おおいに作家的好奇心が刺激される瞬間でもある。
韓国でもアフタヌーンティーがはやっているが、昨年、ソウルの梨花女子大学近くのカフェで、親しい韓国の友人とともにアフタヌーンティーをいただいた。マリア―ジュフレールやNINA、フォートナムメイソン、フォションなど、たくさんの紅茶の銘柄をそろえ、スコーンも美味しく、とても素敵な店だった。また、あそこも訪ねてみたい。一緒に行った友人は、仕事やプライベートで嫌なことがあると、ひとりでそこに行き、アフタヌーンティーというぜいたくな時間を過ごしているという。心の栄養を摂っている、その行為、すごくよくわかる。
一昨年、ベトナムで泊まったいくつかのホテルのアフタヌーンティーもとてもよかった。そのひとつホーチミンのホテルは、ベトナム戦争時、米軍の将校が泊っていて、実はベトコンが職員で、銃撃戦もあったという話を聞いたが、いまは、優雅なアフタヌーンティーを味わえる場所となっている。フルーツが豊富で、スイーツも秀逸だった。
また、ハノイのホテルでアフタヌーンティーをしたとき、横から韓国語が聞こえてきた。つい目をやると、中年のおじさんと若い女の子という、いかにもパパ活のような組み合わせの二人がいた。女の子はベトナム人で男性が韓国人だった。彼らの姿を見て、私のアフタヌーンティーの時間は、もやもやとしたものに変ってしまった。
平和だからこそ、アフタヌーンティーを堪能できるのだと、しみじみ思うが、戦争や、格差や差別、搾取の片鱗は、アフタヌーンティーの場にも存在する。そして思い出までも、いま起きている侵略に汚される。パレスチナのことを思うと、もはや無邪気にスターバックスのチョコレートスコーンを食べることはできない。
先日、キティちゃんのアフタヌーンティーに娘と行った。50年近く在るキャラクターのおかげで、わずかに現実逃避できた。

(著者提供)
【プロフィール】 深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
■ 小説家 深沢潮 エッセイ「李東愛が食べるとき」
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、「無関心を関心に」「声なき声に光をあてる」ために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。