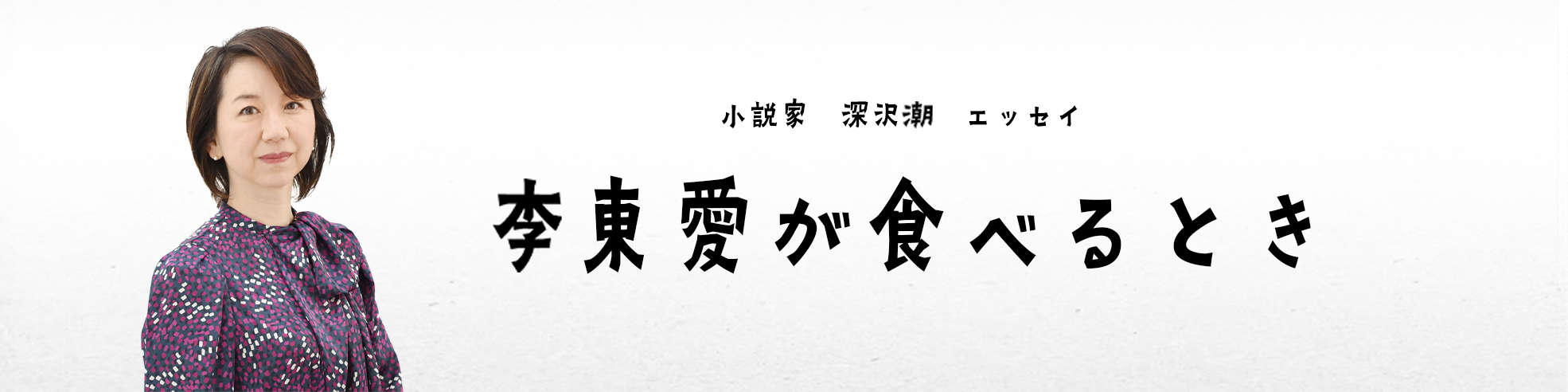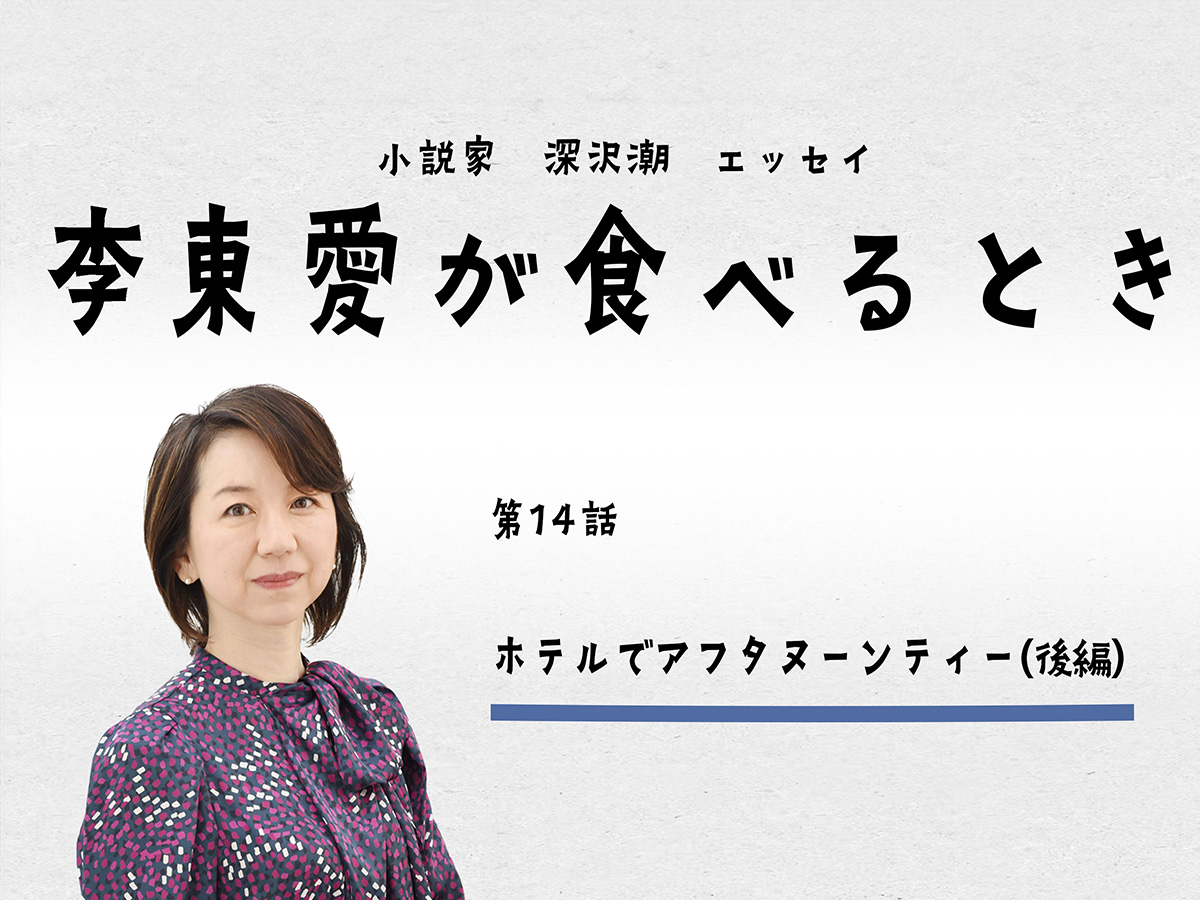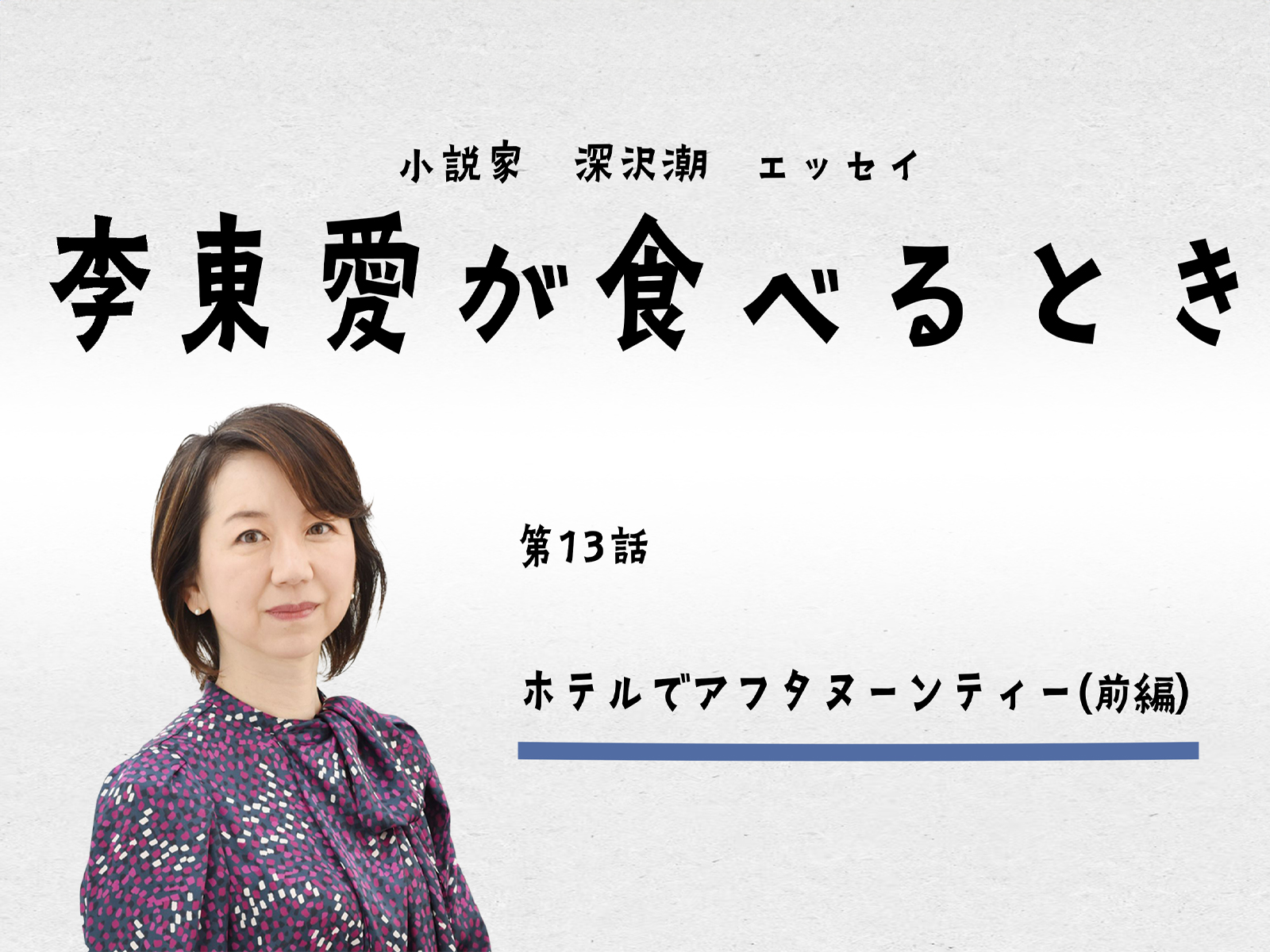最終話 しめは、ヌルンジかお茶づけか
10年くらい前、小説の取材のため、韓国に一週間ほど滞在した。そのとき初めて、韓定食のコースをいただく機会に恵まれた。
全羅道の郷土料理店で、ハンバーグのように、ひき肉をこねて焼いたトッカルビが出てきたのが、印象に残っている。テーブルからはみ出るほどの品数で、とうてい食べきれなかったが、最後のヌルンジに、ほっこりとした気持ちになった。
土鍋に炊いたご飯をよそって残ったおこげの部分に、お湯を流し込んでいただくのがヌルンジだった。
あ、これはもしかして。
私は、祖母の家で「お茶づけ」と呼んで食べたものが、ヌルンジだったことに気づいた。
余談だが、ヌルンジの飴を、本物のヌルンジを食べる前に、韓国のどこかで食べたことがあったが、そのときは、ヌルンジがああいったお茶づけ的なものだとはまったく想像できなかった。だけど、あれはけっこう好きな飴だ。
母方の祖母は、祖父と居間で食卓をともにすることなく、いつも台所で残り物を食べていた。そのとき、たいがい、ガス炊飯器にやかんの麦茶を入れて、おこげの部分をそぎ落として最後に食べていた。私が傍で見ていると、分けてくれた。その「お茶づけ」は、おこげが香ばしく、大好きだった。
考えてみれば、幼い頃、家でも、最後に「お茶づけにする?」と言われて、残ったごはんにお茶を入れて口に流し込むようにして食べる、ということがあった。ご飯が多すぎても残すことが許されなかったので、最後の「お茶づけ」に何度も救われた。
満腹でもお茶と一緒だと、食べやすかった。食欲がないときも同様だ。
最初から、永谷園のお茶漬けのりをお湯で溶かしてお米とともに食べるのも、好きだった。安藤広重の東海道五十三次の浮世絵のカードが永谷園のお茶漬けのりについてきて、それを集めていたこともあった。
大人になって、お酒の席などで、最後にお茶づけをいただくのも結構好きだ。散々食べたり飲んだりした後でもつい頼んでしまう。
お茶づけはだいぶ成長してから、京都などの観光地のお茶漬け屋さんに行って、なんとなく私が思っていた「お茶づけ」と違うと気付いた。また、だしでいただく鯛茶漬けは、我が家にお目見えしていたものとまったく異なるものだった。ひつまぶしもお茶づけの一種だろうが、あれを食べたときも驚いた。
もちろん、これらの日本式のお茶漬けも、大好きだ。これまでのエッセイを読むと、こってりしたものやボリュームのあるものを取り上げているが、実は、どちらかといえば、ふだんは漬物とお茶づけがあればじゅうぶん、という感じだ。
私がなにげなく当たり前と思っていたことが、実は、朝鮮の食文化や習慣であったことにあとになって気づくことは結構多い。
ごはんを味噌汁にまぜて食べるのも、我が家では日常的におこなっていたことだった。だから、給食で味噌汁が出たとき、私は迷いなくごはんを入れた。すると、友達が先生に言いつけて、先生から「行儀が悪い」と怒られた。
ご飯を汁物に入れる、いわゆるクッパは、私の好物だったので、戸惑ったし、行儀が悪いと言われて傷ついた。いや、そのころは、それがクッパだともわからず、家でいつもやっていることをしてみただけのことだった。
家庭でかろうじて守られていた朝鮮半島の食の片鱗が、ひとたび家の外に出ると「おかしいこと」「変わったこと」になってしまった瞬間だった。
韓国に行ったときや日本の韓国料理店で、好きでテンジャンチゲをよく食べるのだが、ごはんをチゲに入れると、小学校で怒られたことがいつも思い出される。
そういえば、私自身も、祖母が片膝をたてて食べたり、父が器を持たずに、日本で言う「犬食い」みたいに、食卓の上の食器に顔を近づけて食べたりするのがみっともないなあと思っていた。のちにあの座り方や食器を持たないことが朝鮮半島では当たり前のことだと知って、みっともないなどと思っていて申し訳ないと罪悪感にさいなまれた。
ところで、私はとにかくスープが好きなのだが、これもやはり幼い頃からなじんでいたからだと思う。なかでもワカメスープには特別な思いがある。
長男を出産後、実家に一ヶ月ほど滞在したが、そのあいだ、「お乳がよく出るように」と母がワカメスープを作って毎日のように出してくれた。ワカメスープはいろんな味付けに替えてくれて、ちっとも飽きなかった。たぶん、朝鮮半島の人が思いもつかないようなレシピにアレンジもしていたと思う。
夏場に母が作る冷たいワカメのスープも忘れられない。酢が入っていて、きゅうりとゴマがアクセントになり、さっぱりしている。こちらは、韓国で食べられているものとほぼ同じだったようだ。
母の作る、干しだらが具のプゴクスープもかなり好きだった。以前、ソウルで行われた自著のプロモーションイベントで、好きな韓国料理は何かと聞かれて「プゴクスープ」と答えたら、笑われてしまった。
「お酒をかなり飲むんですか? プゴクスープは二日酔いのときに飲むから」と司会の方に言われて、へー、と不思議な気分になった。我が家では、父が下戸だったが、けっこうな頻度で食卓にプゴクスープが味噌汁の代わりに出たからだ。今思うと、ハンバーグとプゴクスープなんて、洋韓折衷料理だ。フュージョン料理が韓国で流行って久しいが、母は時代を先駆けていたのかもしれない。
そうそう、ワカメスープといえば、産後の思い出と結びついていたけれど、我が家では誕生日にワカメスープという習慣はなかった。韓国ドラマを観るようになって、誕生日に食べることを知った。三世代を過ぎると、抜け落ちてしまう文化や習慣はけっこうある。強い意志を持って守って行かなければ消えて行ってしまうだろうが、いまは、韓国に行ったり韓国ドラマを観たりすることで、文化や風習をあらためて見直すことができるのが楽しい。
このように、実は、ある意味、韓流ブームは、アイデンティティやルーツの確認作業におおいに役立っている。
たとえば、私にとって、韓国ドラマや映画は答え合わせのような一面もあった。
韓国ドラマや映画を観て、過干渉すぎる家族関係が描かれていて「うちの親だけではないのか」と思うこともある。あの、強烈なまでに子どもに執着する母親を見て、うちの母と変わらないと思ってぞっとすることもしばしばだ。
また、父が、大声で威嚇したり、ちっちっちっと舌を鳴らして不平を表したり、すーっと音をたてて息を吸って威嚇すること、すぐに怒鳴ることなどが嫌でたまらなかったが、ドラマでは頻繁におじさんたちのそういう仕草を見る。女性が舌を鳴らしていることもある。
ところが、在日料理と言われるものは、韓国のコンテンツや韓国で実際に見るものと、どこか異なる。
そもそも在日料理とは、朝鮮半島の食が、海を越え、断絶や時間経過によって、日本の地でしなやかに変化してきたものだ。焼肉にしろ、冷麺にしろ、スープにしろ、独特のものである。
たとえば、テグタンスープというのが、焼肉屋によくあったと記憶しているが、あれは、在日料理そのものだろう。辛い肉のスープ、韓国であれば、カルビスープやユッケジャンに近いものだ。だが、その両方とも微妙に違う。慶尚北道の大邱出身の在日コリアンがきっと名付けたのではないかと思う。牛肉と牛骨で作られるスープに野菜を入れ、唐辛子で味付けるスープは、本場の大邱では、タロクッパと呼ぶようだ。
韓国でテグタンスープというと、魚のタラと野菜を入れ、ニンニクや生姜、唐辛子で煮込んだものになってしまう。
あの赤いテグタンスープは、 ガラパゴス化した朝鮮半島の料理であり、まさに、在日料理だろう。
私は、在日料理が愛おしい。
結婚後、婚家で祭祀や秋月の準備をしたが、あれもガラパゴス化の象徴のようだった。ジョンやチジミがまるでお好み焼きのようだったり、チャプチェに京人参を入れたり、味付けも毎回異なったりしていた。もちろん、韓国でもそれぞれの地域や家庭の味というのはあるだろうが、在日コリアンにいたっては、オリジナリティがさらに豊富だ。一世たちが日本で、その土地で手に入るものを使って苦心して料理を作ってきたことがうかがえる。
在日コリアンのアイデンティティがさまざまであるように、在日料理も多様で、濃淡もそれぞれ異なり、いろどり豊かである。そして、「そんなの韓国(朝鮮)料理じゃない」と本国の人たちに言われたり、驚かれたりするのも、在日コリアンが「あなたは韓国(朝鮮)人とは言えない」と言われることと通じている。
けれども、私たちのような存在は、もっと胸を張っていいのだと、このごろは強く思う。
別に、どちらの国の人でもいいじゃないか。
どちらの国の人でなくてもいいじゃないか。自分は、自分なのだ。
唯一無二のごちゃまぜの存在じゃあだめなのか。
食にまつわるエッセイを書いてきたが、私自身の来し方をつづったものになっている。両親、とくに母との確執が、私の人生において、どれだけ大きなものだったかをあらためて自覚した。
また、信仰が厚かったことや、恋愛にエネルギーを注いでいたこと、自分の中にある根強いルッキズム、作家になるまでの歩みなどを思い返し、すべてのことを書いたわけではないが、心にわだかまっていたことが表出できて、人生の棚卸ができたような気がしている。
このエッセイに書いたことのなかで、その後、いくつか新しいエピソードがあるので、ここに記しておきたい。
第5話、「酒とともにうたう」で、祖父のことを書いた。
母方の祖父は、関東大震災の際に、自警団に殺されそうになり、警官が止めに入ったことで命を救われた。そして、警察署にいる旨が、収容者の名前が朝鮮の新聞に載ったことで、韓国にいた祖母が祖父の存命を知るにいたった。
この話をある大学教授に話したところ、研究室の大学院生が当時の新聞から、祖父の名前を見つけてくれたのだ。祖父は、大井競馬場に収容されていたことが東亜日報に載っていた。また、来日目的が学業のためだったことなどが明らかになった。
家族に語り継がれていたことが、確固たる証拠によって裏付けされて、とても嬉しい。
もうひとつ、第7話の「肉をともに食べるひと」に、大学生一年のとき、英語のスピーチ大会を見学に行って、韓国の学生と交流を持った話を描いた。そして、金君に心惹かれたこと、さらに、金君から父宛に手紙が来たエピソードがある。
英語のスピーチ大会には、私の大好きな先輩が出ていたのだが、このエピソードのおかげで、しばらく疎遠だった先輩と久しぶりに会うことができた。
先輩は、韓国の学生たちの名前と当時の住所を記したメモをいまも持っていたのだった。学生たちのなかに、金君はふたりいて、私がエッセイに書いた金君のことは「かわいいキム」と添え書きしてあり、先輩の記憶に強く残っていた。
先輩によると、私たち皆で焼肉を食べたあと、金君がしきりに私のことを先輩に聞いてきた、とのことだった。
「純粋に東愛ちゃんのことが好きだったんだと思うよ。それで手紙を書いたんだと思う」と先輩は言った。
メモの住所によると、1985年当時金君は、ソウルの江南の一軒家に住んでいた。もしかしたら、その住所にまだ親や親族が住んでいるかもしれない、ひょっとして本人が住んでいる可能性もある。だから、連絡を取ってみる、と先輩が言ってくれて、金君宛に手紙を書いてくれた。
私は、ひょっとすると、再会できるのではないか、とわくわくして待ったが、返事はなく、半年以上が経っている。
まあ、ドラマや映画、小説のようなことは、そう簡単には起きないものだ。
けれども、先輩と旧交をあたためることができたのだから、あのエピソードを書いてよかった。
先輩はあのときの学生のひとりといまでも連絡をとっている。その人は私と父のことを覚えてくれているそうだ。そして先輩は、韓国語訳された「海を抱いて月に眠る」を彼の住む米国に送ってくれた。
本を通して、なつかしい人と再び会うことができるなんて、幸せなことである。
食べることは生きることであり、生きてきた軌跡の断片を、このエッセイに書いた。
ここまでお付き合いくださり、ありがとうございました。

(Photo by hot8030/iStock)
【プロフィール】 深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
■ 小説家 深沢潮 エッセイ「李東愛が食べるとき」
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、「無関心を関心に」「声なき声に光をあてる」ために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。