私たちがイスラエルを出た理由―「閉ざされた壁の向こう側」に目を向けるとき(高橋真樹さん寄稿)

本記事はノンフィクションライターの高橋真樹さんによる寄稿記事です。高橋さんは持続可能性や人権問題をテーマに取材・執筆を続けており、国際協力、核廃絶、パレスチナ難民支援などに携わってこられました。高橋さんの新刊『もしも君の町がガザだったら』(ポプラ社/2025年7月24日出版)では、本記事インタビューの一部が掲載されています。
パレスチナの人々に激しい攻撃を加えるイスラエル軍や社会のあり方に疑問を持ち、イスラエルを離れた家族がいる。2024年2月、イスラエル人のリラン・ベンアミさん(45)と北原葉子さん(50)のご夫婦は、幼い息子を連れて、日本に移住した。
建築家のリランさんと、クリエーターの北原さんは、2006年からイスラエル最大の都市・テルアビブに暮らしてきた。しかし、2023年10月7日のハマスによる襲撃を受けたイスラエル社会の空気は一変したという。以降、夫婦間で対話を繰り返す中、二人はイスラエル政府や軍を批判し、パレスチナ人との真の共存を求めるようになった。
イスラエルの一般市民として暮らしてきた二人が、なぜパレスチナ人の命に目を向け、イスラエルを離れる決断をしたのか。そしていま、何を思い日本で発信を行うのか。その思考のプロセスは、ガザの人々の命に無関心なイスラエル社会を映し出す鏡にもなる。お二人に話を伺った。(お二人への取材は、2024年12月と25年6月の2回、合わせて5時間にわたり行った)

リラン・ベンアミさんと北原葉子さん(2025年5月©高橋真樹)
Contents 目次
国のために命をかけることは誇りだった
――イスラエル国民には兵役義務があります。イスラエル社会の中で、イスラエル国防軍(IDF)はどのような存在なのでしょうか?ご自身の経験と合わせて教えてください。
リラン 私はリベラルな家庭で育ちました。パレスチナの占領には反対だし、暴力的な入植者ともかかわりたくありませんでした。そんな私にとっても、軍は特別な存在でした。物心ついた頃から、イスラエルは敵に囲まれていて、軍が守っていると教えられます。親も兄弟もみんなが軍の経験者で、家族や自分と一体の存在なのです。
1998年、18歳で兵役(※)に就いた際には、(パレスチナの)ガザ地区や西岸地区といった占領地ではなく、国境地帯を守る部隊を希望し、実際にその任務に就きました。レバノンとの国境にあり、ヒズボラ(レバノン南部のイスラエルへの抵抗勢力)に関する情報収集を行う部隊でした。戦闘そのものはありませんでしたが、国境地帯には地雷が仕掛けられていて、常に命の危険が伴っていました。それでも当時は、命をかけて国を守るということに誇りを感じていました。
もっとも、あの頃の自分は、命の重みを本当の意味で理解できる年齢ではありませんでした。まだ社会を知る前の若者が、当然のように命を差し出すような状況にあったことは、今振り返ればとても恐ろしいことだったと思います。
(※)イスラエルの徴兵制:イスラエルには18歳以上の男女に兵役義務がある。男性は32ヵ月、女性は24ヵ月の間、軍務に就く。

兵役に就いていた当時のリラン・ベンアミさん(左側/1998年/リランさん提供)
――リランさんの軍との接し方が変わったのはいつからでしょうか?
葉子 ユダヤ系イスラエル人は、軍を退役した後も予備役兵として毎年およそ1ヵ月間、仕事を離れて軍事訓練を行います。戦闘があれば、前線に動員されることもあります。私は国のために命を捧げるという考え方自体に根本的な疑問を抱いており、その価値観は私には到底理解できないものでした。2012年、私が妊娠中だったとき、彼が予備役に参加することに強く反対しました。「子どもが生まれようとしているのに、戦争で命を落とすかもしれないなんて、受け入れられない」と。
リラン 予備役を抜けても明確な罰則はありません。少数ですが、家族などの理由で抜ける人もいます。私が司令官に「予備役には行かない」と伝えると、司令官は「きっと部隊が恋しくなって後悔するよ」と言いました。確かに部隊には、18歳から一緒に過ごしてきた仲間たちがいます。友人たちと年に一度集まって訓練するのは、同窓会の合宿のような懐かしさもありました。
葉子 イスラエルの人は、軍を離れた後も予備役の訓練を毎年受けるので、その度に、心理的に軍のシステムに引き戻されます。これが、軍への信頼度をより高めることになっているんだと思います。
リラン この時、予備役を辞めた理由は、彼女の立場や気持ちを尊重したかったからです。軍のしていることに疑問を持ったわけではありません。自分の中で本質的な変化が起きたのは、10月7日の事件が起きてからです。
壁の向こう側に目を向ける
――2023年10月7日にハマスがガザの壁を乗り越えて、イスラエル側におよそ1200人の犠牲者と250人以上の人質が出ました。その後、軍によるガザへの激しい爆撃がはじまります。お二人はどのように感じ、どのような対話をされたのでしょうか?
リラン 最初は他の多くのイスラエル人と同様に、「なんてひどいことをするのか」と、非常に大きな衝撃を受けました。これほど多くのユダヤ人が一度に殺されたのはホロコースト以来のことであり、「第二のホロコースト」と呼ばれるほどの深い痛手として受け止められました。
それにもかかわらず、社会は徐々に日常に戻っていきました。イスラエルでは、戦争や衝突が周期的に起きるため、多くの市民が無関心でいることに慣れてしまっています。嫌な気持ちにはなっても、それ以上考えない、あるいは見ようとしないという態度が身についているのです。特にテルアビブのように、直接の被害を受けにくい都市では、その傾向が顕著です。向き合わなければ、嫌なものを見なくて済むという感覚が、私自身の中にもありました。
葉子 私の受け止め方は違いました。もちろん、ハマスが無防備な民間人を標的にし、命を奪い、恐怖と破壊をもたらしたことは、凄惨で耐え難いものです。これらの行為は、明らかに人道に対する重大な罪です。
しかし、壁一枚隔てて抑圧されている人たちの隣で行われる平和で自由な時間を求めるパーティは、まるで向こう側の人々の人間性を無視することを象徴しているように感じました。あのような悲劇が起きた背景に、壁の向こうにいる人々の長年の抑圧や苦しみがあったのではないか。そうしたことを無視して「テロ」だけを強調する語りに、強い違和感を覚えました。どんなに許されない行為であっても、そこに至るまでの怒りや絶望が存在していたという事実を無視してはならないと思いました。
けれど、周囲のイスラエルの知人たちはまるで口をそろえたように、「私たちは戦争をしたくないのに、ハマスが襲ってくる。だからガザ攻撃は仕方ない」と言うのです。それは信念というより、まるで思考停止の合言葉のように感じられました。話をする中で「あなたはパレスチナ側だ」と言われ、関係が途絶えた友人もいます。
10月7日からすぐ、戦闘機が、朝から夜までテルアビブの空を絶えず往来していました。ガザでは毎日、子どもたちが殺されていきました。私はそれを想像するだけで恐ろしかったです。しかし、イスラエル社会の多くは、表面的には通常の生活に戻っていきました。この「日常への戻りの早さ」こそが、長年の戦争慣れと、他者の死に対する感覚の麻痺を物語っているように思えました。
とはいえ、今回の事態は、従来の戦争や事件とは明らかに異なっていました。イスラエル側の被害の規模がかつてないものであったことから、イスラエル政府による軍事的対応も大幅に拡大され、予備役兵の招集数は過去に例を見ないほど増加しました。国全体に強い緊張感が走り、加えて「国家を守らなければならない」という感情の共有によって、社会全体にかつてないほどの一体感が生まれていました。人々は不安と怒りを抱える一方で、まるで一つの集団として同じ方向に動かされていくような、強い同調圧力に包まれていたのです。
当時、リランがまったく無関心だったわけではありません。ただ、私とは受け止め方が大きく異なっていました。背景には、イスラエルという「戦時国家」としての社会構造と、その中で育つことによって培われた感覚的な慣れがあったのだと思います。私はさまざまな情報を調べ、学び、ガザの写真や動画を彼に見せながら対話を重ねました。時には言い合いになり、私が感情をあらわにすることもありましたが、そうしたやりとりを通じて、彼も次第に向き合うようになっていきました。
リラン 私は最初、見たくない現実には目を向けず、心を閉ざしていました。受け止めきれる自信もなかったのだと思います。でも、葉子が何度も真剣に訴え続ける姿に向き合う中で、私は次第に無関心ではいられなくなっていきました。彼女の痛みが、私自身の中にも響くようになっていったのです。それまで私は、パレスチナ人の犠牲者のことを深く考えたことがありませんでした。でも、葉子は、ガザの子どもたちが受けている理不尽な暴力に深く心を痛めていました。彼女を通して、私ははじめて、この地で本当にどれほど残酷で悲しいことが起きているのかを、自分のこととして感じるようになったのです。けれど、こうした気づきを得る機会は、残念ながら多くのイスラエル人には与えられていません。

テルアビブ中心部にあるカフェの風景。ガザ攻撃が続く中でも、変わらない日常がある(2024年6月/Teo K / Shutterstock.com)
社会の空気に慣れる恐怖
――その後2024年2月に、日本への移住を決めました。23年10月からおよそ4ヵ月後です。出国を決断した背景には、何があったのでしょうか?
葉子 彼の母国であり、私自身も20年を過ごしてきた場所なので、良い思い出は数多くあります。日本にいた頃よりも、人との絆や温かさを身近に感じ、とても深い愛着がありました。しかし現在は、そうした連帯感が、別の形で作用しているように感じています。2023年10月7日の出来事を経て、この社会の空気の中で暮らし続けることは、自分にはもう難しいと感じるようになりました。もちろん安全面への懸念もありましたが、それ以上に、自分自身がこの空気感に慣れてしまうことへの強い恐怖がありました。
当時11歳だった息子の存在も、大きな理由です。息子は18歳になれば徴兵対象となるため、その影響から守りたいと考えました。また、社会的な空気や教育環境のなかで、パレスチナ人に対する偏見が身近にあることにも不安を感じました。そうした環境では、子どもを健全に育てることは難しいと判断しました。

北原葉子さん(2025年5月©高橋真樹)
「Never Again」の真意
――ガザの犠牲者は、増え続けています。イスラエルの人たちの多くは、なぜガザの惨状に目を向けようとしないのでしょうか?
リラン イスラエルでは、ホロコーストの悲劇を乗り越え、荒れ果てた土地を耕し、ゼロから国を築き上げたという誇るべき歴史が美しく語られています。この物語自体には確かに重要な意味があります。しかし同時に、ホロコーストの記憶は政府や教育の都合によって利用されてきたとも感じています。
学校では「Never Again(二度と繰り返さない)」という言葉が繰り返されますが、それは「人類に対して」ではなく、「ユダヤ人に対して」という限定的な意味で用いられています。子どもたちは、自分たちユダヤ人だけが永遠の被害者であるという意識を、幼い頃から徹底的に刷り込まれます。
また、イスラエルの教育では、自国の歴史が美化される一方で、パレスチナ人についてはまったく教えられません。土地の奪取や占領の歴史、そこに生きてきた人々の存在、彼らの苦しみや犠牲について触れられることはありません。日常生活でも、アラブ人(パレスチナ人)は「危険」「テロ」「ミサイル」といった文脈でしか語られません。
そのような教育の中で10月7日のような事件が起きると、多くの人々は、その背景にある複雑な現実を見ようとせず、すぐに「第二のホロコーストだ」と反応します。私は、こうした一方的で排他的な教育こそが、他者の犠牲に対する無関心を生む土壌を作り、加害の現実から目を逸らす口実になっていると感じています。
「人間動物」
――10月7日の後、イスラエルのガラント国防相(当時)は、ハマスを「人間動物」と表現し、後にガザのパレスチナ人全体にも当てはめられていきます。こうしたパレスチナ人の「非人間化」は、なぜ可能になっているのでしょうか?
リラン 私は、教育の他に大きな要因が2つあると思います。
ひとつ目は、物理的な「壁」が築かれたことです。私が子どもの頃の80年代は、今よりも少しは、相手に対する共感力が社会にあったように思います。パレスチナの民間人に対する虐殺に、抗議の声を上げるイスラエル人も少なくありませんでした。レバノン戦争(1982年)の時の虐殺では抗議デモが広がり、国防大臣が辞任したこともあります。
しかし、西岸は分離壁で閉ざされ(2002年〜)、ガザは封鎖されました(2007年〜)。そうしてパレスチナ人の暮らしは「壁の向こう側」へと追いやられ、私たちの目に触れることはほとんどなくなりました。壁の向こう側の人々の姿も、声も、日常の痛みも、感じずに済む社会が出来上がってしまったのです。この視界と感情の遮断が、パレスチナ人を他者ではなく、非人間的に扱うことを可能にしてしまっているのだと思います。
第二次インティファーダ(2000〜2005年)の際、自爆攻撃が相次ぎました。私は「バスで自爆するなんて、正気とは思えない、到底理解しがたい人間だ」と思っていました。多くの市民と同様に、「壁の向こう側からテロリストがやってくる」というイメージで捉えていたのです。一方で同じ頃、イスラエル軍の戦闘機が落とした爆弾で、大勢のパレスチナ市民が殺されていました。でも私たちは、壁の向こうの被害については、見ようとしませんでした。戦闘機のパイロットは、「国を守るヒーロー」として扱われていました。
もう一つの原因は、メディアの伝え方です。10月7日の事件は、ハマスの「絶対的な悪」のイメージをイスラエル社会に植え付けました。平和的なキブツを襲い、人々を撃ち殺し、子どもを誘拐し、家を焼き、という一連の衝撃的な出来事が、人々にホロコーストを想起させたのです。メディアは、人々に怒りや恐怖の感情をより強く引き出すために、映像やストーリーを巧みに構成しました。
あの日の出来事は、過去の一瞬の事件として扱われることはなく、その後も現在に至るまで、さまざまなメディアで繰り返し報道され、社会の記憶に強く刻まれ続けています。一方で、一部の報道では、ガザの住民すべてがハマスを支持しているかのような印象を与える内容も見受けられました。
こうしたメディアの手法は、ときに正義の名のもとに行われる暴力のように感じます。実際には、私たちの思考や感情は巧みに操作されているのです。それが、ガザの人々の命への無関心さにつながっています。

リラン・ベンアミさん(2025年5月©高橋真樹)
――25年5月以来、停戦を求める声が高まるなど、イスラエル社会のガザ攻撃に対する変化が伝えられるようになりました。これについてはどう感じていますか?
リラン 確かに変化はありますが、正しい理由から起きているものではありません。大半の人々の関心は、イスラエル人の人質と兵士の命です。「ガザ攻撃は、人質の命に危険をもたらしている」「それなのに、ネタニヤフ首相は、自分の政治生命を伸ばすために、戦争を継続している」という理由です。停戦を求めるほとんどの人の心には、パレスチナ人側の苦しみへの想像力はありません。
私が見てきた限り、本当にパレスチナ人の命や尊厳を思って声を上げている人は、ごく一部の活動家だけです。彼らは社会から強い圧力や非難を受けながらも、声を上げ続けています。たとえば、テルアビブやエルサレムで「占領の終結」や「パレスチナ人との共生」を訴えるデモに参加した人たちは、警察に排除されたり、時には職場や家族から非難されたりすることもあります。SNSで意見を表明しただけで「裏切り者」「ハマスの味方」と激しい言葉を浴びせられることも少なくありません。それでも彼らは、街頭でプラカードを掲げたり、大学での討論を主催したり、国際的なメディアに寄稿したりして、声を上げ続けています。
停戦を求める声自体はもちろん重要ですが、その声が「自国の損失」を起点とする限り、壁の向こうにいる人々の存在にはつながりません。そこに目を向ける想像力なしには、真の意味での平和は実現しないのです。
自分たちだけが幸せにはなれない
――真の平和を実現するために、イスラエルは何をするべきでしょうか?
リラン すべては教育からはじまります。もっとも大切なことは、子どもたちに、隣人が抑圧を感じている限り、自分たちだけが幸せに生きることはできないと教育することです。パレスチナ人を恐れることをやめ、同じ人間であると教えるのです。パレスチナ人にも、イスラエル人が持っている人権、教育、経済などを持てるようにしなければ、いくら壁を作り、兵士を送り、攻撃を続けても、安全にはなりません。
イスラエルには2つの選択肢があります。隣人を自分たちと同じように幸せにしようとするのか。それとも、ホロコーストのように殺すのか。いまの政権は後者を選ぼうとしています。しかし、そのやり方では、イスラエル人も多くのものを失い続けます。

空爆を逃れてエジプト国境の町、ラファに避難した家族。厳しいテント生活を送る(2024年2月/Anas-Mohammed/Shutterstock.com)
――パレスチナ難民については、どのように考えているでしょうか?
リラン イスラエル人がもっとも恐れているのは、パレスチナ人が元々住んでいた家に帰ってくることです。自分たちの暮らしが失われることが怖いので、パレスチナ難民(※1)の帰還の権利を認めないのです。でもこの問題は、帰りたいと願う人たちに、帰る権利を与えることでしか、解決できません。
ドイツには、国家による歴史的責任への補償として、ナチス政権下で迫害を受けたドイツにルーツを持つユダヤ人とその子孫に対して、90年近く経った現在でも、市民権再取得の制度(※2)があります。
それと同じように、イスラエルもパレスチナ人から奪ったものを補償するべきです。「パレスチナ人が戻ってきても、住まわせる場所がない」と言う人もいます。しかしイスラエルは多くの入植地を作り、外国からの移住を奨励してきました。その気になれば、パレスチナ難民が住む場所も作ることはできるのです。大事なのは、和解のための道を、イスラエル人とパレスチナ人が一緒に、対等に築くことです。それが民主主義というものです。
(※1)パレスチナ難民:1948年のイスラエル建国の前後に、故郷を追われて難民となった人々。当時、約75万人の人々が難民となり、ヨルダン川西岸地区やガザ地区、周辺のアラブ諸国に逃れた。現在では、その子孫を含めて約600万人(2023年12月時点、UNRWA)に増えている。
(※2)ユダヤ人のドイツ国籍取得:ドイツでは、ナチス時代(1933年〜1945年)に、ドイツ国籍を奪われたり、出国したりしたユダヤ人とその子孫に対して、申請があれば「再取得」という形で国籍を与えている(ドイツ基本法第116条第2項)。

和平交渉時も、パレスチナ自治区での入植地建設は続けられてきた。写真は東エルサレムにあるピスガット・ゼエブ入植地(手前)とアナータ難民キャンプ(奥)(ImageBank4u/Shutterstock.com)
「生存のための平和」は強い
――国際社会に求めるものは何でしょうか?
リラン 今回の件で、イスラエルを離れた人は、私たち家族を含めて何十万人もいると言われています。国の中で、国を変えることを諦めたからです。今後、イスラエル自身に問題を解決していく力があるのかどうかは、私にはわかりません。カギを握るのは国際社会です。
いまの状況を作り出した国際社会には、大きな責任があります。だからこそ、「イスラエルのしていることは、国際法違反だ」と圧力をかけるべきです。もし欧米の大国が、イスラエルに対して武器や資金の提供をやめれば、イスラエルは孤立して、平和の道を選ぶしかなくなります。日本政府も、イスラエルに対する態度をあいまいにしていますが、圧力をかけるべきでしょう。
生存のための平和の力は、単なる理想論ではなく、とても現実的なものです。それまで戦争を繰り返していたヨーロッパ諸国は、第二次世界大戦後に平和の道を選び、EUを作りました。戦争であまりに多くの被害が出たことで、生存のために戦争の可能性を排除しようとしたのです。強固な平和は、それ以外の道がないと理解することから始まります。
――日本に移住してから、お二人はメディア出演や講演などを通じて、国内外に自らの考えを発信しています。最後に、その心境について教えてください。
葉子 自分が経験したことを伝えて、この状況を止める力になりたいという思いに、迷いはありませんでした。もちろん世界は一晩では変わるものではありません。それでも、粘り強く続けていくしかないと思っています。そして私は、この時代だからこそ、決して人々が人間性を失ってはいけないと強く感じています。暴力や分断が広がる中で、他者の痛みに想像力を持ち続けること、それが私たち一人ひとりに求められていることだと思うのです。
リラン 日本に移住し、自分たちの生活もすっかり変わる中で、どこまでできるかというのは大きなチャレンジです。時々、なぜこれほどまでにひどいことが続いているのか、なぜイスラエル社会は変わろうとしないのか、やるせない思いにとらわれます。イスラエルの人々に対して、「なぜ気づかないのか」と怒りを感じることも少なくありません。
でも、その怒りをぶつけても、今のイスラエル社会の中では、真意が届かないことが多いと感じています。伝わるとしたら、「反対側の立場を理解することが、自分たち自身の利益にもつながる」という視点ではないでしょうか。隣人の痛みや苦しみに寄り添うことが、自らの幸福にもつながり、子どもたちにより良い未来を手渡すことになるのですから。問題の大きさに圧倒され無力感を抱くこともありますが、それでも、小さな声や行動が社会を変える力をもたらす可能性を、私たちは信じています。

リラン・ベンアミさんと北原葉子さん(2025年5月©高橋真樹)
【プロフィール】
高橋真樹(たかはし まさき))国際NGOピースボートの職員として世界約70カ国を訪れ、国際協力、核廃絶、パレスチナ難民支援などに携わる。2010年からはフリーのノンフィクションライターとして、SDGsなどの持続可能性や人権問題をテーマに取材・執筆を続けている。著書に『観光コースでないハワイ 楽園のもうひとつの姿』(高文研)、『「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札』(集英社新書)ほか多数。25年7月の最新刊に『もしも君の町がガザだったら』(ポプラ社)。
あわせて読みたい・聴きたい
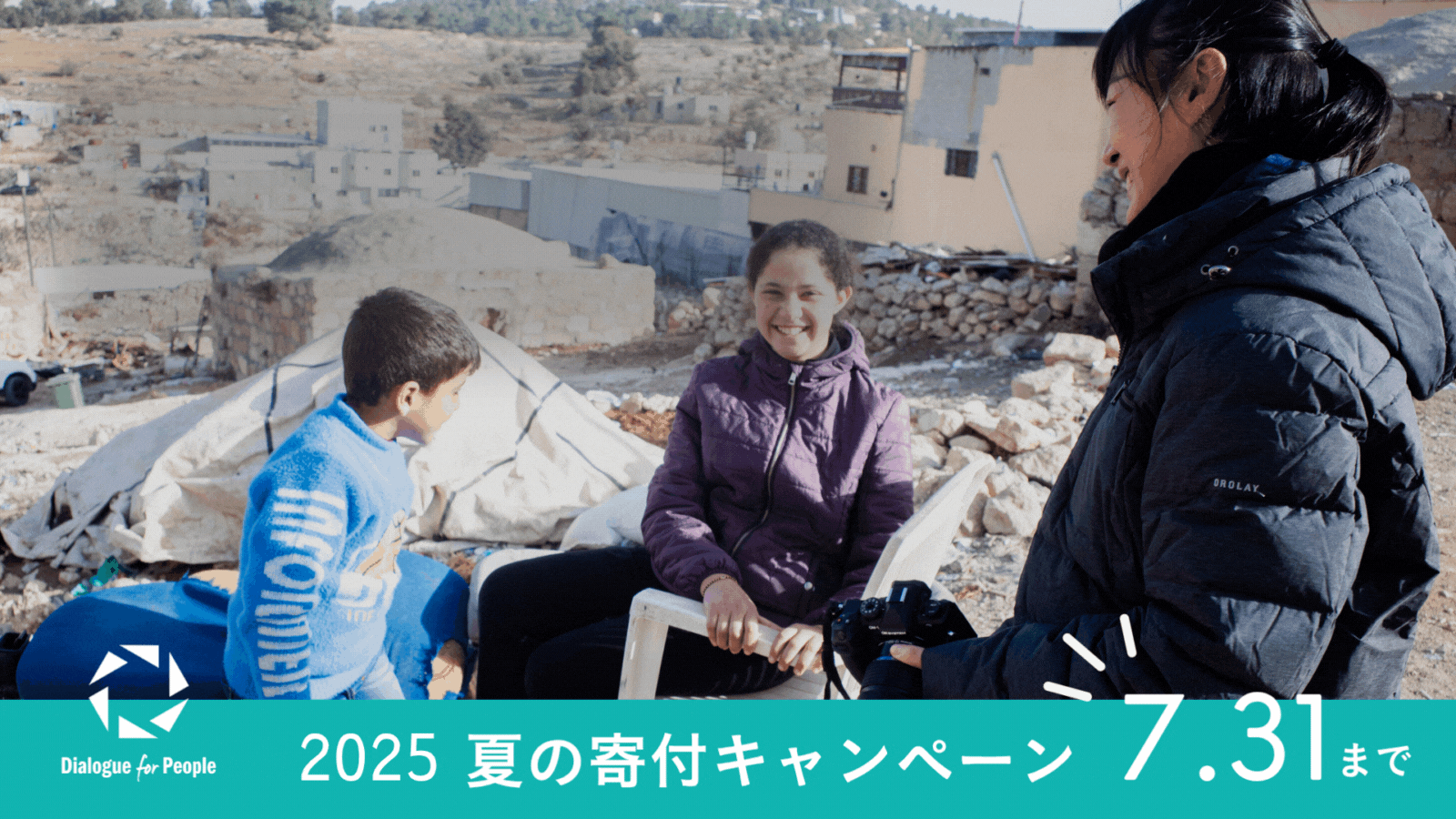
D4Pの夏の寄付キャンペーンに、ご寄付をお願いします!(2025年7月31日まで)
認定NPO法人Dialogue for People(D4P)では、取材や発信を続けるためのご寄付を募る寄付キャンペーンを行っています。 D4Pの「伝える活動」の継続に、どうかあなたの力を貸してください。
※ご寄付は税控除の対象となります。
D4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。






