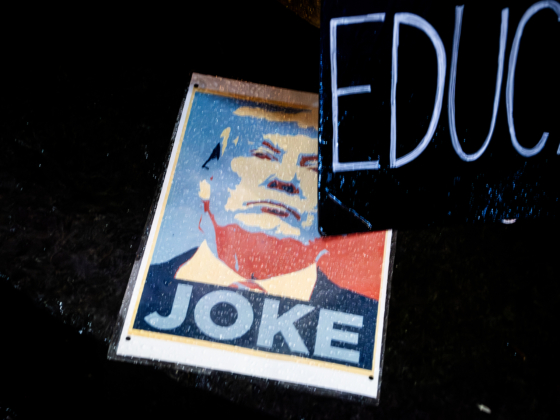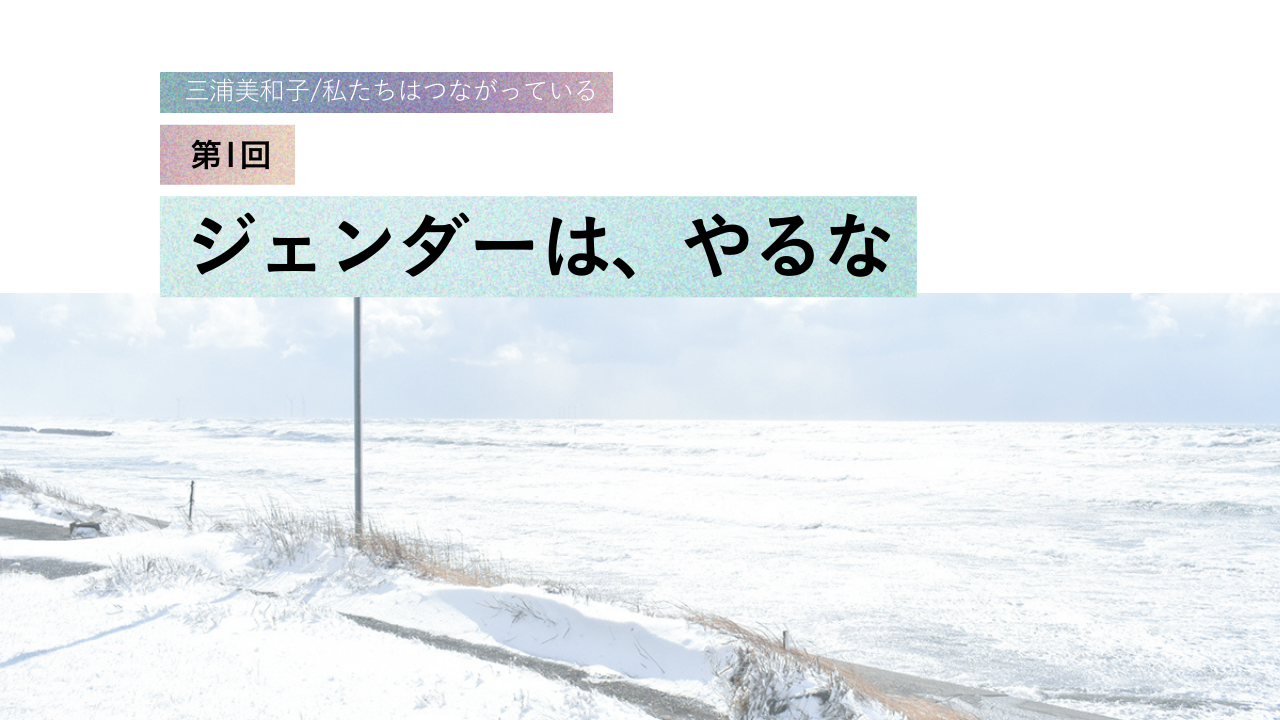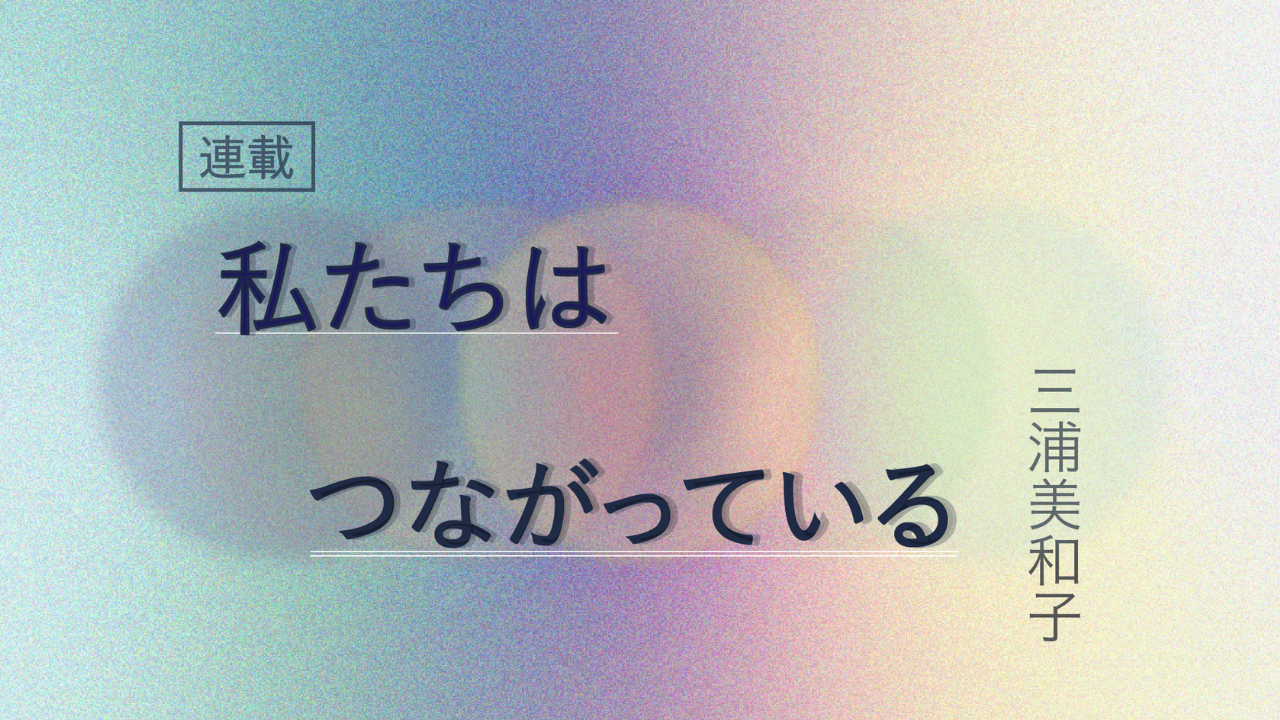アメリカの核戦略に取り込まれるヒロシマ―「平和記念都市」の発するメッセージの意味とは?(高橋真樹さんインタビュー)

高橋真樹さんが著書『観光コースでないハワイ 「楽園」のもうひとつの姿』(高文研)で描いたのは、観光地のイメージとは全く異なるハワイの姿でした。コロナ禍前には年間200万人もの日本人が訪れ、投資目的の豪邸が建ち並ぶその裏側では、元々ハワイに住んでいた先住民の子孫が貧困層へと追いやられる現実があります。
1810年、カメハメハ大王がハワイを統一しましたが、その王朝は1893年に欧米の白人によるクーデターで倒され、1898年にはアメリカへ「併合」されました。先住民が大切にしてきた「アロハ・アイナ(土地を愛する)」という概念は、欧米の「土地は売買するもの」という考え方によって奪われていきました。
土地を奪われ、サトウキビのプランテーションで働くことを強いられたハワイアンは、その労働形態になじめず、白人経営者は代わって世界中から移民労働者を呼び寄せ、その中には多くの日本人、特に広島県出身者が含まれていました。そんな歴史を持つハワイと広島の関係ですが、近年では2023年に「広島平和記念公園」と「パールハーバー・ナショナルメモリアル」が姉妹公園協定を締結しています。この協定の問題点や、「平和記念都市」を掲げる広島の発するメッセージの意味とは――?

高橋真樹さん。(高橋さん提供)
Contents 目次
戦争に巻き込まれたハワイ
――ハワイのオアフ島は観光客が多く訪れる場所ですが、この島のパールハーバーへの攻撃を機に、日米は全面戦争に突入しました。高橋さんの著書には、日系人だけで構成された米軍の「第442連隊」があり、その主力がハワイの日系2世だったと書かれています。この部隊はどのような経緯をたどったのでしょうか?
日米開戦後、日系人は敵国の国民として敵視されるようになりました。カリフォルニアでは、約10万人もの日系人の8〜9割が強制収容所に送られています。しかし、当時のハワイでは日系人が全人口の約3割を占めていたため、全員を収容することは社会の崩壊を意味しました。そのため、大規模な収容は行われなかったものの、教師や宗教指導者、商工会の要人といった社会のリーダーたちは収容されたり、アメリカ本土の収容所に送られたりしました。
収容されなかった人々も厳しい監視下に置かれ、仕事や資産を凍結されるといった措置を受けました。そのような状況の中、特に日系2世の若者たちは「自分たちは敵ではない、アメリカ人だ」という忠誠心を示すため、自ら志願して日系人部隊を結成しました。これが後の「第442連隊」です。
当初は日系人の部隊ということで差別や危険視もされましたが、彼らは勇敢に戦いました。ヨーロッパのイタリア戦線など、壮絶な最前線に投入され、軍事的には大活躍をします。死傷率は非常に高かったものの、その功績によって、戦後のハワイにおける日系人の地位は大きく向上しました。彼らは今も、日系ハワイ人の英雄として語り継がれる存在です。
――アメリカ社会に「認めてもらう」という視線の下で、命を危険に晒すことの対価として、地位向上があった……この点に暴力性を感じずにはいられません。同時に忘れてはならないのが、パールハーバーへの攻撃を機に日米が全面戦争に突入したという文脈の中で、先住民であるハワイアンたちの存在が抜け落ちてしまうことです。彼らが植民地支配、併合、そしてこの戦争に巻き込まれていったという視点は、決して欠かせないものだと思います。
私がインタビューしたハワイアンの子孫の方は、パールハーバーで日本軍の攻撃によって祖父が負傷したにもかかわらず、日本軍を恨んでいるわけではないとおっしゃっていました。
「そもそもなぜパールハーバーが攻撃されたかといえば、アメリカが来て基地を作ったからでしょう。アメリカが基地を作り、日本がそこを攻撃して戦争になった。私たちは、アメリカと日本の戦争に巻き込まれた犠牲者なんです」
この言葉を初めて聞いた時、胸に深く響きました。戦争は単なるアメリカ対日本の構図だけではないのだと、その視点の重要性を改めて感じました。

基地はどこにもいらない。道行く車にアピールする。(高橋さん撮影)
「不戦の誓い」よりも「軍事力」
――日本の敗戦後も、ハワイ経済は軍事への依存をますます強めていったとのことです。特に経済界や産業界が、このように軍に依存する構造は、なぜ、そしてどのようにして作られていったのでしょうか。
日本との戦争以前にも、ハワイには基地がありましたが、ハワイで軍の存在はそれほど大きなものではありませんでした。ハワイがアメリカの一大軍事拠点となって行ったのは、日本軍によるパールハーバー奇襲攻撃以降のことです。当時人口40万人のハワイに、100万人の軍人が押し寄せました。第二次世界大戦終結後も、ハワイの軍事基地はアジア支配、朝鮮戦争やベトナム戦争への拠点として使われ続けたのです。こうした流れの中で、ハワイにおける米軍の存在は、観光産業に次ぐ一大産業となり、もはや不可欠なものとなりました。観光業は景気に左右されますが、軍事産業は安定した経済をもたらします。そのため、商工会議所と結びついて、いかに軍の施設を誘致するか、いかに軍にとって快適な社会を作るかが優先されるようになりました。
――近年では、2023年に「広島平和記念公園」と「パールハーバー・ナショナルメモリアル」が姉妹公園協定を締結しています。「メモリアル」を「公園」と訳すことにも疑問を感じますが、そもそもこの「パールハーバー・ナショナルメモリアル」とはどんな場所なのでしょうか?
パールハーバーには、日本軍の奇襲攻撃で沈んだ戦艦「アリゾナ」があり、その真上に記念碑が建てられています。ボートで上陸すると、その浮き台のような場所に慰霊のためのスペースがあります。そのすぐ隣には、日本が降伏文書に署名した戦艦「ミズーリ」が展示されています。このアリゾナとミズーリを中心に、様々な施設を含めたエリア全体が、いわゆる「戦勝記念館」としての意味合いを強く持っているのです。
アリゾナとミズーリの陳列は、「卑怯な奇襲攻撃で我々は最初にやられたが、立ち上がり、最終的には勝利した」という、アメリカの戦争の始まりと終わりを示す物語を象徴的に展示しています。メモリアルの中には、戦争中に活躍した潜水艦や武器が展示されているほか、「抑止力を強化すべき」というメッセージも掲げられています。
――パールハーバー・ナショナルメモリアルには、沖縄からの疎開児童らを乗せた「対馬丸」を撃沈させた潜水艦「ボーフィン号」も展示されているそうですね。「戦勝」という側面が非常に強く強調されているこの施設は、「不戦の誓い」や「恒久平和」を祈る場所というよりも、「だからこそ、強い軍事力が必要だ」というメッセージを訴えかける意味合いが強いのでしょうか?
はい、「戦争に勝った」という側面が強調されています。館内のお店の名前も「ビクトリーショップ」など、全体的に明るくて軽い雰囲気です。「パールハーバーの復讐者」の異名のあるボーフィン号の艦橋には、対馬丸を含めて沈めた日本の艦船の数を示す日の丸のマークが、誇らしげに記されています。アリゾナの小さな慰霊スペースだけは厳粛な雰囲気ですが、全体を見ると、戦争の悲惨さや命の重みを感じることはできません。戦艦ミズーリの横にあるパールハーバー航空博物館には、最新鋭戦闘機による空中戦を体験できる「フライトシュミレーター」があり、人気アトラクションになっています。広島が掲げる平和の祈りや核廃絶の思いとは、まったく相容れない場所だと感じました。

「対馬丸」を撃沈させた潜水艦「ボーフィン号」。(高橋さん提供)
原爆投下の責任を曖昧にする協定
――なぜか協定の中では「パールハーバー国立記念公園」と訳されていますが、英語の名称は「パールハーバー・ナショナルメモリアル」であり、「メモリアル(記念館)」を「公園」と訳すのはおかしいですよね。協定締結の過程で、「公園同士の協定である」ことを明示するために、「公園」という言葉を「便宜上」使うことにしたと、市民局長が広島市議会で答弁しています。この提示の仕方について、高橋さんはどのようにお考えですか?
協定の提示の仕方だけでなく、その内容そのものに無理があると考えています。戦後の1959年には、広島市とホノルル市は人口規模が近く、広島出身者が多いという理由で、すでに姉妹都市協定を結んでいます。これは「市と市」の対等な協定なので問題ありません。
しかし、今回の協定は市同士ではなく、要請してきたのがアメリカという「国家」です。広島市長とアメリカ国家が協定を結ぶという、普通ではない関係になっており、非常に不自然です。「メモリアル」を日本語で「公園」と訳すのはかなり無理がありますが、それだけでなく、根本的におかしい点が多々あると言えます。

パールハーバー・ナショナルメモリアル。(高橋さん提供)
――この協定は、G7広島サミットが約1ヵ月後に迫った2023年4月に、在大阪・神戸のアメリカ総領事館から広島市に電話で提案されたという経緯がありました。そして、同年9月の市議会で、市民局長が「原爆投下に関わるアメリカの責任の議論を現時点では棚上げする」と答弁し、物議を醸しました。この件は、アメリカが「国家として」持ちかけてきたことが重要な点だと思うのですが、アメリカ側の意図をどう見ていますか?
端的に言うと、アメリカは原爆投下の責任を曖昧にしたいのだと思います。そして、反核を掲げてきた広島のメッセージを骨抜きにし、広島をもアメリカの核戦略の一員に取り込む、そうした流れがあると考えています。
この件について、かつて広島市長を務められた平岡敬さんにインタビューしたのですが、「これは原爆攻撃を正当化したいアメリカの意向がかなり強く働いているだろう」とおっしゃっていました。平岡さんは、パールハーバーと広島はメッセージが全く違うものであり、和解するにはまず、原爆投下はアメリカが犯した過ちだと「謝罪」し、「補償」と「再発防止」の3条件を満たす必要があると明確に述べています。
しかし、今回の協定はそうしたプロセスを経ずに、うやむやにしようとする流れです。平岡さんによると、この流れは2016年にオバマ元大統領が広島を訪問した際、日本側が「謝罪しなくてもいい」と伝えたことに端を発しているそうです。当時オバマ氏が「空から死が降ってきた」と、まるで自然現象のような表現をしたことにも、それが表れています。
――アメリカ側の意図があからさまに現れていますが、だからこそ、議会や市民を含めて、この姉妹協定を結ぶべきなのかどうか、しっかりと議論し、合意形成をしなければならなかったはずです。しかしそうしたプロセスを飛ばして、宙ぶらりんな状態で決まってしまったように感じます。この意思決定のあり方について、高橋さんはどのようにお考えですか?
私もその点について平岡さんに伺ったのですが、彼が広島市長在任中に韓国の大邱市と姉妹都市協定を結んだ際は、市と市の対等な関係だったこともあり、問題はありませんでした。しかしその時ですら、互いに何度も足を運び、議会からの質問にも丁寧に答えながら、1年かけて協定を結んだそうです。
それに比べて今回は、議会への打診も、市民との意見交換もなく、いきなり決まってしまいました。これはあまりに政治的で、G7の流れの中で、アメリカの強い要請のもと、広島市が受け入れたのだと考えられます。さらに、協定を結ぶ際に、広島側からは「若者交流」や「植樹」「原爆展の開催」など様々な交流案が提案されましたが、パールハーバー側からは何も提案がありませんでした。
このことからも、交流そのものが目的ではなく、協定を結ぶこと自体が目的だったことがわかります。そしてその目的は、広島や日本をアメリカの核戦略に取り込むことだったのではないでしょうか。G7サミットでも、ロシアの「無責任な核のレトリック」を批判しながら、暗に自分たちの側は「責任ある核」だからいいのだというような内容で、核廃絶を宣言しませんでした。この協定はそうした一連の流れの中にあるのだと思います。

真っ白な壁に犠牲になった1177名の兵士の名が刻まれているアリゾナ・メモリアル。(高橋さん提供)
――今回の協定は、市民や議会での議論を経ていないという点で、民主主義としてどうなのかという問題があります。また、アメリカ側の意図に懐柔されていくような流れが、私たちが次の世代に引き継ぎたい社会の形なのか、という問いも投げかけられていると思います。原爆投下から80年を迎える今、広島、そして日本社会全体として、世界に向けてどのようなメッセージを発信していくべきでしょうか。
松井一實市長は「世界の為政者たちは広島に来て、記念館を見てほしい」と訴えましたが、G7や今回の平和公園協定を見ていると、ただ来て記念館を訪問しただけでは世界は変わらないと改めて感じました。私たちは、原爆はどの国が持っていても悪いものだし、アメリカの原爆投下は間違いだったと、しっかりと訴え続けなければなりません。
また、広島の被爆者たちが求めてきた平和のメッセージは、「原爆さえ落とされなければいい」というものではないのです。ガザの子どもたちが今、飢餓や空爆に苦しんでいるのは、かつての広島の子どもたちと同じです。原爆ではなくても、様々な武器やドローンで殺されています。広島のメッセージは、こうしたあらゆる暴力や殺戮を止めなければならないと訴え続けることだと思います。それを広島が発信することは、世界の誰よりも説得力を持つはずです。
しかし、残念ながら、今の日本は状況によりイスラエルの自衛権を支持したり、防衛省がイスラエル製のドローンを輸入したりしようとしています。平和記念式典のスピーチでは良いことを言っていても実際の行動が伴っていないように思います。スピーチだけでなく、具体的な批判や提言も含めて行動することこそが、日本の進むべき道であって、広島のメッセージだと僕は思っています。元広島市長の平岡さんも、「このままでは、広島がヒロシマじゃなくなる」と強く危惧していました。アメリカの原爆投下が間違いであったと言い続けることこそ、ヒロシマの重要なメッセージなのに、それが言えなくなりつつあるということだと思います。私も全く同感です。

広島平和記念公園内の原爆ドーム。(安田菜津紀撮影)
※本記事は2025年8月6日に配信したRadio Dialogue「ハワイと広島」を元に編集したものです。
(2025.8.22 / 聞き手 安田菜津紀、 編集 佐藤慧)
【プロフィール】
高橋真樹(たかはし まさき)国際NGOピースボートの職員として世界約70カ国を訪れ、国際協力、核廃絶、パレスチナ難民支援などに携わる。2010年からはフリーのノンフィクションライターとして、SDGsなどの持続可能性や人権問題をテーマに取材・執筆を続けている。著書に『観光コースでないハワイ 楽園のもうひとつの姿』(高文研)、『「断熱」が日本を救う 健康、経済、省エネの切り札』(集英社新書)ほか多数。25年7月の最新刊に『もしも君の町がガザだったら』(ポプラ社)。
あわせて読みたい・聴きたい
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。