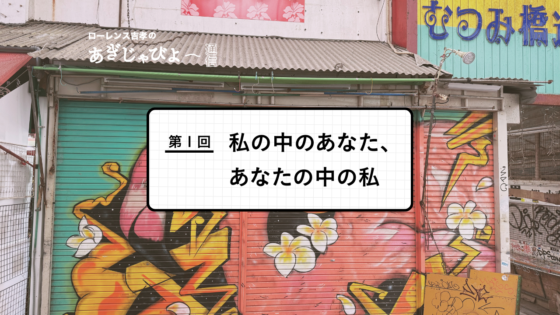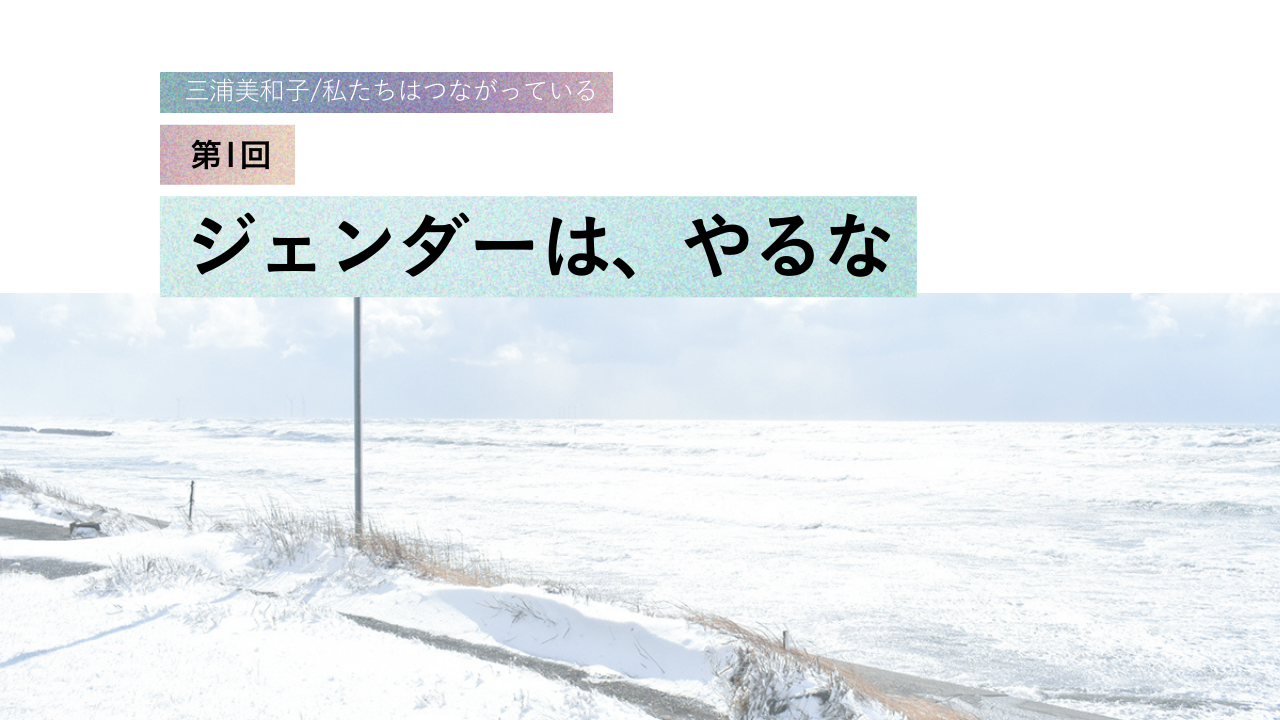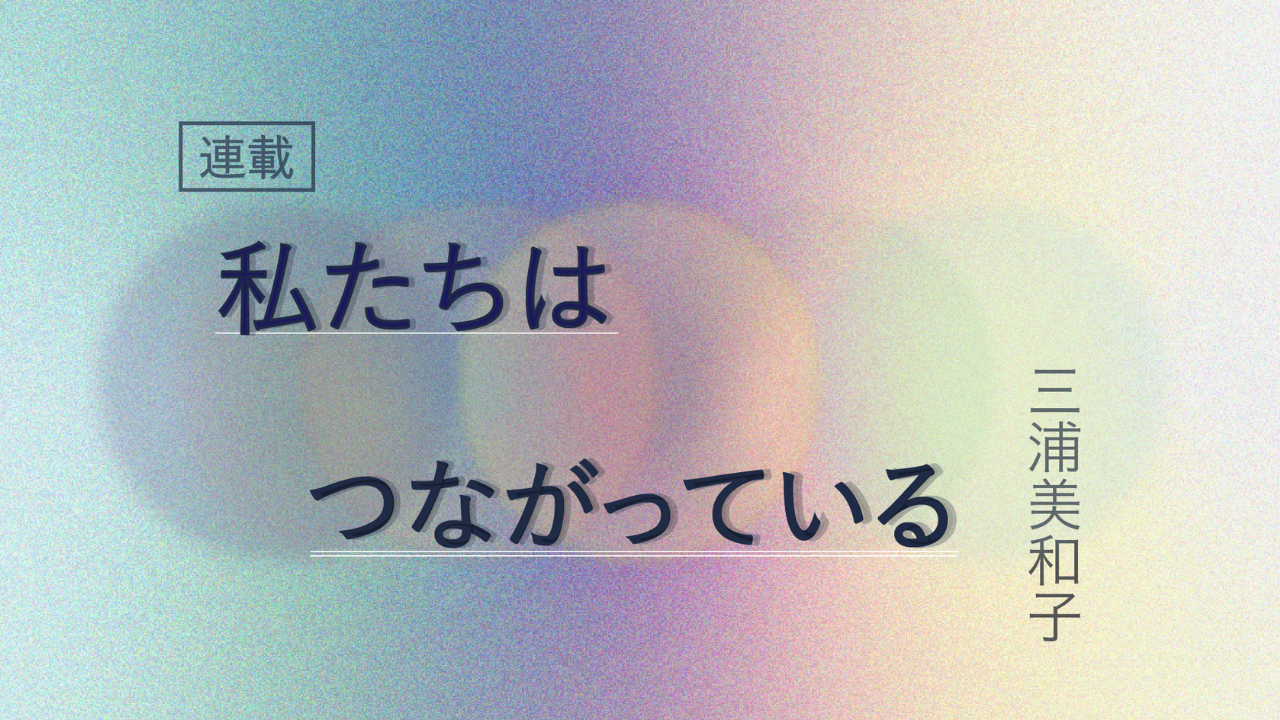PFAS汚染に声を上げる。沖縄と世界各地の女性たち―平良いずみさんインタビュー

2016年に沖縄県で表面化した、PFAS問題。汚染源の可能性が高いとされたのは、米軍嘉手納基地でした。
2020年には米軍普天間飛行場からPFOS、PFOAを含む泡消火剤が大量に流出。その後も全国各地の基地周辺からPFASが検出されたほか、岡山県吉備中央町では、放置されていた使用済み活性炭からPFASが流出し、ダムに流れ込むという事態も起きています。
映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』で、この問題に声を上げる女性たちの姿を追った、監督の平良いずみさんに、そもそもPFASとはどんな物質なのか、国や自治体の対応や、世界各地でPFAS汚染に立ち上がった女性たちについて、お話を伺いました。

PFASとは何か?
――PFASとはそもそもどんな物質なのでしょうか?
PFASというのは「有機フッ素化合物」の総称で、100%人工的に作られた化学物質のことです。焦げ付かないフライパン、食品包装紙や化粧品、泡消火剤など、私たちの身近な日用品に多く使われてきました。
しかし、2000年代に入ってから、人体への有害性が非常に強いということがわかり、国際条約によってPFASの一部であるPFOSやPFOA、PFHxSが禁止されてきました。
人体への影響としては、アメリカの学術機関の発表によると、腎臓癌、乳児・胎児の発達への悪影響、心疾患につながる脂質異常症、そしてワクチンへの反応の低下などが、PFASとの関連性に十分な根拠があるとされています。
――平良さんがこの問題を追いかけようと思ったきっかけは、どういったことだったのでしょうか?
私が映画を作る起点となったのが、2016年に沖縄県が開いた会見です。私たち沖縄県民45万人が飲んできた水道の水に、人体への有害性が指摘されるPFASが含まれていたと発表されました。
私はちょうど息子を産んだばかりで、産婦人科から「水道水を使ってミルクを作りなさい」と推奨されていました。ミネラルウォーターに含まれるミネラルは、水が取れる場所によって異なり、乳児の内臓の負担になることもある。日本の水道水は安全だから、それを煮沸して使いなさいと。
自分の乳飲み子に、水道水を使って与えていたミルクの中に毒が入っていたのかもしれないと思うと、本当に不安と怒りで体が震えて止まらなくなったのを覚えています。それが起点になり、この物質って何なんだろうと調べ始めたのが取材のきっかけです。
――2016年に沖縄県が問題を公表してから9年が経ちます。その後様々な調査を重ねているとは言え、いまだに汚染源の特定ができていないのはなぜなのでしょうか?
2016年の沖縄県の会見では、汚染源は嘉手納基地である蓋然性が高いと県が発表しました。全県的に隈なく調査した結果、基地周辺でPFASの値が高かった。しかも川の上流、基地に入る前は濃度が低く、基地を通って流れてきた後の下流になると濃度が高くなっていた。
沖縄県は嘉手納基地に立ち入り調査を求め、これまで再三に渡って要請し続けているのですが、汚染発覚から9年経っても、調査にすら入れていません。
壁になっているのは「日米地位協定」です。アメリカ軍に排他的な管理権を与えているこの協定を盾に、アメリカ軍は立ち入り調査を拒み続けています。

沖縄の構造的な問題とPFAS汚染
――PFASについては、日本各地で同様の問題が起きていますが、沖縄に関しては、基地負担が集中しているという構造的な問題があります。この事実の深刻さに関して、どのように感じてきましたか?
沖縄で市民が声を上げたことによって県、そして国が動き、2020年には水道水に含まれるPFASについて、あくまで暫定値ですが、これくらいまでは安全であるとする値が設定されました。
それにより全国で調査が行われ、PFAS汚染がどんどん明るみに出てきているというのが現状です。
汚染源としては工場や産業廃棄物など色々ありますが、沖縄や東京の横田基地周辺に関しては、米軍基地である可能性が高いとされています。
構造的に非常に問題だと思うのは、やはり汚染源に立ち入り調査ができないことです。国際ルールとしては、「汚染者負担の原則」(汚染の除去や環境復旧、汚染防止のために必要な費用は、環境汚染を引き起こした者が負担すべきという考え方。PPP)があり、またそもそも汚染源を断たなければ根本的な解決にはならないのに、その調査にすら入れないというのは、現実に打ちのめされます。
――映画には独自に調査を続けているジャーナリストや学者の方も登場しますが、こうした方々はどのような指摘をしているのでしょうか?
ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんは、枯葉剤や放射性物質の汚染について情報開示による調査報道を続けていますが、ある講演会で「このPFAS汚染は、沖縄の近現代史において最も広範囲で最も深刻な環境汚染だ」とおっしゃっているのを聞いて、私たちもこの問題の深刻さに気づかされました。
PFASは「永遠の化学物質」と言われており、自然界ではほぼ分解しないという特性があるために、汚染源を特定して浄化していかないと、環境中に撒かれたPFASは分解せず、環境の中でずっと循環してしまう。
沖縄で供給される水道水に関しては、活性炭によって安全性は一応担保されてはいます。ただそれはあくまで対症療法で、汚染源を特定して根本を解決していかないと、生物濃縮環境に放置されたPFASが周りまわって、魚が食べ、それを私たちが食べ、次世代へ受け継いでいってしまう。その点が科学者の皆さんも警鐘を鳴らしている現状です。

生活への影響、動かない行政
――映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』では、PFAS汚染に声を上げる女性たちに焦点を当てています。彼女たちの生活や日常の取材を通して、汚染がどんな影響を与えていると感じますか?
「不安」が一番影響としては大きいと思います。
沖縄県がPFASの調査を始めたのは2013年ですが、アメリカ国防総省は1970年代にはPFASを含む泡消火剤を使い始めたとしていて、嘉手納基地でもかなり前から泡消火剤が使われてきたとみられています。
京都大学に残っている沖縄県民の血液サンプルでも、1980年代にはかなり高濃度でPFASが血液中に含まれていたことが事実として残っています。
沖縄で今声を上げている女性たちが求めているのは、健康影響への調査です。私たちがどのくらい汚染にさらされてきたのかを知る手がかりも、健康調査をしてみないとわかりません。
PFASによる影響があると言われている特定の疾患について、医療モニタリングを継続的にすることによって、発症前や発症してすぐに対処ができれば、予防にもつながります。
そのために、女性たちは健康調査を必死に行政に対して求めているのですが、その声がなかなか届かないというもどかしさがあります。
――国や自治体などの行政は、この問題に対してどう対応してきたのでしょうか?
残念ながら、日本の環境行政はこの問題について非常に消極的です。
沖縄の市民の皆さんが、何度も何度も行政に対して要請しても、返ってくる答えはお決まりの通りで、「基準がないから調査をしない。調査をしないから健康影響がわからない」と。悪循環なんですね。
世界では最新の研究で人体への悪影響がわかってきていて、アメリカでは規制値を厳格化していますし、EUなどでも「予防原則」(健康被害が出てから規制するのではなく、健康影響との因果関係が十分に証明されていなくても対策を講じる原則)に基づいて、悪影響があるものは減らしていく流れになってきています。
日本では、アメリカが2016年に設定した「水1リットルあたり70ナノグラム」PFASが含まれる水を毎日飲んでいても健康には影響ないという値に準じて、「水1リットルあたり50ナノグラム」という目標値を2020年に設定しました。
去年、アメリカで正式に決定した値は「4ナノグラム」です。しかし、日本の環境省が今固めている方針では、50ナノグラムのまま据え置くとされています。
市民の皆さんは、アメリカに準じて値を厳格化すべきだと訴えています。
世界各地で立ち上がる女性たち
――アメリカやイタリアなど世界各地でも、汚染に苦しむ人たち、特に女性たちが声を上げてきました。各地での取材を通して、見えてきたことはいかがですか?
映画の冒頭でも言っているのですが、私、本当に執念深いんですよ。
この問題は日本だけでは本当に光が見えないので、沖縄の言葉で怒りを表す「わじわじー」してですね。でも、世界には光が見えているところがあるので訪ね歩いていきました。
アメリカでは、ミネソタ州という工業地帯でPFASを作り続けていた企業が、PFASを水源に垂れ流していたということがわかり、20歳で末期の癌になったアマラ・ストランディさんという方が議会で証言を続けていました。
彼女は余命宣告を受けて、残された短い時間の中で環境団体からの要請を受けて、「私は最後の時間を、次の子どもたちのため、PFAS規制をしてもらうために声を上げたい」と本当に粘り強く証言を続け、その結果として、2023年にミネソタ州で製品からPFASをすべて規制する法律が制定されます。
一人の人間でも、こうやって社会を変えることができるというメッセージを、私はアマラさんから受け取ったので、その責任として皆さんにお伝えできればと思っています。
イタリアでも、工場跡地からPFASが水道水の水源に流れ込んでいたことから、お母さんたちが「ママ・ノー・PFAS(Mamme no PFAS)」という組織を立ち上げて行動を起こしていきます。
汚染度は深刻なのですが、イタリアならではなのか、本当にお母さんたちが明るいんですよね。
今年の6月、そのお母さんたちが成し遂げたことが画期的な判決として出ました。訴えを全面的に認めて、汚染した企業の責任者に対して、最長で禁錮16年という非常に重い禁錮刑が出たのと合わせて、環境浄化のための費用負担に関しても全面的に認めて、巨額な賠償金の支払いを命じる判決でした。
お母さんたちのコメントで非常に印象的だったのが、「私たちは母親という普遍的な感情で、社会を感情的に訴えて動かしてきた」と。
その一方で、「科学者を巻き込んで、技術的なデータを私たちは必死に勉強して集めた。その客観的なデータに基づいて訴えたから、社会を動かせたし、司法までも動かせた」とも、誇らしげにおっしゃっていたのが印象的でした。
それは日本でも、沖縄や東京で、女性たちが皆さん手弁当で活動されているのと、まったく同じ姿なんですよね。
――イタリアで禁固刑判決を受けた幹部として、日本人も含まれていたと報じられました。
イタリアでは工場を経営する企業が既に倒産してしまっていたのですが、(今回の刑事裁判の1年前に判決を出した)地方行政裁判所は、元々その企業を経営していた親会社である日本の三菱商事に対して、浄化の費用負担の責任があるという判決を出しました。
これはすごく画期的だということで、イタリアでもニュースになっていました。企業が倒産した場合には、誰が環境汚染の責任を取るのか、責任追求が難しくなります。しかし、イタリアの司法はその責任を明確にしたということで、国際的にもこれからの明るい希望になるだろうなと思っています。

国連に届いた女性たちの声
――映画のタイトルにもなっている「ウナイ」は、女性や姉妹を意味する沖縄の言葉です。「シスターフッド」にも置き換えられる言葉ではないかと思います。女性たちを取材の中心に据えたのはなぜだったのでしょうか。
男性/女性でくくることには葛藤もありましたが、この問題を取材していると、声を上げている人たちには、圧倒的に女性が多いということに気づきます。
それは裏を返せば、男性は経済や軍事上の利益が優先される社会構造の中に取り込まれてしまっていて、声を上げづらい現実があると痛感しました。
女性たちが言っているのは、本当に当たり前のことです。
たとえ経済的な利益を得たとしても、命や健康がなければ、何になるんだと。本当にシンプルだけれども普遍的なメッセージを発信しています。
今、トランプ政権の再登場や、自国ファーストの流れの中で、一番大事な命や人権、これまで人類が積み上げてきた英知が一瞬にして吹き飛ばされようとしている。その今だからこそ「みんな原点に帰ろう」ということを、この問題を通して伝えたいと思っています。
――映画では、日本の女性たちが昨年の「国連女性差別撤廃条約委員会(通称CEDAW)」の会議に出向くシーンも出てきます。PFAS汚染が女性の安全と子どもを産み育てる権利を侵害しているという訴えが、CEDAWから日本政府への勧告につながりました。この意味をどのように捉えていらっしゃいますか。
勧告の意味は非常に大きいと思います。日本では行政側でPFASを計測できる技術が確立できていないなど、本当に腹立たしい状況がありますが、それを吹き飛ばすためにも、国際社会に訴えて、日本ではあまりにも問題への対応が後手に回っているということを浮き彫りにすべき時です。
CEDAWの委員は日本に対して、調査した結果を公表するよう釘を刺しました。そうした指摘は、沖縄の女性たちが一生懸命、現状を訴えかけて、その声が届いた成果で、本当に大きな前進だと思っています。
もう一つ、付け加えておきたいのが、沖縄の女性たちが委員に向けたスピーチで、「この声は決して沖縄だけの声じゃない。日本で今、このPFAS問題を不安に思っている日本全体の人々の声なんです」と締めくくったことです。
点在する地域で不安を抱えている人たちと、手を取り合って問題解決しようと訴える沖縄の女性たちの声が、より大きくつながっていけばいいなという思いを新たにしています。

――しかし、CEDAWの勧告の後、日本政府は同委員会への拠出金を対象から除外すると言い出しました。CEDAWが男系男子に皇位継承を限る皇室典範の改正を勧告したことが、その理由とされています。
いかにこの国が男女平等に背を向けてきたのかということが、如実に現れたように感じました。
――水の汚染というのは目に見えにくいもの、可視化しづらいものだと思います。それを映像で伝えることの難しさはありましたか?
目に見えず、無味無臭であるPFASについて、当事者意識を持ってもらうことは本当に難しく、映像クリエイターとしては七転八倒して作り上げたというのが正直なところです。
ただ幸いにも沖縄では、市民の皆さんが次世代を守るために声を上げてくださって、その背中を追いかけたらここまで来られたということには、もう感謝しかないです。
――最後に、改めてこの映画を通して特に伝えたいことを伺ってもいいですか?
とにかく次世代、子どもたちを守るために、このPFAS汚染について知ってほしいということが一つ。
そしてもう一つは、沖縄の女性たちの姿から「声を上げることで社会は変えられる」ということを伝えたいと思っています。
※本記事は2025年9月3日に配信したRadio Dialogue「PFAS汚染の今」を元に編集したものです。
(2025.9.29 / 聞き手 安田菜津紀、 編集 伏見和子)
・参考:映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』公式サイト
【プロフィール】
平良いずみさん(たいら いずみ)沖縄生まれ。1999年沖縄テレビに入社。基地問題、医療、福祉等のテーマでドキュメンタリーを制作。共通するのは、主人公が社会や人のために闘う!ということのみ。『どこへ行く、島の救急ヘリ』(2011報道部門優秀賞、『菜の花の沖縄日記』で第38回「地方の時代」映像祭グランプリを受賞。映画『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』で初監督を務める。PFASによる水汚染を追った番組『水どぅ宝』(2022年)は、ギャラクシー賞の優秀賞など受賞多数。今夏からGODOM沖縄 ディレクターとしてPFASの規制値の厳格化が進む海外の事例等を取材し、映画を製作中。
あわせて読みたい・聴きたい

【目標50人!9月末まで】D4Pの「伝える活動」を毎月ともに支えてくださるマンスリーサポーターを募集します!
9月1日〜9月30日の1ヵ月間で、50人の方の入会を目標にしております。
多くの方のご参加をお待ちしております!
※ご寄付は税控除の対象となります。
D4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。