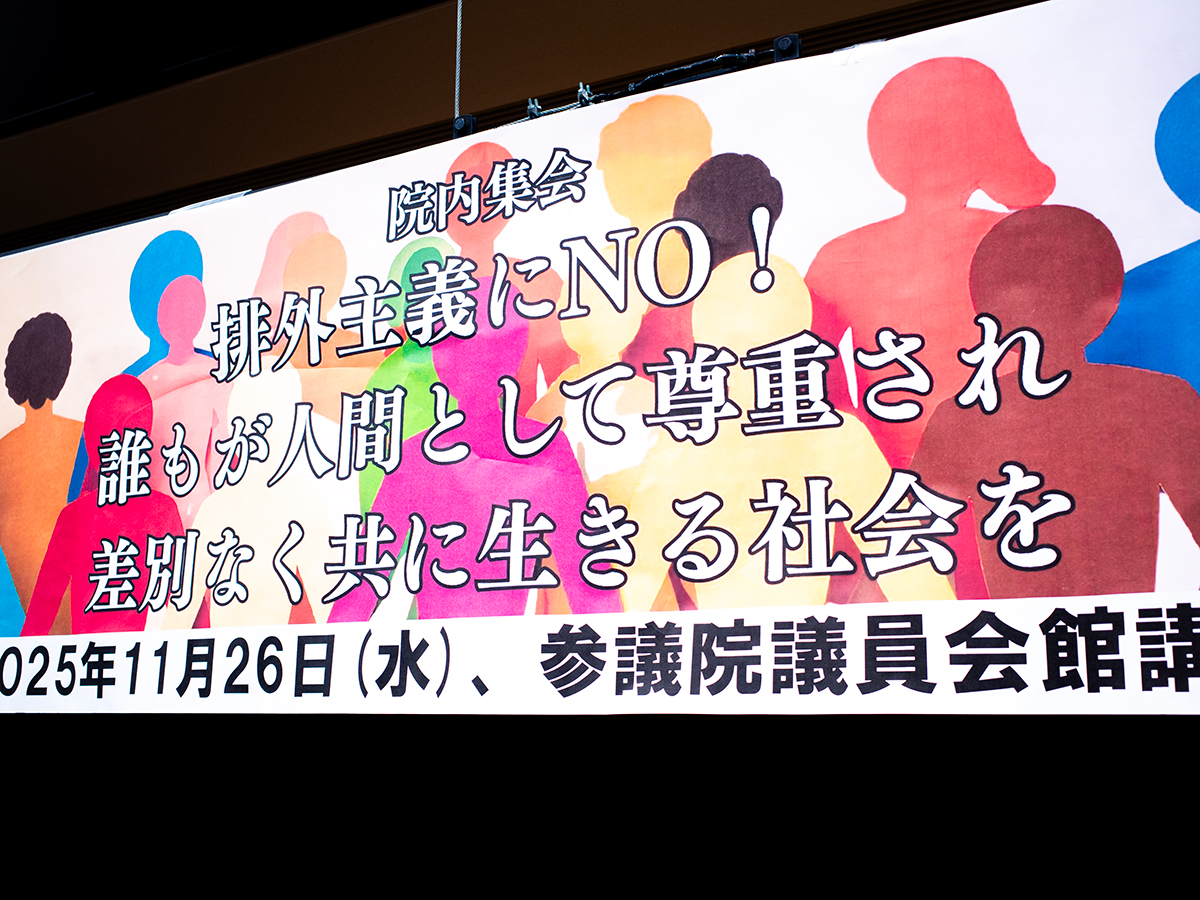#検察庁法改正案に抗議します というハッシュタグと共に、Twitter上などで多くの声があがっています。1月31日、政府は黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定しました。1981年の政府答弁では、国家公務員法の定年延長は検察官には適用されないとしています。これについて問われた首相は、「今般、解釈を変えた」と答弁。ところが「法解釈変更」という非常に重大な経緯を示した文書を、森法務大臣は「口頭決裁で問題ない」としたのです。その「協議文書」には、日付さえ記されていませんでした。そして衆院で審議入りした「国家公務員法等の一部を改正する法律案」に含まれる検察庁法改正案には、こうした不可解な経緯を後付けで、追認するかのような「特例措置」が盛り込まれています。法案の中では、63歳以上の「役職定年」を導入するとしながらも、内閣や法務大臣が認めた場合、例外的に延長することも可能という規定を設けており、検察官の独立性、中立性が現状よりも損なわれる恐れがあります。
つまり、政権にとって有利な人物がその役職に留まることを認められ、反対に政権に不利益な捜査を行う検察官は定年延長が認められない、ということも起きかねません。そのような状況で本当に検察官は、政権の顔色を窺うことなくまっとうな公務を行うことができるのでしょうか。
これに対し、東京弁護士会会長声明は1月31日の閣議決定の撤回と、検察官の定年ないし勤務延長に係る「特例措置」を設ける部分の削除などを求めています。
私が今、こうした動きに危機感を持っているのは、これまで人々が守られず、権力者が守られるような国を取材してきたからでもあります。例えば、日本を含め様々な国に逃れてきた難民の方々はみな、国や司法に守られなかった人々です。日本では難民認定率が非常に低く、その受け入れを「負担」と考える風潮も根強く残っています。けれどもこれまで私たちが出会ってきた方々は、単に保護を必要としている“弱い人々”ではありません。強大な国家権力などを相手に、人間の権利と自由を信じて、幾多もの困難を乗り越え、日本にたどり着いた人たちなのです。そういった人々の声は、「日本が自分たちの国のような政治体制にならないように」という、私たちの社会にとっての大切な投げかけでもありました。そうした声に触れながら、今の法案審議について思うことを書きたいと思います。
2011年3月、シリアでは「自由」を求める人々が路上へと繰り出し、長年感じてきた抑圧や政治腐敗に対して声をあげ、大規模なデモが行われるようになりました。これに対して政権側は、彼らの声に耳を傾けるのではなく、武力で応じてきたのです。
国外に逃れてきた人々の声を聴きながら改めて痛感するのは、人々の安全を脅かす権力の乱用は、戦争が起こるよりずっと前から繰り返されてきたということです。私と同年代のある男性は、戦前のシリアで、父親が理由もわからず突然拘束され、数千ドル近くの大金を支払いようやく釈放してもらったといいます。父親は、10日間に渡り厳しい尋問と拷問にさらされました。国際的な人権団体が、拘束時の様子の聞き取りをしたいとやってきたものの、「また自分を捕まえる口実を与えてしまう」と、父親は頑なにそれを拒んだといいます。正式な逮捕状を提示されたことは一度もありませんでした。
こうした積み重ねの上に戦闘が起これば、更なる迫害が横行してしまうことは目に見えています。何の法的根拠もなく、突然拘束されてしまえば、彼らはただこの社会から「いなくなっただけ」となってしまいます。
私たちが翻訳した『シリア 震える橋を渡って』(ウェンディ・パールマン著)には、こうした証言が残されています。
「私はその後の8年半を刑務所の中で過ごしました。はじめの半年は、私の妻は私の行方すら知りませんでした」
「シリアの刑務所というのは、地球上でもっとも恐ろしいところです。理由は単純です。そこでは人間の命に価値なんて無いのですから。私は政治犯の収容される特別な棟に投獄されており、当初から激しい拷問を受けていました。私たちは完全に世界から隔離されていました」
「私の逮捕に関する事件が超法規的な治安裁判所に持ち込まれました。裁判官は15分間で30人もの人を裁きました。そこには裁判もなければ、弁護士もいませんでした。特別な罪状もありませんでした。彼らが常に難癖をつけてくることを除けばですが。秘密の組織を立ち上げようとしたとか、政権に対する間違った情報を流した、政権転覆を試みた、根も葉もない噂をばらまいたり出版したり、政府の権威を傷つけたとか、そんなことです」
(弁護士、タイシールの証言より)
こうした事実をもって、「日本でも同じことが起きるかもしれない」と脅かしたいわけでもありません。「国家公務員法等の一部を改正する法律案」がそのまま通ってしまったとしても、すぐさまシリアのような暴力が横行するわけではないでしょう。ただ、私たちがこうした証言から受け取ったのは、一度歯止めが利かなくなると、法は権力者のためのものになる、あるいは法を権力者たちが捻じ曲げ、人々を守らなくなる、という警鐘でした。「これくらいのこと」と見過ごしてしまえば、権力の乱用はエスカレートしていき、そしてその肥大化した力を止めようとするには、多大な犠牲を払わなければならないのだと。
もちろん、国の歴史的背景や文化はそれぞれに違い、一概に比べられるものではありません。私たちには今、幸いにも選挙という手段があり、おかしいことには「おかしい」と言える権利があります。問題はそれを、私たちがしっかりと行使できているか、ということだと思います。
あるとき、「日本には表現の自由、投票の自由があるけれど、特に若い人たちの投票率が低い」と話したとき、シリアの友人が絶句してしまい、それ以上、何も言えなかったのを覚えています。その「自由」を得るために9年以上、あまりに多くの人々が命を奪われてきたからでしょう。
権力にとって最も都合がいいのは、人々の「無関心」や「忘却」です。私たちが持ちえる「自由」をどんな風に、何のために使うのかが、改めて今、問われているのではないでしょうか。
(安田菜津紀/2020年5月12日)
あわせて読みたい
■ イラク戦争と沖縄、無関心の「犠牲」になるのは誰か [2020.3.20/安田菜津紀]
■ 国に帰れないことは「罪」なのか ー誤った事実を元に議論されていた「刑事罰」 [2020.4.1/安田菜津紀]
■ 人との確かなつながりで、私はどんな武器よりも強くあれる ー映画『娘は戦場で生まれた』ワアド監督インタビュー [2020.3.5/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。