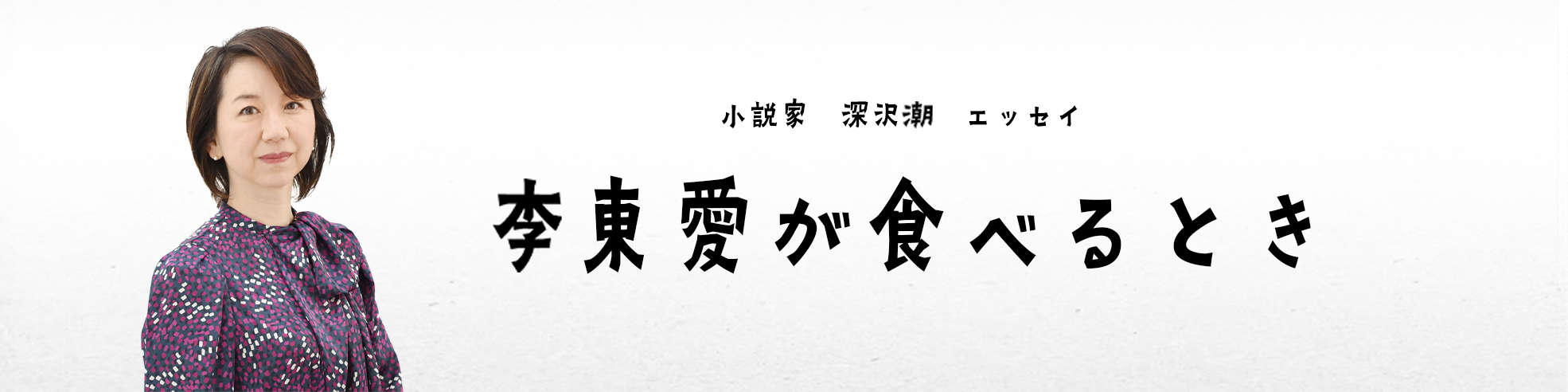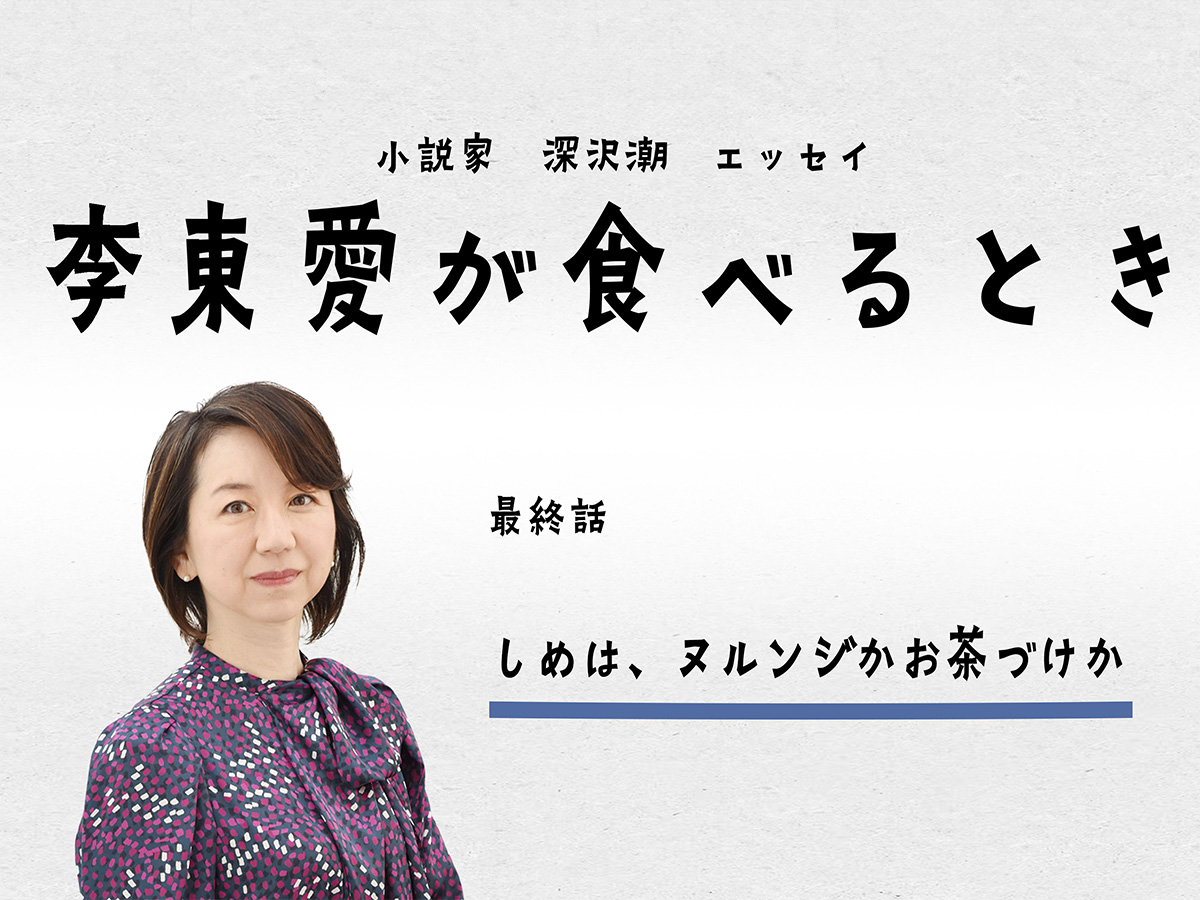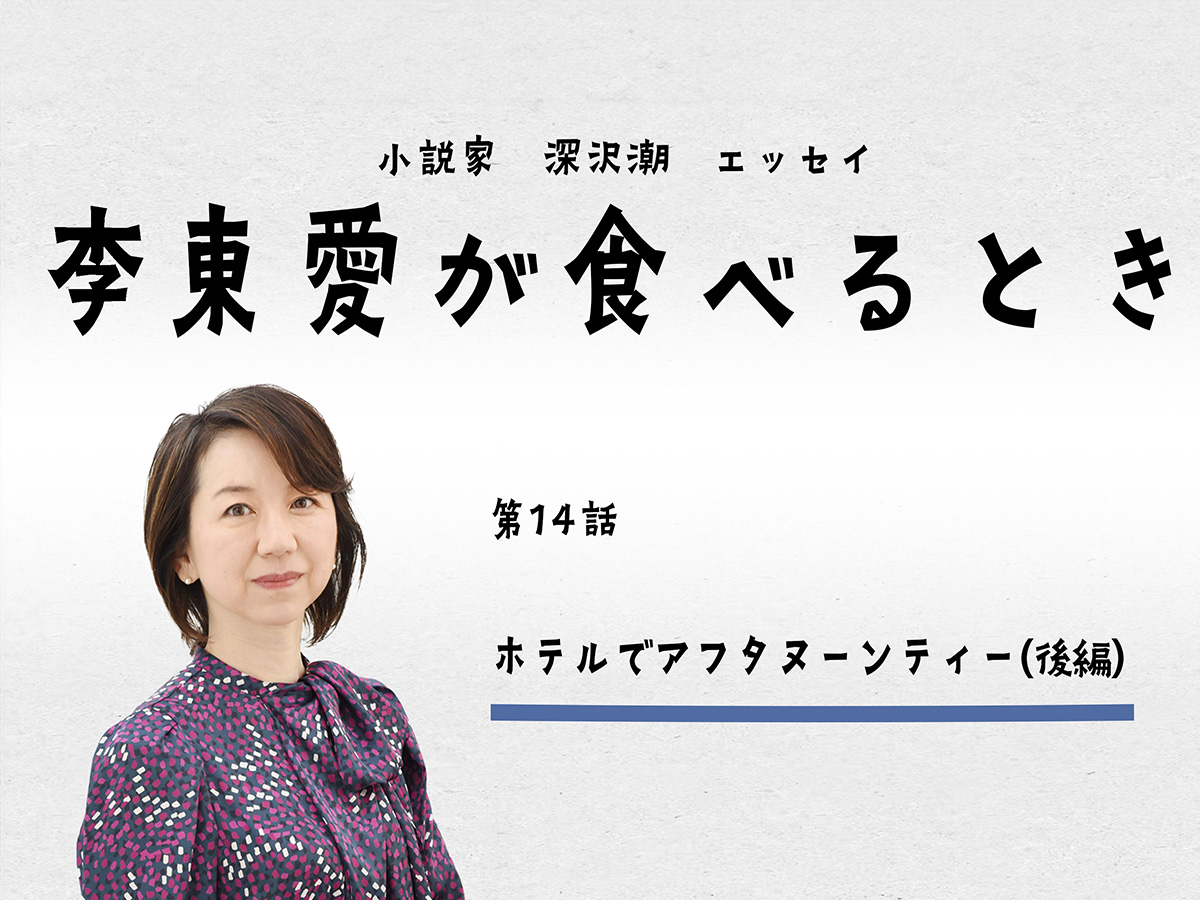第4話 カップ麺を食べ続ける
私にとってのカップ麺は、ちゃんとした食事ではなく省略したもの、つまりは手抜きであり、どうしても料理ができない、あるいは、時間がないときに食べる、とりあえずのもの、という印象がつよい。
また、日清のカップヌードルは、あさま山荘事件で警察官が食べているのがテレビに映って普及したというエピソードもあって、私の世代やそれより上のひとたちにとっては、カップ麺は(外で)簡単に食べるもの、というイメージがあるのではないだろうか。
とはいえ、いまやカップ麺は、さまざまな種類があり、商品開発もさかんで、コンビニやスーパーの棚にびっしりと並び、工夫をこらした新商品がつねに目に留まる。老舗の店の味もあれば、エスニックな海外の味も手に取ることができて、もはや省略や臨時の食べ物といった位置づけではないだろう。そして、インスタント食品は身体に悪いという固定観念を打ち破るような、健康や栄養に配慮したカップ麺もある。
けれども、私はカップ麺を食べたり、子どもたちに与えたりするとき、手をかけていないという、うっすらとした罪悪感を持つことから逃れられなかった時期が長かった。それだけでなく、寿司ほどではないけれど、カップ麺を目にすると、姉の死が頭に浮かんでしまうのだった。
姉が亡くなったのは1975年7月21日で、それから通夜、葬式が済み、斎場で遺骨となり姉は家にかえってきた。そのころ、我が家は東京都品川区旗の台の一軒家に賃貸で住んで間もなかった。一階にリビングダイニングと和室があって、二階に三部屋という間取りで、ごく小さな庭もあった。その家を借りるまでは、大家さんの家の二階、2DKに生まれて間もない妹を含めた家族五人で暮らしていたので、二階建ての一軒家に住めたことが、とても嬉しかった。しかし、姉が発作を起こしたその家からは、半年後に引越した。
姉の遺骨は、二階の子ども部屋の隣にあった和室に置かれた。小さな机の上には白い布がかかった祭壇がつくられ、木の十字架と姉の遺影と遺骨が並び、蝋燭がたっていた。そのとき、我が家にはお墓がなかったので、遺骨は埋葬までしばらくそこにあった。父の一家のお墓は韓国にあったし、いずれは韓国に戻るつもりでいたので、父は日本でお墓を持つ、という発想がそれまでなかったのだ。
母は、ロザリオを握りしめて祭壇の前に座り、まだ赤ちゃんの妹を横に寝かせ、毎日泣いていた。涙というのは無限に出続けるものなのだなと、私はふすまを隔てた子ども部屋から嗚咽を聞いていた。母は、祭壇のある部屋にほぼ一日中いた。泣いていないときは、聖書を読むか、焦点の定まらない目でただ座っていた。
おりしも学校は夏休みだったが、私は「喪中だから」と外に遊びに行くことを禁じられ、友人とも会えなかった。校庭で毎朝行われるラジオ体操にも行かれなかった。ましてや、姉の発作の原因だったかもしれないプールに入ることなどとうてい許されず、プール開放にも参加できなかった。暇を持て余した私は、母の気配を隣の部屋に感じながら、本を読んだり、ベッドの上で夢想したり、物語を作ったりしていた。時折、階下のリビングでテレビをつけてみるのだが、昼間にあまり興味を引く番組はなかったのだろう。テレビを長く観ていた記憶はあまりない。
私は耳をふさいでベッドの上で自分のつくりあげた世界へひたすら逃げていた。現実にかえると、ときどき妹の面倒もみた。母に強いられ、祭壇の前にも一日に三度は座らされたが、姉の遺影や遺骨をまっすぐに見ることができなかった。祈りの言葉を早口で言ってすぐに立ち去ろうとすると、母が深いため息をついたり、眉根を寄せたりして私を見るのがしんどかった。
食事の時間だけ母と向き合うことができたが、その食事も、朝は食パンをそのままと牛乳、昼と夜はカップ麺だった。母に命じられて、カップ麺を含む食べ物は近くのスーパーに私が買いに行った。まだ1歳に満たない、8歳下の妹の粉ミルクも一緒にかごに入れてレジに持って行くと、レジのおばさんが、「お手伝いしてえらいね」と言ってくれて、そのときは得意になった。
カップ麺の種類もたくさん出はじめていたので、毎回いろんなメーカーのものを選んで買った。食べたことのないものを試すのは楽しかったが、「母が気に入るかどうか」が大事なので、緊張をともなう買い物だった。当時、カップ麺以上に、インスタントの袋めんも種類が豊富だったが、母は、鍋ひとつですむとはいえ、袋めんすら作る気力がなかったので、買うように指示されたのは、もっぱら、お湯をそそぐだけですむカップ麺だった。ちょうど、カップ焼きそばが売りに出されたばかりで、私はさっそくカップ焼きそばも買ってみたが、母には不評だった。お湯を捨てるというひと手間が煩わしかったようだ。
当時、父はほとんど家にいなかったが、姉の死でますます仕事や(社会)運動に没頭したようだった。毎晩遅く帰るか外で泊まってくるので、あまり顔を合わさなかった。けれどもある日、珍しく夕飯時に帰ってきた父が、カップ麺をすすっている私を見ると、母に対してものすごい剣幕で怒鳴った。
「死んだ子でなく、生きている子のことを考えろっ」
私にとっての父は、愛情をストレートに表すような人ではなく、いつも怒ってばかりの、恐怖の大魔王のような存在だったので、私を気にかけて言ったであろうその言葉に驚いた。母が激しく泣きじゃくり、なにか言い返していたが、細かくは覚えていない。85歳になった母はいまだに「お父さんは、麻由美(姉)の死を悲しんでくれなかった」とよく恨みがましく口にする。母は、よほど一緒に悲しんでほしかったのだろう。
「海を抱いて月に眠る」(文藝春秋)を書くにあたり、父の人生を詳しく訊いた。その際、姉の死に触れたとき、父は、「私の人生の中で、あのことはもっとも辛くて悲しかったことだから、小説に書かないでほしい」と言った。その言葉を聞いた私は、父は辛すぎて目を背けていたのだ、忘れることで姉の死をのりこえようとしていたのだ、と初めて理解した。それまでは、母同様、父を「冷たい人」だと思っていた。そしてその冷たさを私も継いでいるのだろうと考えていた。
結局、小説「海を抱いて月に眠る」には、亡くならず心臓の病を克服した兄、という設定に替えて姉に近い人物を描いたが、父の気持ちを想うと、心臓の病気を患う登場人物を書いた私は、どうしようもないエゴイストだ。作家だから、という言い訳でごまかすことはできない。そしてまた、姉の件に限らず、モデルがいる人物を描くとき、いや、モデルがいなくても、何かを書くということは、少なからず誰かを傷つけてしまう可能性があり、誰かを傷つけるということは自分も傷ついてしまうと思い知らされた。最新作「李の花は散っても」(朝日新聞出版)においても、長男を亡くした李方子さんの描写は、姉を亡くしたときの母の様子を思い出しながら執筆した。私にとっても痛みが伴う作業だったが、子を亡くした経験のある人にとっては、とくに読むのが辛かった部分だろう。刊行後、ある読者の方から実際にそのように言われた。
なにを書くのか、書いていいのか、書くべきなのか、につねに悩みながら物語を生み出しているが、答えはまだ出ておらず、ずっと考え続けている。答えは容易に出せないと思いながら、こうしてエッセイに姉の死のことを書いている。書くことで私自身が多少は救われたり楽になるのは確かだが、やましさはつきまとう。
ともに深い悲しみから生じているのに、泣き暮らす母と、一刻も早く姉のことを忘れようとする父は、表出する態度が真逆だ。夫婦がその悲しみをわかちあえなかったことが切ない。父はつねに言葉足らずで、母とすれ違い、私はその狭間で、おろおろするばかりだった。そして、私自身はというと、姉の死を、いまだにうまく乗り越えられていないような気がする。その後、祖父母や親族、友人、知人の死を経験するが、人が死ぬことによる悲しみや喪失の気持ちをうまく処理できない。かといって、父のように積極的に目を背けたりすることもできない。それなのに、泣くことだってなかなかできないのだ。
私は、姉が死んだことを周りの人に触れられたくなかった。悲しみや辛さがうまく感情として表せなかった自分を見つめたくなかったのだ。だから、いまだに誰かが親しい人を亡くしたときにどう接したらいいのかわからず戸惑う。言葉をかけようにも、混乱して黙ってしまう。
両親の言い争いのあとも、私はしばらくカップ麺を食べ続けた。やはり母は料理ができる状態ではなかったのだ。売っているカップ麺のほぼすべての銘柄を食べ、くりかえし買った。姉の遺骨が墓地に埋葬されたのが、夏休みの半ばぐらいだったから、それまでたぶん三週間ぐらいカップ麺三昧だった。
父が買った真新しいお墓は、母の実家のお墓があった府中カトリック墓地にあった。このお墓を買うにあたっても、激しい夫婦げんかが繰り広げられた。まず、日本にお墓がいるかいらないか、つまりは、文字通り、日本に骨をうずめるつもりで生きるか否かで、父と母は意見が対立した。また、信者ではない父は、カトリック墓地にも抵抗があったようだ。そして結局は買うことに決まったあとも、墓に刻む家名を本名の苗字にするか、それとも通称名にするかということでひと悶着あった。骨はいつか祖国の韓国に移すことができるからと妥協した父も、名前についてはなかなか譲らなかった。しかし、そのとき我が家の苗字は李ではなく金だった。これは父が玄界灘を小さな漁船で密航して日本にたどり着いて以来、他人の名前で生きていたからだった。(のちに、金が李になるのは、私が結婚する直前)父としては、偽りの家名よりは通称名の方がましだろうと自分を納得させて、どうにか決着がついた。
私はそのとき、両親が子どもを亡くすのが初めてではないことを知って驚いた。私が生まれる一年前に鐘珉(チョンミン)という名の兄を1歳で亡くしていたのだ。兄の遺骨は姉の納骨の日に、臨時に入れられていた母の実家の墓から移された。母は兄の死も思い起こされたようで、号泣していた。
納骨が済むと、私たち一家は、山口の宇部にいる父の知人を訪ねた。たぶん、父が母の様子を見かねて、家から出さなければと思ったのだろう。もしくは父自身が気持ちを切り替えたかったのかもしれない。
父の知人の家には外飼いの立派なドーベルマンがいて、私たちに吠えてばかりだったことや、優しい高校生のお姉さんが同行してくれて秋吉台に行ったことを覚えている。そしてその家のおばさんが作ってくれたカレーがとても美味しかったことも忘れられない。まぶたが腫れあがった母が旅行中にかすかに微笑んだことも見逃さなかった。
山口から戻った後の母は、私と妹を連れて頻繁に交通の便の悪い府中のカトリック墓地に通った。教会にもしょっちゅう行った。もちろん、遺影の前にも長く座っていたが、徐々に通常の生活に戻っていき、カップ麺生活は終わりとなった。不思議なことに、三週間ほど食べ続けたカップ麺が美味しかったのかまずかったのか、私は味をまったく覚えていない。
やがて母は、電車やバスを乗り継がないといけない府中カトリック墓地に車で行くため、運転免許を取ることに決め、自動車教習所に通い始めた。母が気力を取り戻していくのは安心したが、そのあいだ、また私は妹とともに母の実家に預けられたことが不満だった。
それからしばらく、カップ麺とは無縁に暮らした。母がカップ麺を買ってくることもほとんどなく、私も自分から食べたいとは思わなかった。けれども、中学三年の夏に、忘れられないカップ麺の思い出がひとつできた。
私には13も歳の離れた妹が増えていた。小学生と幼児の妹たちと、中学三年の私の生活はまったく異なるものの、我が家では当然のように妹たちに合わせた夏休みの生活が営まれた。そんな私の様子を見て、母方の伯父が「家族で富士山に登るから東愛ちゃんも」と誘ってくれた。私は8月のはじめ、歳の近い三人のいとこたち、伯父伯母とともに、富士山の頂上を目指した。楽しくて楽しくて、私はかなりはしゃいでいた。慣れない登山だったが、景色も美しく、会話も弾み、笑い声をたてながら歩いた。
私たち一行はご来光(日の出)を見るために八合目の山小屋に泊まった。その晩、伯父が子どもたちにカップヌードルを振舞ってくれた。歩き疲れた体に塩分たっぷりのスープが染み渡る。湯気を放つ縮れた緬がつるつると喉に入っていき、空腹を満たしていく。いとこたちと一緒で嬉しいうえに、富士の自然に感動した興奮もあいまって、そのとき久しぶりに食べたカップヌードルは、いま思い出しても私にとって生涯最高のカップ麺と言えるだろう。翌日のご来光はぼんやりとしか記憶にないのに、カップヌードルを食べたことはくっきりと映像が頭に浮かぶ。
2011年、3月11日、東日本大震災が起き、私は東京で大きな揺れを経験した。しばらく食材の品ぞろえが薄い日々が続いていた。そんなとき、関西に住んでいる友人が、段ボール二箱分のカップ麺を送ってくれた。種類もさまざまで、友人の心遣いが心からありがたかった。原発事故による不安にさいなまれているなか、カップ麺を家族で食べていると、前向きな気持ちになれた。
震災後は、カップ麺を非常食として常備するようになり、コンビニやスーパーでもカップ麺の棚に目が行くようになった。また、韓国のカップ麺が容易に手に入るようになり、いろいろと試すのが楽しくて、新大久保の韓国スーパーに行くたびに袋めんとカップ麺を買うようになった。韓国ドラマを観ていると、カップ麺を食べている場面がよく出てくるが、韓国のカップ麺も実に種類が多い。ソウルに行ったときはかならずマーケットに寄るのだが、日本で手に入りづらい銘柄のカップ麺をおみやげに買うのも楽しみの一つになっている。
そういえば、数年前、アメリカ留学していた娘を迎えに行って日本に帰る前、ニューヨークの空港のカフェで食べたのも、辛ラーメンのカップ麺だった。アメリカ式の食事に飽きていたから、とても美味しかったし、妙にほっとした。
娘によると、アメリカの高校や大学では辛ラーメンが自動販売機で売られていて、かなり人気があるそうだ。また、アメリカ国内のスーパーマーケットには、多くのカップ麺が並んでいるという。そこには日本のカップ麺もあるが、銘柄は、日清よりマルちゃんが多く見られるらしい。海外で食べるカップ麺は格別の味で、多少高くてもつい買ってしまうというのもうなずける。
娘の留学中、EMS(航空便)でカップ麺を送ったが、牛肉エキスなどのなんらかの成分がひっかかかり、箱を開けたらカップ麺がすべて没収されていたということがあった。それ以来、娘は留学する際、スーツケース二つのうちの一つのほぼ半分にカップ麺をつめて行った。
横浜みなとみらいにカップヌードルミュージアムがある。カップ麺を生み出した日清食品の創業者、安藤百福は、カップラーメンの製造技術を独占しなかったということをそこで知った。そのおかげで、カップ麺は多彩になり、日本だけでなく、世界中に広がった。そして、ありとあらゆる状況で、カップ麺が登場するようになった。安藤百福は、ノーベル賞にも匹敵する発明をしただけでなく、平和にも貢献したと思う。ひとは、同じような食をわかちあえば、心を開き、いさかいや戦争も起こさないのではないだろうか。そうであってほしい。
コロナ渦中、感染したひとのところに行政から送られる食材のなかにもカップ麺が入っていた。もうすでにカップ麺は私たちの生活になくてはならないものとなりつつある。手抜き、なんていうレッテルは過去のものだ。それこそ、コロナ禍やその後のロシアのウクライナへの侵攻により、気軽に海外に行かれないなか、海外の(味の)カップ麺を食べてちょっとした旅行気分だって味わえる。
これからも私はカップ麺を食べ続ける。
創り出した人のすごさを感じたり、人の痛みや悲しみを想ったり、ひとときの安寧を求めたり、世界の味を楽しむために。あるいは、単純に手っ取り早く空腹を満たすために。そして、平和についても考えられたらいい。
いま、かなりお腹が空いている。このエッセイを書き終えたら、ストックしておいた辛ラーメンを食べよう。
私が気に入っている辛ラーメンのカップ麺の食べ方は、お湯の代わりに豆乳や低脂肪乳を注ぐというものだ。ぬぐい切れぬ「インスタントは不健康」というやましさを健康的と思われる豆乳や低脂肪乳が払しょくしてくれるうえに、辛ラーメン独特の酸味も和らぐ。夜中のカップ麺の誘惑によって引き起こる胃もたれも少しだけ軽くなる。
いやいや、やっぱりこってり食べたいというひとは、普通の牛乳を注ぎ、とろけるチーズとねぎを足して、さらに韓国のりをのせたら最高。カロリーが高くて塩分たっぷりの体に悪そうなものは悪魔の味で美味しいなあと、背徳感で悦に入ること間違いなしだ。

【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。