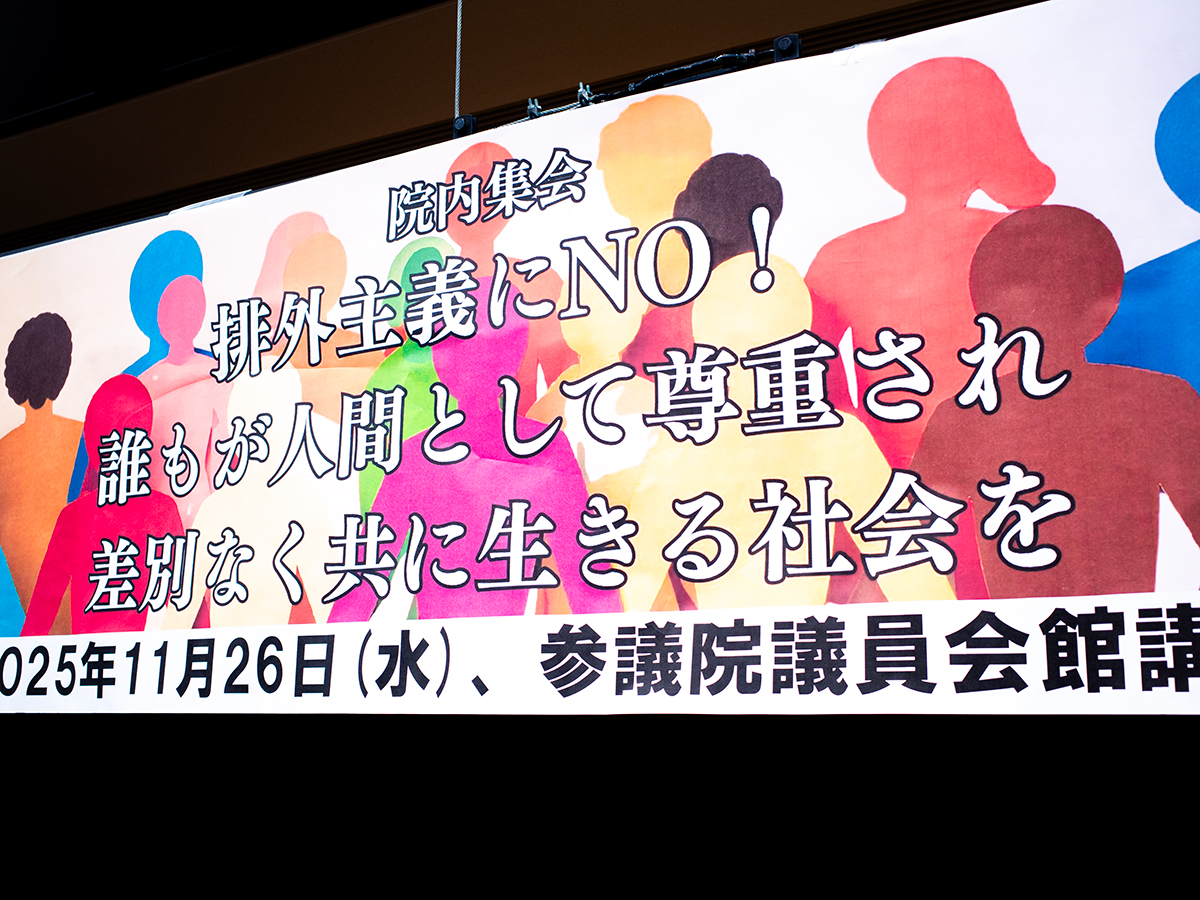「学校で倒れるまで、睡眠時間を削って成り立つ日々に歯止めがかからなかったんです」
「時間が経ってからようやく、家庭での時間や自分の身体を犠牲にしてこの仕事が成り立っていたんだって気づきました」
――公共訴訟を支えるプラットフォーム「Call4」とともに、働き方について訴訟を起こした教員やその関係者を取材し、それをまとめた動画「人間を育てる教員に、人間らしい働き方を」が公開された後、現役、もしくは現場をすでに退いた教員から、相次いで悲鳴のような声が寄せられた。文部科学省が2016年に実施した「教員勤務実態調査」によると、小学校教諭の33.4%、中学校教諭の57.7%が、「過労死ライン」といわれる月80時間以上の時間外労働をこなしているという。

文部科学省が教職の魅力を広める目的で始めたツイッター上のプロジェクト「#教師のバトン」には、現場の過酷な労働環境を訴える声が寄せられた
取材に応じてくれた兵庫県内の中学校教員Aさんは、30代女性、6月から産休中だという。本来は今年4月から年休を使って休みをとりたい気持ちはあったものの、教員不足などから、どうしても現場を抜けにくいと感じたという。
「女性教員の流産の話も聞いていたので、産休に入る前、自分も部活の指導で一日極寒の体育館にいて大丈夫なのだろうか、ということも心配でした。病院に行こうと思っても、人手が足りないと職場から抜けづらいですよね」
Aさんの本来の定時は8時15分から16時45分となっているが、実際には、早ければ朝7時に出勤する。給食の時間に「休憩時間」があるはずだが、それを「休憩」にあてるのは不可能に近いという。味わう間もなく数分で食事をかき込み、「給食指導」にあたる。「日中はとにかく時間がかつかつ。一番しんどいのは、部活動の時間が長い夏場ですね。19時頃に生徒が帰宅してから、次の日の授業の準備、報告書の作成、不登校の子どもたちのフォローをします」。夜9時~10時頃までの勤務も珍しくはない。時間外労働は「過労死ライン」の80時間を大幅にこえる、100時間に及ぶこともあった。夏休みなどの長期休暇に入ったとしても、そこには研修が詰められている。春休みにいたっては、3月後半まで次年度の人事異動などの通達が来ないため、そこからぎりぎりの時間をやりくりして、新学期のための会議を朝から晩まで重ねることになる。
こうした長時間労働の要因のひとつに、勤務時間内では終わらないほどの業務が、事実上「校長からの指示」で割り振られることも指摘されてきた。そしてこうした問題を広く考えていくと、「校長の指示」の背後には、より大きな構造の問題が見えてくる。
「とにかく、教育委員会や国から降りてくる案件がとても多いんですよね。例えばタブレットを500台導入します、数ヶ月後までに先生たちで手分けしてパスワードやアドレスの設定を済ませて下さい、というのがこちらの同意なしに降ってくるんです。学校に送られてくるのはタブレットそのものだけで、教員や生徒に使い方をサポートしたり、修理に対応したりする人は研修に一度来たのみでした。トラブルや不具合は全て、教員が通常業務にプラスしてやらなければならなんです」
Aさんは、文科省に現場の声が十分に伝わらない仕組みにも問題があると感じているという。学習指導要領に記載されている年間の「中学校標準授業時数」の総授業時数は、1051単位(1単位あたり50分)となっている。
「実際は、これだけの授業数をこなすのは現場として困難で、試験や体育大会の後に授業をしたり、なんとか帳尻を合わせているような状況です。けれど文科省には数字上、標準授業時数をこなせている、というデータが届きます。だからこそ、じゃあもっとできるでしょう、と上乗せした授業数を要求されてしまうのではないでしょうか」
さらに今、現場にのしかかっているのがコロナ対策だ。「感染拡大し始めた当初は、子どもたちに掃除をさせず、全クラス、全校の清掃と、消毒なども教員が担っていました。私たちは感染していいんだろうか?と思ってしまいますよね。生徒たちの健康観察カードを毎日チェックしなければならず、家で体温を計っていない子に対処したりと、朝の騒がしい教室の中で細かな確認を行っていくのは、教員にもストレスが大きい。
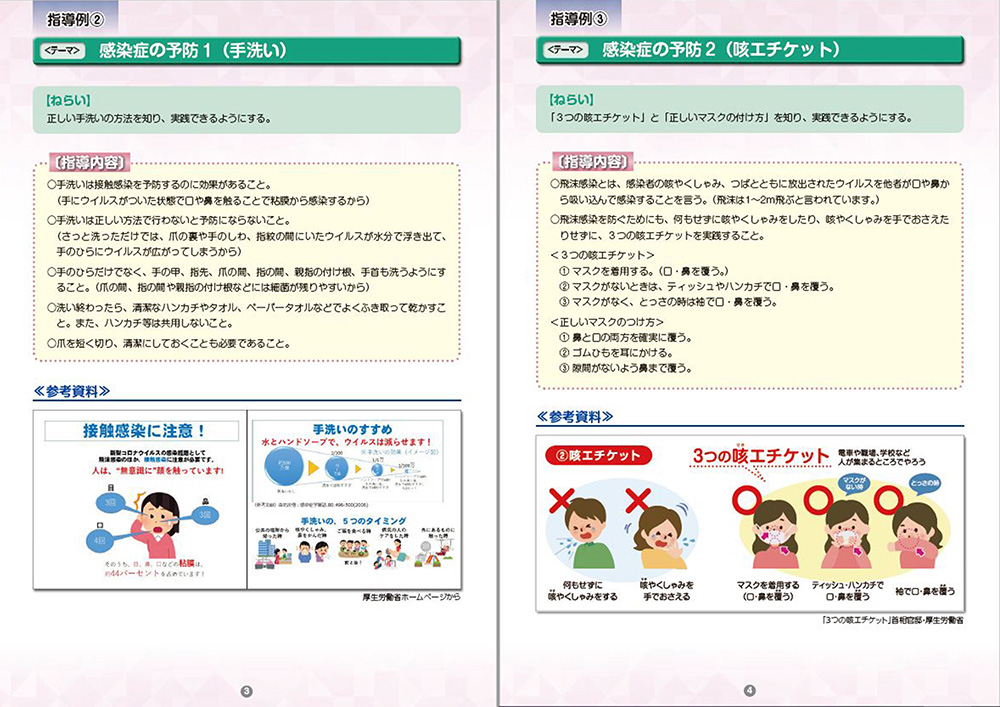
文部科学省「新型コロナウイルス感染症の予防~子供たちが正しく理解し、実践できることを目指して~」より抜粋
こうした過酷な労働環境にさらされ続けている周囲を見ていると、家庭生活や家族との関係性に著しい支障をきたしている教員も少なくないという。「うつで倒れて休職になった同僚もいたのですが、周囲が強く説得しなければ、病院に行かず学校に来るつもりだったようです。やはりそれも、“担任を持っていて、代わりができる人がいない”という、人材の余裕がないことが一因でしたね」。
文部科学省が今年2021年4月に公表した、2019年度の公立学校教職員の「人事行政状況調査」によると、精神疾患による病気休職者は5,478人にのぼり、前年度に比べて266人増加、過去最多の人数となった。
問題は長時間労働の問題に留まらない。「賃金をちゃんと支払われずに働かされているのが、働き方という意味でも、これからの人材を育てていくという意味でも最大の問題だと思います」と、Aさんは切実に語る。
公立学校の教員には、「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)と呼ばれる法律が適用されている。この「給特法」では、教員に対して命じることができる時間外労働を①実習、②行事、③職員会議、④非常災害など緊急の処置の4項目のみに限定した上で、この4つに対する手当を支払わない代わりに、基本給の4%を「教職調整額」として上乗せ支給するものだ。ただ、Aさんが語っていた通り、実際には勤務時間外に、この4項目以外の業務をこなさなければ、仕事が追いつかない現実が厳然と存在している。けれどもそれらは“自主的・自発的”なものとみなされてきた。まさに実態は「定額働かせ放題」だ。
こうした実態に声をあげ、訴訟を起こした人がいた。
埼玉県内の小学校に教員として38年間務めてきた田中まさおさん(仮名)は、教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求め訴訟を起こしている。判決は9月17日に言い渡される予定だ。

裁判所に向かう田中さん(左)と若生弁護士
田中さんは教員として、子どもたちと向き合うこと自体には、やりがいを感じてきたという。
「初めて担任した5年生たちや、その後受け持った1年生たちも、優しさや思いやり、相手をいたわる気持ちなど、ちゃんと“心”を持っている、子どもってすごいって感じたんです。そんな子どもたちと接して、僕は一生小学校の教員やろうって思ったんですよ」
ところが今の現場に立つ若い教員たちが、常に時間に追われる姿を目にするようになった。とりわけ田中さんが訴訟を起こした学校は、清掃や給食の配膳など、何でも“無言”で作業をさせることが負担になっていたという。
「子どもは静かになるはずがないし、どんなテクニックを使えば静かにできるか、朝から晩までそれを考えなければならない、それが“いい先生”であるかのようになってしまっていました」。コロナ対策以前から、何でも沈黙のままにこなさなければならない理由は何なのか…「そこに“なぜ”は関係ないんですよね。なぜかと言えば、校長先生がそうしなさいって言うから」
こうした負荷が「常態化」してしまっている現場を、根本から変えていくのは決して容易ではない。
「例えば、本来の勤務開始時間に“朝会”が始まるのであれば、教員たちはそれより前に学校に行って、静かに子どもたちを連れて並ばせていなければなりません。こうしたことが“当たり前”になってしまっていて、これは裁判でなければ変えられない、と思ったんです」
3月に傍聴した口頭弁論では、先述したように、事実上の指示された仕事であり、勤務時間内に終わらない業務量であるものが、「自主・自発的」な活動としてみなされている点が終始問われた。
「“命じる”という言葉を使わなければ、労働に当たらないっていう解釈をされてるんですよね。そうではなく、仕事が発生した以上、それは命じたことと同じだというのが、僕の主張なんです。今の法律は、残業代は出しません、その代わり時間外勤務は命じません、となっているんですから、それに従って時間外勤務をなくせばいいと思うんです」
県側は、「教員の勤務時間管理は、一般の労働者とは異なる」としたうえで、「教職調整額は超勤4項目にかかる時間外勤務の対価としてのみ支給しているものではない」と主張している。つまり、基本給の4%の額が支払われる「教員調整額」は、超勤4項目以外の時間外労働に対しても支払われている、ということになる。けれどもこれは、超勤4項目以外の勤務は、「自主的・自発的」なものとしてきた文科省の見解とは異なる。
今回の訴訟でとりわけ注目すべきは、田中さんが訴えている実態が、「労働基準法32条」違反にあたるのか、という点だ。32条では、労働時間の限度を1日8時間、1週間40時間と定めている。

テストの採点とその記録も、時間を要する仕事の一つだ
代理人を務める若生直樹弁護士は、「今回の訴訟では、教員にも労働基準法が適用されるという原則に立ち返り、労働基準法に従った判断というのをするべきであるということをかなり強調しています。この法に従って考えれば、勤務時間外に教員が行っているテストの採点や、登校指導などは、学校からの指示による職務として行っている、つまり労働時間に当たることは間違いありません」。
その上で、訴訟の社会的な影響についても若生弁護士は語る。「当然この裁判の結果は、原告やひとつの学校だけではなく、全国の教員の方、全てに関係してきます。仮に今回の訴訟で、今の教員の働き方が違法だということになれば、抜本的に状況を変えなければならないという問題提起にもなると思います。それは教員だけの問題ではなく、一般の全ての労働者にとっても、今の働き方が本当に妥当なのかを問う機会にもなると考えています」。
そんな田中さんの支援の輪が、次世代にも広がりつつある。大学4年生で、教育学科の学生の五十嵐悠真さんは、田中さんの裁判をサポートする学生の一人だ。

教員を目指す友人たちへの思いを語ってくれた五十嵐さん
五十嵐さんは高校三年生の時、教員の過労死裁判を、判決日に傍聴したことがあった。「それ以来、裁判というものが“ニュースで見る、誰かが起こしているもの”ではなくて、“生きている一人の人間が起こしているもの”という実感が湧くようになったんです。訴訟って、判決の時に一番報道されると思うんですけど、そこまでにずっと、原告の人や弁護士さんは闘っているんですよね。判決後の報告会で、“見てるよ”“関心持ってるよ”っていう声が集まることが、そんな原告の力になると聞きました」。
田中さんのことは、「田中まさお支援事務局」を立ち上げた学生との出会いをきっかけに知り、メンバーに加わった。
周囲の教員を目指す学生が、「子どものためだったら、いくらでも働いていい」と真っすぐに語る姿を目にする度、五十嵐さんは複雑な思いを抱くという。「実際に今、教員がやらなければならない業務自体がかなりの量で、子どものために頑張れる時間が圧迫されていると感じています。このままでは、きらきらと夢を持っている友人たちが、先生になりたくてなっても、仕事を続けられなくなっちゃうんじゃないかと思って……。制度が変えられるなら、そんな友人たちが“こどものために頑張れる”先生になれる現場、仕組みができたらいいなって、僕は思っています」。
五十嵐さんはこの問題が裁判によって提起されたことで、「こんなにおかしい制度がある」ことへの気づきが広がっていくのではないかと感じているという。
インタビューに応じてくれたAさんは、「自分の家のこと、自分の人生も犠牲にし、でも教員とはそういう仕事、仕方がない、でこれまでまかり通ってきてしまったんだと思うんです」と、硬直化してしまった現場、仕組みへの問題意識を語った。こうして誰かの犠牲を前提に成り立つ社会は、果たしてあるべき社会の姿だろうか。これまで、「子どものためだから」という言葉に押し込められてきた実態を、根本から見直す時ではないだろうか。

3月、口頭弁論へと向かう田中さんと若生弁護士
▶︎田中まさおさんの訴訟についての詳細はこちら
「人間を育てる教員に、人間らしい働き方を」訴訟 (CALL4のページに遷移します)
(2021.6.15 / 写真・文 安田菜津紀)
(書き起こし協力:渡辺加代子、三宅大生、永橋風香)
あわせて読みたい
■兄へ もう、死ぬために働くのはやめよう[2020.5.20/安田菜津紀]
■「私たちの身に起きたことが、明日また誰かに起きるかもしれない」 ―せやろがいおじさんから、ウィシュマさん家族へのインタビュー[2021.5.29/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。