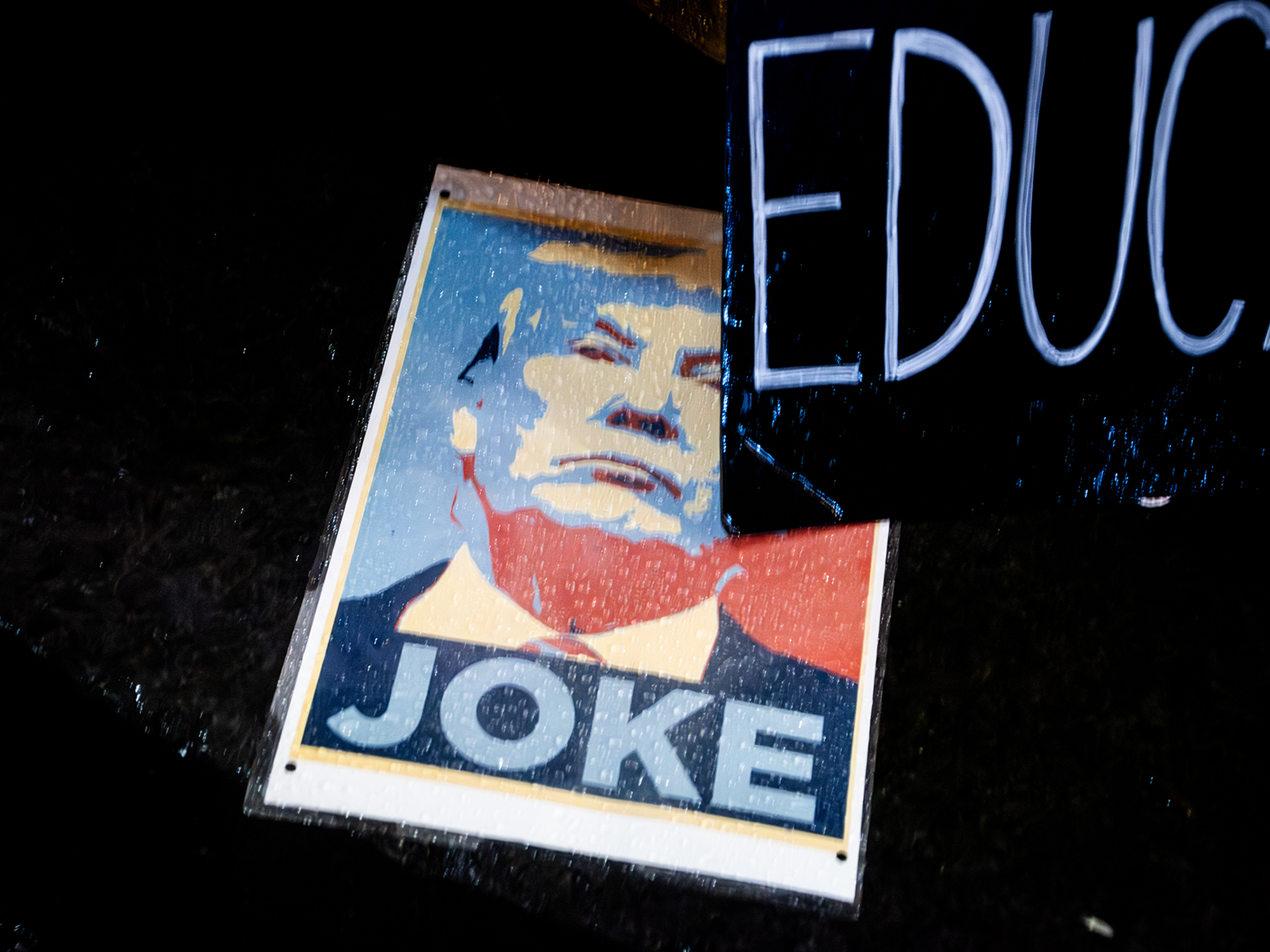
トランプ氏が再びアメリカ大統領に就任して5ヵ月以上が経ちました。6月には、イスラエルがイランの核施設や軍事拠点に対して大規模な空爆を行ったのに続き、アメリカもイラン国内の核施設に対してB-2ステルス爆撃機による精密攻撃を実施しました。
国際秩序、経済、そして民主主義のあり方までが問われる中、政権は混迷を極め、アメリカ社会にはさまざまな混乱が続出しています。
ニューヨークに20年以上在住するジャーナリストの津山恵子さんに、お話をうかがいました。

イラン攻撃と「トランプ劇場」
――6月にはイスラエルに続き、アメリカもイランの核施設を攻撃しました。トランプ政権のイランに対する対応について、どのようにご覧になってきましたか?
やはり「トランプ劇場」だと捉えています。その効果がどうだったのか、あるいは今後どうなるのかといったことは不透明なまま、12日間で攻撃は終わった。ただ、お伝えしておきたいのは、アメリカ国内は「戦争が始まるんじゃないか」と、ものすごく緊張したということです。
大統領選挙中、若いトランプ支持者の中には「トランプは戦争をやめさせてくれるから支持する」という人がたくさんいました。ところが、今回のイランへの攻撃は、ほとんどトランプ氏の独断でやったように見えました。これはトランプ支持者に対する裏切りとも映りましたし、トランプ氏を支持する・しないに関わらず、かなりの驚きがありました。
――トランプ政権は中東への関与を最小限に抑える傾向があったと思いますが、今回イランに対する直接的な攻撃に踏み切った思惑、背景としては何があるのでしょうか?
トランプ氏自身は軍隊の経験もなく、国防長官のピート・ヘグセス氏も元FOXニュースのアンカーで、軍隊の経験はありますが軍事が専門ではありません。国家情報長官のトゥルシー・ギャバード氏は若い女性ですが、彼女も軍隊経験があるというだけで軍事情報機関の知識は全くない。こういう人たちだけに囲まれて、戦争に踏み切ったことへの不安はとても大きいです。
では、なぜ踏み切ったのかと言うと、これはやはり「トランプ劇場」の一部だと考えています。トランプ氏は注目を浴びたい人で、物事をディール(商談)、要するに「ここにある不動産の物件を手に入れるかどうか」という勝ち負けだけで見ているので、中東で起こった事に対しても自分が出て行って勝ちを取ってこなくてはならない。そうしないと支持者の注目を維持できないと思っています。この「トランプ劇場」に、世界的に巻き込まれたという緊張感は大きいと思います。

アメリカ国内の温度差
――イスラエルがイランを攻撃した際、トランプ大統領はイスラエル支持を明言しましたが、マルコ・ルビオ国務長官は「イスラエルは単独で行動した。アメリカは関与していない」と述べました。政権内にも意見の違いや温度差があるのでしょうか?
今回の決定に関して驚いたのは、議会が全く絡んでいない点です。オバマ氏やブッシュ氏も議会の承認なしに軍事行動を起こしたことがありますが、軍事については素人と言える国防長官と国家情報長官の意見だけを聞いて踏み切ったという点では、共和党内でもかなりの驚きがあり、議会を無視したことに対してまだ反対している人たちがたくさんいます。
また、今も続くイスラエルとガザの状況については、アメリカ国内がほぼ二分されています。日々の生活でも、周囲の人がどちらの立場なのか配慮が必要な状況なので、その文脈からも今回の対応はショックであり、意見も分かれていると思います。
――アメリカの若者世代やリベラル層は、今回の軍事衝突やトランプ政権の対応をどう見ているのでしょうか?
私が住んでいるニューヨークでは、9割前後くらいがリベラル派と考えられるので、すぐに若い人たちがデモに出ていました。イランへの攻撃が行われたのは、アメリカ現地時間の土曜日でしたが、日曜日にはもうデモ隊が出てきて、同時多発的に市内でデモを行いました。
それから、警察のいつもの対応ではありますが、たとえばイスラエルの国連代表部やシナゴーグなどの警備がいきなり強化されたことに対する市民の反応というのはとても強いです。
――アメリカのメディアでは、イスラエル・イラン問題へのトランプ政権の対応について、どのような視点やトーンで報じられていますか?
ニュースはこれ一色になりましたが、やはり一番集中していたのは、「なぜイランを攻撃したのか」ということです。トランプ氏は戦争をしないと言って当選したわけですから、ホワイトハウスの中でどういったプロセスがあって、こうした軍事行動に出たのかということについて、かなり記事が出ていました。
ただ、その中身としては「よくわからない」。軍事の専門家ではない国防長官や情報長官がどういう立場にあるのか、憲法学者に相談をしたのかなど、詳細は不透明なままです。
――専門家ではない人間が軍事的な手綱を握っているとなると、生活者として、自分たちの生活にそれがどう跳ね返ってくるかわからないという怖さはありますか?
それはありますね。かつて軍隊に在籍していたとか、あるいは家族が今も軍隊にいて、中東に配備されているというような人たちも周りにたくさんいます。アメリカが軍事行動に出た途端に、中東にいる自分の息子や娘がどうなるのかという緊張感が彼らにはあります。
――今このお話をしている時点(2025年6月25日)では、脆弱であるとはいえ停戦状態が維持されているように見えますが、今後アメリカはどのような立場を取っていくのでしょうか?
その点も本当に不透明です。政権としてイスラエルとの関係を友好的に保っていくという点はブレないだろうと思われます。今回の攻撃は夜中に突然、停戦合意の速報が流れて、あっという間に終わった印象ですが、その結果について、おそらくトランプ氏自身は満足しているのだろうとは思います。

ICEへの抗議デモと州兵派遣
――もうひとつ、津山さんと考えたいのが、6月上旬にカリフォルニア州ロサンゼルスで始まったICE(移民税関捜査局)に対する抗議デモについてです。一部で衝突があったことを受けて、トランプ政権はカリフォルニア州知事の頭越しに州兵を派遣しました。抗議デモに関して、津山さんのもとにはどんな声が届いていましたか?
ニューヨーク在住の私の友人が、たまたまロサンゼルスに家族を訪ねていたところ、アパートの近くでデモが始まったと聞きました。最初に目にしたのは平和的なデモで、犬を連れてきている人がいたり、ベビーカーもいくつか見たという状況だったのですが、いきなり警察官がガスマスク、つまり催涙ガスを使うための準備をして来たそうです。
催涙ガスを使うようなデモというのは、私は20年間ニューヨークに住んでいますが、見たことがありません。さらに警察はマシンガンも持っていて、防弾チョッキもつけており、一気に緊張感が増したということでした。
それから、トランプ氏が過剰反応をして投入した州兵ですが、これはデモ隊とぶつかったわけではなく、州や連邦の施設を守る目的で連邦政府ビルの周りに警備として配備されました。フル装備の州兵がビルを囲み、その前に平和的なデモの人たちがいるというその状況を見て私が思ったのは、トランプ政権は民主党が強い州の首長などを怖がらせるようなことを、意図的にやっているということです。
カリフォルニア州にはギャビン・ニューサム氏という州知事がいますが、リベラルな人が多い地盤で「俺の方が権力がある」ということを見せて、首長をまず怖がらせる。それを目にした人々も怖がるという、「恐怖政治」と言っていいようなことを狙っているなと強く感じました。
――こうした対応がなされてしまったことの影響というのは、どうご覧になっていますか?
各地の民主党の地方自治体首長、それからリベラル派の市民に対して恐怖感を与えるという意味では、ものすごく効果があったのではないかと思います。
ニューヨークでも、市民はものすごく警戒しています。たとえば今週末(2025年6月末)にLGBTQ+の権利を祝うプライドパレードがありますが、私は(催涙ガス対策として)水や濡れたタオルを持っていこうと考えています。同じようなことを考えている人はたくさんいると思います。ニューヨークでもロサンゼルスと同じような事態になるのでは、という恐怖感を増幅させた効果は、十分にあったと思います。
――抗議デモの背景には、ICEによる非正規移民の一斉摘発があります。合法的な移民さえも摘発するICEのやり方について、アメリカ国内ではどのような議論が起きていますか?
個人的には反対しています。非正規移民を全部一掃してしまったら、たとえばレストランの店員や、キッチンのコックさん、倉庫で働いている人などがいなくなってしまう。アメリカの経済が成り立たなくなるわけです。非正規移民=犯罪者と捉え、強制送還するという考え方は間違っていると思います。
滞在許可をまったく持っていない人たちはデリバリーの食事を運んだり、スーパーマーケットの棚に物を並べたりしている、アメリカの生活と経済の縁の下の力持ちです。しかし、そういう正しい情報を与えずに、グリーンカード(永住権カード)を持っている人たちまで空港で職質をされているのが今の状況です。これも恐怖政治の一端であり、そしてその最先端で行っているのがICEになると思います。
ニューヨークのデモと市長選
――リベラルなニューヨークであっても、ここまで強権的なことをされると、移民ルーツの人たちは摘発などを恐れて、抗議デモに参加しづらいのではと想像します。現場への影響はどう感じられていますか?
4月15日に「No Kings Day」というデモが全米2,000ヵ所くらいで行われ、ニューヨークでも大きなデモがありました。しかし、その参加者は約5万人で、私はこれは少ないと思いました。
逮捕などを恐れて出てこられない人たちが、たくさんいると思います。実際にデモでインタビューをすると、「友だちの非正規移民の人たちが出てこられないから、自分は白人としての優位性を活かしてここに来ている」と言う人もいます。
6月には、ニューヨーク市長選挙の候補者で、市会計監査官のブラッド・ランダー氏がICEに逮捕されるということもありました。拘束された移民の収容施設について、健康に対する配慮などが非常に悪いということで見学を求めていたところ、ICEに拘束されたんですね。
ICEはそもそも、9・11の後にテロリスト対策として設置された国土安全保障省の下にある組織です。なぜそのICEが、抗議をしただけで何もしていない市長選候補者を拘束したのか。こうしたことが心理的な衝撃を与えていると感じています。
――ニューヨーク市長選挙について、候補者を決める予備選の結果もかなり注目されています。
昨日(注:インタビュー前日の2025年6月24日)参加した私的なパーティーでは、民主党の予備選で33歳のゾーラン・マムダニ氏が予備選のトップに立ったという速報が出て、若い人たちがワーッと盛り上がっていました。
本選挙は11月ですが、ニューヨークはリベラルなので、民主党のトップに立った人が市長になる可能性が極めて高いです。マムダニ氏を次期市長にということで、若い人たちの期待感がものすごく高まっていましたが、「本当に勝った」という感じでした。
抑圧された環境で、目の前でトランプ的な世界が広がっていくのを止められないと感じている中で、「デモには行けなくても、選挙に行って一票を投じれば、もしかしたら何か物事を動かせるかもしれない」という若い人たちがかなり選挙に行って、こうした結果につながったのではと感じました。
マムダニ氏の掲げる政策で若い人たちに受けていたのは、たとえば公共交通機関の完全な無料化や、富裕層に対する増税です。彼は急進左派で、「民主社会主義者」と新聞記事にも書かれています。歴代の民主党の市長よりも、かなりリベラルに振れた公約を掲げているのは間違いないと思います。
予備選の相手候補は、元州知事のアンドリュー・クオモ氏という、新型コロナウイルスのパンデミックの時に一時有名になった方でした。その後セクハラが明らかになり辞任した方ですが、父親も州知事でニューヨークの政治家ファミリーの中でも強力な人で、ブルームバーグ元市長などもこの人を推薦していましたが、あっけなく負けたのです。

日本人コミュニティへの影響
――今アメリカで暮らしている日本人コミュニティの中では、何か動揺が広がっていたり、直接的な影響はあるのでしょうか?
もちろん動揺はものすごく広がっています。4月11日から、大統領令により移民はグリーンカードか、あるいはビザ付きのパスポートを外出する際持ち歩くことが義務化されました。それまでも実は法律的には義務だったのですが、大切なものなので実際には持ち歩く人はいなかった。この時は日本人コミュニティで、どうやって持ち歩くのか、お財布を変えるのかなど、ショックが広がりました。
日本との行き来についても、やめた方がいいのではないかと考えられています。既に日本人でグリーンカードを保持している人でも、空港に留め置かれたという例が出ています。学生ビザを取り上げられてしまい、訴訟を起こしたという例もあります。
――様々な点で市民同士の断絶が浮き彫りになってきた、トランプ政権の5ヵ月間だったかと思いますが、今後注目されていきたい点はありますか。
取材を続けていくことが、私にとって声をあげることになるので、取材活動はやめずに続けていきたいと思います。もう1つは、アメリカで何かが起きるのを待っているというよりは、日本国内にいる日本人も、企業も団体も政治家も、見通しが不透明なトランプ時代にどうやって生きていかなければいけないか、「プランB」として考えていかなければならない時だと思います。自分はこのトランプ時代をこうやって生きていこうという、私自身もですがみなさんも、そういう視点を持っていかなければいけない時代に入ったのだと思っています。
※本記事は2025年6月25日に配信したRadio Dialogue「混迷のトランプ政権」を元に編集したものです。
(2025.8.7 / 聞き手 安田菜津紀、 編集 伏見和子)
【プロフィール】
津山恵子(つやま けいこ)ニューヨークに20年以上在住するジャーナリスト。専修大ジャーナリズム学科講師。社会、ビジネスなどについて現場第一主義で取材を続けている。米大統領選挙の取材は5回目となる。著書に「現代アメリカ政治とメディア」(共編著)など多数。元共同通信社記者。
あわせて読みたい・聴きたい
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。





