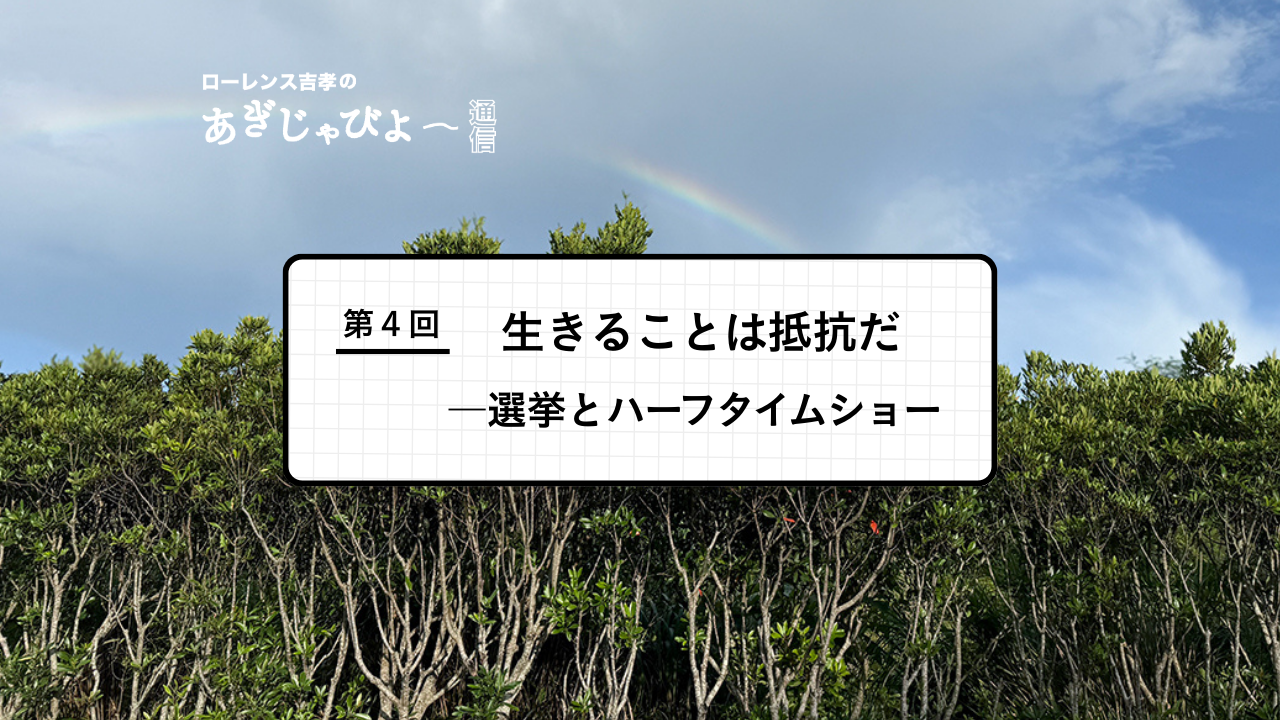ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル&ギターを務め、新しい時代とこれからの社会を考える新聞『THE FUTURE TIMES』の編集長を務める後藤正文さんに、「今という現在地から見える過去と未来」についてインタビューを行いました。自然災害や、世界規模の環境問題、国家という境界線と、それぞれの自由と権利、そして現在猛威を振るうCOVID-19(新型コロナウイルス)まで、思索し、行動するひとりの人間としての後藤さんにお話を伺いました。

お金ではない価値観で繋がる
佐藤:4月17日にリリースされた『Stay Inside』を聴かせて頂きました。売上はすべてCOVID-19により苦境に立たされている音楽関係者の方々への寄付になるとのことですが、後藤さんは2011年の東日本大震災後もすぐに曲を配信したりと、様々な活動をされています。その時と比べて軽やかになったというか、身軽に活動を行っている気がしたのですが、当時と比べて何か変化などあったのでしょうか?
後藤:当時はレーベルとミュージシャンとの契約の縛りがまだきつかったんですよね。震災後すぐに『砂の上』という曲を出したのですが、それも自由にシングルとして配信することは難しかった。レーベルのサイト内で、ストリーミングでならなんとか、という状況でした。でも今は、僕はソロ活動に関してはかなり自由にやらせてもらっていて、例えばYouTubeだとか、レーベルの外のサーバーに楽曲を置いたり、発信できるようになりました。そういう意味では、レーベルとミュージシャンの在り方というものが、柔軟になってきていると感じます。おかげで非常に動きやすくなってはいるけれど、それも黙っていて変わったわけではありません。ちゃんと対話を行いながら、アーティストもきちんと自分たちの独立性を確立していかないと、いざという時に動けないんだと学んだのです。震災後10年近くかけて、ゆっくりとそうやって学んだり話し合ったりしたことが、今に繋がっているんですよね。
佐藤:今回(『Stay Inside』)の作品は、SNSで一緒に活動できる人を募ったりといったこともされていたと思うのですが、それも10年前では考えられなかったことでしょうか。
後藤:そうですね。『THE FUTURE TIMES』をみんなで作ったじゃないですか。色々な人と一緒に紙面やイベントをつくってみて、広く呼び掛けると、「気持ちのある人とは繋がれる」ということを知りました。それは僕としては、東日本大震災のあとに見つけたひとつの希望のようなものです。仕事ひとつ作るのもそうですが、やっぱり「やってみたい人」というのはいて、まだ見ぬ才能とか、持て余している人はたくさんいると思います。こういうのも、以前だったら思いつかなかったことというか、みんなとの出会いの中で気づいたことです。これで「一発儲けてやろう!」なんて考えていたら繋がっていかないと思いますけどね。
佐藤:善意、といってしまうと安易な言葉かもしれませんが、みんな新たな可能性を求めているのかもしれません。『THE FUTURE TIMES』に関わらせて頂いた中で、常に考えてきたことが「現在地」というものです。これまで人類はどんな道を歩いてきて、この「現在地」へとたどり着いたのか。またこの「現在地」から、僕たちはどこへ向かっていくのだろうか、という。後藤さんはこういった視座を「地図を書き直す」「マッピングをする」という言葉で表現されていますが、今現在の後藤さんの地図には、どんな景色が広がっているのでしょうか?
後藤:お金だけの繋がりではやっていけない、ということがわかった気がします。例えば今、COVID-19によってライブハウスが苦境に立たされていますが、音楽が好きだから支援したいという人はたくさんいると思います。そんな中でも如実に支援の集まるライブハウスというのは、やっぱり単にお金のやり取りだけではない繋がりを、きちんと積み重ねてきたところだと思うんですよね。資本主義というものによって、僕らはいつのまにか「お金」というマインドに浸食されてしまうところだったのですが、やっぱりそうではない、「信頼関係」のようなところに戻っていかないと難しいんじゃないかと思います。そのために大切なのが、「みんなで考えなきゃいけないよね」って問いかけていくこと。全てをお金という尺度で測って本当にいいのかと。新自由主義のようなものを基盤にしていくと、「自己責任」とか、「お金を稼げない人は価値がない」という見方が強くなっていくように思うのですが、それで本当にいいのか?と。
命の価値に優先順位があるのか、という話にも繋がってきますよね。新型コロナウイルスによる現状を見ても、お金のある人ほど選択肢がある。そういう現状を「どう変えていけばいいだろうか?」と、考えていく必要があると感じます。僕が何か答えを出せるわけではないので、色んな本を読んで勉強したり、有識者の知恵を持ち寄ったり、みんなで社会の在り方を問い直さないと、貧富の差、機会の差だけが拡がってしまうんじゃないでしょうか。でも実際は、そうした取り組みを世界規模でやっているわけでもなくて、繁栄の裏側で何が起きているかなんて、あまり考えることもない社会になってしまっている様に思います。
「Stay Inside feat. mabanua」 Gotch
「生まれながらに選べないもの」を是正していく
佐藤:お金を稼げるかどうかで人の価値を測るという見方が、どれだけ人間社会にとって破壊的な作用を及ぼすのかということは、僕たちも世界各地を取材していて感じます。おそらく、この危機意識というのは今現在に限ったものではなく、特に産業革命以降の文学や思想というものは、そういった世界観に警鐘を鳴らし続けてきた部分もあるではないでしょうか。「地図」の話に戻って例えると、人間の歩いて来た「過去の地図」にも、「こっちに進んだら危険だぞ!」という標識が立っていたかもしれない。それがいつの間にか、見慣れてしまったのか、見ないふりをしているのか、こんなに奥まで進んできてしまった。でも逆に、こういった道を歩いて来たからこそ感じる新たな道の可能性、希望などはありますか?
後藤:どうなんでしょうね(苦笑)。なかなか、今から引き返すにはタフなところまでマインドセット(思考様式)が凝り固まってしまっている人もいる気がします。例えば生活保護にしたって、それを受給することを叩く人たちがいますよね。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」といった、憲法に書かれていることにすら理解がない。資本主義的な考え方に寄っていっても、生活者が何も買えないぐらい困窮していったら、どのみち経済も成り立ちません。このままじゃ全員倒れてしまうよって、思うんですよね。やっぱり普通の市民たちが豊かじゃないと、社会というのは回らないようにできている。今の現状は、生活に困ったこともない「富める側」が政治を行ってきて、市民から搾るだけ搾ってきた積み重ねでもあると思います。だからCOVID-19に関してもこれだけ給付が遅い。市民をないがしろにすることで、全体的に首が絞まるということは普通わかるじゃないですか。みんなが家賃を払えなかったらビルのオーナーが困ります。オーナーは銀行からお金を借りてるわけで、その銀行の先には日本銀行がある。そう考えると、政府にできることはもっとあるんじゃないかなと、そう思えますよね。
佐藤:ちょっとした想像力で考えられることだと思うんですけどね。後藤さんのおっしゃられたような強固なマインドセットというものは、COVID-19によっても鮮明に浮かび上がってきたように思います。ウイルスは本来、国や人種、貧富の差などといった境界線とは関係ないもので、人類が恣意的に引いた境界線というものは、「概念」に過ぎないということを示しています。ただその一方で、「自分だけは助かりたい」という、内に内に固まっていく、逆に頑なな境界線を保持しようという、反発するエネルギーも出てきているように思うんですよね。大きなものとしては、「国」と「個人」の問題があると思います。国は国で、個人を、国家を維持するためのパーツのように見ている部分があり、個人は(特に政治に関心の薄いところでは)政治とは自分の皮膚の外側のことであって、自分とは関係ないという境界線を引いてしまう。こういった問題に関してはどう思いますか?
後藤:そういう問題意識は僕もありますね。国って何なんだろう?って問いは、ずっと持っています。最近、メソポタミアなどの原初の国というのはどのようにして成り立ったかというようなことに興味があって、『反穀物の人類史――国家誕生のディープヒストリー』という本を読んでいます。やっぱり国家っていうのは、労働力を必要としていたんですよね。奴隷と呼ばれる人々が、昔からずっと取引されてきたっていうのは凄い話であって、国民がいないと国というのは成り立たない。疫病が流行ったり、重税を課したりするとやっぱり人々は逃げていく。そうやって崩壊した国もありました。それから、定住して穀物を食べて生きるというのは、カロリー的に考えると実はあまり良くないとも書かれています。移動して狩猟採集した方が、「飢える確率」が低いらしいです。
佐藤:『サピエンス全史――文明の構造と人類の幸福』にも似たようなことが書かれてましたね。でもそれって、学校とかで習ってきたこととは逆で、むしろこれまでの歴史の教科書なんかには、「農耕と定住により人類は繁栄を手にした」とか、書かれていたわけじゃないですか。
後藤:でもそれは実は国(支配者)がつくったロジックなんじゃないかっていうのが、この本(『反穀物の人類史』)の論旨なんですよね。本当はそうじゃない可能性だってある。何が野蛮なのかっていうことにしても、定住している側の論理でしかありません。だから「国の住民である」ということは、本当は自明のことではないし、たまたま今は国家という体制、考え方があるから、こうなっているだけなんですよね。紛争の続くシリアの人たちのことをどう考えるのかっていうのは、人類的な問いじゃないですか。たまたま生まれた場所が戦乱の場所だったとして、その人たちには「安全な場所に逃げる権利」が無いのかっていうことですよね。そういう人たちに対して、国境でスパッと区切って、「いや、お前たちは入ってくるな」ということを、誰がどういう論理に基づいて言っているのか。それは考えてみると、根源的にはおかしなことなんですよね。
佐藤:難民と呼ばれる人々は、自分で生きる力がないわけではないですからね。社会制度に喘ぐ人であったり、戦乱で故郷を追われる人たちの多くは、「国境というルール」によって能力を奪われている人たちだと思います。「あなたはここから出てはいけませんよ」「こっちに入ってきてはいけませんよ」と。でもこのルールの根拠って、なにか自明なものがあるわけではないんですよね。
後藤:そうなんですよね。だからその辺りの矛盾っていうのも、世界的にみんなで考えていかなければならないはずです。反対に「個」というものに割って考えていくと、例えば子どもは親を選べませんよね。このCOVID-19に際して、「困ったら頼れるのは家族だけ」などと言う人もいますが、家族って選べませんし、家族によって大変な環境に置かれている人もいますよね。そういった、「生まれながらに選べないもの」というのは、なるべく機会を平等にするなり、是正していくべきものだと僕は思います。

故郷シリアの戦禍から逃れ、隣国イラクの難民キャンプで暮らす人々。
多層的なセーフティネットを
佐藤:そういった不平等性のようなものを埋めるために、人類は社会というシステムを築いてきたはずなんですけどね。
後藤:それなのに、社会の仕組みがそうなっていない。それをじゃあ、どうしたらいいのかっていうのはわからないのですが、ずっと不思議に思い続けています。富裕層の子どもだけがいい教育を受けられるとか、そういった不平等性がありますよね。全ての差を完全に克服することはできないのかもしれませんが、でも、そこに対して「改善していこう」という社会の努力が希薄な気がします。「それは不条理だろ」って本当は怒らなければいけないはずなのに、「あの子かわいそうだよね」、というところで止まってしまう。今この状況(COVID-19)にあって、「ステイ・ホーム」という言葉に怒っている人もいると思うんですよね。そもそも家にいれるというだけで、職業的には特別なんじゃないかと。でも実際その通りで、「ステイ・ホーム」っていうのはそういう人たちのことをまったく考えてない言葉なわけですよね。
佐藤:何に驚くかって、そういった言葉や政策が社会に届けられるまでには、何層ものフィルターがあって人がいて、「それはちょっと違うんじゃないか」と言う人がひとりぐらいいると思うんですけど、それがまったく機能しないままスルっと出てきてしまうことなんですよね。
後藤:徹頭徹尾、そういう思考の政権だってことですよね。マスク配布の件でも思いましたが、もう誰も止められない。466億あったら、ほかにできることがあったと思います。やっぱり国政におけるトップダウンという仕組みは上手くいかないんだと思います。地方自治レベルで迅速な対応ができる人もいるわけですから、権力というものはもっと細分化していかないと。中央集権ではなく、地方のことは地方に戻していくということも考える必要があるのでないでしょうか。地方選挙の投票率とか見ると愕然としますけどね(苦笑)。東日本大震災の後もあったことですが、やっぱり国単位で動いて「みんな平等に支援を」とやっていると、大変な時間がかかりますよね。大きな組織にも大切な役割があると思いますが、現場をもっと細かく割っていくことで、素早く動けることもあると思います。僕だってすべての人を助けるなんてできませんが、繋がりの中で物資を送ったり、助け合うことはできる。「セーフティネット」とはよく言ったもので、色々なところに繋がるポイントのある「網」のような社会が必要なのではないでしょうか。正確な網がひとつ、という形ではなく、複雑に重なり合った網がいくつもある社会。
佐藤:どこか一点が切れても全てが崩壊しないという仕組みは大切ですね。
後藤:複雑な繋がり方が必要。もっと地方に権限を戻していくほうが、現場のニーズに細かく対応できるんじゃないでしょうか。そういうニーズって町ごとに違いますからね。電気とかも一緒ですよね。大きいグリッドではなく、スマートグリッドのように割っていったほうが効率的だと言われている。同じように、もう少し細かい単位で社会を考えてみたらどうでしょう。そうじゃないと、地方の議員を中央に送って、どこに利益を引っ張ってくるかという考え方ばかりが強調されてしまいます。国会議員は国のことを考えればいいし、地方のことは地方にきちんと権限を渡す。いいリーダーというのは、「責任をとる」人のことだと思うんですよね。僕も音楽のプロデュースなんかしていて、一番大切だなって思うのは、現場がノビノビと動くこと。自分の命令に従っているときではないんです。それぞれが自分の思うことを好きに行う、でも、その作品が破綻したら僕(プロデューサー)が責任を引き受けるっていうね。もちろん技術と政治は違うから、音楽に例えて話すのは危ういことでもありますが。

『THE FUTURE TIMES』の取材で震災後の東北沿岸をめぐる後藤さん(2015年)。
このまま行ってもゴールは無い
佐藤:それと真逆の働きをするのがトップダウンですよね。上からひとつの命令が下ると、その途中で「こうかもしれない」「ああかもしれない」という意見の入る余地がない。
後藤:現場に裁量を与えて、でもきちんと現場の情報は把握しながら、「何かあったら僕の責任です」っていうのがいいリーダーだと思います。
安田:今の国レベルの政治って、極端なトップダウンと極端な無関心が平行して存在しているように思えるんですよね。マスクを配布するというトップダウンと、休業に関する補償なんかは地方で勝手にやってくれという無関心さ。地方に任せる、というやり方には、地方を切り捨てるという危うさもあるような気がしますがどうでしょうか?
後藤:国と地方の仕組みを変えていくしかないんじゃないでしょうか。「地方が勝手にやってくれ」と言うだけではなく、お金はもちろん交付金として戻すなり、財源を与えたうえで権限を渡すということをやらないと何もできませんよね。例えば河川にしたって国交省の管轄じゃないですか。国は最終的に地方を支えるべきだけれど、地域ごとに必要なものは違うのだから、もう少し柔軟さが必要だと思います。そうしないと市民の参加意識も上がりませんよね。どうせ投票しても政治をやるのは国会だし、オレたちには落ちてこないって思わせてしまう。結局地方に戻ってくるのは公共事業というイメージがありますからね。そういった事業ももちろん大事ですが、もっとそれぞれの地域に必要なことができるんじゃないでしょうか。東北の復興にしても、そういう意識があればもっとうまく進んだかもしれません。国策として行うのではなく、財源を渡したうえで地域ごとに行っていく。本当に難しいことではあるし、不満も出ると思いますが、きちんと住人たちの合意を形成しながら行っていくしかないと思います。
佐藤:トップダウンという仕組みに寄り掛かってしまう要素のひとつに、「面倒なことは任せてしまいたい」という心理もあると思います。「厄介なことは他の誰かが考えてくれよ」という。仕事を終えて家に帰ってきて、ほっと一息つこうと思っているときに、シリアやコンゴ民主共和国の紛争のニュースをみたいなんて思う人は少ないわけです。それが自分の生活を成り立たせるために払われている犠牲だなんてことも考えたくない。もちろん全ての人があらゆることを考えて責任を感じて過ごすなんてことは不可能ですが、その責任はみんなで少しずつ分担しなければいけないものですよね。それぞれが感じる不条理に、その人なりに向き合っていく。その集合で社会は成り立っているんじゃないでしょうか。ところが、それをトップダウンに委ねてしまうと、「それはオレの決めたことじゃないし」という、ある種の無責任さが生まれてしまう気がします。今回のCOVID-19に際して、政府の配るマスクに対して色々な問題が提起されていますが、僕が気になったことのひとつに、「そのマスクを作っている国の人々はどうなんだろうか」ということがありました。その人たちの労働環境というのはどういったものなのだろう。感染対策は行っているのか。日本にマスクを送らなければ、その原材料は地元の人たちが使えたものかもしれない。そういった視点が抜けたまま「国内の問題」というものにだけ注目が集まり、その先の責任というものを考えない。
後藤:そういうことをずっとやってきたわけですよね。労働力を安く買えればいいと。そうすれば企業の利益が上がる。それこそが「社会の価値」だと考えてきたことが間違いなんですよね。それは我々コンサート業界にも突きつけられている問題で、大きなドームでやる音楽が本当に音楽的に幸せなものなのかというのは問われるべきことだと思います。フェスとかも含めて。もちろん美しい瞬間もありますが、それこそが最高のものだっていう価値観はどうなんでしょう。何枚売ったとかっていう「数」が、本当に音楽の美しさと関係あるのでしょうか。今はプラスチックというものが世界的に問題になっているというのに、プラスチックのケースを山ほどつくってますよね。そういったことも全部地続きなんだと思います。資本主義という価値観に、みんなでどっぷり浸かっていたんですよね。そこはやはり変えていかなければいけない。世界中の経済学者や思想家は、それを変えていくのは相当タフなことだとは言ってますが。でもこのまま行ってもゴールは無いし、地球自体がもたないのではないかという問題になってきているわけですよね。難しいけれど、みんなで考え直すしかないと思います。
(後編へ続く)
(インタビュー 佐藤慧,安田菜津紀)
PROFILE
後藤正文。1976年静岡県生まれ。 ASIAN KUNG-FU GENERATIONのボーカル&ギター。新しい時代とこれからの社会を考える新聞『THE FUTURE TIMES』の編集長を務める。インディーズレーベル『only in dreams』主宰。
あわせて読みたい
■ “新型コロナウイルス感染拡大、自殺問題へ及ぼす影響は ―NPO法人ライフリンク代表、清水康之さんインタビュー [2020.4.7/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。