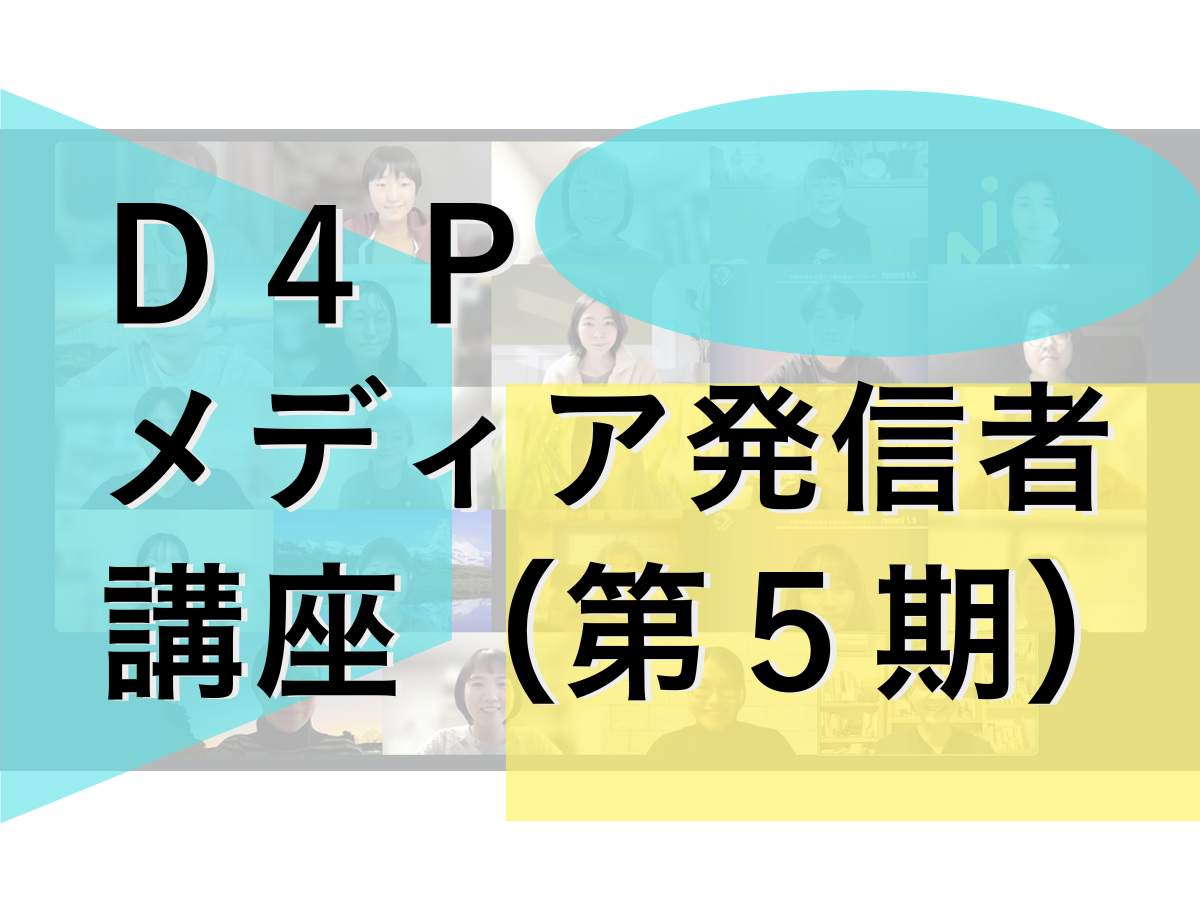ある、お昼時。次の打ち合わせまでのわずかな時間でお昼を済ませようと、私はめったに入らないチェーンの牛丼屋さんに入った。店内は混雑していて、慌ただしい雰囲気だった。辛うじて空いていた小さなテーブル席の並びに滑り込んだ。
二つ向こうのテーブルに、私服の若いお兄さんが席をとった。食券をテーブルに置くとすぐ、トイレに立った。ところが人の往来が激しかったからだろう。いつの間にかその食券がテーブルから舞い落ち、どこにいったのか分からなくなってしまったようだ。テーブルに帰ってきたお兄さんが「すいません、トイレ行ってる間に食券がなくなってたんすけど。注文は●●です」と店員さんに告げる。
店員さんは外国から来た女性のようだった。お兄さんの言ったことが落とし込み切れなかったのかあいまいにうなづくと、またカウンターの向こうへ走っていった。この間、もう一度お兄さんは注文の催促をしたと思う。しばらくすると「返金です」と500円玉を持って同じ店員さんが現れた。「いや、返金じゃなくて。●●注文したんですよ」とお兄さん。一瞬店員さんの顔がゆがむ。またカウンターの奥に走って行ってしばらく、今度は別の店員さん(やはり外国の方のようで、女性だった)が現れ「ドレッシングはフレンチとゴマどっちがよいですか?」と少しなまりのある日本語で話しかけた。「じゃ、フレンチで」と注文してしばらく、お持ち帰り用の袋を抱えて最初の店員さんが現れた。「お待たせしました」と少し息を切らして。「いや、だから、お持ち帰りとかじゃなくて、●●ここで食べるために待ってるんすよ」。抑え気味とはいえ、お兄さんの語気が少し強まった。その店員さんは顔を伏せ、そのまままたカウンターの奥へと走った。
「いや、ひどいね」と私の隣の席のおじさんがお兄さんに話しかける。「彼女今、舌打ちしてましたよ」とお兄さんの奥のサラリーマン風の男性。それまで目さえ合わせなかった客同士が、彼女の失敗を共通話題にして初めて会話が生まれる。その冷笑、嘲笑が悲しかった。
何かしなければ、と思ううちに打ち合わせの時間直前となり、私はその結末も見届けずに席を立っていった。
あの時、どうすればよかったのだろうか。「席が少し離れていた」ことなんて私の言い訳にすぎない。立ち上がって一緒に注文を見て、分かりやすい言葉にくだいて彼女に説明すればよかっただろうか。
お店の店員さんは皆、海外から日本に来た方々だった。ただ見る限り、店員さん同士も国籍が違い、まだ十分に使いこなせない日本語を共通言語にしてコミュニケーションを取らざるを得ない状況だった。
もしも私が彼女だったら、と想像した。
牛丼屋さんはゆっくり食事を楽しむのではなく、さっと食事を済ませたい人たちが多くやってくる。急いでいる人も少なくない。そして私もその、時間に追われた人間の一人だった。
お客さんの心の内の小さな「イライラ」を一身に受けながら、慣れない異国の地で働く。どうしたらよいのか分からないときに頼りたい同僚たちとも、言葉の壁から上手く連携が取れない。私はきっと、パニック状態に陥ってしまうだろう。
「もしも私が彼女だったら」。もちろんすべてを理解することは不可能で、これ自体がおこがましい想像に思えるときもある。でもそれを止めたら、私たちの日常はもっと、粉々に分断されていってしまうかもしれない。
これから外国人労働者の受け入れを拡大する、という法案が通った。だからこの、誰の身にも起こり得るであろう出来事を忘れないために、あの日のことを書き残しておく。想像力が凍りついてしまう、その前に。
(2019.5.30/写真・文 安田菜津紀)

あわせて読みたい
【エッセイ:中東音楽交流事業】長休符の後に ~ 心を震わす交響曲[2019.8.5/安田菜津紀]
【エッセイ】「想定の範囲内」で死ななければならなかった人々のこと[2019.6.27/安田菜津紀]
世界各地での取材活動は皆様のご寄付によって成り立っております。世界の「無関心」を「関心」に変える、伝える活動へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。