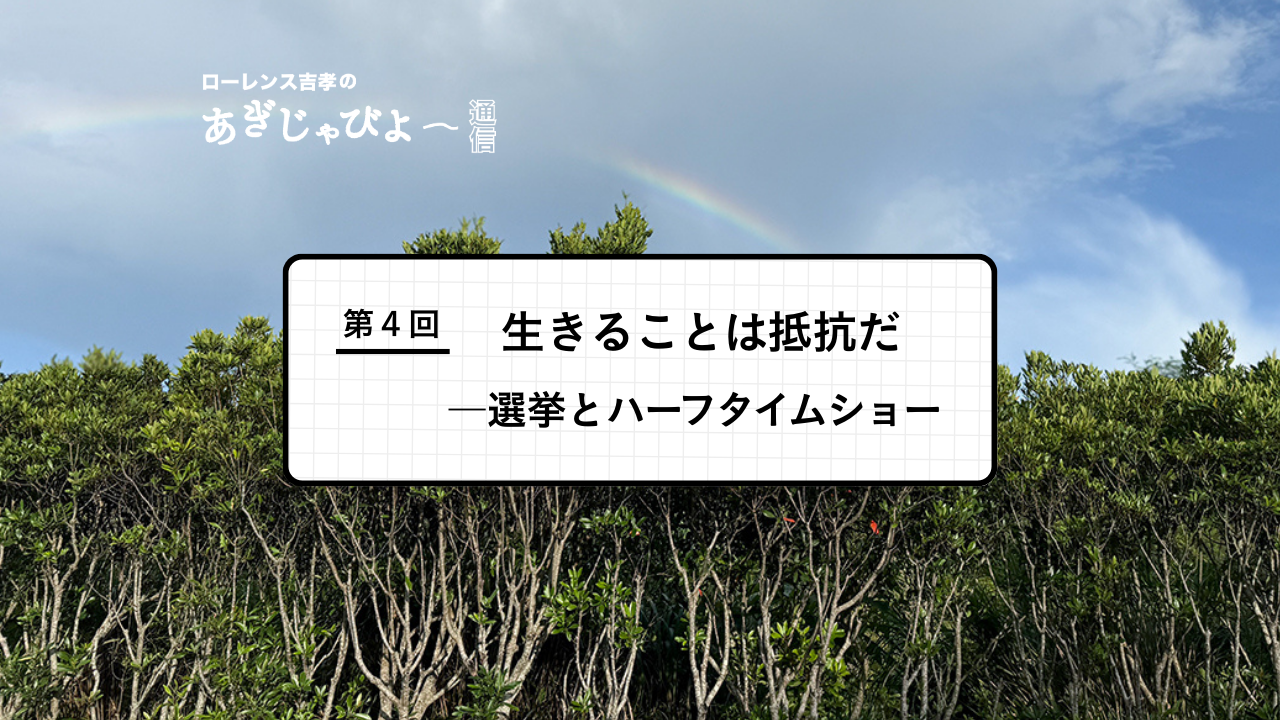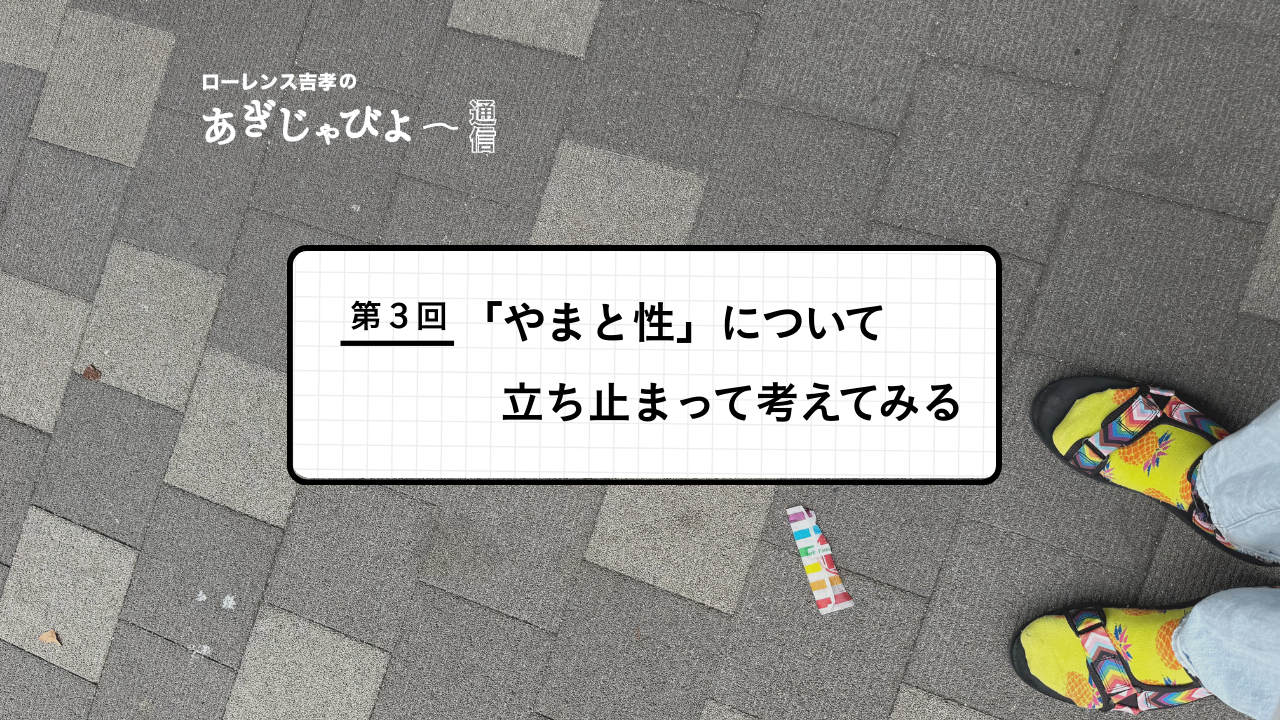アンニョンハセヨ。小説家の深沢潮です。エッセイの連載は初めてなので、ちょっと緊張しています。こちらで書かせていただくにあたり、どんな内容にしようかと悩みましたが、なにしろ食いしん坊なので、食べることにまつわる話がよいのでは、と思いいたりました。そして、記念すべき第一回は、キムチ以外はありえないと、こうしてキーボードを打っています。キムチについてのあれやこれやを書けば、これすなわち在日コリアンである私のルーツや生い立ちに触れることにもなり、自己紹介も兼ねることができると考えました。
さて、タイトルにある李東愛(イー・ドンエ)とは誰? ともどかしく感じていらっしゃるかもしれません。李東愛とは、私が韓国籍を有していたときの本名です。深沢潮はペンネームです。小説家を目指していたときに東京都世田谷区の深沢に住んでいたので、深沢を苗字とし、潮は、大好きな石川啄木の歌集「一握の砂」の「忘れがたき人人」の冒頭の歌「潮かおる北の浜辺の砂山のかの浜薔薇よ今年も咲けるや」から、潮、を取りました。本当は潮かおるとしたかったのですが、ネットの字画占いであまりよい結果ではなかったので、苗字を変えました。すると深沢潮はとても字画がよかったので、以来使っています。
実際、深沢潮のペンネームで初めて応募した作品が新人文学賞を受賞し、プロの作家になることができました。追々、名前の変遷についてのエピソードを書いていきますが、この辺の経緯は父をモデルにした小説「海を抱いて月に眠る」(文春文庫)を読んでくださればわかるかと思います。
ちょっと前置きが長くなりました。なぜ「李東愛が食べるとき」、というタイトルにしたかを説明します。それは、私がこのエッセイを書くにあたって、自分を偽らない、と決めているからです。素の自分にたちもどって書きたいのです。小説という虚構を書くことを生業として十年あまり、話を盛ってしまう傾向があると自分を分析し、それを戒める意味も込めています。
日本で一番売れている漬物がキムチだと知ったのは、つい一昨年のことです。驚くと同時に、本当に時代が変わったのだなと思いました。かつて、私の幼い頃は、キムチはひっそりと身を隠すように存在し、在日コリアンの家庭か焼肉屋でしかお目にかかれなかったのに、いまはどこのスーパーの棚にもでーんと鎮座しています。テレビをつければどこかのチャンネルで韓国ドラマをやっていて(サブスクではいつでもアクセス)、街中でカフェに入るとK-POPアイドルの歌が流れるなんて想像もしていませんでした。いい時代になったと感慨深いものがあります。キムチは古くは朝鮮漬けと呼ばれ、「キムチ臭い」は朝鮮人に対する蔑みの言葉でしかなかったからです。キムチ臭いから家を貸さないと不動産屋から言われたと母も言っていました。これは、「ひとかどの父へ」(朝日文庫)にエピソードがあります。かくいう私も、自分の家の冷蔵庫がつねにキムチ臭いことが、嫌でたまりませんでした。かなり大人になるまで、キムチは苦手でした。
私の記憶が正しければ、キムチを初めて口にしたのは、というより、キムチを食べさせられたのは、たぶん六歳ぐらいのころです。普段はほとんど夕食時におらず、たまにいても一人膳で食べていた父が、その日は横に来て座り、珍しく一緒に食べ始めました。咄嗟に正座になり、身体が強張ったのをいまでも鮮明に覚えています。しばらく黙っていた父は、不意に自分の前にあったキムチを箸でさし、「キムチを子どもたちに食べさせろ」と母に命じました。母は味噌汁で洗ってくれたキムチを白米が入った私の茶碗の上に載せ、私は恐怖で震えんばかりに、それを白米とともに口に詰め込んだのを覚えています。キムチはしょっぱくて、ちっとも美味しくありませんでした。私の隣には後に重い心臓の病で亡くなる姉がおり、その姉も泣きながら洗ったキムチを食べていました。けれども姉はすぐに吐いてしまい、父は母に「ちゃんとお前が韓国人として育てないからだ」と食卓をひっくり返しました。
当時、父と母は、子どもたちに韓国人のアイデンティティを持たせること、韓国の文化風習をきちんと教えることについて意見が対立し、しょっちゅう言い争っていました。父は、十六歳で単身玄界灘を渡ってきて、民主化運動にも与し、韓国人としての誇りが高く、韓国人として堂々と生きることを子どもにも望んでいました。一方、二世の母は戦後わずかのあいだ民族学校に通ったもののその後転校した日本の学校で自分がかなりの差別をうけた経験と、父親(私の祖父)が関東大震災で自警団に殺されかけたことがあったので、身体の弱い姉を守るため、いじめられないために、韓国人であることを周囲に極力隠そうとしたのです。(こちらも「海を抱いて月に眠る」に近いエピソードがあります)
外に対しては韓国人であることを隠していた母も、家では父のためにキムチを漬けていましたし、父には韓国式の食事を作っていました。魚を煮るときは、こどもには甘い味、父にはコチジャンたっぷりという感じで味付けを変えていました。韓国料理を好む父と子どもたちは別のメニューにするなど何種類もおかずを用意した母は相当大変だったはずです。大きな青いたらいに白菜を大量に入れ、風呂場から低い椅子を持ってきて座り、白菜をひとつずつ手にし、葉に塩をすり込んでいる光景はいまでもときどき私の脳裏によみがえります。韓国の唐辛子じゃないとだめだと言って、東上野の朝鮮乾物屋に買い出しに行っていました。荷物が重いからつきあってと言われてついていき、褒美として帰りに精養軒に寄ってビーフシチューを食べたこともありました。
韓国に帰ることが出来なかった父が自分の両親を日本に呼んで一ヶ月ほどともに暮らしたことがあったのですが、そのときも母は毎日手作りの韓国料理を作っていました。在日二世であるがゆえに認めてもらいたくて頑張ったとのちに話していました。もちろん、キムチも出していました。母のキムチは母曰く「工夫」してニンニクを控え目に、林檎や梨がたくさん入っていて、「サラダみたいに食べられて臭くない」というものでした。「お義父さんとお義母さんにも好評だった」ことが母は自慢でした。
母は、ニンニク臭くなることも過剰に気を付けていました。ニンニク臭いと韓国人だとばれるという恐怖が抜けなかったのです。現在八十五歳の母は、八十歳ぐらいからキムチを外で買うようになりました。「日本人もキムチを食べるのよ、だから安心して買える」と言うときの笑顔がなんとも嬉しそうです。「ヨンさまのおかげかしら」と付け加えることも忘れません。暴君のようだった父もだいぶ丸くなり、家でキムチを漬けなくても怒らなくなって、母もずいぶん楽になりました。私が高校生のときに生まれて初めて家族で行った韓国以外の海外旅行先のグアムにまで、父のために母手製のキムチをスーツケースに入れて持って行ったことを思うと隔世の感があります。(それが漏れて悲惨なことになりました……)
私が祖国である韓国に初めて行ったのは、小学校六年生のときで、祖母の葬式に参列するためでした。朴正煕が暗殺される直前でした。韓国の空港では荷物検査に一時間以上かかり、あげく別室に連れて行かれたことが強く印象に残っています。空港から舗装の悪い道路を走り、父の故郷、慶尚南道(現在の)サチョン市に着きました。韓国ドラマ「応答せよ1994」に三千浦出身の青年がとんでもない田舎者として描かれていますが、韓国では、話があちこちに飛ぶことを話が三千浦に行った、というくらい、僻地として認識されているようです。たしかに三千浦は本当にのどかな海辺の町でした。海辺といっても、港があるわけでもなく、商店もぽつりぽつりとあるくらいで、ほとんどが細々とした畑と赤茶色の土の低い丘でした。コンクリートの駐車場が遊び場だったような品川区に住んでいた私には、なじみのない風景でした。
慣れない土地で居心地の悪さを感じていたところ、日本からだれか来たらしいと、町の人たちが父の実家の周りに集まって我々家族を見に来ました。父は9人きょうだいなので、親族も多く、いとこやおじおばが大集合して、私たちの一挙手一投足を見つめます。私と八歳下の妹は(姉はすでに死亡)、まるで上野動物園のパンダになった気分です。食事どきはさらに拷問のようでした。そして、「東愛はキムチを食べられるか」というのが彼らの大きな関心事だったようです。キムチを決して食べない私は「やっぱり日本人なんだね」と言われました。数年前に「海を抱いて月に眠る」の取材で三千浦の父の実家を再訪したときに、私がキムチをバクバク食べているのを見て、いとこやおじおばはとても驚いていました。私はと言えば、三千浦にスターバックスがあったことにびっくりしました。
私がキムチを食べられるようになったのは、結婚してからです。「縁を結うひと」(新潮文庫)でモデルとなっているお見合いおばさんの紹介で在日同胞と夫婦になった私は(のちに離婚しますが)、祭祀や秋夕、その他親族の集まりで、嫁ぎ先の家族と食卓をともにし、韓国家庭料理を作るのを夫の実家で手伝うようになりました。しかし、夫はキムチや韓国料理を特に欲するわけではなかったので、ふだんは洋食、中華、和食などのつたない料理をせっせと作っていました。そんなある日、焼肉屋に夫の家族と行ったとき、義理の兄嫁が肉をサンチュに巻いてその上にキムチを載せて食べるのを見て、ほほうそういう食べ方もあるのかと興味をひかれ、ちょっとだけ白菜キムチをちぎってカルビの上に載せ、サンチュに包んで食べてみました。口に入れて噛むと、キムチの辛みと酸味がカルビの甘みと脂に溶け合っている。それがサンチュの爽やかな風味とあいまって、極上の調和を作り出していました。なんでいままでこんなに美味しいものを食べなかったのか、と私は続けてこんどは白菜キムチでどーんと肉を覆いサンチュで挟んで食べました。その日はいつもの倍くらい肉を食べたのではないでしょうか。それ以来、キムチは私の大好物となりました。味だけでなく、同胞と結婚したことで韓国人である自分をやっと認められたことが、積極的にキムチを食べることにつながったのだと思います。私が結婚したのは1994年の春なので、そのころはまだ冬ソナブームもなく、韓流という言葉もありませんでした。キムチを置いているスーパーもそれほど多くなかったように思います。ですから、結婚してからできた在日コリアンの友人が分けてくれるキムチや実家の母の作るキムチがことのほか貴いものでした。最近は埼玉の朝鮮学校のオモニが作るキムチを取り寄せるのが楽しみとなっています。
いまやキムチは世界的に人気の食べ物です。ニューヨークのホールフーズに大きな瓶詰のキムチが売られ、キムチーという名のドラァグクイーンだっています。世界のあちこちでキムチを手にすることができ、中国と韓国でどちらがオリジナルかというキムチ戦争が勃発していたりもします。小説の資料として読んだなにかの本に、唐辛子は日本から朝鮮にわたったもので、もともとキムチは辛くなかったとありました。一口にキムチと言っても、ソウルのキムチと釜山のキムチは味が全く違うし、それぞれの家庭で味付けも少しずつ異なります。水キムチもあるし、種類も豊富で、そのままだったり調理したり、食べ方もいろいろです。実に多様で、そう言った意味ではとても現代的です。
在日コリアンにとってのキムチも、人それぞれです。私にとっては、愛憎渦巻く食べ物であると同時に、それは自分の韓国への想いと深くつながっているものでもあります。私の韓国への想いは、小説を通して描いてきましたが、今後、少しずつここにも書いていくつもりです。
最後に、私が気に入っているキムチの食べ方をひとつご紹介します。
白菜キムチでキリチーズ(クリームチーズ)をはさむ。ぜいたくにミルフィーユ状に重ねてもいい。これは、川崎のハルモニたちのお手製キムチをいただいた折につくってみました。ちょうど長編の原稿を書きあげたときで、ひとり打ち上げをしたときに食べました。スパークリングワインにぴったりでした。もちろんビールにもあいます。30秒くらい電子レンジでチンしたらおかずにもいいです。白米にのせたら最高です。
このエッセイを書き終えたら、つくろうかな。たしかビールがあったはず。キリチーズは常備しているし、キムチもまだ残っている。
冷蔵庫を開けて、キムチの、あの匂いがすると、ちょっと嬉しい。

深沢さんオススメの食べ方は「キリキムチ」。(写真は深沢さん提供)
本連載の掲載終了について
本連載をもとにした書籍『はざまのわたし』の発売(2025年1月24日)に伴い、第1話以降の掲載を2025年1月24日に取り下げました。
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。