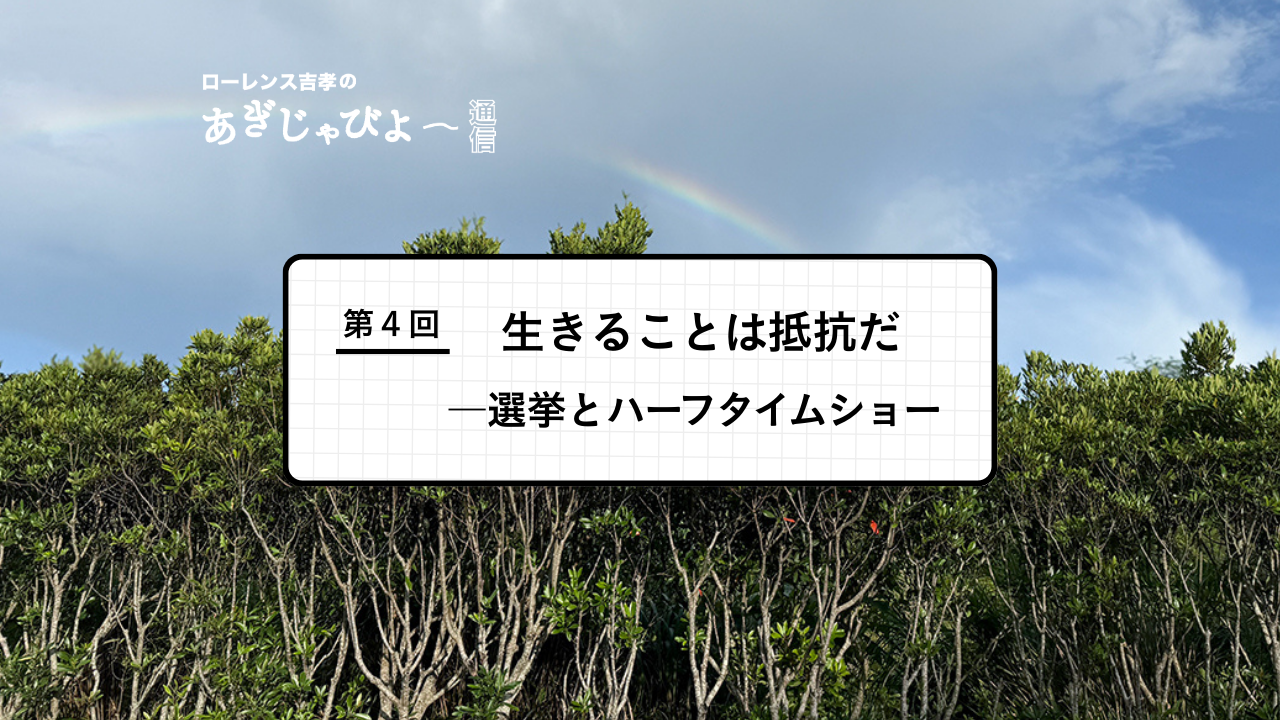【エッセイ】「嘘」をついているのは誰なのか―ウィシュマさんのビデオ5時間分を見て、飲酒診療の放置に思うこと
「あー!」
ウィシュマ・サンダマリさんが痛みに声を上げると、看護師と職員どちらかから、なぜか笑い声があがる。彼女たちは会話を続ける。
「(外部病院の医師が)かっこいい」
「(別の医師は)ピチピチのギャル系」
2021年3月5日、ウィシュマさんが亡くなる前日のことだった。
人間性を否定する組織体制
2017年6月、ウィシュマさんは「日本の子どもたちに英語を教えたい」と、英語教師を夢見てスリランカから来日したものの、その後、学校に通えなくなり在留資格を失ってしまった。2020年8月に名古屋入管の施設に収容されたが、同居していたパートナーからのDVと、その男性から収容施設に届いた手紙に、《帰国したら罰を与える》など身の危険を感じるような脅しがあったことで、帰国ができないと訴えていた。
真相解明にとって欠かせない「証拠」のひとつが、ウィシュマさんが最後に過ごしていた居室を映した監視カメラ映像295時間分だ。国側から裁判所に提出されているのはわずか5時間ほどにすぎない。私はその映像を今年2月、閲覧した。
映像の続きを語ろう。2021年3月6日、14時過ぎ。職員が入室しても、ウィシュマさんはもう、微動だにしなかった。ウィシュマさんの胸に耳をあてたり、肩をゆする居室内の職員からは徐々に焦りが伝わってくるが、なお、救急車は呼ばない。
やがて、男性職員なども加わり、皆で名前を呼んだり、腕を引っ張ったりと、体の反応を試す。やはり誰も、「救急車を」とは言わない。職員のひとりがつぶやく。
「いつもだったら、これで痛いって言うんですけど……」
私は当時の名古屋入管幹部はもちろん、現場で対応にあたった職員たちにも責任はあると思っている。ただ、彼らだけの責任と矮小化することもできない。
彼らはきっと、一歩収容施設の外に出て、道端で人が倒れていれば、すぐさま救急車を呼ぶのではないか。この「外界の常識」が、入管施設内に踏み込んだ途端、彼らから削げ落とされてしまうのはなぜか。誰かを非人間的に扱う組織は、結局、そこで働く人々の人間性さえ否定するからではないのか。
命を救うのは「人間の判断」
ウィシュマさんの死亡事件の本質は、「脆弱な医療体制」という表面的な問題ではない。
『最終報告書』には、ウィシュマさんの仮放免を不許可にした理由が《一度、仮放免を不許可にして立場を理解させ、強く帰国を説得する必要あり》と記されている。苦痛を伴う環境下での収容を、日本に留まることを諦めさせるための「手段」として用いていたことが堂々と書かれているのだ。当たり前のことだが、収容は「拷問の道具」として、入管が恣意的に使うべきものではない。
ところが入管側はあくまでも、事件の背景を「医療体制の不備」という文脈に回収することに固執してきた。そして、2022年2月に公表された「入管収容施設における医療体制の強化に関する提言」には、驚くべきことが書かれている。
提言内の「入管収容施設で働くことの魅力の発信」という項目には、「意図的・作為的な訴えや心因性の訴えを含め、様々な訴えに対応する総合的な診療経験を積む機会」が“魅力”として記されている。つまり、“被収容者は「嘘」をつくこともあるから、それを含めて対応することもまたいい経験だ”と、被収容者を道具のように位置付けることをはばからない内容になっているのだ。
「最終報告書」には、複数の職員が、ウィシュマさんの体調不良を、「仮放免許可に向けたアピール」と認識していたことも記されており、日頃から“外国人は嘘をつくはず”といった差別的な目線で被収容者を見ていたことをうかがわせる。
「提言」には他にも、「医療用機器の整備」も盛り込まれているが、命を救うのは器具そのものではなく、それを駆使する人間の判断だ。救急車を呼ぶことさえできなかった施設にいくら機材を搬入したところで、どこまで意味をなすのだろうか。
“知らぬ存ぜぬ”を決め込む法務大臣
そして今回発覚した大阪入管の医師の問題だ。飲酒しながら診療にあたっていた医師がいるという疑いが齋藤健法務大臣のもとに届いたのは今年2月下旬だという。そして翌月の3月7日、入管法政府案が閣議決定されている。
入管はこの法案の前提として、「大阪入管に常勤医師1人を確保」したことを含め、「医療体制の改善」を前面に打ち出してきた。齋藤法務大臣も「改革の効果が着実に表れてきている」と審議中、はっきりと答弁している。
入管の資料や大臣の答弁だけを追っていれば、「1月に当該医師からアルコールが検出され医療業務から外されていた」ことも、「2月にはそれを大臣が把握していたにもかかわらず、今回報道で発覚するまで“知らぬ存ぜぬ”を決め込んでいた」ことも、「今に至るまでその医師が在職状態にあること」も、誰も予想だにできないだろう。
「自分たちは嘘をついても許される、責任も取る必要などない、だが外国人、お前たちは許されない」――そう言わんばかりの大臣が指揮をとり、今、入管の権限をさらに強め、難民に「死刑のボタン」を押す法案が通されようとしている。こんな不条理があるだろうか。
「嘘」をついているのは誰か。まともな民主国家なら、最低でも辞任に値するだろう。
「難民を見つけたくてもほとんど見つけることができない、認定されていない人々は“嘘”をついているだけ」――そんな言い分が、法制化を通して肯定されようとしている。
杜撰な難民審査の問題が発覚していながら、「保護すべき者を保護している」と強弁することこそ虚構ではないだろうか。
国会の審議に「人間の話」を取り戻すために
このエッセイを、「私」という主語にしたのには理由がある。ウィシュマさんの映像開示を求める会見でマイクを握った大学生が、こんなことを語ってくれた。
「私は2種類の怒りを感じています。ひとつは、ウィシュマさんやたくさんの人々を差別して殺した、日本政府、入管に対してのものです。もうひとつは、この問題について無関心でいることができる、できていた、自分自身に対してのものです」
この言葉はぐさりと刺さった。入管の実態を許してきてしまったのは、杜撰な難民審査を見過ごしてきたのは、これまで内部で何が起きているのか、関心を払ってこなかった私自身にも責任があるのだ。
2021年5月に、入管法の前法案が廃案となったとき、市民の声に力があることを実感しつつ、もどかしさも残った。多くの報道がなされたのは、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなり、遺族が矢面に立ち、声をあげ続けてきたことが大きい。
「人が死ななければ変わらない社会」を脱しなければならなかった。
けれども昨年11月、イタリア国籍のルカさんが東京入管で亡くなった。2007年以降だけでも、入管で亡くなるのは18人目となる。
「姉が好きだった食べ物、好きだった服、その“小さなこと”すべてが、姉の命なんです」
ウィシュマさんの妹、ワヨミさんの言葉だ。
この法案を押し通す側にすれば、ウィシュマさんもルカさんも、「送還忌避者のひとり」という「数」に過ぎないのかもしれない。けれどもそこには、血の通った人生があったのだ。だからこそ国会の審議にも、「人間の話」を取り戻さなければならない。
2021年の法案提出前に、入管や外国人の人権問題に取り組んできた弁護士が、ぽつりとこう語ったことがある。
「日ごろから脆弱な立場にあるような外国人は、(こういう法案で)殴っても反論できないと思っているんでしょう」
勝手に殴らせてたまるか――。今、心の底からそう思う。責任あるひとりとして、私は今日も言葉を紡ぐ。彼らが振り向くまで、彼らが向き合うまで、そして、社会の仕組みが血の通ったものに変わるまで。

ウィシュマさんが通っていた寺院に咲く花。
(2023.6.4 / 安田菜津紀)
あわせて読みたい・聴きたい
■ 「赤く見えているリンゴが、この人には青く見えている」――参与員経験者が見た審査の現実[2023.6.3/安田菜津紀、佐藤慧]
■ 不可解な「訂正」、立法事実はどこへ? 柳瀬参与員の「1年半で対面500件」難民審査、法務大臣発言は「可能」から「不可能」に[2023.5.31/安田菜津紀、佐藤慧]
■ 難民審査参与員は「難民認定手続きの専門家」ではない――「12分の審査」の闇[2023.5.25/安田菜津紀、佐藤慧]
■ 入管法政府案「立法事実」への疑問 同一難民審査参与員が2年間で2000件審査[2023.4.23/安田菜津紀]
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。