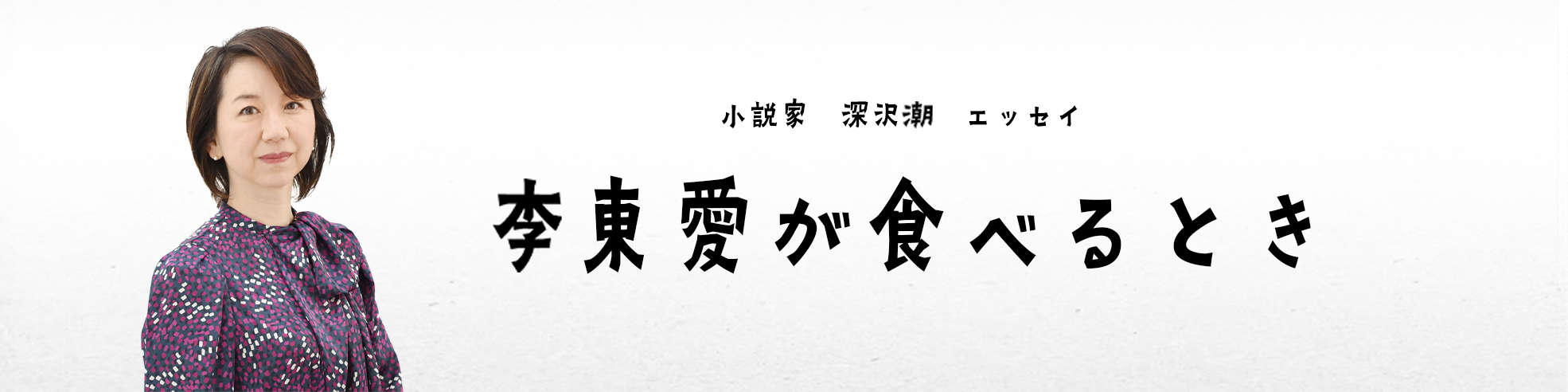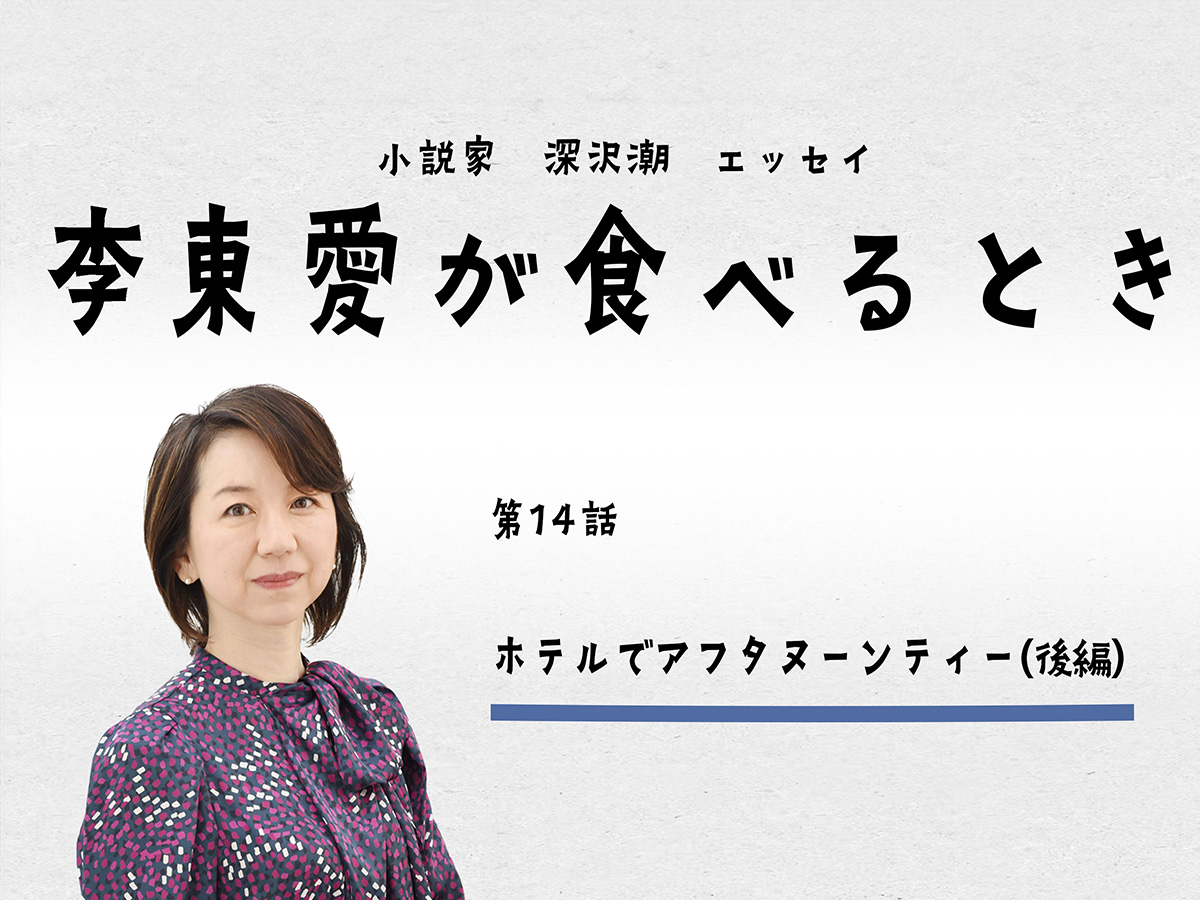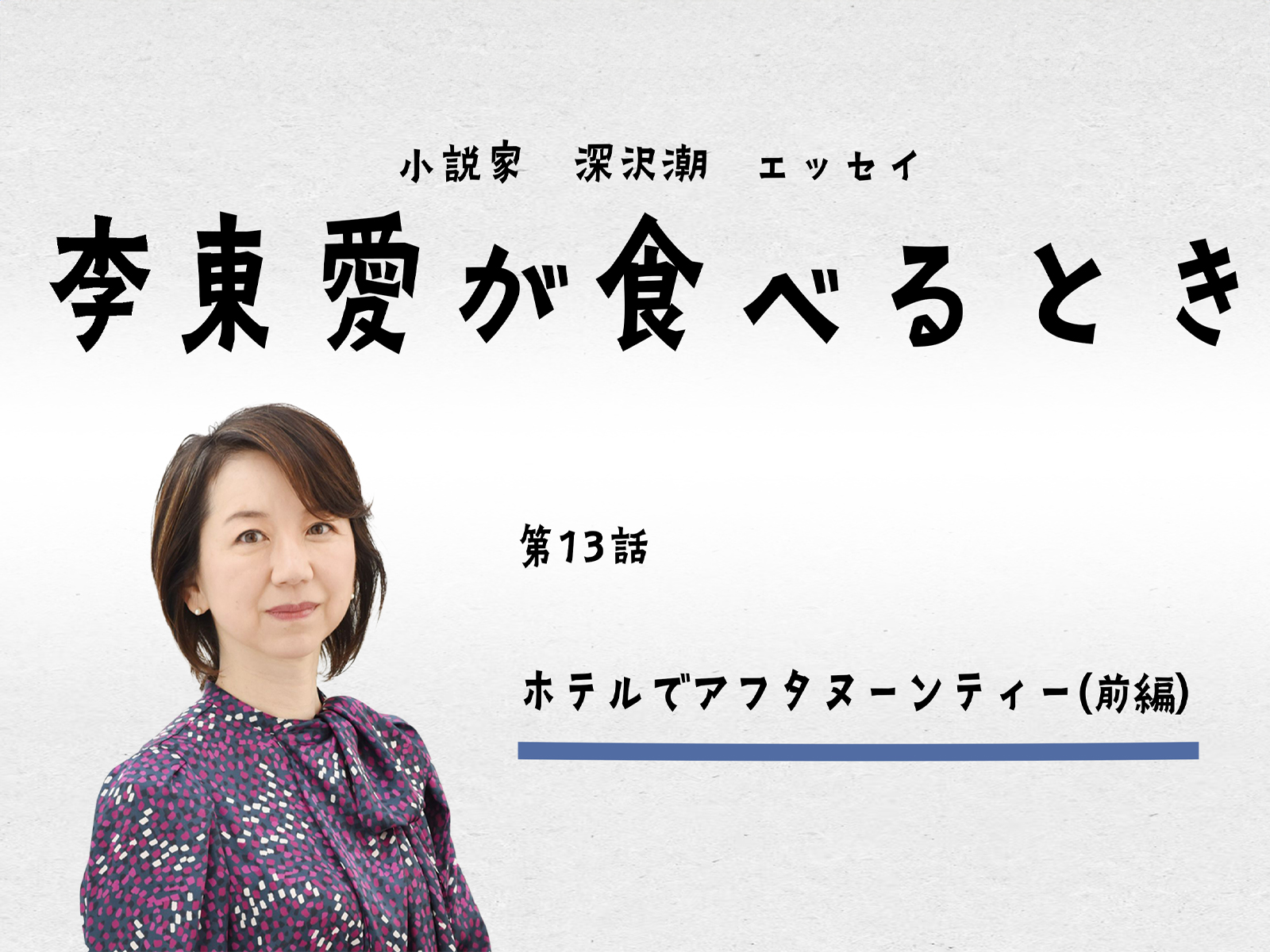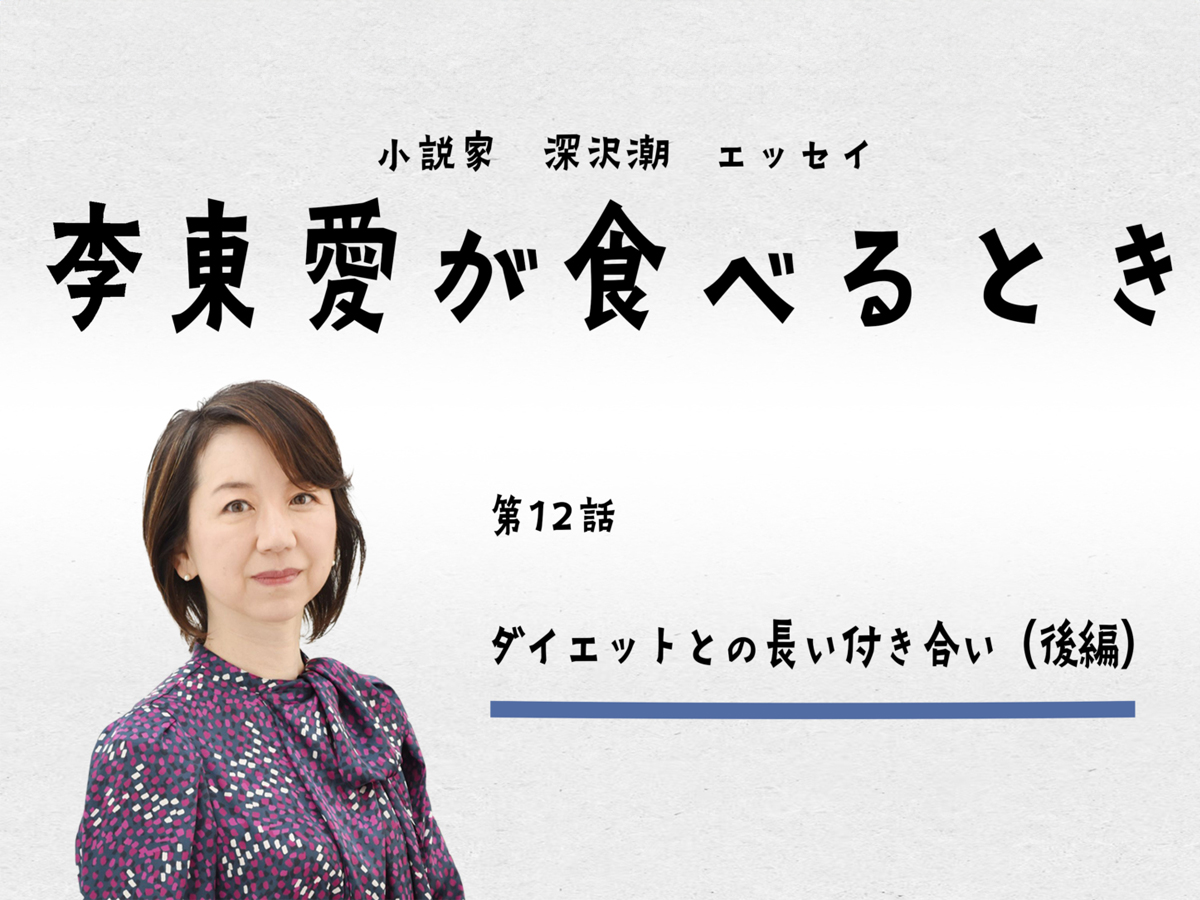第6話 嗚呼、フライドチキン
フライドチキンといえば、とにかく、ケンタッキーだった。あの、赤い縞模様のパッケージやカーネルサンダースおじさんの顔は、子ども時代の私に強烈なインパクトを与えた。家で作る唐揚げとは異なる、複雑な味付け、骨付き肉のジューシーな口当たりは、特別なものだった。
小学生のあいだは、品川区旗の台に住んでいて、駅のすぐ近くにケンタッキーフライドチキンの店舗があった。出店したのがいつ頃かは覚えていないが、低学年、中学年ぐらいまでは、それほどしょっちゅう食べることはなかった。
ところが、例外があった。必ずケンタッキーフライドチキンを土産に我が家に来訪するおばさんがいたのだ。私は、おばさんが来ると、ケンタッキーフライドチキンが食べられるのが嬉しかった。そして、厳しくてかたい母と違い、朗らかなおばさんが家に来ると、場の雰囲気が明るくなった。私はそんなおばさんが大好きだった。おばさんは、父と同郷の友人、文さんのお連れ合いで、旗の台の二つ隣の駅、大岡山に住んでいた。在日同胞という仲間意識に加えて、父と文さんも元来親しく、住まいも近かったことから、家族ぐるみで文さん一家と我が家は付き合っていた。
文さんのところには、歳がかなり上のお兄さん、私の姉と同じ三歳上のお姉さんと二つ上のお兄さんがいて、私は歳の近いお兄さんとダイナミックな遊びができるのがとくに楽しかった。
身体の弱い姉が少しでも健康になるようにと、我が家は毎年のように伊豆へ海水浴に行っており、文さんの家族とも一緒に行った。姉は泳ぐことはしないものの、ビーチパラソルの下で同い年のお姉さんと一緒に寝転んで嬉しそうだった。私はお兄さんと砂浜で転げまわったり、砂の中に埋め合ったり、ヒーローもののごっこ遊びなどをしたりした。海に入って浮き輪で浮かんでいたら波にあおられひっくり返り塩辛い海水を飲んでしまったこともいい思い出だ。
私はふだん家で静かにしなければならなかった反動で、文さん一家といるときは、思いっきり騒いでいた。互いの家を行き来もし、多摩川に遊びにも行き、花見も一緒にした。おばさんが、実家のある川崎の桜本まで私を連れて行ってくれたこともあった。おばさんの親族も明るい人たちで、見知らぬ子どもの私に果物やお菓子をたくさん出してくれた。そのときのことが忘れられなくて、私は「ひとかどの父へ」という小説の中で、川崎の桜本に住む一家を描いた。
けれども、姉が亡くなってからは、家族ぐるみの交流はほとんどなくなってしまった。文さんの家の子どもたちは、みな朝鮮学校に通っていて、ある日、目黒の駅でチマチョゴリ姿のお姉さんをみかけたことがあった。その時中学生だった私は、進学した女子校の校風にも馴染めずもんもんとし、アイデンティティに悩み、学校で必死に韓国人であることを隠していることが負担でもあった。だから私はお姉さんのチマチョゴリの制服姿が神々しく見えた。堂々と生きていることが羨ましくもあった。自分がそうできないこともわかっていたから、気持ちが引き裂かれた。セーラー服に身を包み、複雑な思いを抱えていた私は、お姉さんに話しかけることができなかった。
実は、今年(2023年)の4月に、お姉さんと再会することができた。それまで連絡先がわからなかったが、共通の知人から、韓国ソウルに在住と知らされ、渡韓の際に会いに行ったのだった。お姉さんは昔と変わらず美しく、そして優しかった。お姉さんは私に会うのが姉の葬式以来だと言っていた。互いに感極まってしまう瞬間もあったが、お姉さんとそのお連れ合いと会えて、私はとてもかけがえのない時間を過ごした。ソウル市内の平壌式冷麺の店でプルコギと冷麺をいただき、思い出話やこれまでの互いの来し方、家族の近況などを話した。
お姉さんは、目黒のルノアールという喫茶店で、父親同士がそれぞれ新聞を読みながら向かい合い、煙草を吸っている姿を見かけたことがあるそうだ。まったく会話はないのに、ふたりの仲の良さがガラス越しに伝わってきたという。私の父は91歳で健在だが、お姉さんの父親である文さんは亡くなっている。父は私に会うたびに、友達がみな死んでしまって寂しいと嘆くのだが、きっと文さんのことも思い浮かべているに違いない。
さらにお姉さんは、「東愛ちゃんはいつも動いている印象があった」と言った。確かに私には、落ち着きがない、じっとしているのが苦手、よくこぼす、やたらに転ぶ、ものにぶつかるといった特徴があった。家庭での抑圧が強いうえにつねにエネルギーを持て余していて、きっかけがあるとはじけてしまっていたのかもしれない。お姉さんやお兄さんといるときは、フルスロットルだったのだろう
元気すぎる私が勢いあまってなにか粗相をすると、母はかなりきつく叱った。そして、おとなしい姉と比べてうんざりしているのを子ども心に敏感に察知していた。そんな私がこともあろうに、母の意向で、お嬢さん学校といわれる私立のカトリックの中高一貫女子校に入学したのだから、そりゃあ息苦しいのも当然だ。「良き母」がモットーの学校に馴染むわけもない。母としては、おしとやかになってもらわなければならないとの強い思いだったに違いないが、あまりにもミスマッチすぎた。それなのに、私は私で、母の望む娘にならなければ、母に好かれたい、と一生懸命だったのだ。お嬢さん学校にふさわしい生徒にならなければならないと自分を押し殺す日々だった。
少し時をさかのぼる。
姉が亡くなった翌年、小学4年生になったときから、中学受験の準備のため、私は学習塾に通わされた。姉へ注いでいた母の愛情と労力、ケアの対象は幼い妹へと変わり、私に対しては、「勉強をさせる」「いい学校に入れる」という形の愛情が用意された。
最初は家から徒歩圏内の個人塾に週に2回と、日曜日に四谷大塚進学教室に通っていたのだが、5年生になると本格的な中学受験の進学塾に移り、週3回と日曜日の四谷大塚、6年生には週5回と日曜日の四谷大塚、つまりほぼ毎日通塾するようになった。そこは寺子屋式のスパルタ学習塾で、板張りの部屋に成績順に正座して3時間授業を受けるというスタイルだった。成績下位のものたちの席はくみとり式トイレの近くでものすごく臭かった。行きは電車で、帰りは運転免許を取った母が車で迎えに来た。帰るころには足の感覚がなくなっていた。
正直言って、中学受験の勉強は、大嫌いだった。友達と遊びたかった。学校では6年生の頃、放課後に缶蹴りがはやっていたが、塾に行く私は、放課後居残りや公園での遊びができずにその仲間に入れなかった。当時私の通っていた公立小学校では、中学受験をする生徒は少なく、ほとんどが放課後の遊びに加わっていたので、非常に疎外感をもった。そして、その思いは、「みんなが行く公立の中学校に行きたい」という考えになり、ますます受験勉強が嫌になった。一度だけ、塾をさぼってみたりしたが、見つかってこっぴどく叱られ、父に殴られた。その後も泣いて中学受験が嫌だと喚いてみたが、無視されて放置されたので、中学受験は避けられないと悟り、諦めて勉強することにした。
そもそも性格に難のあった私は友達も多くはなかったが、姉の死後は、「いい子」にならなければと必死だった。そして努力は少しずつ実を結び、6年生になると、担任の先生から「東愛ちゃんはいい子になるために頑張っているから先生も応援している」とみんなの前で言われるまでになった。仲の良い友達もでき始めていた。この先生と母は妙に親しくて、母は先生になんでも言っていたきらいがある。今では考えられないことだが、母がお中元やお歳暮を贈ると、みんなの前でお返しをくれるようなこともあった。のちに校長先生になったらしいが、私は母と違って卒業する最後まで担任の先生が苦手だった。
さて、フライドチキン。
暗黒の中学受験準備時代の楽しみ、いや、救いは、夜中のココアと、夕方のケンタッキーフライドチキンだった。
学校から帰って、塾に行く前に、ケンタッキーフライドチキンを食べる。本格的な夕ご飯は塾から帰ったのちに食べるので、間食というかおやつみたいなものであるが、それにしてはボリュームがある。さすがに毎日ケンタッキーフライドチキンというわけではなく、中村屋の肉まんや、おにぎり、サンドイッチなどのこともあったが、私はだんぜんケンタッキーフライドチキンを望んだ。いろいろと制限ばかり強いる母だったが、チキンはできるだけ用意してくれた。6年生の頃は、週に2~3回は食べていたのではないだろうか。勉強させるため、塾に通わせるための餌だったのだろう。まんまとその策略にはまり、2ピースのチキンとコールスロー、ロールパン(当時はビスケットではなかった)のセットをお腹に収めて、いざ、闘いに出向く日々だった。成績は徐々にあがり、体重もそれにともなって増えていった。脂っこいものばかり食べるからか、ニキビも花盛りだった。
塾にせっせと通い、帰宅後は毎日深夜2時くらいまで勉強し、朝6時に起きて漢字や計算ドリルをやった。四当五落(四時間睡眠は合格、五時間睡眠は落ちる)と言われていたのを信じて睡眠時間を削って勉強した。そのなかで、どうにも辛い思い出がある。朝、父がわざわざ起きてきて監視してきたことだ。私を勉強させるという一点においては、両親が意気投合していたように思う。私が眠気のあまりうつらうつらとすると、父が怒り狂って「たるんでいる。わしが起きているのになんだっ」と頬をたたいた。(父は岡山にいた影響で、わし、という一人称をつかう)目が覚めたのはもちろんだったが、なぜこんな仕打ちを受けなければいけないのか、寝ていてくれたらいいのにと理不尽でたまらなかった。また、頼んでもいないのに、父はテレビを押し入れにしまい、「受験だから、お前にテレビを見せないためにテレビをわしも我慢する」と宣言したが、私は、我慢しなくていいから優しくしてほしい、と心の内で思っていた。父も母も、本当に厳しく勉強を強いてきた。とはいえ、両親の厳しさがあったからこそ無事に合格できたというのも事実だろう。第一志望の学校は落ちたが、母の希望するお嬢さん学校には行けたので、親孝行にはなったのではないだろうか。そこは、母が通いたかった学校だった。
私の人生の中で、中学受験の準備時代ほど勉強した時期はない。いま思えば、いい経験だったし、嫌なことを我慢してやる、という耐性は獲得できた。それに、そのときの基礎や勉強に集中する訓練があったおかげで、大学受験も乗り越えられたように思う。国語力もついたし、文章力も鍛えられた。だからいま、ものを書く仕事ができているのかもしれないと思うことにしよう。
6年生の2月に志望校に合格し、穏やかな日々を過ごしていた。そのころには、親友と呼べる友人もできて、私は幸せだった。だが、父方の祖母が亡くなって、急遽、韓国の父の故郷へ学校を休んで行くことになった。
生まれて初めて飛行機に乗り、釜山の空港につき、そこから車で2時間あまり走り、父の故郷、慶尚南道の三千浦に着いた。亡くなった祖母は日本に来て我が家に一ヶ月ほど滞在したことがあったが、そのとき会ったきりだったので、悲しい、という感情はなかった。あまりにも感情露わに大声で泣く人々が芝居じみて見えた。親族はみな白い韓服を着ており、母もそろいの服で涙に濡れていた。父も顔をゆがめて嗚咽していた。私はただ、なんの感情も湧かずにそれを眺めていた。虚無、と言っていいほどだった。
葬儀が終わってもしばらく父の実家に滞在した。祖父がそのとき、街に一軒しかないおもちゃ店に私を連れて行ってくれて、兎のぬいぐるみを買ってくれた。祖父が孫におもちゃを買ったのは初めてで驚いた、めったに会えない孫には特別な思いがあるのだろうと後にコモ(父の妹)が言っていた。
2月の韓国はとても寒かったが、親族のもてなしは、熱かった。毎日のように、9人いる父のきょうだいのだれかの家に呼ばれて食事をごちそうになった。海辺の街なので、食卓を飾るのはおもに魚料理だった。そのころは魚よりも肉が好きだった私は、出された料理をほとんど食べられなかった。もちろん、キムチを含む辛いものも受け付けない。仕方なく、白米や果物で空腹を満たしていた。すると、料亭を営んでいるコモ(父の姉)が、「東愛の好きな料理を作ってあげるから、言いなさい」と言ってくれた。コモは日本の占領下で女学校に通っていたので、日本語が上手で、私にもしきりに話しかけてきてくれた。柔らかい笑顔で訊かれたので、私は、遠慮なく「ケンタッキー」と答えた。しかし、よくわからないようで、首をかしげている。私の傍らにいた母が、「フライドチキン、鶏の唐揚げです」と補うと、コモは破顔して「まかせなさい」と言った。
翌日、私たちはコモの料亭に呼ばれた。私は、フライドチキンにありつけるのかとわくわくしていた。だが、いざ席について目の前に出されたのは、大量のエビフライだった。「鶏が手に入らなかったからね」とコモがにっこりとほほ笑んでいた。
がっかりしたのもつかの間、私はケチャップをたっぷりとつけて、エビフライを次から次へと口に放り込んだ。コモの気持ちも嬉しかったし、エビフライはすごくおいしかった。
私の好きな韓国映画に「おばあちゃんの家」というのがある。ソウル育ちの男の子が田舎のおばあちゃんの家に預けられるというあらすじだ。男の子が、フライドチキンが食べたいとせがんでおばあちゃんが作ったのが鶏をまるごと一匹蒸したものだったというエピソードを観ると、コモのエビフライを思い出す。
一週間ほどの父の実家での滞在を終えて釜山に立ち寄り、ロッテリアのハンバーガーを食べた。久しぶりのファストフードに大満足で、美味しかったー、と店から出ると、道ばたの屋台でポンテギ(蚕のサナギを蒸して味付けしたもの)を売っていて、飛び上がるほど驚いた。ここは、異国なのだなと実感した瞬間だった。
それでも自分の国に初めて行って、血のつながった親族たちと触れ合って、私は自分が韓国人であるということを強く意識するようになった。そして、だんだん、そのことを人に言ってみたくなったのだ。6年生の時点では、まだまだアイデンティティの葛藤はそれほど強くなかった。韓国に葬儀に行ったことはクラスメートには言っておらず、どこかの地方に行ったことにしてあった。母がそうしてくださいと先生に頼んでいたのだった。だが、もう姉がいじめられることはないし、嘘をついている必要はないのではないだろうか、と私は思い始めていた。
当時、毎日ひとりずつ、三分間スピーチというのを朝の会でやることになっていた。そして私には3月の初めの卒業まじかに順番が回ってきた。
「いままで隠していましたが、私は韓国人です」
私が告白すると、クラスのみんなと先生が息を呑んで、沈黙がその場を支配した。そして、しばらくして先生が、「東愛ちゃん」とハンカチを目に当てた。
「先生、涙がこぼれそうよ。かわいそうで……よく、頑張ったわね、つらいでしょ」
その後、クラスメートがどういう反応をしたかはよく覚えていない。担任の先生の「かわいそう」という言葉に衝撃をうけてしまい、混乱してしまった。誇らしい気持ちで告白したのに、私は、かわいそうなのか。韓国人であることは、かわいそうなことなのか……。つらいことなのか……。
その後、親友となってくれた友達が、気を遣っていつもそばにいてくれたことは覚えている。すぐに卒業式となり、私はクラスメートの多くとサイン帳を交換し、別れを惜しんだから、私の告白は、おおむね大きな問題もなく、クラスメートから嫌な思いをさせられることもなく彼らから受け入れられたのだと思う。
それから、カトリックの女子校へと入学した。卒業した小学校からは私しかその学校に行っていない。いや、まさに、そこは別世界だった。付属の幼稚園や小学校から上がってきた子たちの親は、大学教授だったり、大手有名企業に勤めていたり、経営者だったりした。医師の娘も多かった。ある中学から入った生徒は、「あの人、家が本屋らしいよ」と馬鹿にするような口調で噂されていた。私は、本屋であんなことを言われるなら、自分が韓国人だとばれたらどれほど見下されるのだろうと恐ろしかった。だから、記入してきた身上書を後ろの席から集めるのに、細心の注意を払って次の人に見えないように間に挟んで回したりした。私の身上書には、本籍地に大韓民国と書いてあったからだ。
私は卑屈の極みにいた。仲良くなった子の家に呼ばれて行ったら、お手伝いさんがいたり、ものすごい豪邸だったり、品川区の公立小学校とは異世界だった。30坪の建売住宅に越したばかりの私は、「これは、まずい」と思った。だから、必死に適応しようとした。セーラー服での通学時に毎日のようにあう痴漢に耐え、友達にこびへつらい、容姿にコンプレックスを募らせつつも、なんとか学校に、まわりの子たちに馴染まなければならない。そして、その焦りが、とんでもない行動を引き起こした。
小学校6年にしてやっとできた親友と文通をしていたのだが、私は、その子に、許しがたい手紙を書いたのだ。
「私はもうあなたとはつきあわない。この学校で生きて行かなければならないから。あなたとはレベルが違うところに来たから」というような内容だったと思う。
親友は、激しく傷ついただろう。手紙を送ってすぐに、なんてひどいことを書いたのかと後悔した。しかし、謝ることもできずに今にいたっている。
過剰適応してしまって、ネトウヨになって、自らの同胞にヘイトスピーチを吐く在日コリアンみたいだ。
もしも、このエッセイを彼女が読むことがあったら、本当にごめんなさい、の言葉を伝えたい。あんなに寄り添ってくれたのに、私は最低だ。
自分自身のなかにある差別心、傲慢さに辟易する。
フライドチキンはいまでも好物だ。
ケンタッキーフライドチキンを食べることは年に一度あるかないかとなってしまった。中高の文化祭に、ケンタッキーの出店があったが、買うことはなかった。カーネル・サンダースおじさんが雨にぬれているのを見て、シスターが「あの人に傘を」と言ったという逸話だけが記憶に残っている。
フライドチキンはときどきむしょうに食べたくなる。とくに、韓国ではおなじみのチメク。チキンとメクチュ。フライドチキンとビールの組み合わせは最高だと思う。韓国でチキン屋さんに行くのも楽しみの一つで、行くたびに新しい店を試している。ヤンニョムチキンも好きだけれど、やはり、シンプルなフライドチキンを選ぶことが多い。
フライドチキンだけでなく、鶏の唐揚げも好きで、時々自分でも作る。私の母は、父がパチンコ店を経営しているとき、元日に働く従業員のために唐揚げを200個近く揚げて送り届けていた。私も実家にいるときは手伝っていた。母のレシピは、ショウガがけっこうきいている。私が作るときも母の味を継いでいる。
唐揚げでも、フライドチキンでも、ケンタッキーでもいいから、それらを食べながら、あの親友だった彼女とビールを酌み交わせたら、私の人生における悔いはひとつなくなるのに。
嗚呼、フライドチキン。
人生はままならない。

(筆者提供)
※本文に修正を加えました。(2023/9/17)
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
これまでの連載はこちら
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。