差別の放置はやがて、醜い怪物となる―絵本『ママたちが言った』著者、アリシア・D・ウイリアムズさんインタビュー
2023年12月、クレヨンハウスから絵本『ママたちが言った』(アリシア・D・ウイリアムズ/文 ブリアナ・ムコディリ・ウチェンドゥ/絵 落合恵子/訳)が刊行されました。
日に日に背が伸びる主人公ジェイの姿を、母親は複雑な表情で見つめます。路上で、店先で、黒人のジェイたちには日々、怪訝そうな目線が向けられていました。ある日、意を決したように、家族がジェイに言い聞かせます。万引と疑われないためのふるまい、警察に撃たれないための方法を――。
警察などが、人種や肌の色、出自をもとにして職務質問や取り調べの対象者を選んでいく問題は「レイシャルプロファイリング」と呼ばれ、日本でも少しずつ、認知されるようになってきました。
この本に込められた思いを、作者のアリシアさんに伺いました。
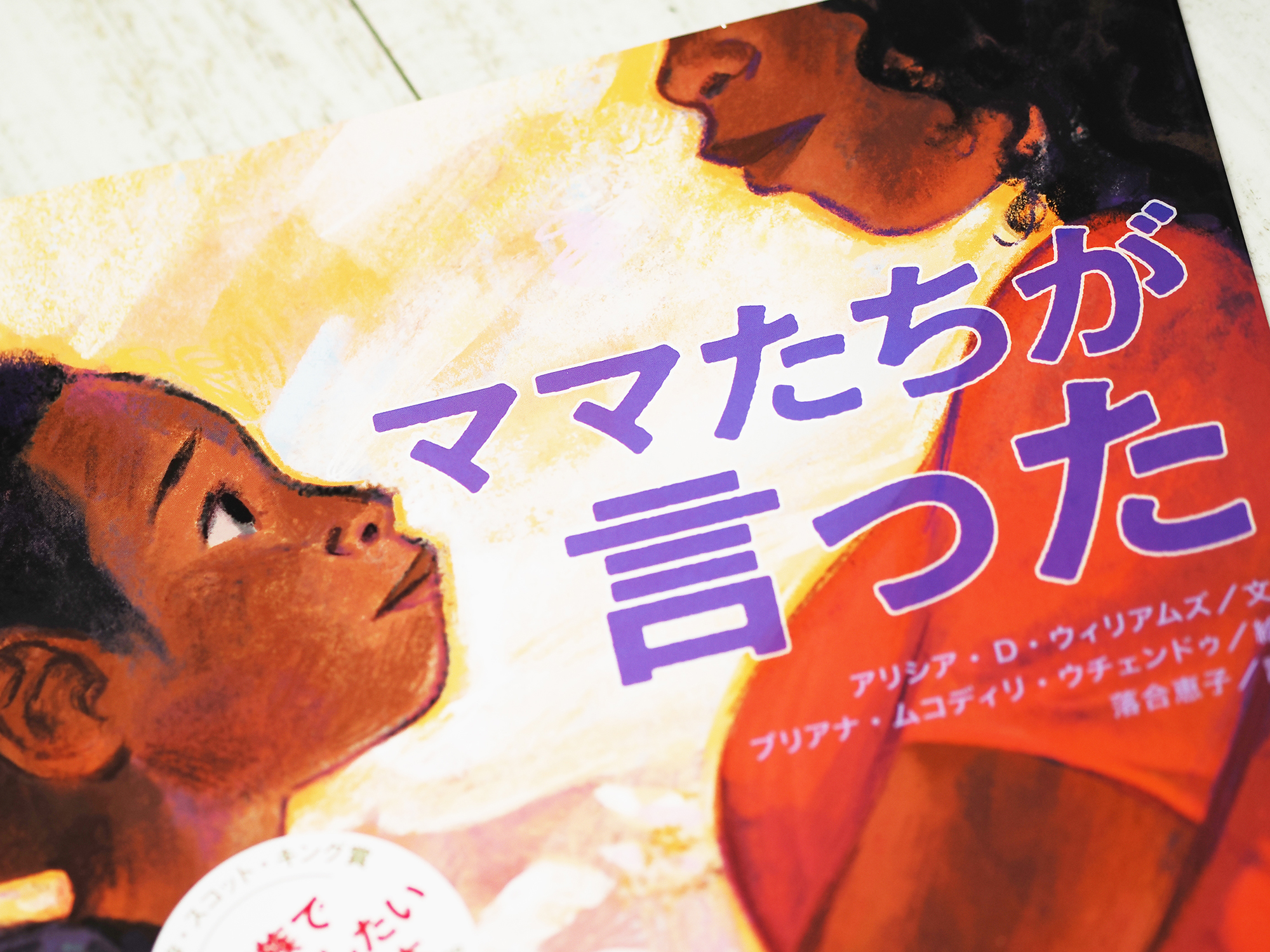
『ママたちが言った』の表紙。(安田菜津紀撮影)
問題なのは子どもたち自身ではなく差別をする側
――この絵本は、どんな読者を想定して作ったのでしょうか?
『ザ・トーク』(『ママたちが言った』の原題)を書いたとき、読者は黒人や褐色の肌の子どもを育てているアメリカの家族だと考えていました。そうした家族はあまりにも頻繁に、「差別」という難しい話をしなければならないからです。白人優位主義の上に築かれたこの国で、子どもたちが無事に家に帰ってくるための方法を、何度も何度も教えなければならないのです。
また、このような出来事の影響を直接受けない家族にもぜひ読んでもらい、私たちのコミュニティで何が起きているのかを知ってほしいと思います。
今、レイシャルプロファイリングは世界的な問題となっています。絵本で描いたような、家族の中での「トーク」は、アメリカだけでなく、カナダ、イギリス、オーストラリア、そして今では日本でも行われているでしょう。人々が抑圧されている場所ならどこでも、「あの話」が交わされているのです。
人種差別的な出来事が起こると、子どもはそれを自分自身の問題として受け止めてしまいます。多くの子どもが、「自分はどこが悪かったんだろう?」「自分は悪い子なのかな?」「きっと悪い子に違いない」と思い込んでしまいます。肌の色だけで、何かを決めつけてくる人がいるかもしれない、ということを、子どもに伝えるのは難しいことです。
この物語は、問題なのは子どもたち自身ではなく、差別をする側なのだということを伝えています。
――力強い絵本は、世代から世代へと受け継がれています。絵本の可能性についてどう思いますか?
絵本作家は、物語を伝える方法について細やかに気を配っており、少ない言葉数で表現しようと工夫しています。無駄のない言葉遣いは、読者が何度も本を読み返すことを促し、最終的には小さなお子さんたちが物語全体を覚えてしまうほどになります。これは口承文学の文化にふれることでもあり、心温まる体験をもたらします。さらに、絵本は十代の読者や大人にもアピールする力を持っています。
絵本は、休日、悲しみ、食べ物、祖父母、犬、学校の初日、歴史など、ありとあらゆるテーマを扱っています。その中には、最も難しいテーマにも取り組むものもあります。読者の中心は子どもたちなので、物語は可能な限り優しく表現され、そのテーマに対して抵抗感を持つ人でも少し受け入れやすくしています。
絵本というのは、最も創造性に富んだものです。作家が物語を語るだけでなく、イラストレーターもまたイラストを通して独自の物語を提示しているからです。この二重の物語こそが、絵本が大切にされる理由のひとつです。私たちはみな、それぞれがユニークであり、それはつまり、学ぶ方法や、心に響くものが人それぞれ違うということです。言葉が心に響く人もいれば、アートワークに心を動かされる人もいるでしょう。
「世界中で安全な場所なんてあるの?」という娘の声
――米国ではかねてから、レイシャルプロファイリングの問題が深刻でした。
3年前の午前3時、携帯電話が鳴りました。大学に通う娘からの電話でした。言葉は不明瞭で、息遣いも荒く、彼女を落ち着かせようとしながら、心臓がドキドキしました。彼女はパニック発作を起こしていたのです。世界中で起こっている社会的不正義が繰り返しトラウマとなり、恐怖を引き起こし、「世界中で安全な場所なんてあるの?」と彼女は泣きました。私は彼女に何を言うことができたでしょうか?
私は、人々に犯罪者だと決めつけられ、自分がそうではないことを証明しなければならないことに苦悩しています。アメリカ人全員ではないですが、白人の中には、この人種差別は黒人やメキシコ人、アジア人の問題だと考える人がいます。「自分はそういう人種じゃないから心配しなくていい」と思い込む人がいるのです。
アメリカでは、人種によるレッテル貼りは、奴隷制の時代からずっと存在しています。奴隷から解放された人(法的に奴隷ではない人)たちは、自分が「自由黒人」であることを証明するために書類を持たされることを強制されていました。想像してみてください、ひとりの人間が別のひとりの人間に対して、自分が(奴隷制度から)自由であることを証明しなければならなかったのです。そして、その書類でさえも極めて限定的なものでした(※筆者注:「自由黒人」と呼ばれる人々も、黒人法によって様々な制約を受けていた)。
奴隷制度が廃止された後も、1950年代と60年代を通して、黒人アメリカ人は公民権のために、メキシコ系アメリカ人はチカーノ(アメリカに暮らすメキシコ系アメリカ人が自らのアイデンティティを表現する呼び名)の権利のために闘いました。
こうした運動を通して、そして今日に至るまで、何十万人もの命が失われました。子どもも大人も警察に対して本物の恐怖を抱いています。家族はトラウマを抱え、悲しみと闘っています。抗議活動は平和的に行われることもあれば、ときに暴力的な事態に至ることもあります。コミュニティは破壊され、政府に対する信頼は失われています。
「自分はそういう人種じゃないから心配しなくていい」と思う人は、間違いを犯しています。公民権運動のリーダーであるマーティン・ルーサー・キング牧師は、「どこかの不正義は、あらゆる場所の正義への脅威である」と言いました。特に、社会的不正義に対する沈黙は問題です。沈黙は、このような暴力は許されるものである、というメッセージを社会に送ります。レイシャルプロファイリングは暴力であり、被害者の中に恐怖を生み出します。
恐怖は壁を作り希望を破壊する
――日本でもレイシャルプロファイリングの問題を巡る訴訟が起きています。日本の読者にメッセージをお願いします。
日本でも在日外国人や観光客を対象としたレイシャルプロファイリングが存在することを知り、悲しくなりました。人種によるレッテル貼りが根付いてしまうと、それは醜い怪物へと成長し、破壊するのが難しくなります。少数の職務質問から始まるかもしれませんが、やがては死者が出るようになり、市民は敵対関係になり、抗議活動が起き、他者に対する恨みと憎悪がその人たちのアイデンティティの基盤となってしまうでしょう。これは人間としてあるべき姿ではありません。
警察は市民を守るために存在します。選挙で選ばれ、職務に就いている人たちは、安全を提供し、ステレオタイプに頼らないことが求められています。レイシャルプロファイリングは恐怖にとらわれる風潮を作り出します。恐怖は壁を作り、希望を破壊します。
私たちは子どもたちに、他者に対しての決めつけをしないようにしてほしいと思っています。子どもたちに自分で考えることを促し、偏見を持たないようにしてほしいと思っています。ステレオタイプを信じることは危険であり、否定的な思い込みは決して良いことではありません。互いの humanity (人間性) を見るように願っています。なぜなら、私たちはみな、自由に生活し、移動する権利があるのですから。
Writerこの記事を書いたのは
Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda
1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。
あわせて読みたい
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。






