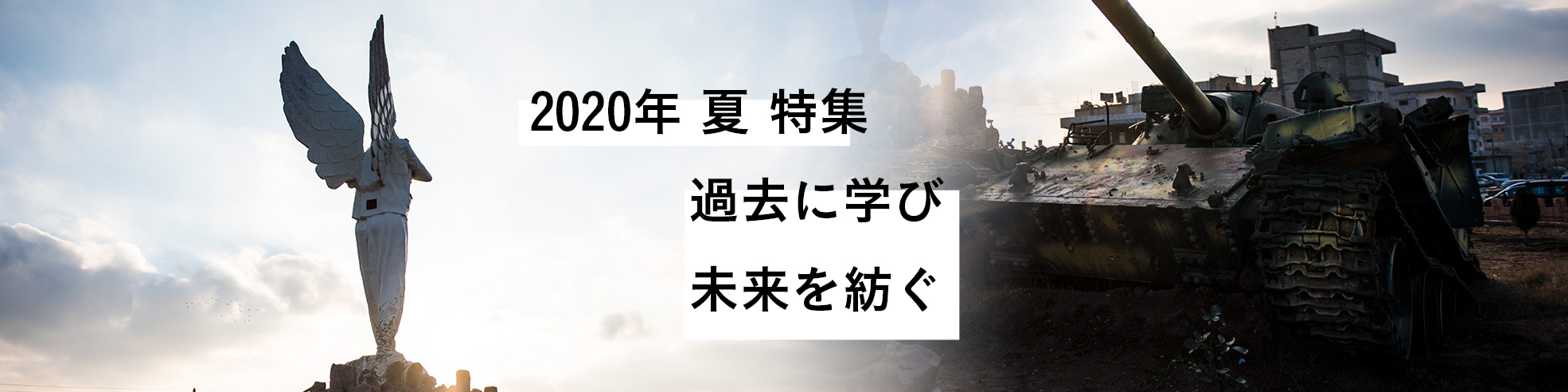8月、大人も読みたい戦争を伝える絵本
【エッセイ】月300冊の読み聞かせの時間が私にくれたものにも書かせてもらいましたが、私の母は絵本の読み聞かせにこだわる人でした。その冊数はなんと月に300冊。絵本に添えられた言葉は簡潔で短いものではありますが、だからこそ伝えるべきメッセージがそこに凝縮され、むしろ力強い問いかけが詰められているように私は感じてきました。幼いときに慣れ親しんだ絵本を大人になってから読み返しても、はっと気づかされることがたくさんあります。8月、子どもにも大人にも、「戦争」について伝えてくれる絵本を、私なりに選んでみました。
※()内の対象年齢は飽くまでも目安です。
Contents 目次
● 戦争って、なに?
・ 『ぼくがラーメンたべてるとき』 長谷川義史 (3・4歳~)
「ぼくがラーメンたべてるとき、となりでミケがあくびした。」
「となりでミケがあくびしたとき…。」
「となりのみっちゃんがチャンネルかえた。となりのみっちゃんがチャンネルかえたとき…。」
と、この絵本はバトンを次々手渡していくように展開していきます。やがて、「となりのいえ」から「となりのまち」、「となりのくに」へ、そしてアジアの農村や、中東の町を思わせる場面へと広がっていきます。そして「そのまたやまのむこうのくに」で倒れている男の子の姿が…。小さな子どもたちに「世界では大変な子どもたちがいて、戦争もあって」と突然“異世界”のことを伝えるのは難しいかもしれません。けれどもこの本は、「ぼく」の家から少しずつ想像力の階段を世界へとのばしてくれるのです。「私」という枠を拡げた延長線上に、貧困や戦争があることを教えてくれます。
・ 『せかいいちうつくしいぼくの村』 小林豊 (6歳~)
絵本の舞台はアフガニスタン。主人公の少年、ヤモが暮らす村は、豊かな収穫の季節を迎えていました。真っ青な空の下に広がる、甘酸っぱい香りに包まれた果物畑。その傍らで会話を楽しむ人々の顔はどれも和やかです。その果物を売りにお父さんと出向いた街中は、一見活気に満ち溢れているようでも、戦闘の影が確実に忍び寄っていることがうかがえます。よく見るとそこには、松葉杖をつく人、片足のない人の姿。ヤモは兵士として戦地に向かった兄の帰還を信じていました。
「戦争」を伝える絵本でありつつも、激しい争いは最後までここには描かれていません。「この村は戦争で破壊され、今はもう、ありません」と、ただこの一言で物語が締めくく
られているのです。ヤモの村の美しい風景が、“想像してほしい”と私たちに投げかけてくるようです。最初から戦地だった場所はない。最初から難民だった人々もいない。それを知ったあなたは、どう生きるべきか、と。
・ 『わたしの「やめて」』 塚本やすし (4・5歳~)
“せんそうは
「ぼくが ころされないように
さきに ころすんだ」
という だれかの
いいわけで はじまります“
戦争はなぜはじまるのか、誰が儲かり、誰が傷つくのかを、平易な言葉で的確に語っています。私たちは何のために学校で学ぶのか、それは人を無為に傷つけるためではなく、互いの命を尊重するためではないのか、ということを、読者に強く投げかけてくれます。文章の元になっているのは、2015年7月に、学生と教員が中心となって結成された「自由と平和のための京大有志の会」の声明文で、末尾に全文と英訳が記してあります。
● 太平洋戦争のこと
・ 『被爆者』 会田法行 (10歳~)
広島、長崎で、ある日突然「被爆者」となった6人の生きる姿を、写真を通して伝える1冊です。中には原爆投下当時、お母さんのお腹にいたために、原爆小頭症で生まれてきた女性もいます。写真は戦後60年時点の「現在地」をとらえたもの。けれどもそこには確かに、それぞれの60年間の歩みが凝縮されているのです。それは何十年が経とうとも、体験者の心に、体に、「あの日」が刻まれているからでした。ケロイドや傷跡、体の健康をむしばむ後遺症、悲しみや怒り。繰り返さないために私たちが受け取るべきバトンは何なのか…。原爆ドームの絵を描き続けていた、原廣司さんの言葉に、その鍵があるように感じます。「私だってアメリカという国を好きになれませんよ。でも、核兵器がなくなってほしいという想いや平和を願う気持ちは、そういう憎しみを超越するのです」。
・ 『チロヌップのきつね』 高橋宏幸 (5歳~)
春になると、北の海の島へと漁にやってくるおじいさん、おばあさんに、ひょんなきっかけでかわいがられたこぎつね、ちびこ。やがてその島は、漁師たちではなく、兵士たちの島へと姿を変えていきます。戦争は、自然の恵みと共に暮らしていたおじいさん、おばあさんをその営みから遠ざけ、ちびこの家族までも、理不尽に引き裂いていきました。動物たちの視点で描いているからこそ、人間の身勝手さが突きつけられます。
・ 『花ばあば』 クォン・ユンドク
押し花をして、花に触れている時だけ、花ばあばの顔はぱあっと輝きます。なぜ、それ以外の時を過ごしている時、彼女の顔に陰りが見えるのか、その歩みをたどると、朝鮮半島での日本の植民地支配と戦争に突き当たります。この本は1940年頃、日本軍「慰安婦」として連れていかれたシム・ダリョンさんの証言を元に作られたものです。彼女の苦しみは「戦後」を迎えておさまるものではありませんでした。日本軍「慰安婦」についての記述が教科書などから次々と消える今、こうした絵本の存在は貴重なものとなってしまいました。世界の中でなお、戦争と性暴力が人々の尊厳を傷つけ続けています。だからこそ国境をこえ、痛みを分かち合うことが、繰り返さないための礎となるはずです。
・ 『てっぽうをもったキジムナー』 たじまゆきひこ
きじむなーは、沖縄に伝わる大木の精霊で、夜になると木から降りてきて、沖縄の人たちを守っているのだといいます。主人公のさっちゃんは病気で歩くことができなくなり、いつもおばあの押す手押し車で学校に通っていました。やがてアメリカ軍が上陸し、爆撃の嵐に巻き込まれていくさっちゃん。逃げ込んだはずの壕では、日本兵が住人たちに「“自決”できなければ非国民だ」と迫る。誰にも守ってもらえないさっちゃんに手を差し伸べたのは、「きじむなー」でした。きじむなーは、決して単純化して語れない戦争の姿そのものでした。絵本では、いまだ上空を戦闘機が飛び交う沖縄の姿を描き、この地が「戦後」を迎えられていないことを伝えています。最後に、おじいが語る言葉が、私たちへの大切な警鐘でした。「てっぽうをもったひとは、てっぽうに たおされるのさあ。おおきなきちのある おきなわが、また おおきなせんそうに まきこまれなければ よいがね」。
● 世界で起きている戦争と難民問題
・ 『せんそうがやってきた日』 ニコラ・デイビス (小学校低学年~)
ある時、一人の少女が学校でランチタイムを過ごした直後に、激しい爆撃が街を襲い、彼女の日常を根こそぎ、奪っていきました。安全を求めてたった一人、長く過酷な旅へと出た少女は、たどり着いたぼろぼろの小屋の中でぽつりと語ります。「わたしの心は せんそうに せんりょうされてしまった」。その心の中の戦争を追い払おうと、彼女は街をさまよい続けます。けれどもそこで直面したのは、冷たい視線と、「あなたの居場所はありません」という人々の壁でした。
2016年春、イギリス政府が3000人の難民の孤児を避難所へ収容することを拒否したことや、「座る椅子がない」という理由で難民の女の子が入学を断られたことを聞き、この詩を綴ったそう。行き場がなく、教育を受ける機会を奪われてしまった子どもたちへの連帯として。
・ 『なんみんってよばないで。』 ケイト・ルミナ― (小学校低学年~)
「このまちを でていかなけくては ならないの」。母が少年に優しく語りかけるところから、長い長い旅路がはじまります。安全な暮らしを求め、慣れ親しんだ故郷を離れ、何もかも不慣れな中を歩んでいく少年に、母は優しくこう伝えます。「なんみんの こ って よばれてもね これだけは わすれないで あなたの なまえは なんみん じゃないのよ」。「難民」という大きな主語でくくられ語られがちな人々の、一人ひとりに思いがあり、人生があることをこの本が伝えてくれます。「あなたならどうする?」と、1ページ1ページに投げかけがあり、読みすすめるごとに少年の歩みが、“他人事”ではなく“自分事”となっていくのです。日本に逃れてきた難民の方々の支援を続ける難民支援協会の末尾の解説も必読です。
(文 安田菜津紀/2020年7月)
あわせて読みたい
■ 2021年夏特集「この社会は本当に『戦後』を迎えたのか?」
■ かつての特攻訓練場は、福島第一原発の敷地となった「捨石塚」が伝えるものとは[2020.7.30/安田菜津紀]
■ 【エッセイ】月300冊の読み聞かせの時間が私にくれたもの[2019.4.25/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の声の中には、これからを生きていく中で必要な「知恵」や忘れてはならない「想い」がたくさん詰まっています。共感をうみ、次の世代へこの「受け取り」「伝える」枠組みを残していくために。皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。