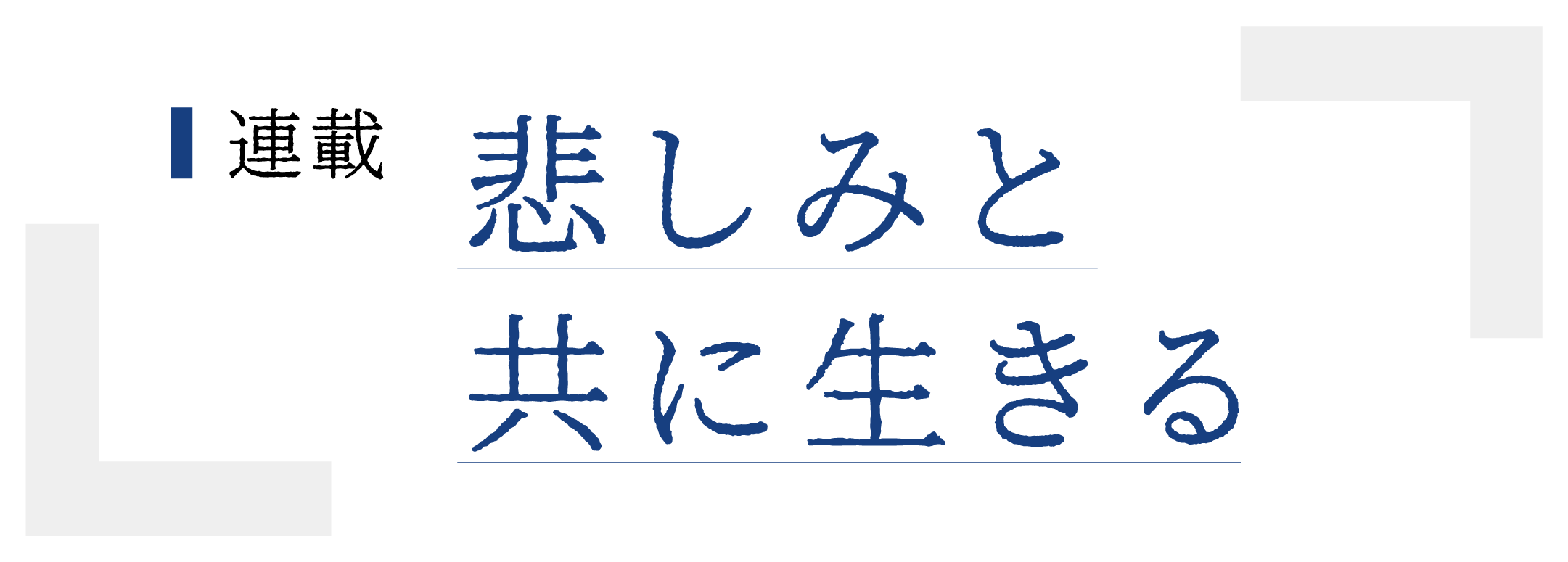本連載では、グリーフケアにまつわる人々へのインタビューを通し、喪失体験と共に生きる人々の姿をお伝えしていきます。第4回は、世田谷事件の遺族として、「悲しみを生きる力に」をテーマに発信・活動を続ける入江杏さんにお話を伺います。「悲しみは決して癒えることはないけれども、少しでも前向きに生きることの大切さを伝えたい。命の儚さとともにその尊さも伝えられたら」と話す入江さんは、「ミシュカの森」を主宰し、さまざまな苦しみや悲しみに向き合い、共感し合える場づくりに努めています。
本文中には身近な人の死や、自死に関する記述がございます。そうした内容により、精神的なストレスを感じられる方がいらっしゃる可能性もありますので、ご無理のないようお願い致します。

あいまいな喪失
―入江さんは「世田谷事件」の遺族として、突然の喪失による悲嘆と向き合いながらグリーフケアと関わり続けています。未解決事件という、答えのない問いを抱え続ける「あいまいな喪失」と、どのように向き合ってこられたのでしょうか?
▶︎世田谷事件
2000年の大晦日に発覚した殺人事件。入江さんの隣に住む妹一家4人が殺害された。いまだ犯人の特定・逮捕にいたっておらず未解決事件となっている。
初めて「あいまいな喪失」という概念を知った時は、自分の抱える悲しみに名付けを得た安心感、納得感のようなものがありました。未解決事件の遺族は、わからないことばかりです。曖昧なことが多ければ多いほど、辛さは増すと言われています。東日本大震災の津波によりいまだにご遺体が見つからない方々が抱える「あいまいな喪失」と、私の感じるそれとは必ずしも同じではないと思います。大切な妹一家のなきがらを「自分の目で確かめられなかった」「きちんとお別れを言えなかった」という私の体験も、ひとつの「あいまいな喪失」ではないかと感じています。
▶︎あいまいな喪失
ポーリン・ボス(Pauline Boss)は、あいまいな喪失(ambiguous loss)という概念を提唱している。あいまいな喪失には、①身体的には不在であるが、心理的に存在していると認知されることにより経験される喪失(たとえば、行方不明者の家族)と、②身体的には存在しているが、心理的に不在であると認知されることにより経験される喪失(たとえば、認知症患者の家族)が含まれる。あいまいな喪失を経験している人は、状況の不確実性の継続に困惑し、無力感や、抑うつ、不安などを示しがちであり、家族内での葛藤が生じることもある。(『死生学のフィールド』石丸昌彦・山崎浩司著、2018年、放送大学教育振興会)
ご遺体にまだ巡りあえない方の悲しみを私が理解できるかはわかりませんが、概念の名付けによって、「共有できるもの」が増えると感じます。同じ体験をすることは誰にもできませんが、そのような概念を知ることで、理解の裾野が広がっていくのではないでしょうか。もうひとつ、私が「名付け」を得たものに「公認されない悲嘆」があります。自分の悲しみを公にすることができないために、悲しみが複雑化することを指します。名付けとの出会いは、自分の悲しみの根っこを見つめ、他の方の悲しみ、苦しみにも目を向けるきっかけとなりました。
とはいえ、「あいまいな喪失」「公認されない悲嘆」という、ある意味では、印象の強い言葉に寄り掛かりすぎてしまうと、自分の悲しみを「特異なもの」と見なして、その特殊さにとらわれがちです。悲しみが自分の中に「錨を下ろして」しまうのです。錨を解いて、少しでも重荷を減らしていけたらと思っています。

被害者像というフレーム
―世田谷事件はマスコミでも大々的に報じられました。遺族として世間の注目を浴びるということは、死別による苦しみとはまた別の困難さもあったのではないでしょうか。
母から強く求められ、事件との関わりを世間に知られないように努めていましたので、遺族として注目を浴びることなどあってはならないと、ただただ、世間の目を憚って暮らしていました。コロナ禍の中、世界中の人が体験した「ステイホーム」が当時の私たちの生活です。当初は、本当に「もうおしまいだ」「二度と前を向くことはできない」と思い、閉じこもっていました。何より、それまで培ってきた、社会や人々に対する信頼がいっきに失われてしまったのですから。一度失われた安心や信頼をどのように取り戻すかは、容易にはわかりませんでした。
事件について、最初の「聴き手」は警察でした。自分の時間をすべて費やし、全面的に捜査に協力しました。どんな些細なトラブルの種も「手がかり」になるかもしれないと、伝え続けました。それは悪意の痕跡を探る作業でしたが、同時に、過去の棚卸しをしていたのだと、後になって感じました。
また、世間の抱く「被害者遺族像」から少しでもはみ出ると、とたんに攻撃の対象となってしまうことがあります。社会的な弱者と思われる人たちは「無力な状態にあるはずだ」と一般の人には思われがちです。それに反して明るくふるまうと「おかしい」「生意気だ」と、攻撃の矢が飛んできます。
「あの人、被害者なのに能弁だよね」「被害者遺族という立場を利用して何をしたいんだ?」と、そんな言葉を投げかけられたこともあります。社会から疎外されないように、とりわけ、亡くなった人の名誉や自分自身の家族の安全を守るためにも、「世間の考える被害者遺族像」から外れないように、当時から気を付けていました。

本を通じて人と出逢う
―社会を信頼することができなかったという数年間から、どのようにして社会とのかかわりを取り戻してこられたのでしょうか?
本当に何もできなくなってしまった時期というのがありました。本を読んだり、音楽を聴いたりということもできなかったんです。なんだか心が乱れてしまうんですね。先日刊行した『悲しみとともにどう生きるか』(集英社新書)第二章は、批評家・随筆家の若松英輔さんですが、若松さんに初めてお目にかかったとき、こんなことをおっしゃっていました。「自分の中で物語が書かれている時に人は、読めない。読むと書くとは同時にはできない。物語がその人の中で生まれている時は、本は読めないんですね」と。確かに「本を読めなかった時期」というのは、私の中で何かが生まれている時だったんですね。
事件から半年ほどして、ノンフィクション作家の柳田邦男さんと知己を得ました。柳田さんが送ってくださった本の中には、ご自身の息子さんとの死別を綴った本や、グリーフケア関連の書籍が含まれていました。読むのが辛いものもあったんですが、本への興味が次第に蘇ってきて、少しずつ、子どものときに読んでいた絵本などにも手を伸ばすようになり、それが回復への一歩になりました。
こもりがちの生活から、思い切って少しずつ外に出てみようと、上智大学で開かれていたアルフォンス・デーケン先生の講座に出席しました。先生は「あなたのやっていることは、セラピーですね。芸術と出逢う“アートセラピー”、本と出逢う“ビブリオセラピー”、そして、人と出逢う“出逢いセラピー”です。」とおっしゃってくださった。嬉しかったです。悲しみと向き合うグリーフケアへの関心が一層深まった瞬間でした。
「自分だけが幸せになるんじゃなくて、どうすれば世の中がもっとよくなるんだろう」と、子どもの頃からそんなことを考えていました。亡くなった妹が、私のその問いを受け止めてくれたことを思い出します。学生時代には、その問いを携えて死生学や心理学なども学びました。答えにならない問いを抱いて思い悩んだ体験も、グリーフケアに関わる上で、その一助になっているのかもしれません。

悲しみをないがしろにしない
―グリーフケアというものを考えたとき、悲嘆を背負っている方個人の問題だけではなく、社会の側にもそれを受け取る、受け容れる力が必要なのではないでしょうか。
世の中には「悲しみを受け取りたくない」「できれば関わりたくない」という雰囲気が、確かにあると思います。自死遺族の方から「入江さんは殺人事件の遺族だから、同情されるかもしれない。でも自ら命を絶った私の子どもは“自分で勝手に死んだ”と言われて同情されない」という辛い言葉を聞きました。生きている時もさまざまな分け隔てに苦しめられますが、亡くなってなお、受け容れられる死とそうでない死があることに言葉を失いました。自ら命を絶たざるをえなかった人に対して、「大切な命をないがしろにするのか!」と咎めるような言葉が投げつけられる。それは本当に「命を大切にする」社会といえるのでしょうか。「命を大切に」という言葉が、単なるお題目になってはいないでしょうか。
「どのようにして悲しみを克服したのでしょう?」とよく聞かれることがあります。その質問の趣旨は理解できるものの、悲しみは「克服すべきもの」という前提があるように感じます。悲しみから目をそむけようとする社会は、実は生きることを大切にしていない社会なのではないでしょうか。グリーフケアは、「悲しみの意味」を問いかけることから始まります。悲しむことも、誰かの悲しみに耳を傾けることも、ともに、とても人間らしいことと伝えています。
―ケア(Care=気に掛ける、世話をする)ではなくキュア(Cure=治す、矯正する、取り除く)を想定すると、悲しみが置いていかれるということでしょうか。
悲しみは、時間とともに深まりこそすれ、解消することはありません。悲しみとともに生きていくことを探っていくのが「グリーフケア」です。グリーフケアが特別な処方箋や対処法と受け取られてしまうのは、「悲しみを克服し強く生きる人」への称賛を、一定の枠組みの中で伝えるメディアにも原因があるのかもしれません。「グリーフケア」は、日常のことなんです。誰かの悲しみに気づいてそっと手を差し伸べる、そうした日常が当たり前となる社会を願っています。

魂の痛みに耳を傾ける
―入江さんが大切にされている言葉に「悲しみの水脈」というものがあります。どのようなイメージから生まれた言葉なのでしょうか。
妹一家の死は、もちろん大きな悲しみでした。でも、事件から10年経って急逝した夫との別れは、それ以上の悲しみだったと思います。
東日本大震災でご家族を亡くされた方々とお話しする機会がありました。ご家族を亡くされた方が、私が夫についてした話が心に響いたとおっしゃってくださったんです。なにか胸の奥深くの悲しみが通じ合って、広がっていくような気がしました。お互いの悲しみの水脈が繋がって、同じ湖を一緒に見ているような気持ちになったんです。
個人の悲しみは、それぞれ大きさも形も違っていて、それらは一見何の関係もないように思えます。でも、悲しみを誰もがもつ感情ととらえ、地中に水脈が広がるように、それぞれの悲しみが目に見えないつながりをもっていると考えてみたらどうでしょう。そうすれば、悲しみをもっと大きな存在として共有できるのではないでしょうか。
―『悲しみを生きる力に~被害者遺族からあなたへ』著:入江杏(岩波ジュニア新書)

―入江さんは「ミシュカの森」や講演のほかにも、絵本の創作や読み聞かせなど、様々な活動を行ってらっしゃいますが、それはどのような思いからなのでしょうか?
そうした活動に対して、「なんで犯罪被害者がそんなことをやってるの?」と言われることもありました。ホームレス支援や貧困問題、自殺の問題なんて、世田谷事件と関係ないじゃないかと。けれど、それはどこか私の中では繋がっています。
誰も耳を傾けてくれない魂の痛みとでもいうべきものに、心を寄せる。それが「グリーフケアのある日常」だと思います。一人ひとりの悲しみに耳を傾けてこそ、希望ある未来も見えてくるのではないでしょうか。
生きている人間は幸せにならなくてはならない。あるいは、どこまでも幸せになっていい。それだけが死者の望みだと思うんです。だから、まず、自分の幸せを恐れない。そして、死者を恐れない。恐れる必要は全くない。あとは、自分はどこまでも幸せになる。生きていて申し訳ないなんて思う必要はなくて、誰に遠慮することなく、どこまでも、どこまでも、幸せになっていいんです。(若松英輔さんとの対談より)
―『悲しみとともにどう生きるか』編著:入江杏(集英社新書)

【プロフィール】
入江 杏(いりえ・あん)
東京都生まれ。国際基督教大学卒。「ミシュカの森」主宰。上智大学グリーフケア研究所非常勤講師、世田谷区グリーフサポート検討委員。犯罪被害の悲しみ・苦しみと向き合い、葛藤の中で「生き直し」をした体験から、「悲しみを生きる力に」をテーマとして、行政・学校・企業などで講演・勉強会を開催。「ミシュカの森」の活動を核に、悲しみの発信から再生を模索する人たちのネットワークづくりに努める。著書に『悲しみを生きる力に~被害者遺族からあなたへ』(岩波ジュニア新書)、絵本『ずっとつながってるよ こぐまのミシュカのおはなし』(くもん出版)ほか。編著『悲しみとともにどう生きるか』(集英社新書)を2020年11月に刊行。
(2020.11/インタビュー 佐藤慧 ・ 写真 安田菜津紀,佐藤慧)
主な参考文献
・『悲しみを生きる力に~被害者遺族からあなたへ』入江杏 著(岩波ジュニア新書)
https://www.iwanami.co.jp/book/b223770.html・『悲しみとともにどう生きるか』入江杏 編著(集英社新書)
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/1045-c/
【支援・相談窓口/参照リンク】
▶︎ 全国自死遺族総合支援センター
身近な人を自死(自殺)で亡くした方のつどいに関する情報や、相談先が記載されています。▶︎ 自殺対策支援センターライフリンク
「生き心地の良い社会」の実現をめざし、自殺対策、「いのちへの支援」に取り組んでいるNPOです。○ 相談先リンク
▶︎ 電話相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)
▶︎ SNS相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)○ グリーフケアについてもっと知りたい方へ
▶ 上智大学グリーフケア研究所
▶ 一般社団法人The Egg Tree House
あわせて読みたい・聴きたい
■ 連載「悲しみと共に生きる」 (※記事は順次更新して参ります)
■ 【Radiotalk】「グリーフケア」を学びながら[2020.8.28/佐藤慧]
「それぞれの声が社会をつくる」
Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。2020年冬は「それぞれの声が社会をつくる」と題し、民主主義のアップデートをテーマとした特集を実施中です。一人一人の声を「伝える」ことから「共感」を育み、「対話」を生み出すこの取り組みを支えるため、あたたかなご支援・ご協力をよろしくお願いします。