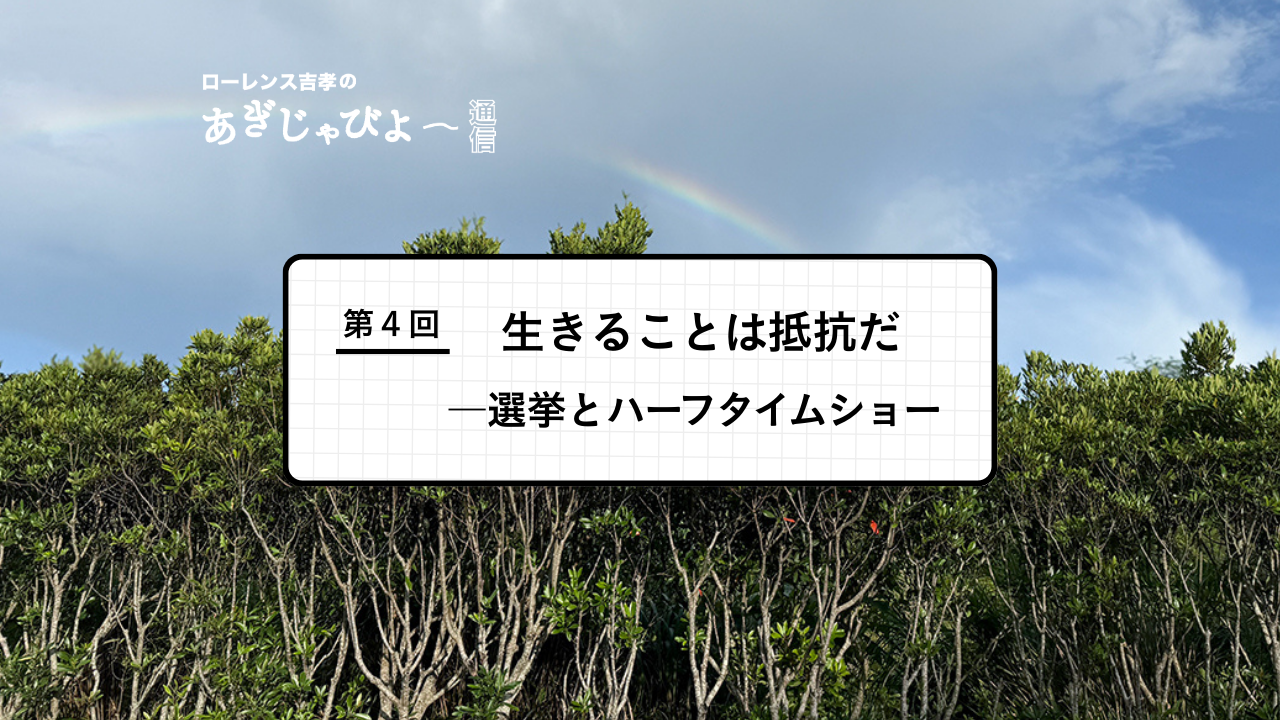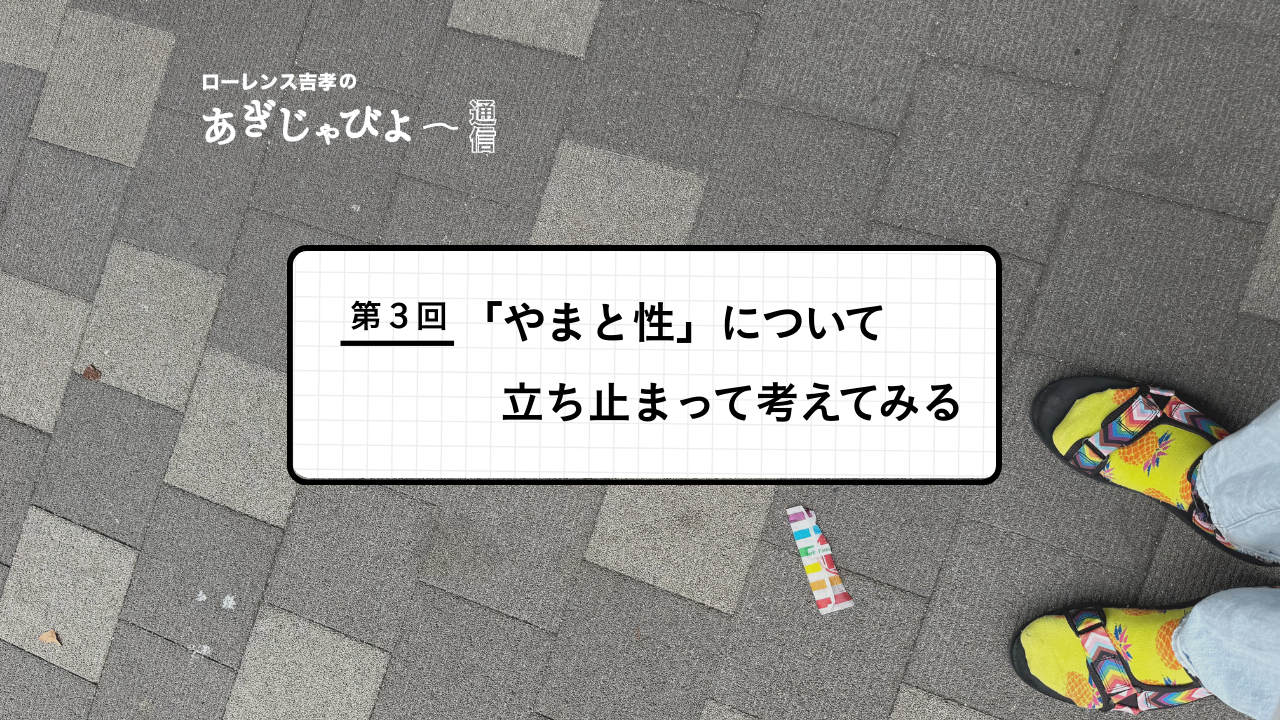本記事は『10分後に自分の世界が広がる手紙』(東洋館出版社)という小中学生向けのエッセイシリーズの一冊、『君はどんな大人になりたい?』から、WEB記事用に整え、転載したものです。書籍詳細は記事末をご参照ください。
※書籍では難しい漢字にはルビをふっています。
※本記事に掲載している写真はWEB記事のみのものです。

ほんの少し大人になった日
ぼくが生まれたのは、東北地方の太平洋がわ、岩手県の内陸にある盛岡市というところです。「どこで生まれたか」「どこで育ったか」というのは、自分では選ぶことのできないものですが、それから先の人生の、長い時間にわたって、とても大きなえいきょうをあたえることだと思います。
雪国で育ったぼくは、雪景色というものが大好きです。こごえるような冬になると、何もかもが、真っ白にぬりつぶされます。街を出歩く人もへり、夜になって、音もなくまい落ちる雪をあおぐように空を見上げると、静まりかえった暗やみの中に、他の季節よりも、ひときわかがやく星空が広がります。そんな時はなんだか、世界中の時間が止まって、自分だけがこの世界で呼吸をしているような、とても不思議な気持ちになるのです。
そんな土地で子ども時代を過ごしたせいか、今でも雪を見ないと、冬が来た気がしません。雪が降らず、星空も見えない都会にいると、こころとからだの奥底が、なんだかムズムズしてきます。きっと、育った環境の空気やリズムが、ぼくの中にしみついているのだと思います。
すぐそばに山や川のある田舎で育ったおかげで、幼稚園に通っていたころから、けがをしてばかりの少年でした。ズボンのひざはすぐにすりむけるし、いつも体のどこかにばんそうこうをはっていました。クローバーのみつを吸ったり、クワガタをつかまえるために樹液の出ている木を探したり、手作りのつりざおで小魚をつったりして、過ごしていました。
毎日が、たくさんの発見と、未知への冒険にあふれていたように思います。ときにいたずらをして両親にしかられたり、兄弟げんかをして泣いたり、さわがしくも、たのしい日々でした。

ふるさとの風景を見ると、たくさんの思い出がよみがえってくる。
そういえばぼくは、はじめて自分という存在の「わく」を意識した瞬間のことを覚えています。「ぼく」というものが、この皮ふで区切られた存在であって、目の前の友達や両親とは、ちがう存在なのだと気づいた瞬間です。
そんなことを言うと、「あたりまえじゃないか」と思うかもしれませんが、少なくともぼくにとっては、そうではなかったのです。
幼稚園の年少クラス(ひよこ組と呼ばれてました)に通い始めたぼくは、帰りの時間に、ふたつ上のクラスに通う姉がむかえに来るのを、教室で待っていました。そして姉が「けい!」と、ぼくの名前を呼んだ瞬間、なにかが「ひゅっ!」と、ぼくのからだの中におさまったのです。それまでは、からだの外がわにも、ふわふわとただよっていたぼくの一部が、ぜんぶすっぽり、からだの中に入ってしまったように感じました。
「あ! ぼくは、この皮ふの中で生きているんだ!」と、手のひらをまじまじと見つめました。それがぼくの思い出せるかぎりの、一番ふるい記憶です。
君はどうでしょう?
人生で一番最初の記憶は、どんな記憶でしょうか。
ぼくのその体験は、今思い出しても、「世界って不思議だな」と感じることのできる、大切な思い出として、心の中にしまってあります。
そんなワンダーランドに生きる少年のぼくに、それまでの人生のよろこびすべてが、ひっくり返るような出来事が起こりました。
ぼくが小学1年生のときのことです。まだ幼稚園に通う2歳下の弟に「がん」が見つかり、入院してしまったのです。
「きっとすぐよくなるよねえ」と、無邪気に笑うぼくに対し、「ううん、これはね、大変な病気なんだ」と言った、父のけわしい顔を覚えています。
それから間もなく、ぼくが2年生に進級するタイミングで、家族で岩手県を出て、すぐ南の宮城県、仙台市に移り住みました。弟の病気を、都会の大きな病院でみてもらうためです。
オニヤンマが庭を飛び回り、近所のねこが自由に部屋を出入りする田舎に暮らしていたぼくは、マンションの5階からながめる都会の光景におどろきました。夜になっても、まるで暗くならないのです。
新しい学校への転校は、とてもドキドキするものでしたが、すぐにみんなと仲良くなり、放課後は山遊びではなく、校庭でドッジボールをしたり、友達の家でテレビゲームをして過ごすようになりました。
弟の入院は長引き、いつまで経っても退院できません。ごくたまに弟が家に帰ってくるときがありましたが、弟は「がん」の治療のためにかみがぬけ、体には、手術のためにマジックペンで線が引かれていました。
今思うと、手術前に「もしものこと」を考えて、数日だけ家にもどってきていたのかもしれません。岩手にいたころはよくけんかをしていましたが、ぼくも幼いなりに何かを感じていたのでしょう、少しでも弟が楽しんでくれるようにと、時間の許す限り、いっしょに遊んで過ごしました。

家にかえってきた弟と遊ぶ姉。
またたく間に1年が経ち、ぼくも小学3年生になったある日、1本の電話がかかってきました。その当時、母は病気の弟といっしょに病院でねとまりをしていて、父とぼく、姉、一番下の弟と、おばあちゃんがいっしょに暮らしていました。その電話が鳴ったときは、ちょうどみんな買い物に出ていたところで、ぼくはひとりで留守番をしていました。とても不思議なことですが、ぼくはそのとき、「何かよくない知らせだぞ」と、感じたことを覚えています。
それは父からの電話でした。弟の具合が良くないから、おばあちゃんがもどってきたらすぐに病院に来るようにと言うと、父はあわただしく電話を切りました。なんだかこわくなったぼくは、いつか両親に買ってもらった、ランドセルにぶら下げてあった「交通安全」のお守りをぎゅっとにぎりしめ、おばあちゃんたちが帰宅すると、急いで病院へと向かいました。
病院へ着くと、泣いている両親のおくのベッドで、弟が冷たくなっていました。「死」というものを、ぼんやりとしか理解していなかったぼくは、弟が動かなくなってしまったことよりも、両親が泣き止まないことにおどろき、泣き出しました。大人である両親が、こんなに弱く泣きくずれるなんて、きっとぼくには想像できないぐらい、おそろしいことが起こったにちがいない、そう思ったのです。
それから数日後、お葬式も終わり、火葬場へと行きました。大きなえんとつから、モクモクとあがるけむりをながめながら、父が言いました。
「たっぷり深呼吸をしておきなさい」
そのけむりは、弟のからだだったものが、燃えたものだというのです。
弟は、燃えて、小さな小さな、目には見えないかけらに分解されて、空気の中にとけていったのだと、父は言いました。
だからきっと、深呼吸する空気の中にも、弟のかけらが入っているのだと。そうして染みこんだ弟の命は、ぼくの中で生き続けるのだから、ちゃんと幸せな大人になりなさいと。
そう言われてぼんやり空をながめていると、何かとても細かな光のつぶが、きらきらと空気中をただよっているように感じて、ぼくは力いっぱい息を吸い込みました。

キラキラとかがやく植物のたね。
▶佐藤慧著『10分後に自分の世界が広がる手紙』 目次
ほんのすこし大人になった日 / かくれ家は本棚 / ぼくは欠陥品なのかな? / 15才 / 大切な人がいなくなるということ / もっと世界を知りたい! / 旅は終わらない
あわせて読みたい