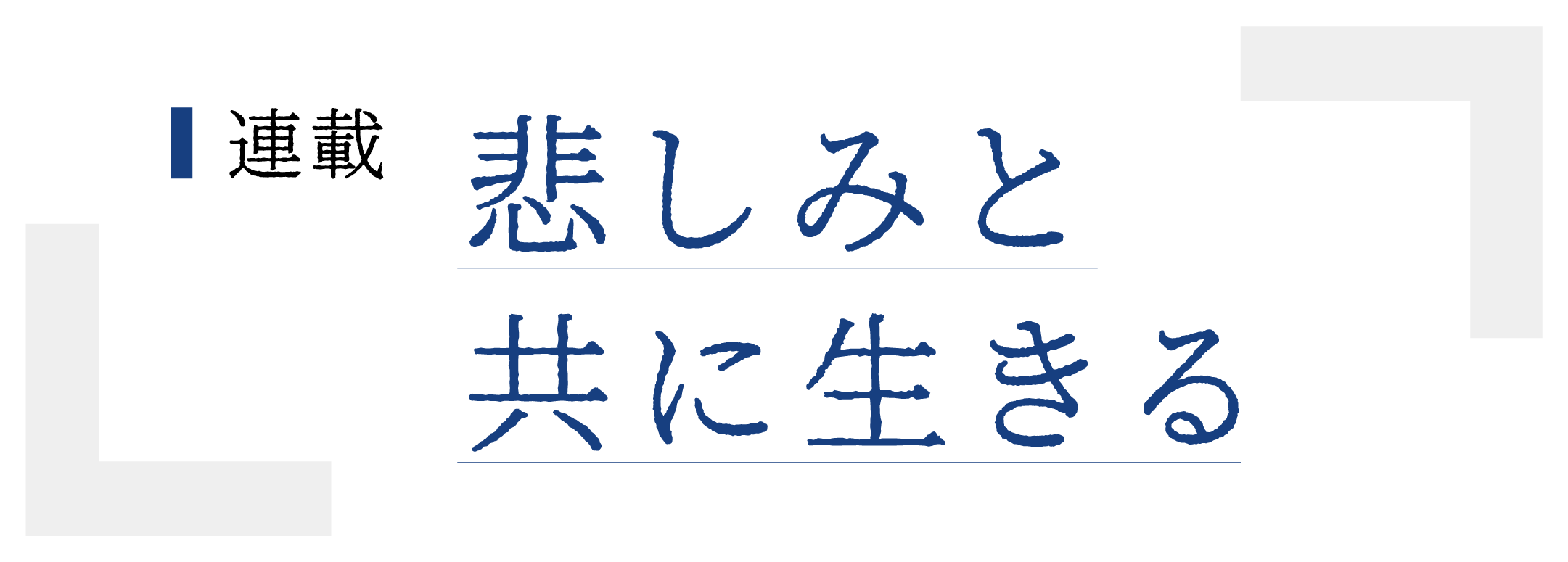本連載では、グリーフケアにまつわる人々へのインタビューを通し、喪失体験と共に生きる人々の姿をお伝えしていきます。第5回は、執筆活動と並行して、絵本・木のおもちゃ・オーガニックの専門店「クレヨンハウス」を主宰する、落合恵子さんにお話を伺います。7年間の母の介護、そして死別を通して感じてきたこと、グリーフケアにおける絵本の役割などについて語って頂きました。
本文中には身近な人の死や、自死に関する記述がございます。そうした内容により、精神的なストレスを感じられる方がいらっしゃる可能性もありますので、ご無理のないようお願い致します。

「いつか終わりがくる」ということ
―お母さんの介護を綴った『母に歌う子守唄 私の介護日誌』とその続編を拝読しました。7年間という介護の日々の中で、落合さんはどのように別れを意識しながら過ごされてきたのでしょうか?
当初は新聞の連載だったということもあり、暗い方向に行きそうな時は、文末でふっと肩の力が抜けるように、ということを心がけて書いていました。介護されているかた、しているかたも読んでおられるかもしれないので。従って、必ずしも自分の気持ちを100%忠実に描けたかというと、自分でもわかりません。介護は、けっして軽やかにはいかないことのほうが多いので。一昨年に刊行し、この春文庫になった小説、『泣きかたをわすれていた』(河出書房新社)で、ようやく心の蓋を全開できたと感じました。
今振り返ってしみじみと、私は“予習”の時間を母から贈られたのだと考えています。ひとつは私自身の老いについて。もうひとつは、「いつか母はいなくなる。その、いつかは明日かもしれない」と。そうした予感をいつも持って暮らすのは、それはそれで辛いことではありましたし、大切な人を失ったという喪失の悲しみは変わらずあるのですが、やがて来るであろう“その日”を予期しながら過ごせたということは、たとえば災害や事故などで、突然別離を迎えることと比べると、また違った喪失感であったかもしれません。
―過去の思い出や語彙の記憶が薄れていくお母さんとの時間は、『あいまいな喪失』と向き合う日々でもあったのではないでしょうか?
▶︎あいまいな喪失
ポーリン・ボス(Pauline Boss)は、あいまいな喪失(ambiguous loss)という概念を提唱している。あいまいな喪失には、①身体的には不在であるが、心理的に存在していると認知されることにより経験される喪失(たとえば、行方不明者の家族)と、②身体的には存在しているが、心理的に不在であると認知されることにより経験される喪失(たとえば、認知症患者の家族)が含まれる。あいまいな喪失を経験している人は、状況の不確実性の継続に困惑し、無力感や、抑うつ、不安などを示しがちであり、家族内での葛藤が生じることもある。(『死生学のフィールド』石丸昌彦・山崎浩司著、2018年、放送大学教育振興会)
たとえば、人が持っている、生きていく上でのエネルギー、キャパシティのようなものが「50」だとすると、毎日それが「0.5」ずつ、あるときは「1」ずつ減っていくということを実感せざるを得ない日々でした。それも辛いことではありましたが、一方で「人が老いていくということ」、あるいは「病と共に生きること」を学ぶ機会でもありました。私自身がどのように自らの老いと向き合うかということ、そしていのちには「いつか終わりがくる」ということを、手渡されたように思います。

“終着”までに味わう様々な悲しみ
―医療の方向性や治療法などを、お母さんに代わり決断しなければいけなかったということには、どのような葛藤がありましたか?
母は私が小さなころから、「あなたの人生なんだから、あなたが決めなさいよ」ということを言い続けてきました。子どもの私は母の言葉を信じて、そのように暮らしてきたと思います。ところが、母自身が老いて病を得た瞬間に、母の人生でありながら母自身で決められないことがある……。その現実は、とても衝撃的でした。自分の病の治療法から、薬を飲むか、あるいは飲まないかまで……。
「胃ろう」というものがありますよね。胃に穴を開けてそこにカテーテルを入れて、栄養をとる方法です。母は望まないだろうと想像はできても、その証拠はない。そう、単なる想像でしかないのです。結局は選ばざるを得なかった。そのようなことの繰り返しで、「自分の人生は自分で決める」という母が、選べない状況の中にいるのです。
戦争や自然災害、原発事故などで、選びようもなく日常がある日突然変わってしまうということもありますが、表面的には平穏な日常を重ねているつもりでも、個別の人生の中には、そうした「自分で選べない」状況がありえるのだということを感じました。
私の中で大きなショックとして残っている記憶の一つは、ある日、母がまじまじと私を見つめて、「お母さん?」と呼んだことです。そうした状況も十分想像してましたし、介護体験や手記の中にも出てくることなのですが、やはり動揺してしまいました。
人がどこを、なにを人生の“終着”と呼ぶかは様々だとは思いますが、その“終着”に辿り着くまでに味わうであろう「悲しみ」、あるいは「無念さ」、そして周囲がそれを見てどのように感じるかということは、十分に味わわせてもらったなと思います。
それでも私の場合は、長い介護の時間があってそれから、のことでした。それが突然の別離だったとしたら……。私はいったいどのように思ったか、わかりません。

私の悲しみは私のものである
―あらがうことのできない選択が人生にはあるということですが、落合さんはそんな日々の中でも、お母さんの感性を大切に過ごされていたということがエッセイから垣間見えます。
たとえば嚥下したものが逆流を起こし、母が緊急入院したことがありました。退院しても口から食べたり飲んだりすることが難しく、鼻管を入れたままの状態だったのですが、管を通して高カロリーの液体を落とすということだけではなく、僅かでも「口から食べる喜び」を捨ててほしくなかった。それで母の好きだったポタージュをゼリーにして食べてもらったり、シャーベットを少し口の中に滑り込ませたり。
どんな状況であっても、日常の中に喜びを見つけようとするのは、私の基本的な性格なのかもしれません。どれだけしんどいことがあっても、きっと何か美しいものがあるだろうと思ってきましたし、事実そうでした。言葉を失った母がにこっと小さく微笑むだけで、何だかその日一日が満ち足りた気持ちになったり、母の大事にしていた球根が、季節が廻り花をつけるのが嬉しかったり……そうした瞬間をすべて大事にしたいと思ってきました。
それと同時に、そうした身近な日常に意識を向けることによって、「わたしは逃げてるんじゃないか?」という不安もありました。現状が辛すぎるので、花鳥風月に逃げ込んでいたのかもしれません。
ちょうど母の介護をしていた頃、いまでもそうですが、政治がキナ臭い方向に向かっていって、色々な異議申し立ての運動が行われていました。私もそうした場に呼ばれることがあったのですが、母のこともあり、どうしても「行きます!」とは言えずに、「行けたら行きます」と中途半端な返事しかできない。私は自分のことしか考えていないのではないか、と。「花が咲いたよ」と笑顔で告げつつ、心の中にはトゲを抱えているような。
―そうした日々の悩みや葛藤は、どなたかと共有することはできていたのでしょうか?
同じような体験をしてきた友人たちもいましたし、「ある部分は共有できる」ということはあったように思います。けれど、自分の心の本当に奥深い部分というのは、共有できた、できないということではなく、「言葉にできなかった」ような気がします。
「これは私が背負っていくしかない」という思いが強くありました。私がひとりっ子だったことと関係しているのかもしれませんし、良いことなのかどうかはわかりませんが、「自分の悲しみは自分で背負うしかない」と、どこかで学んできて、それが性格の一部になっていたのかもしれません。
喜びとか、嬉しいことは共有できるのに、悲しみを人と共有するのが私は苦手なのかもしれません。きっとそれは、「これが私の悲しみです」と、掌に載せて見せた瞬間に、それを差し出された側がとても辛いと感じてしまうんじゃないか、負担になってしまうんじゃないかという思いがあるんだと思います。自分の心の渦に、相手を巻き込んでしまうことが怖かったんですね。
でもそれと同時に、「その悲しみでさえも、私は十二分に味わいたい」という思いがあったことも確かです。もっと積極的な意味で、私の悲しみは私のものである、という感覚も強く持っています。
母を見送った空洞は、たぶんわたしが生きている限り、埋められないものに違いない。愛するひとを見送ったすべてのひとはその空洞を抱えて生きていくのだろう。
時を経ても、わたしは母を想い、時々は号泣するだろう。けれども、その空洞も耐えがたい喪失感も、悲しみもまた、忘れたくはない私がいる。ずっともっていきたい。ずっと抱きしめていたい。それが、血縁、結縁に限らず、愛するひとを「見送る」ということなのかもしれない。
―『母に歌う子守唄 その後 わたしの介護日誌』著:落合恵子(朝日新聞出版)
構造的な社会問題と医療
―エッセイの中では、医療の在り方についても触れられています。果たして現代の医療というものが、きちんと目の前の人間に対する想像力や共感といったものに根ざしているのかと問うと、必ずしもそうではないと感じられたということでした。
そうした靴擦れのような感覚を、介護を通して感じたことは少なからずあります。でもそれは、医師や看護師さん個々人の問題というよりも、構造的な医療行政の問題が大きく影響していると思います。現在のコロナ禍でも、頑張って医療を支えてくださる現場の方がいる一方で、そうした方々自身が、あらゆる意味で充分なケアを受けられているのか、まっとうな労働環境や制度に支えられているのかというと、疑問を抱かざるを得ないと思う。
そうした現状の中で、目の前の患者を、そうでありたくないと思いつつ、「効率的に」診ていかなければならないといった現実もあるのだと思います。ただ、「あなたたちが診ているのは、それぞれ長い個人史を持った人間なのだ」ということを、常にというわけにはいかなくとも、一瞬でも良いから思い浮かべていただきたい。そのために、わたしたちは何ができますか? 何をしたらいいですか? とお訊きしたい。私たちがどのように声をあげれば、風穴をあけられるか、とわたしたち自身も考えていきたいです。
―そうした大切なものを切り捨てざるを得ないような、「社会構造の変化」というものは感じられますか?
表現が適切かどうかはわかりませんが、誰かが椅子を必要としているだろうときに、立ち上がって「どうぞ」と言える自分自身であるだろうか、と考えています。社会構造は以前からそうだったのかもしれませんが、「椅子取りゲーム」の“勝ち組・負け組”意識はまだまだ続いているような。ひとつ前の政権も、現政権も、勝ち組になれば何でもあり、という社会を具現化しているような。無念です。
非正規の若者の困難や、正規の仕事に就いていたとしても、非常に多くの理不尽な現実がある。あるいは教育システムの中で傷ついている子どもたちもいる。貧困問題もそうです。
高齢者だけが辛いという社会ではありませんが、「今まで大変なこともあったけれど、長生きして良かった」と高齢者が思える社会は、高齢者から一番遠いところにいる世代である子どもたちが、「生まれてきて良かった」と思える社会と、どこかで繋がっているのではないでしょうか。
ところが今は、どの年代を見ても、呼吸が浅い。これが私たちが目指していた社会であり、人間関係でしょうか。特に社会的に周辺に置かれた人たち、声をあげにくい人々に、より過酷な状況が押し付けられていく社会に感じます。そしてそれを「自己責任」と呼ぶのです、不当なことに。

飾り気のない言葉
―効率化や新自由主義のようなものに切り捨てられがちなもののひとつに、「悲しみを悼む時間」があると思います。落合さんは著書の中で「穏やかな悲しみには、まだ辿りつけないでいる私がいる」と書かれている一方で、「彼に会ったら今度こそ一緒に暮らしなさい。……よかったら、も一度わたしを産むかい?」と、事情があって結婚できなかった母の冥福を穏やかに祈ってもいます。
本人はかなり照れながら書いているんですけれど(笑)。でも人間って、本当にギリギリの状況――愛する人を失うというのは、まさにそうしたギリギリの状況だと思うのですが――で掴めた言葉は、案外“はだかの言葉”で、飾り気のないものになるんじゃないでしょうか。
装飾的なものがすべて消えて、ただシンプルに「大好きだよ」とか、「ありがとう」「あなたに会えて良かったよ」とか、そうした言葉が出てきたのだと思います。一応もの書きでもあるので、もう少し言葉があるんじゃないかなとか思うこともあるのですが……(笑)。
「穏やかな悲しみ」に、今でも辿り着けているかはわからないです。ちょっとした拍子に、心に火がつくことがあるんですね。社会に対する憤りというか。たとえば今のコロナ禍にしたって、社会的立場の違いや経済的な状況によって、命の選別が行われているようなところがありますよね。たとえば米国で、デスクワークのひとのほうが、そうでないひとより感染率が低いとか。母もそうした社会に納得をしない人間だったので、きっと母が生きてたら、デモに行きたいと言っていたと思います。
そういうことを考えると、私が「穏やかな悲しみ」に辿り着くためには、そうした社会に異議申立てをし続けなければいけないし、なかなか辿り着けるものではないと覚悟しています。

グリーフケアの絵本
―クレヨンハウスには、グリーフケアに関わる絵本の並べられた棚がありますね
はい。あるとき、『ママのバレッタ』という絵本を出されているグループのおひとりが訪ねて来られました。キャンサーペアレンツのメンバーのかたで、看護師さんをされています。
『ママのバレッタ』は、がんになった親が、幼い子どもにそれをどのように伝えていくかということをテーマにした絵本なのですが、自分の最後を子どもに語っていかなければならない親の苦しみ、悲しみを想ったとき、私が置き去りにしてしまっているものがあるんじゃないかなと思ったのです。それは「私の悲しみ」だった、と気付きました。
悲しみには、親としての悲しみや、子どもとしての悲しみ、その中にもそれぞれ違った形の悲しみがあります。ところが今の社会は、「死」というものを語ることがどこかタブー視されている。語られなかった悲しみが、きつく心の奥底にしまわれてしまうことがあるんですね。
そうしたときに絵本には、「きつく閉まった蓋を開けてくれる」役割があるのではないかと思います。「死」というものを、もっと語っていいんだよ!と。
これはそうした悲しみに限らず、差別などの社会的な苦しみに対しても同じことが言えると思います。そうしたことに、ギクシャクしながらも、優しく窓を開けてくれるのが絵本という存在ではないでしょうか。
私の母はシングルマザーだったので、「シングルマザーの子どもでかわいそう」と言われるたびに、「私はかわいそうじゃない!」って怒る子ども時代の私がいました。あの頃に、いまここにあるような絵本に出会えていたら、もう少し違う風景が見えたんじゃないかなって思います。さいわい私は、「こういう風景もあるよ、こっちだけじゃないよ」と、いつも母に教えてもらうことができましたが……。
言葉にすることで、「悲しみが無くなる」わけじゃないんですね。むしろ、目を逸らすことなく、「悲しみがここに在る」と体感することができる。この“体感”が、大事なものじゃないのかなと思います。
―中でも大切にされている絵本はありますか?
スーザン・バーレイの『わすれられないおくりもの』という有名な絵本があります。アナグマが、自分はもうすぐ最後を迎えると知っていて、「長いトンネルの、むこうに行くよ」と。
残されたモグラやカエル、キツネなど、森の動物たちは寂しくて寂しくてしょうがない。でも最後に、「アナグマさんにこういうこと教わったよね」とか、アナグマさんの思い出を話し合うことによって、彼らなりにグリーフケアを行っていくんですね。
『ずーっとずっとだいすきだよ』という、ハンス・ウィルヘルムの絵本もあります。人間より早く歳を取ってしまう犬との出会いの中で、「大好きって何なんだろう?」とか、「別れって何?」というようなことを、男の子と一緒になって考えていくような絵本です。
こうした絵本は、もちろんこれまでにも存在していた絵本なんですけれど、それを今までは作者別とか、それぞれの棚に並べることが多くて。けれど、ひとりひとりがたどっていく「死への想い」のようなものを考えられるようなコーナーが必要だと、この棚が生まれました。
―落合さんが翻訳され、昨年末に日本でも刊行された『悲しみのゴリラ』(著:ジャッキー・アズーア・クレイマー)を読ませて頂きました。色彩も言葉も、悲しみをそっと包み込むような絵本だと感じました。
この絵本に出てくるゴリラは、お母さんを亡くした男の子が心の中に作り上げた存在なんだとも読めます。「悲しみっていつまで続くの?」「死ぬってどういうことなの?」っていう男の子の問いは、お父さんには訊きづらくて、ゴリラとの対話を重ねて行く。
(男の子)「ぼくのママ、しんだんだよ」
(ゴリラ)「そうだね しってるよ」
(男の子)「みんな しぬの?」
(ゴリラ)「そう だれだって いつかは死ぬんだ」
そうした会話が続いて、ようやくおずおずと父親と言葉を交わすことができるようになる。そして、父であり、夫であるひともまた悲しみの中にいるのだということに男の子も気づき、気持ちがひとつになっていくんですね。息子と父がいっしょにゴリラに抱きしめられながら。
小さな子どもだけではなく、大人だって、きっとこうしたゴリラのような存在が必要なんだと思います。

『悲しみのゴリラ』(作: ジャッキー・アズーア・クレイマー/絵: シンディ・ダービー/訳: 落合恵子/出版社: クレヨンハウス)
深呼吸のできる社会を
―クレヨンハウスの会社案内には、「もっと楽しく、もっと深呼吸のできる、拓かれた文化をつくっていきませんか?」と書かれています。この「もっと深呼吸のできる」という部分は、グリーフケアを考えるうえでも非常に大切なことだと思います。
人は肉体的にも精神的にも、追いつめられると呼吸が浅くなりますよね。社会がもう少し、深呼吸のできるところであってほしいと思います。一握りの人間が得をして、だれかにそのしわ寄せの行く社会は、アンフェアだと思います。
今の私たちの社会に欠けているものがあるとしたら、それは希望であり、信頼であり、他者へのほんのわずかな「どうぞ」という想いとアクションかもしれません。
加齢はいやではないのですが、最近はあと何年元気でいられるだろうかって考えます。もうそんなに沢山はないかもしれない。けれど、「だからこそ、私は最後の数ページをここで踏ん張っていきます」と、自分と約束できる。
私にとっての「穏やかな悲しみ」、グリーフケアの道程というのは、誰かが理不尽な扱いを受ける社会に、「異議あり!」と手と声をあげ続けることと両輪になっているんです。そのように声をあげ続けていくことが、私にとっての「生きる意味」に繋がっているのだと思います。
【プロフィール】
落合 恵子(おちあい・けいこ)
1945年生まれ。執筆と並行して、東京青山、大阪江坂に クレヨンハウスを主宰。総合育児雑誌『月刊クーヨン』、 オーガニックマガジン『いいね』発行人。 社会構造的に『声が小さな側』の声をテーマにした作品が多い。 主な著書 『明るい覚悟』、『母に歌う子守唄』、『泣きかたをわすれていた』他多数。
▶クレヨンハウス
(2021.4.8 / インタビュー 佐藤慧、写真 安田菜津紀・佐藤慧)
【支援・相談窓口/参照リンク】
▶︎ 全国自死遺族総合支援センター
身近な人を自死(自殺)で亡くした方のつどいに関する情報や、相談先が記載されています。▶︎ 自殺対策支援センターライフリンク
「生き心地の良い社会」の実現をめざし、自殺対策、「いのちへの支援」に取り組んでいるNPOです。○ 相談先リンク
▶︎ 電話相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)
▶︎ SNS相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)○ グリーフケアについてもっと知りたい方へ
▶ 上智大学グリーフケア研究所
▶ 一般社団法人The Egg Tree House
あわせて読みたい・聴きたい
■ 連載「悲しみと共に生きる」 (※記事は順次更新して参ります)
■ 【Radiotalk】「グリーフケア」を学びながら[2020.8.28/佐藤慧]
「それぞれの声が社会をつくる」
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。