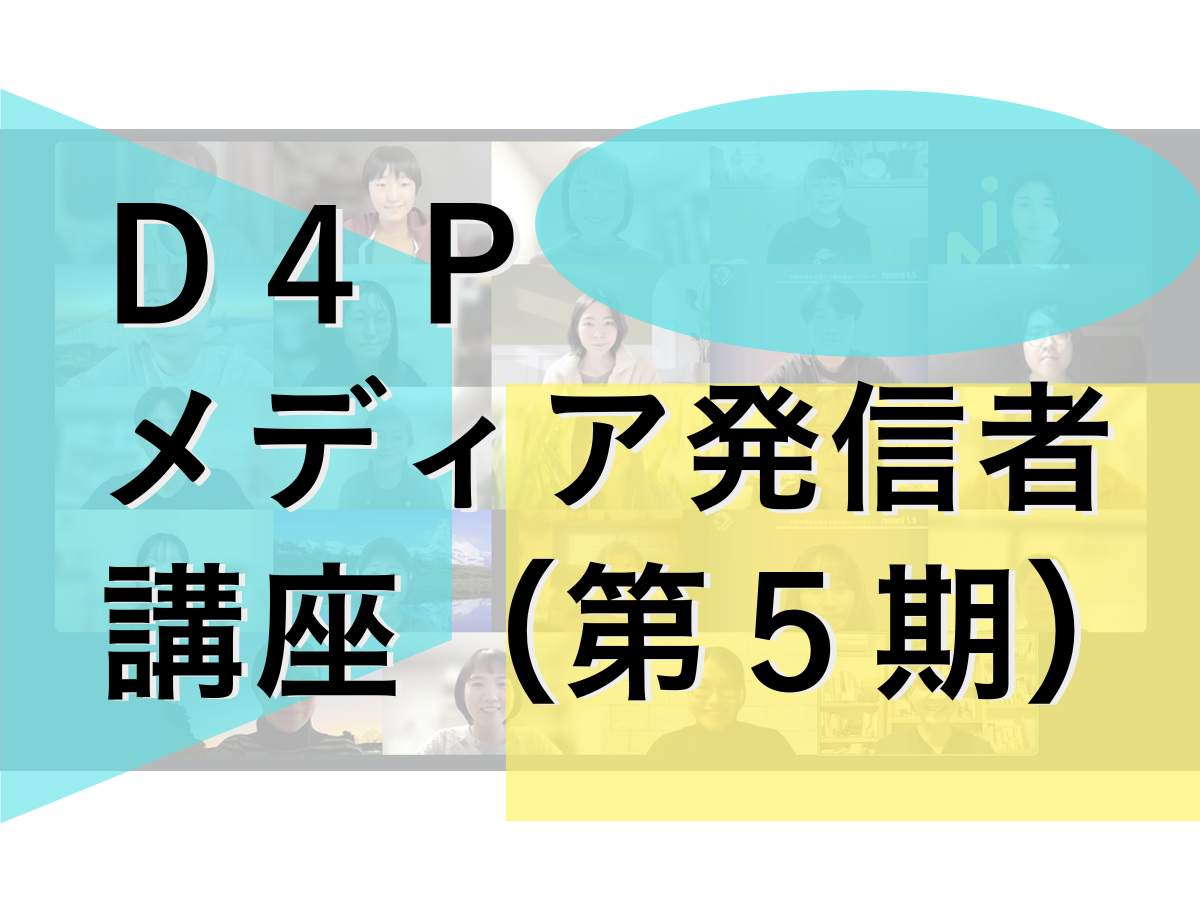「人間の歩みは社会の映し鏡そのもの」―深沢潮×安田菜津紀 『国籍と遺書、兄への手紙―ルーツを巡る旅の先に』刊行記念トークイベント
Dialogue for People 副代表でフォトジャーナリストの安田菜津紀による新刊『国籍と遺書、兄への手紙―ルーツを巡る旅の先に』の刊行記念トークイベントが2023年5月21日、東京都渋谷区の青山ブックセンター本店で開かれました。在日コリアンや女性をテーマに描いてきた小説家の深沢潮さんをゲストに迎え、安田が新刊の中で綴った「ルーツを巡る旅」を軸に、在日コリアンへのヘイト問題や、「なかったこと」にされてきた市井の女性の存在などについて、たっぷりと語り合いました。

東京都渋谷区の青山ブックセンター本店にて。左が深沢潮さん、右が安田菜津紀。(撮影:佐藤慧)
Contents 目次
「人間の歩みは社会の映し鏡そのもの」
安田の父親は、自身が在日コリアン2世であることを語らずに、安田が中学生の時に亡くなりました。「父はなぜ自身の出自を娘にも語らなかったのか」「そこには一体どんな社会背景があったのか」――。その疑問に端を発し、始まったのがこの新刊にまとめられた「ルーツを巡る旅」でした。
「古い書類をかき集めたり、実際に書類に残された住所地などをたどって韓国の親戚の元を訪ねたり、ということがこの1冊の中に詰まっています」と安田は会場に集まった人々に説明しました。その旅の中で、深沢さんにも相談に乗ってもらったといいます。
さらに、新刊に込めた思いを安田はこう語りました。
「人間の歩みって社会の映し鏡そのものだなというのが、私自身の実感です。個人の旅ではありますが、より社会に開いたテーマを皆さんに感じていただけたらなと思いながら綴りました」
「旅」の始まり
安田は中学2年の時に父親を、中学3年の時に兄を亡くしました。
深沢さんも8歳の時に3つ上の姉を亡くしています。
『国籍と遺書、兄への手紙―ルーツを巡る旅の先に』を読んだ感想について、深沢さんは「まず『喪失』というものを感じ、そこから長い時間をかけて回復されていると感じました」と述べました。「痛みや葛藤が滲み出ていて、強い心の叫びのようなものも感じました」。
それを受けて安田は、父や兄の死に対して「蓋をしてきた」といいます。
「向き合うには『しんどさ』があることはもちろん、その空白を埋めるための手立てを知らなかったということがすごく大きかったです。戸籍を見て『えっ、韓国籍?』と、アイデンティティーの前でフリーズするという高校時代でした」
戸籍に記されていたのは、父が韓国籍であるということ、そして、祖父母の名前のみ。朝鮮半島のどこから、いつやってきたのか。どんな人だったのか――。ひとりの人間としての息吹はその戸籍からは感じることはできなかったと振り返りました。
その後、時を経て3年ほど前、出生地や住所などが記録されている「外国人登録原票」の存在を友人から教わり、「旅」が始まりました。
自身のルーツへの「気づき」――「日本人じゃない」
深沢さんの父親は在日1世、母親は在日2世で、深沢さん自身は1994年に日本国籍を取得しました。
深沢さんは幼稚園か小学校に通っていた頃、自分のことを「日本人じゃない」となんとなく気づいた瞬間があったそうです。
ある日の給食の時間。深沢さんは自分のスプーンが配膳されていないことに気づきました。家で言うのと同じように「スッカラ(韓国語でスプーンの意)ちょうだい」と言うと、だれからも反応がありませんでした。「何で通じないんだろう」。家に帰って母に尋ねると「その言葉は学校で言っちゃいけない。スプーンって言うんだよ」。
これをきっかけに、在日コリアンである自身の生い立ちやルーツについてさまざまな「気づき」が始まっていったと振り返りました。

様々なエピソードを交えながら自身のルーツについて話す深沢さん(奥)。(撮影:佐藤慧)
父の人生を知ることで「自分を肯定できた」
深沢さんは父親から人生の歩みを聞き取り、それを基に小説『海を抱いて月に眠る』(文藝春秋)にまとめています。
安田は「今回の(ルーツを巡る)旅の中で特に強い影響を受けたのがこの本だった」と明かしました。「韓国の軍事政権下の中で、時には民主化運動の中で非常に厳しい体験もした方々の声がここに凝縮をされている」と本の内容に触れ、「父親の生きた証というものを手記をもとにしてたどるという1冊で、私自身が取り組んでいることにも重なるところがあって、本当に夢中になって読んだのを覚えています」と話しました。
続けて安田は「親にあらためてその道のりを聞くというのは、どういう感覚だったのかとても興味があるんですが」と尋ねました。
在日コリアンをテーマに作品を発表されている深沢さんですが、元々は、「民主化の闘いやデモなどに参加していない自分が在日のことを書いていいのか」という葛藤があったそうです。
しかし、父親の人生について話を聞いたことで、それまで疑問に感じていたこと――「父がなぜ私に日本国籍を取ることを許してくれたか」、「なぜ母が在日であることをそんなに隠そうと生きてきたか」――が「すごくいろいろ腑に落ちた」といいます。
「腑に落ちたら、こういう人生もあると自分を肯定できた。両親を理解できたし、肯定できたので、(小説に)書こうと思った」
つかめなかった祖母の手がかり
続いて、話題は深沢さんの新刊『李の花は散っても』(朝日新聞出版)に移ります。戦前、戦中、戦後の日本と朝鮮半島を舞台に、2人の女性の人生が錯綜していく物語です。
安田は今回のルーツを巡る旅の中で、祖父については情報が得られた一方、祖母の手がかりは掴むことができず「非常に心残り」といいます。
韓国・峨嵋洞で祖母の名前を伝えて聞き込みを続ける中で、ある男性はこう言いました。
「名前で呼ばれても、分からないな。女性を名前では呼ばないから」
深沢さんは、本の中で特にこの言葉が心に残ったといいます。
深沢さんの母方の祖父は大正時代に日本へ来て、後から祖母を呼び寄せました。
「私が小さい頃に聞いたエピソードで『祖母は外に出ない。女性は出歩いちゃいけない』という韓国の儒教の精神があります」。祖母は日本で暮らしていても、外にほとんど出なかったそうです。
深沢さんは、韓国の族譜(日本で言う家系図のようなもの)では昔、女性は名前でなく「女」としか書かれていなかったという背景に触れた上で「やはり女性は名前で呼ばれない」と力を込めました。
続いて、安田がこう投げかけました。
「特に家父長制と時代の狭間で、確かにそこに生きていたはずの女性たちの姿がなかったことにされたり、かき消されたりすることは、私も取材を通して感じてきました。だからこそ、男性目線で描かれる客体としてではなく、あくまでも、私はこう思う、こう感じるという『主体』として女性を描くということが、この『李の花は散っても』でも、力を入れられたのではないかと思ったのですが、いかがでしょうか」
深沢さんは「やはり過去の歴史的な背景を持った小説は、圧倒的に男性の語りが多いと思いますし、女性は添え物的だったりします。例えば独立運動に参加したとか、立派な女性の歴史は残ってるのですが、市井の女性のストーリーは少ないと思っていました」と答えました。
加えて、「私は(小説の中で書いている)人物との距離が近くないと書けないので、主人公はどうしても女性になることが多い」と、自身の創作スタイルについても触れました。
今と地続きの差別構造
ルーツを巡る旅の中で、安田は父親が生まれた京都にも足を運びました。京都府宇治市のウトロ地区や京都朝鮮第一初級学校を取材し、見えてきたのは朝鮮半島にルーツを持つ人々が標的にされた、凄まじいヘイトクライムが続く現実でした。深沢さんの著作でも、同様の「差別」が描かれています。
『李の花は散っても』について、安田は「ここに書かれている差別の構造は、何もその時代だけの過去の話ではなくて、現代と地続きなんだということを意識しながら読みました」と話しました。

ルーツをめぐる旅から得た気づきを会場と共有する安田。(撮影:佐藤慧)
日本社会を少しでもよくするために
会場にはこの日、約80人の参加者が集まりました。
質疑応答で、ある参加者は「日本社会を少しでもよくするために何をしていけばいいでしょうか」とふたりへ質問しました。2021年3月6日、名古屋出入国在留管理局収容中に亡くなったウィシュマ・サンダマリさんについて「これはウィシュマさんの問題ではなく、日本の問題だと思う」とも述べました。
パートナーからのドメスティック・バイオレンス(DV)被害を訴えていたウィシュマさん。安田は、ウィシュマさんに関して発信すると「たかがDVで」などの言葉が寄せられる現状について言及し、こう続けました。
「1にも2にも、振り向かせるのは市井からの声だと思います。『命に関わらない女性差別なんてないんだ』ということを無理なく、それぞれが持ち寄れる声を少しずつ持ち寄って、法律をつくる側を振り向かせること、向き合わせることがこれからますます重要になってくると、私自身は思っています」
続いて、深沢さんは「まず知ること。知って理解することが大事」と力強く答えました。
例えば、食や文化を通してさまざまな国や地域、そこに住む人々について知ることで「『多様なのって楽しい、面白い』と経験する機会が増えること」に期待を寄せました。加えて、小説などエンターテイメントでも、ただ作品を「消費」するのではなく、人権や差別をテーマに「立ち止まって考えられるような作品」が増えるといいと、小説家である自らにも向けながら語りました。
最後に安田はこの日集まった人々へ向けて、こう語りかけました。
「この本は私自身のルーツという非常にパーソナルなことを掘り下げたものではあるのですが、これからの社会をもう一度組み立て直していく上でヒントになったらいいなという思いを込めています」
(2023.11.14 / 田中えり)
『国籍と遺書、兄への手紙―ルーツを巡る旅の先に』 詳細はこちら
【プロフィール】
深沢潮(ふかざわ・うしお)
小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。
深沢潮さん、「食」テーマにエッセイを連載中
深沢さんは今年4月から、D4PのWebサイト上で「食」をテーマにしたエッセイを連載しています。エッセイの連載は、深沢さんにとって初めてといいます。タイトルは「李東愛が食べるとき」。「李東愛(イー・ドンエ)」は、韓国籍を有していたときの深沢さんの名前だそうです。
「食べ物の記憶は、幼い頃からの思い出や自分自身の人間関係と強く結びついています。このエッセイでは自分の中を掘っていくということも同時にしたいと思いました。李東愛として、自分への問いかけをしながら書いていきたいと思い、このタイトルにしました」
この日のトークイベントの中で、こう語っていた深沢さん。連載ではこれまで、キムチ、珈琲、寿司など食べ物や飲み物をテーマに、自身の思い出や現在につながる記憶を綴っています。
あわせて読みたい
■ 被爆2世、女性として直面した複合差別 ――「韓国のヒロシマ」陜川から[2023.2.26/安田菜津紀]
■ 学校支えるキムチ販売、輪の広がりの先に目指すものは[2023.1.14/安田菜津紀]
■ かつて、「隠れコリアン」だった。今なぜ、「ともに」のメッセージを川崎・桜本から発し続けるのか[2022.1.31/安田菜津紀]
■ 長生炭鉱水没事故――その遺骨は今も海の底に眠っている[2021.9.2/写真 安田菜津紀、 写真・文 佐藤慧]
D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています
認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。
認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。