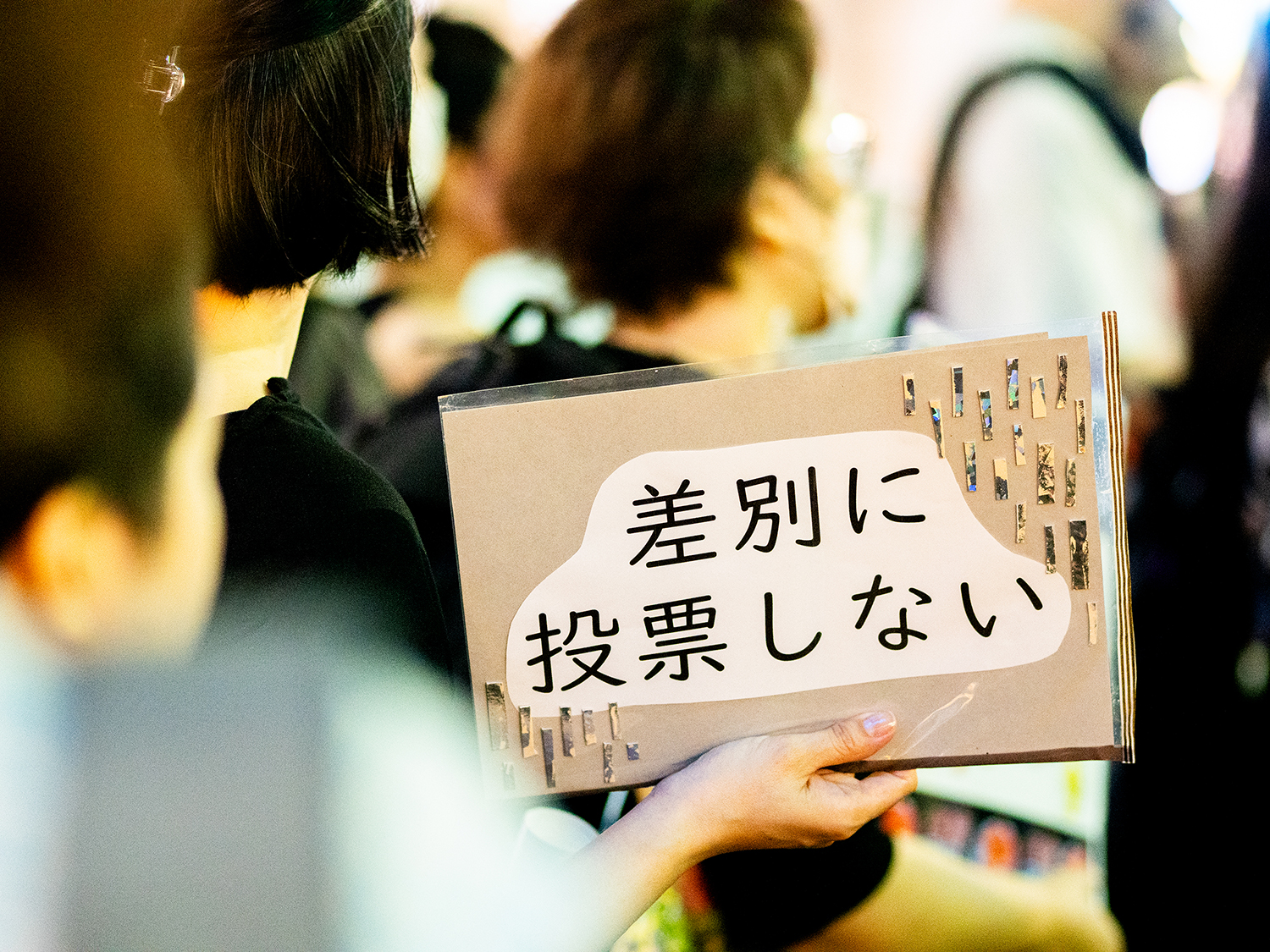「これは氷山の一角」ヘイト繰り返す男に被害者の住所を伝達、3歳の娘を警官ら複数人で聴取―これがなぜ「違法」ではないのか
この対応が違法でなければ、いったいこの社会で何が「違法行為」に該当するのだろうか。母子不当聴取裁判の一審判決では、原告の訴えが退けられた。

東京地方裁判所。(安田菜津紀撮影)
3歳の娘を警官ら複数人で聴取
事件を改めて振り返る。訴状や代理人弁護士らによると、2021年6月、都内に住む南アジア出身のムスリム女性、Aさんが近所の公園で3歳の長女を遊ばせていたところ、突然園内にいた男性B氏が大声を出して長女に近づき突き飛ばしたうえ、「(Aさんの長女に)息子が蹴られた」などと抗議してきたという。
Aさんは「長女は蹴っていない」と一貫して主張したものの、B氏から「ガイジン」「在留カード出せ」などと詰め寄られた。たまたま通りかかって英語で通訳をした別の男性Cさんによると、B氏は遠くからも分かるほどの大声で、Aさんたちに対し「ガイジン生きている価値がない」「ゴミ」「クズ」等、差別発言を繰り返し、「年収3000万円以下は人ではない」などの言動を続けていたという。
その後、B氏の通報で警察官が計6人、現場に駆けつけることになった。日本語でのコミュニケーションがほとんどできない長女に対し、警官は激しい口調で「本当に日本語しゃべれねえのか?」「どうせお前が蹴ったんだろう」などと発言したうえ、Aさんの帰宅希望を無視し、約1時間半にわたってAさんや長女を公園にとどめたという。
Cさんは、こうした態度を警官がとったことや、B氏の差別言動を止めなかったことに驚いたという。「警察官が穏やかな口調で話していたようなことを主張しているようですが、そのようなことは絶対にありませんでした」と、法廷でもはっきりと証言している。
Cさんによると、警官らは、Aさんの話を聞こうとする様子も、Aさんを滑り台近くに連れて行って状況を説明してもらうこともしていなかったという。
さらに警官らは、任意であることを伝えないままAさんと長女を最寄りの警察署に連行し、約3時間の事情聴取を行った。取り調べはAさんの母語ではなく、電話による英語での通訳だった。また、幼い長女がAさんから引き離され、ひとりで複数の警察官から聴取された場面もあったという。Aさんは抵抗したが、部屋から出ていくよう、警官らに強く言われたと語った。
この長時間にわたる聴取の間、トイレ休憩や食事をとることもできなかった。Aさんや娘さんはこの日、午前11時半頃から公園におり、警官らが公園にやってきたのは13時すぎ、そして自宅に戻ることができたのは夜の8時近かった。オムツ交換ができなかった娘の肌はかぶれていたという。
個人情報を同意なく伝達
弁護団は警察官の違法・不当な職務執行があったとして、2021年7月、東京都公安委員会に苦情申出を行ったが進展が見えず、やむなくAさんは9月、都に計440万円の慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
公安委員会からようやく回答があったのは、提訴後の12月に入ってのことだった。「係争中のため、回答を控える」――返ってきたのは訴訟に踏み切らざるをえなかったAさんを蹂躙するような言葉だけだった。警視庁も取材に対し、公安委員会とまったく同じ回答を繰り返し、具体的な実態調査や関係者の処分については明言を避けた。
警察側の姿勢から見て取れるのは、終始、B氏側の主張のみを鵜吞みにしていることだ。取り調べ中、警官らは、Aさんの娘さんが蹴ったことを認めさせようという態度で一貫していた。延々と聴取が続いた理由について、彼らは「事案が判明しないため」「新たな事案が確認できないため」と主張したが、「滑り台をのぼっておりた、娘は蹴っていない」以上の説明はAさんにできないだろう。
仮に子ども同士の接触が公園であったとしても、そのために6人もの警官が駆け付け、母子を夜まで聴取し続け、あげく娘ひとりを複数の警官が囲むのは「異様」だろう。
さらに警察は、Aさんが長女を監督できていなかったとして児童相談所に通告している。Aさんはそれらを否定しているほか、後日、児童相談所の職員が母語通訳を通してAさんに聴き取りをし、それ以上の対応が必要ないとして、ケースを終了している。
また、Aさんが拒否しているにもかかわらず警察側は、Aさんの電話番号をB氏に提供することを承諾しなければ帰宅させないなどと執拗に迫った。Aさんは最後までこれに同意していないが、Aさんが拒んでも、警官は「オワラナイ」「オワラナイ」と繰り返したという。
そして結局、警察側は電話番号だけではなく、Aさんの氏名や住所などの個人情報を同意なくB氏に伝達した。(警官自身も「住所」「氏名」など、一つひとつをAさんに意思確認していない、と裁判の過程で認めている。)それも、B氏の自宅までわざわざ、警官自ら出向いて渡しているのだ。
警察側は、B氏がAさんに対して民事訴訟を起こすと言っていたから、と説明しているが、わざわざ警察がその訴訟の先回りをして一方の便宜をはかったのはなぜなのだろうか。逆に、氏名など含めたB氏の情報は、警察からAさんにはいっさい伝えられていない。Aさんはその後、引っ越しを余儀なくされた。

裁判後に記者の取材に応じる原告のAさん。(安田菜津紀撮影)
「公権力は間違わない」という判決
ヘイトスピーチを繰り返すB氏を制止しないどころか、その訴えを鵜呑みにするような行動を続ける警察自身が、差別を内包しているのではないだろうか。現に法廷で、「なんでこんな外人いれるんだ」というB氏の発言について問われた警官の一人は、「差別発言ではない」と即答していた。
提訴後、取材に応じてくれたAさんは、「こんなことが世界のどこでも、誰に対しても起こってはいけないはずです」と訴えていた。B氏の異様な言動を目の当たりにした後、警察署では母から切り離されて警官に取り囲まれた長女は、トラウマを抱え、落ち込んだ様子を見せたり、逆に落ち着きをなくしてしまったりと、以前と様子が変わってしまったという。
「どんな国籍の人間に対しても、平等な権利が必要です。そうでなければ誰も安心してこの国に来たり、暮らしたりすることはできないでしょう」
しかしAさんの声を、裁判官らは受け止めなかった。2024年5月21日、東京地裁(片野正樹裁判長)は、原告の訴えを棄却した。
Aさんの3歳の娘をたったひとりで聴取したことも、Aさんの個人情報をB氏に手渡したことも、被告である都側は争っていなかった。けれども判決は、「公権力は間違わない」の一点ばりともいえるものだった。
「警察官らの主張をほぼ、事実として認定しています。警察が信じられない取り扱いをした、というのが本件の入口です。ところが判決では、警察官がそんなことをするはずがない、警察官の言っていることが正しいに違いない、というものでした」と、判決後の会見で、原告代理人を務める西山温子弁護士はこう語る。
例えば警官が、Aさんの娘に「どうせお前が蹴ったんだろう」と言ったことについて、その場に居合わせたCさんは、利害関係がない人物であることが認定されているものの、警官がそうした言動をするのは「いささか唐突」「警察官の所為としては不自然」としている。
しかし本当にその発言は、「唐突」で「不自然」なものだろうか。今年2月には、埼玉県蕨市でクルド人の排除デモを警備していた警察官が、差別に反対する市民たちに対し、「ザコども」と発言したことが分かっている。
「昨今レイシャルプロファイリングについての訴訟も起きています。公権力が差別的対応をとっていることがまさに、この社会で問題提起されています。その氷山の一角が、この事件だったのではないでしょうか」
判決でも、B氏による「乱暴な言動」は認定されてる。ところが、「AさんがB氏に個人情報の提供に同意した」という警察の主張が判決では採用されている。つまり、差別言動を繰り返す男性に、義務もないのに個人情報を提供したことに、警察の責任がないものと断じているのだ。
AさんにとってB氏に個人情報を知られることは恐怖でしかない。まさか、氏名、住所までが相手に渡ってしまうとは思わなかったと、法廷でも繰り返し主張していた。同じく代理人を務める中島広勝弁護士はこう語る。
「(Aさんは)警察に求められているのが、電話番号だけだと思っていました。現に『自分は日本語が話せない、相手(B氏)は英語ができない、電話番号を伝えても会話ができない』、と明確に伝えたとしています。この点については、取り上げられてもいません」

判決後の会見。前列右から2人目が西山弁護士、3番目が中島弁護士。(安田菜津紀撮影)
自らの権威性に無自覚な警察の態度
ほかにも、Aさんが「同意していない」と主張していたにも関わらず、「同意があった」と裁判所が認定しているものがある。
例えば警察署での写真撮影だ。Aさんの娘がその際、ピースサインをしたことをもって、判決は「ことさらに撮影を拒んだものではない」「警察官らに対して緊張や怯えの感情を抱いていたとまでは言い難い」としている。
弁護団によると、Aさんは「子どもは反射的にピースサインをするものだと思っていた」のだという。実際、警察署では泣き出した場面があることも認定されている。子どもの「ついしてしまう仕草」を、公権力がこうした聴取の正当性として持ち出すことには違和感がある。
西山弁護士もこう指摘する。
「公園で帰宅を申し出たことも認められていますが、結果として警察署に行くことに応じているから同意があったとされています。けれども外国人で日本語の分からない母子と警察との間には、圧倒的な力の不均衡があります。これで、断れる状況だったのでしょうか」
「もしも仮に同意があったとして、3歳の女の子をたったひとりにして聴取するのは、誰の目から見ても適切ではないでしょう」
裁判の過程で警官のひとりは、「食事や休憩が必要だったら原告から言うだろう」と語ったが、自らの権威性に無自覚な発言ではないだろうか。
差別と不平等、不正義や抑圧を助長する判決
さらにこの裁判は、警察の母子に対する扱いが、人種差別にあたるかを問うものでもあったが、その点は「門前払い」となってしまった。
「人種差別撤廃条約上、公務員側に差別的な意図があろうがなかろうが、助長された結果が残っていれば、それは差別であり、違法であるということが、国際人権法上の常識であるはずです。警察がAさんの情報をB氏に渡したことで、B氏は警察が便宜をはかってくれたと感じたのではないでしょうか」
判決後のこの会見では、Aさん自身も発言した。
「今日の裁判の結果は、差別と不平等、不正義や抑圧を、日本にいる外国人に対して助長するものでした」
西山弁護士は、脆弱な立場にある人々が救われない現状に、こう警鐘を鳴らす。
「原告にとって裁判は、相当の負担があることです。Aさんは事件の翌日から、自力で法務局などに電話をかけるなどして被害を訴えようとしました。弁護団が関与してからも公安委員会に訴え出ていますが、それでもとりあわれませんでした。国内人権機関の創設が急務ですが、それが現時点では存在しない以上、司法が砦だったはずです。これでどうやってこの国で、弱い立場にある人が、被害の救済を求めればいいのか――この判決は、同じような被害に遭っている人を、萎縮させるのではないでしょうか」
Aさんは以前法廷で、「この国が正義の国であることを信じている」と語っていた。この日の会見でも、「日本のみなさん、外国人のみなさん、平和や正義、平等、そして日本に暮らすあらゆる人の人権擁護のために、連帯していきましょう」と呼びかけた。その「正義」と社会の公正さが今、問われている。
Writerこの記事を書いたのは
Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda
1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。
(2024.5.20 / 安田菜津紀 )
あわせて読みたい・聴きたい
■ 差別の放置はやがて、醜い怪物となる――絵本『ママたちが言った』著者、アリシア・D・ウイリアムズさんインタビュー[2024.4.8/D4P取材班]
■ 早稲田大学構内でのイスラエル大使館共催イベントで、なぜムスリム学生に対し荷物検査や警察への通報がなされたのか[2024.4.2/安田菜津紀]
■ 公権力による差別に抗うために――身近なところから社会の仕組みを変えていく[2022.11.10/佐藤慧]
■ 国連が日本に創設を求める「人権機関」とは? なぜ法制化が進まないのか?[2022.11.7/安田菜津紀]
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。