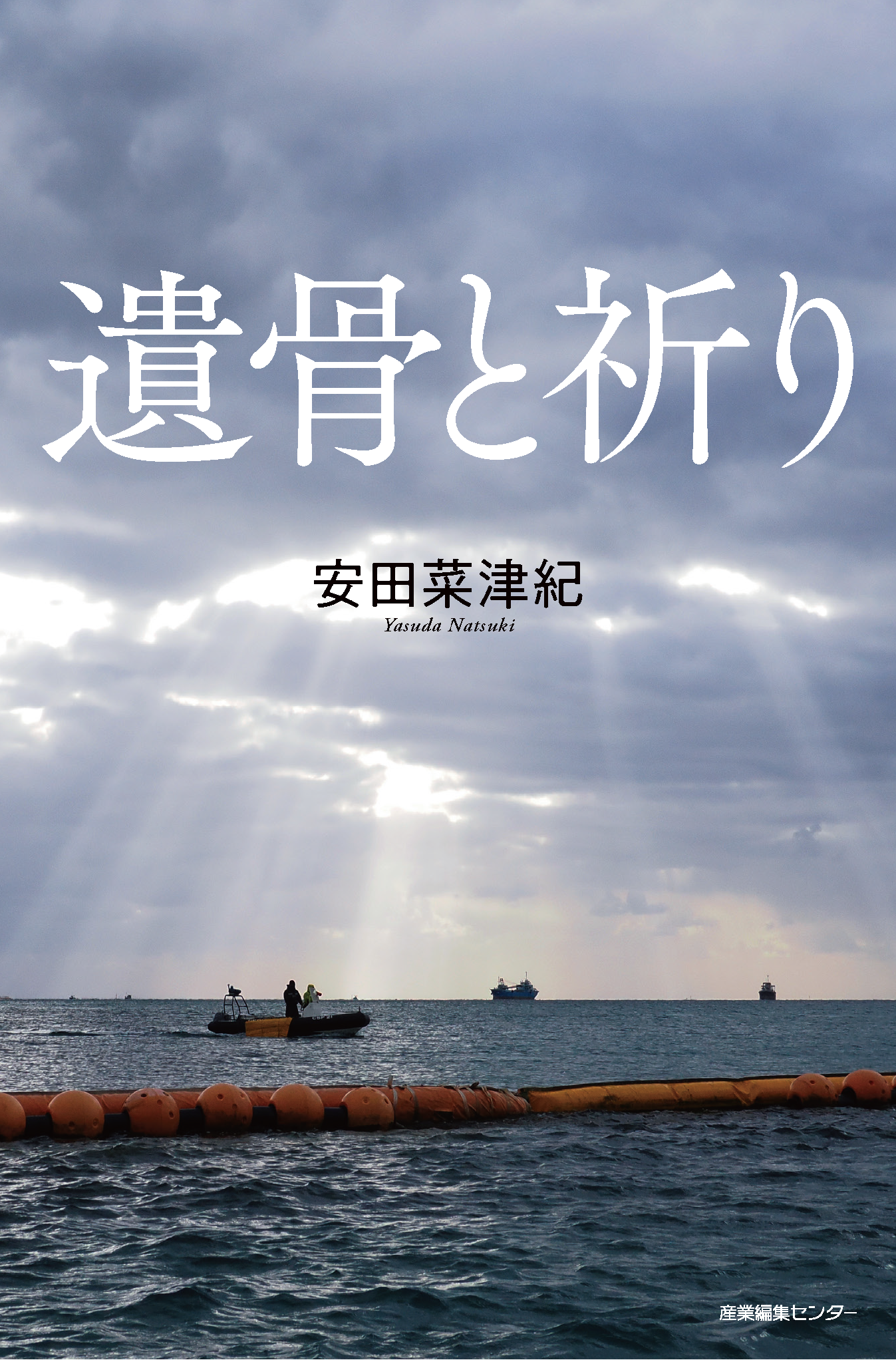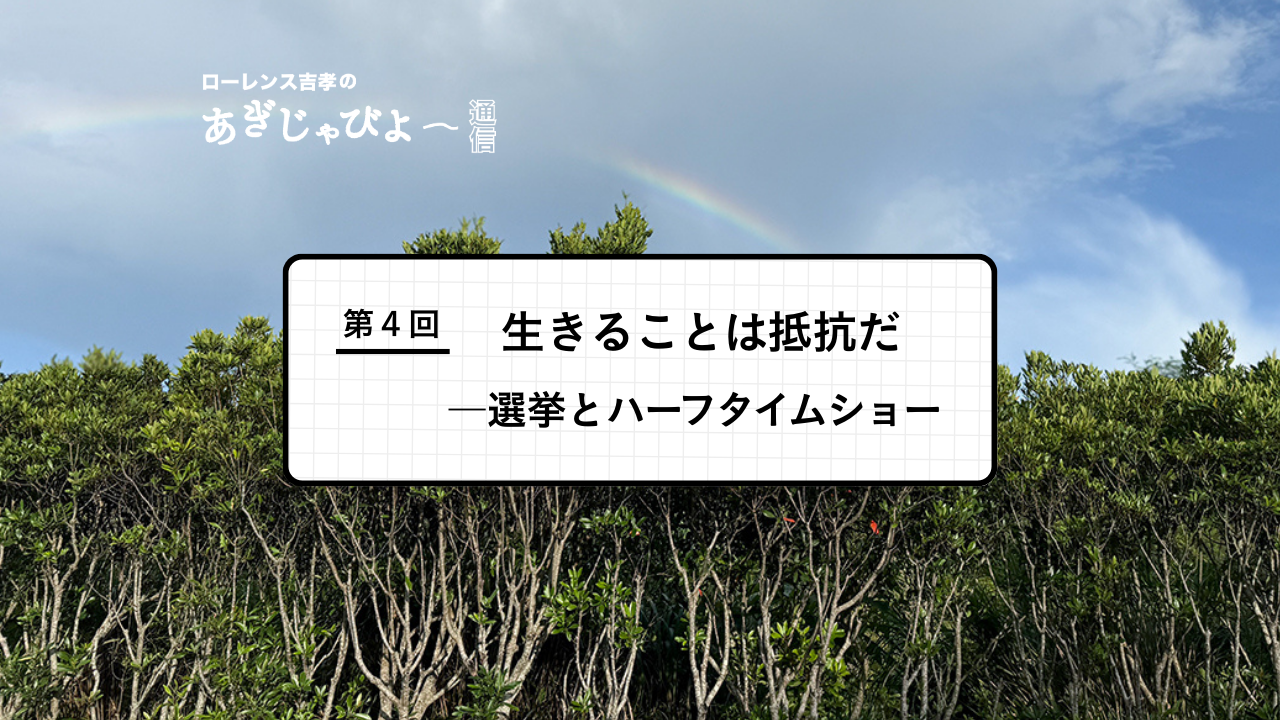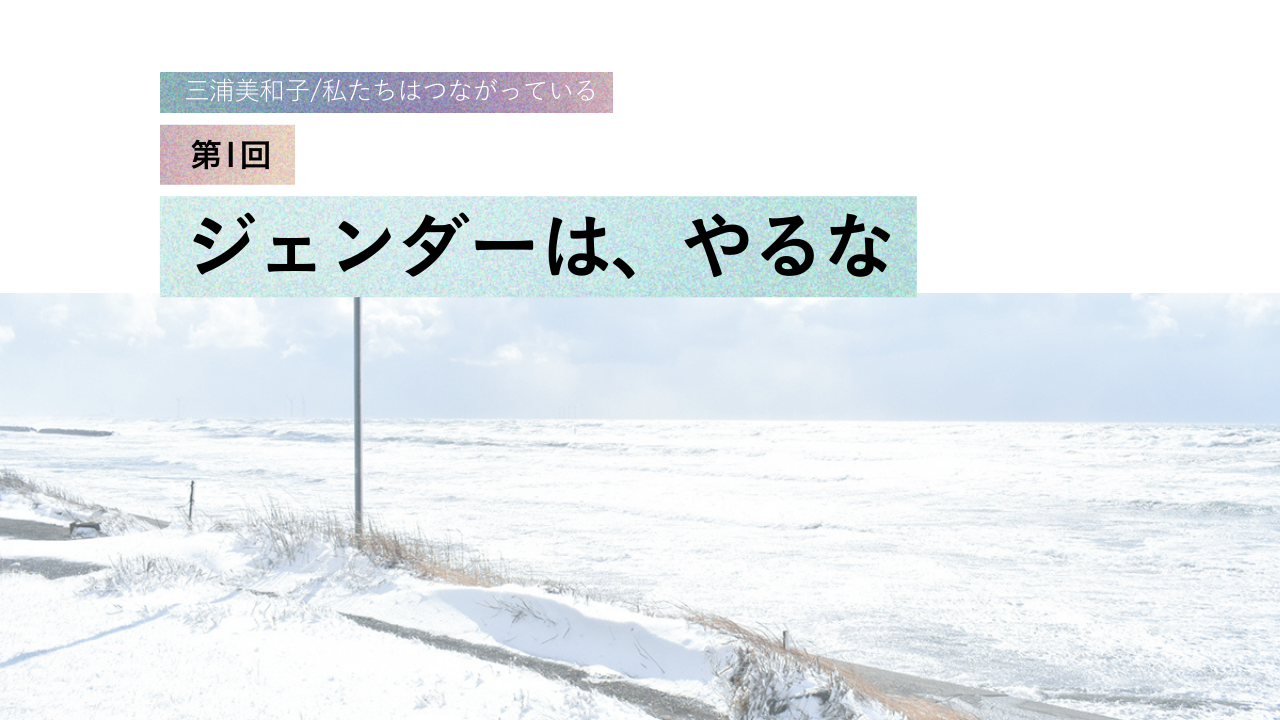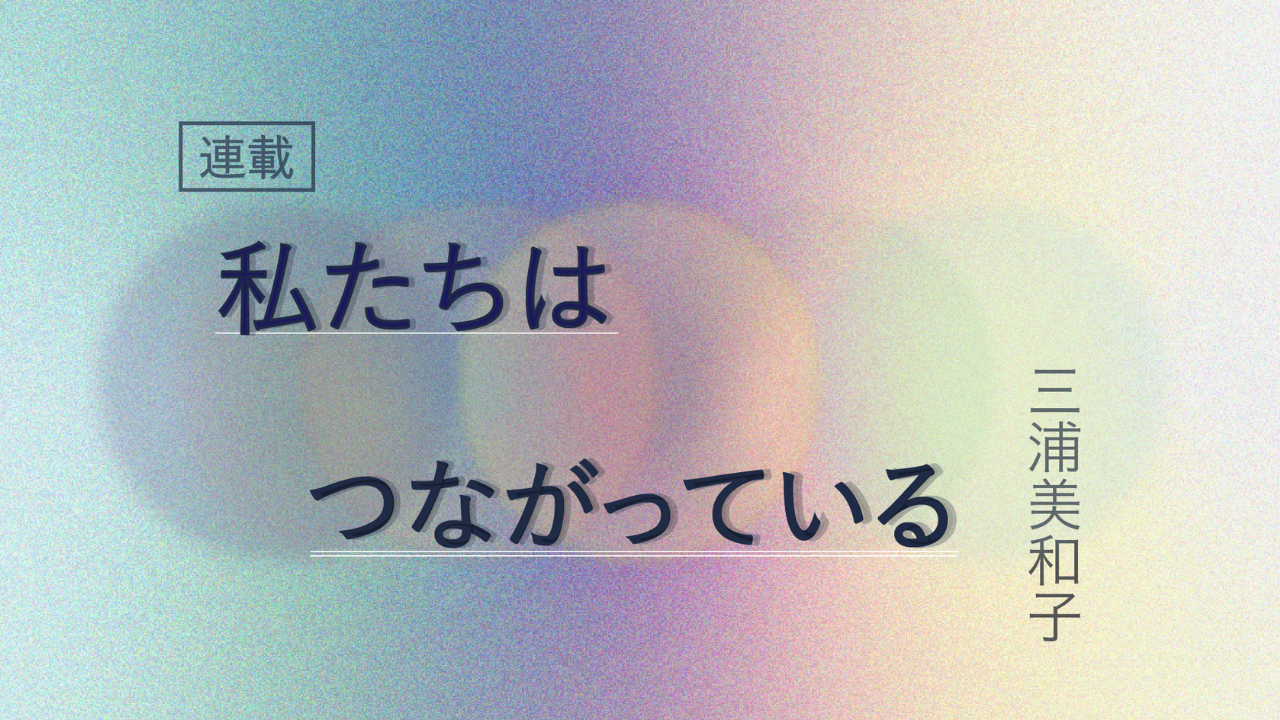「不条理」の上に成り立つ「平和」とは―『遺骨と祈り』対談 安田菜津紀×田中美穂

本記事は2025年7月27日に広島のSocial Book Cafeハチドリ舎で開催された《安田菜津紀新刊『遺骨と祈り』出版イベント》の内容を記事化したものです。Social Book Cafe ハチドリ舎は、「真面目な話も気軽にできる場所」として2017年にオープンしました。 社会の構造的な問題と個人の苦悩は切り離せないという考えのもと、対話を通じて個人の視点を深め、社会をより良くしていくことを目指しています。
死者をないがしろにする社会が、生きた人間の尊厳を守れるのか――? 安田菜津紀が、福島、沖縄、パレスチナを訪れ、不条理を強いられ生きる人々の姿を追った、6年間の行動と思考の記録。
原発事故で娘・汐凪さんの捜索を阻まれてきた木村紀夫さん。沖縄で遺骨収集を続け、辺野古基地建設が戦没者をも冒涜しながら推し進められようとすることに抗してきた具志堅隆松さん。具志堅さんが福島県大熊町を訪れ、帰還困難区域で汐凪さんの大腿骨を発見したのは2022年1月のことでした。
この本は当初、木村さんと具志堅さんの交流を軸に編む予定でした。ところがパレスチナ・ガザ地区での虐殺が起き、ふたりもその不条理と向き合うことになります。
新刊書籍【2025年5月22日発売】
『遺骨と祈り』安田菜津紀・著
(産業編集センター)1,760円(税込)死者をないがしろにする社会が、生きた人間の尊厳を守れるのか?安田菜津紀が、福島、沖縄、パレスチナを訪れ、不条理を強いられ生きる人々の姿を追った、6年間の行動と思考の記録。今起きている民族浄化と人間の尊厳を踏みにじるあらゆることに、抗う意思を込めた一冊です。
「踏んでいる側」としての自覚
田中美穂(以下、田中):みなさん、こんばんは。「カクワカ広島」共同代表の田中美穂です。私たちは、なぜ日本が核兵器禁止条約に参加しないのかというシンプルな疑問から2019年に活動を始めました。「核なき世界を」と言いながら、核抑止に依存していく日本の姿勢はおかしいのではないか。80年前の出来事ではなく、現在の問題として声を上げていきたいと思っています。
実は私も活動を始める前は、核兵器問題に特に興味があったわけではありませんでした。広島を初めて訪れたのも大学生の時です。でも、活動を通して被爆者の方々と出会い、海外にも被爆者がいること、今も被爆者と認められていない人がいることを知った時、これは単なる安全保障の問題ではなく、尊厳や人権の問題だと気づきました。
自分自身も、核に頼る社会に「乗っかってきた」「踏んでいる側」なのだという自覚を持つこと。そこから始めなければ、何も変わらないと痛感しました。『遺骨と祈り』も、そうした点を軸にしながら、福島、沖縄、そしてパレスチナを繋ぐ書籍で、安田さんが記事でいつも書かれている「地続き」というキーワードが大切だと思います。
安田菜津紀(以下、安田):「地続き」という言葉は、まさに私たちの状況を表していると思います。私自身は沖縄に基地負担を押し付けている「本土」に暮らしていますし、東日本大震災までは福島の原発が生み出すエネルギーを、深く意識せず享受してきました。遠いと思われがちなパレスチナでも、日本政府はイスラエルと連携することで加担している側にいます。私たちは常に、誰かを「踏んでいる側」に立っていると思います。
権力勾配を生み出す「中央と周縁」という考え方そのものが暴力的です。だからこそ、この本では、異なる場所で起きている問題が、実は重なり、「地続き」なのだということを伝えたいと思いました。
パレスチナを取材していると、「日本は中立ではない」という厳しい声を聞きます。一方で、「ヒロシマ」の国というイメージを強く持っている方も多い。
そこで伺いたいのですが、2023年にイスラエルの閣僚が、ガザに核兵器を使うことも「選択肢のひとつ」と発言した時、広島ではどのような反応がありましたか?
田中:そのニュースを見た時、「カクワカ」のメンバーはみんな怒りで震えるような状況でした。イスラエルは事実上の核保有国です。本来なら、広島市や日本政府が明確な非難の意思を示すべきでした。でも、核実験の際には即座に声明を出す広島市の反応も鈍かったです。「これは核問題ではないのか?」と、私たちが関わる別の市民グループでも公開質問状を出しました。
安田:日本政府の反応も鈍かったですね。長崎で被爆された木戸季市さんに話を聞いたのですが、ガザの映像を見ると「体が震える」「目を背けたくなる」けれど「見なければならない」とおっしゃっていました。核兵器禁止条約の会議でも、木戸さんは「ガザで起きていることはあの日の再来だ」と訴えていました。
ところが最近でも、アメリカのトランプ大統領が、イランへの攻撃を広島に原爆を投下したことになぞらえて語ったことがありました。歴史認識の上でも、何重にも間違っている発言だと思います。
田中:歴史認識として間違っているのは明らかです。広島や長崎への原爆投下は、戦争を終わらせるためではなく、新兵器の性能を試すための「実験」だったと分かっています。
そして、今回のイランへの攻撃にしても、報道では米国がバンカーバスターを初めて使ったとありました。これは、米国が新しい武器を試したかったという、非常に残酷な意味で、広島・長崎への原爆投下と重なって見えました。
安田:結局アジアに、日本に原爆を使ってもいいという眼差しの根底には差別があったと指摘されています。こうした「実験」をしてもいいという根底には、やはりレイシズムが存在していると思うんです。
ガザは、兵器の典型的な「見本市」とされてきました。誰の体を、誰の命を実験台にして、イスラエルの兵器が売り出されているのでしょうか。
田中:去年、日本政府がイスラエル製ドローンの購入を検討していると報道された際、防衛省の人が「性能が証明されている」と言ったのには本当に驚きました。「誰の命によって証明されているんだ?」と、問い直さなければいけません。
これは核兵器でも同じです。日本が「核抑止」を肯定的に捉えている以上、こうした問題に力強く反論できない。まさに先日も、日米が核使用のシナリオを議論しているという報道がありました。こうしたことがまかり通ってしまっている。それを許し続けていいのかと、今問われていると思います。

「カクワカ広島」共同代表の田中美穂さん。(佐藤慧撮影)
加害の歴史も含めて振り返る
安田:今まさに起きている軍事侵攻や虐殺について考えるとき、「過去の戦争と向き合いきれていない国や社会が、現在のジェノサイドを止められるだろうか」という疑問が湧きます。
先日、西田昌司氏の「ひめゆりの塔はひどい」「沖縄の教育はめちゃくちゃだ」という発言が物議を醸しましたね。沖縄で戦没者遺骨の捜索を続けている具志堅隆松さんに、この発言について伺いました。「ああいう発言をする議員は、具志堅さんが活動するような現場には来ないですよね」と。すると具志堅さんは「来られても『英霊だ』なんて言われるようでは困るんだ」とおっしゃっていました。
「この人たちはなぜ死ななければならなかったのか?」「国にどのような責任があるのか?」といった本質的な部分を抜きにして、「英霊だ」という言葉で歴史を捻じ曲げられても困る、ということです。政治家がよく使う「尊い犠牲」という言葉も、国家としての責任を覆い隠してしまいます。こうした「歴史改ざん」――「歴史修正」という言葉は「修正」という響きに違和感を感じるので、私は「歴史改ざん」という言葉を使用しますが――は非常に問題だと思います。
広島も例外ではありません。例えば、今の市長からは「教育勅語は良いところもあるのでこれからも使う」という趣旨の発言がありました。
田中:教育勅語だけではなく、『はだしのゲン』が平和学習の教材からなくなったり、「第五福竜丸」という言葉そのものが消えてしまったりということもありました。最近では、「核廃絶」ではなく、「核抑止」の意味を説明する記述が増えていると聞きます。そして何より、「祈り」に重きが置かれるようになってきている。一見、良さそうに聞こえますよね。慰霊のために「祈り」を捧げることはもちろん大事です。しかし、その「祈り」によって、広島もまた加害の歴史を持つ軍都であったという事実が覆い隠されてしまうように感じます。
安田:この本にも書きましたが、実は東京電力福島第一原発の敷地も、戦争とつながっていました。一帯はかつて特攻の訓練施設だった「いわき飛行場」だったのです。それが福島第一原発の敷地の3分の1を占めていたことは、あまり知られていません。住民は半ば強制的に土地を接収され、戦後には住民の意思を無視して払い下げられて、今の原発敷地になりました。これも戦争と地続きなのですが、まるでバラバラのピースに分断されてしまっているような感覚があります。
加害の歴史を覆い隠して、表面的にはつるっとした「祈り」だけが残る。もちろん、「祈り」そのものを否定するつもりはありません。しかし、本質を伴わない「祈り」とは一体何なのだろうか、と考えてしまいます。
田中:学校現場でも、「未来志向」「明るく」「楽しく」「仲良く」といったスローガンで物事が進められていると聞きます。これって「ダメだ」とは言いにくいですよね。子どもたちも「仲良くなればいい」と納得して終わってしまう。こうしたことが、「怒っている人を怖がる」という風潮にもつながっているのかなと。市民活動やアクティビズムがなかなか受け入れられない、排除されてしまう。
安田:まっとうな批判までをも「煩わしいもの」と位置づけるような風潮もありますよね。過去の加害の歴史も含めて歴史を振り返ることは、マイナスの意味で「後ろを向く」ことではないはずです。
田中:本当にそうですね。「誇れる国」と言うけれど、都合の悪い歴史は見て見ぬふりをする。そうではなく、すべてを見た上で、自分たちの国や未来を考えればいいじゃないかと思います。しかし、西田議員のような考えを持つ人たちとは、なかなか対話が成り立ちません。そもそも土俵が違うし、向こうが圧倒的な力を持っている中での対話は成立しにくいですよね。
安田:レイシズムの問題も、結局は力の不平等や不均衡、権力勾配から生まれてきます。対話はとても大事なことですが、両者の力の不均衡を無視して、対等なふりをして「対話は大事だ」と言うのは、暴力的に作用することもあると思います。

ハチドリ舎でのイベントの様子。(佐藤慧撮影)
不条理のそばを黙って通り過ぎない
田中:広島に住み始めて、街中に溢れる「平和」という言葉をよく目にするようになりました。もちろん、それは広島が伝え続けてきた大切なメッセージだと思います。でも、2023年10月以降、パレスチナでの虐殺に関わる中で、日本の「平和」について深く考えるようになりました。
日本は「平和」と言い続けてきたけれど、その裏でパレスチナは不条理に苦しみ、沖縄は差別され、福島は搾取され続けてきました。「平和って、本当は何なんだろう?」と。
安田:「沖縄だったらいい」「福島だったらいい」と、誰かの犠牲の上に成り立つ「平和」は、本当の平和ではないということですよね。
田中:そうなんです。パレスチナのスローガンに、「平和の前に解放」という言葉があるのですが、初めてその言葉を知った時、とても大事なキーワードだと感じました。もちろん、「平和がダメ」だと言いたいわけではありません。ただ、「平和」と「不条理」は簡単に両立してしまうことを、私たち自身が理解した上で発信していくことが重要だと思います。
安田:昨年の平和記念式典をめぐって、イスラエルを招待すべきか否か、という議論がありました。広島市はイスラエルを招待しましたが、ロシア、ベラルーシは招待しませんでした。国際法に反する国は一律に招待すべきではないという意見や、ダブルスタンダードを解消すべきだという声など、様々な意見がありましたね。田中さんはこの件について、どう感じていましたか?
田中:最初の頃は、ロシアやベラルーシを排除したこと自体に疑問を感じていました。イスラエルであれ、ロシアであれ、すべての国に来てもらい、事実を知ってもらうことが一番大切だと思っていました。
ですが、イスラエルによるガザでの虐殺が続き、最悪の状態が日々更新される現実を目の当たりにして、考えが変わりました。この虐殺を止めるために私たちができることを全てやらないで、何が平和だと言えるのか、と。
「見てもらうことが大事」という考えも、核保有国が姿勢を変えるどころか、核兵器を増やし続けている現状を見ると、疑問に思えてきました。「人類のための式典」という考え方自体も、本当にそうなのか、と。「今、虐殺されている人たちを覆い隠すようなことがあってはいけない」と思うようになりました。
安田:私もイスラエルを式典に招待すべきではないと考えていました。広島が「ピースウォッシュ」の免罪符として利用されることを危惧しています。イスラエルは2009年から式典に招待されており、参加後にはその旨をSNSなどで発表している。虐殺を続ける国を「招待するだけ」で、本当に市としてのメッセージを伝えられるのでしょうか。「広島ばかりに背負わせすぎてはいけない」と思いつつ、この局面でどういうメッセージを発していくべきか、と考えます。
ガザの友人からは「私たちは世界の一員として数えられていないんだね」といった声が届きます。私たちはどう行動し、どんなメッセージを発していくべきなのでしょうか。
田中:私は現地に足を運べていないことへのもどかしさを感じています。福島を訪ねたのは一度きりですし、沖縄には慰霊や抗議の意味では行ったことがありません。以前の沖縄訪問は、安田さん自身も本に書いているように、単なる旅行として「消費」してしまっていました。
私は広島から核政策のおかしさを発信していくということを大切にしていますが、同時に、自分で現場を訪れ、現地の人と出会い、「不正義に抗う」という連帯の輪を広げていきたいです。権力者たちは、私たち市民がそうした行動を起こすことを望んでいません。だからこそ、それに抗いたいと思っています。
安田:木村さんが沖縄の現状を知って衝撃を受け、沖縄に通い続けたり、逆に具志堅さんが福島の現場を訪れる。パレスチナのこともそうですが、それぞれが「黙って見過ごせない」と発信しています。具志堅さんは「不条理のそばを黙って通り過ぎない」とおっしゃいますが、とても大切な言葉だと思います。黙って通り過ぎないからこそ、地域を超えた連帯が生まれる。権力者が分断しようとしても、私たちは繋がりを保つことで抗っていきたいですね。

平和祈念式典を前に多くの人が訪れる平和記念公園。(安田菜津紀撮影)
自分の「特権」をどう使うか
田中:以前、安田さんが紹介してくださった「自分の特権を使おう」という言葉が心に残っており、常に意識しています。
私は広島に来るまで、自分の特権に気づいていませんでした。地元が北九州で、近くに朝鮮学校があるのに、交流したことがなかったんです。広島に来て初めて在日の方と出会い、いかに自分が不条理から目を背けて生きてきたかを知りました。安田さんが説明されていたように、私は声を上げられる立場、つまり権力者に近い場所にいることを自覚し、その「特権」を使っていきたい。この感覚を多くの人に広めていきたいですね。
安田:「特権を使おう」という言葉は、『人種差別をしない、させないための20のレッスン』(DU BOOKS)という本で紹介されているものですね。著者のティファニー・ジュエル (Tiffany Jewell) さんは白人と黒人のミックスルーツの方です。最も脆弱な立場の人よりも、自分は声を届けやすい場所にいると。そうした「特権」を使おうと語っています。もちろん、その使い方として「自分は救世主である、またはこれを慈善事業だと思い込むといった罠に陥らないように」という前提も共有されています。
自分の特権性を指摘されることは、ときに居心地が悪いことかもしれません。でも、それを認めた上でどう行動するかが大切だと感じています。

80年前の殺戮を伝える原爆ドーム。(安田菜津紀)
Writerこの記事を書いたのは
Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato
1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。
あわせて読みたい

【目標50人!9月末まで】D4Pの「伝える活動」を毎月ともに支えてくださるマンスリーサポーターを募集します!
9月1日〜9月30日の1ヵ月間で、50人の方の入会を目標にしております。
多くの方のご参加をお待ちしております!
※ご寄付は税控除の対象となります。
D4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。