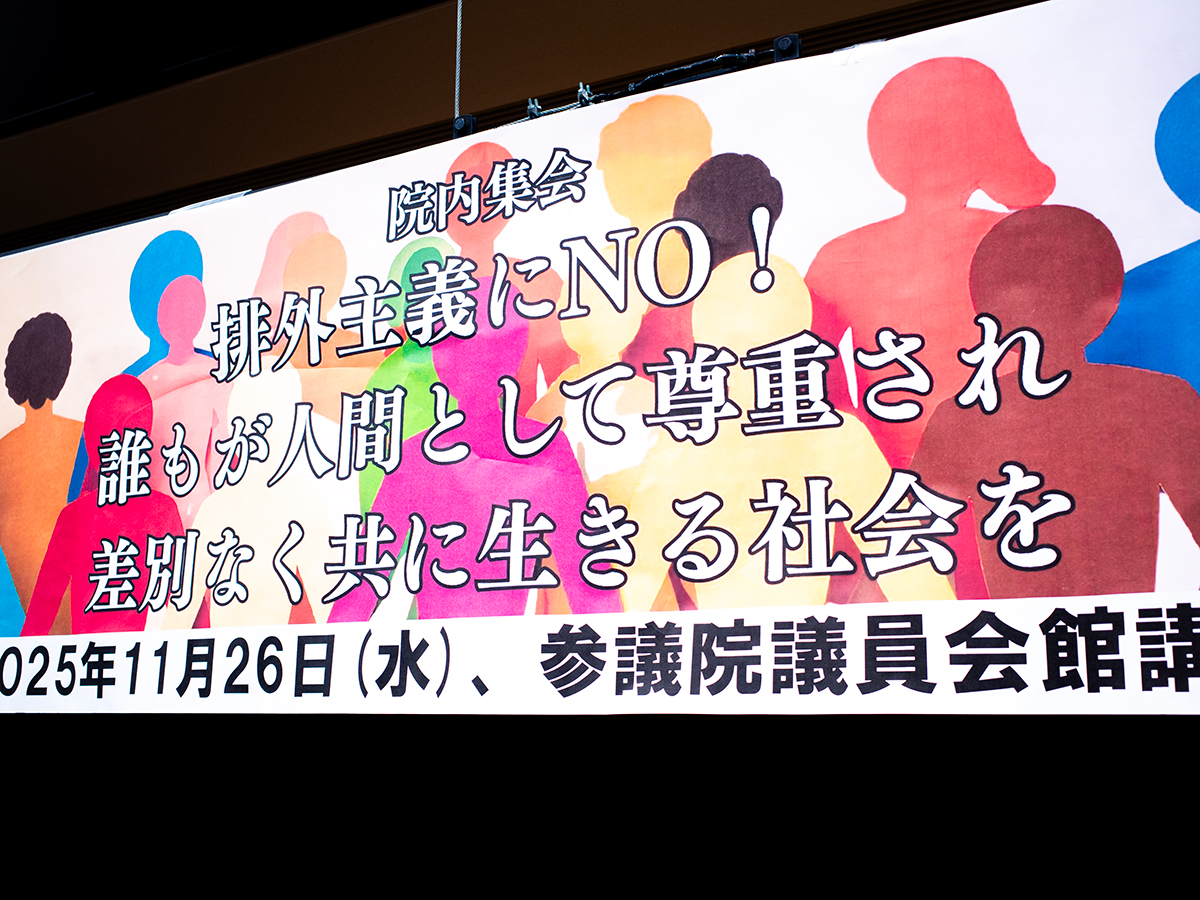※本記事では訴訟の内容をお伝えするために、差別文言を記載している箇所がありますのでご注意ください。
「なぜ裁判官たちは、小さな部屋で警官たちが3歳の少女をひとりで聴取し、脅すことが合法であると信じているのでしょうか。なぜ母親と罪のない子どもの平和な生活を破壊することが合法なのでしょうか」
事件から4年以上が経った2025年10月16日、高裁判決を受けて、訴訟を提起したAさんはこう訴えかけた。「母子不当聴取裁判」を巡り、部分的にではあったが、Aさんの訴えは認められ、東京高裁は計66万円の賠償を東京都に命じた。しかし司法が違法性を認めたのは、ごく一部に過ぎない。
Contents 目次
公園で受けたヘイトスピーチ、3歳の娘たったひとりを聴取
事件は2021年6月に起きた。訴状や代理人弁護士らによると、都内に暮らす南アジア出身のムスリム女性Aさんが、近所の公園で3歳の長女を遊ばせていたところ、突然園内にいた男性B氏が大声を出して長女に近づき突き飛ばしたうえ、「(Aさんの長女に)息子が蹴られた」などと主張してきた。
Aさんは「長女は蹴っていない」と一貫して主張したものの、B氏はさらに「ガイジン」「在留カード出せ」などと詰め寄ってきたという。たまたま通りかかり、英語でAさんの通訳をした別の男性Cさんの地裁での尋問によると、B氏は遠くからも分かるほどの大声で、Aさんたちに対し「ガイジン生きている価値がない」「ゴミ」「クズ」等、差別発言を繰り返し、「年収3000万円以下は人ではない」などの言動を続けていたという。
その後、B氏の通報で警察官が計6人、現場に駆けつけることになったが、日本語でのコミュニケーションがほとんどできない長女に対し、警官は激しい口調で「本当に日本語しゃべれねえのか?」「どうせお前が蹴ったんだろう」などと発言し、Cさんは驚いたという。法廷でもCさんは、「警察官が穏やかな口調で話していたようなことを主張しているようですが、そのようなことは絶対にありませんでした」と、はっきりと証言している。
帰宅しなければならない事情を抱えていたAさんの意思を無視し、警察は約1時間半にわたってAさんや長女を公園に留めたという。Cさんによると、警官らはその間、Aさんの話を聞こうとする様子も、Aさんを滑り台近くに連れて行って状況を説明してもらうこともしていなかったという。
さらに警官らは、任意であることを伝えないまま、差別言動を繰り返すB氏ではなく、Aさんと長女を最寄りの警察署に連行した。聴取はAさんの母語ではなく、電話による英語での通訳で、時間は約3時間にも及んだ。さらに、幼い長女がAさんから引き離され、ひとりで複数の警察官から聴取された場面もあったという。
写真も撮影された上、この長時間にわたる聴取の間、トイレ休憩や食事をとることもできなかった。裁判の過程で警官のひとりは「食事や休憩が必要だったら原告から言うだろう」と語ったが、Aさんとの間にある権力勾配に無自覚な発言ではないだろうか。

記事本文とは関係ありません。(安田菜津紀撮影)
差別言動を繰り返す男に個人情報を漏洩
弁護団は警察官の違法・不当な職務執行があったとして、2021年7月、東京都公安委員会に苦情申出を行ったが進展が見えず、やむなくAさんは9月、都に計440万円の慰謝料などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
警察側の姿勢から見て取れるのは、終始、B氏側の主張のみを鵜吞みにしていることだった。法廷で、「なんでこんな外人いれるんだ」というB氏の発言について問われた警官のひとりは、「差別発言ではない」と即答していた。取り調べ中も警官らは、Aさんの娘が蹴ったことを認めさせようという態度で一貫していた。仮に子ども同士の接触が公園であったとしても、そのために6人もの警官が駆け付け、母子を夜まで聴取し続け、あげく娘ひとりを複数の警官が囲むのは「異様」ではないだろうか。
また警察側は、Aさんが拒否しているにもかかわらず、「Aさんの電話番号をB氏に提供することを承諾しなければ帰宅させない」などと執拗に迫った。Aさんは最後までこれに同意していないが、Aさんが拒んでも、警官は「終わらない、終わらない」と繰り返したという。
そして結局、警察側は電話番号だけではなく、Aさんの氏名や住所などの個人情報を、同意なくB氏に伝達した。それも、警官自らわざわざB氏の自宅まで出向いて渡しているのだ。警官自身も「住所」「氏名」など、B氏に渡す情報の一つひとつをAさんに意思確認していない、と裁判の過程で認めている。
警察側は個人情報を渡した理由を、「B氏がAさんに対して民事訴訟を起こすと主張していたから」と説明しているが、わざわざ警察がその訴訟の先回りをして一方の便宜をはかったのはなぜなのだろうか。逆に、氏名などを含めたB氏の情報は、警察からAさんにはいっさい伝えられていない。
警察の主張を一方的に認めた地裁判決
しかしAさんの声を、一審の裁判官らは受け止めなかった。2024年5月21日、東京地裁(片野正樹裁判長)は、原告の訴えをすべて棄却した。
Aさんの3歳の娘をたったひとりで聴取したことも、Aさんの個人情報をB氏に手渡したことも、被告である都側は「事実」として争っていなかった。けれども判決は、「公権力は間違わない」の一点ばりともいえるものだった。
例えば警官が、Aさんの娘に「どうせお前が蹴ったんだろう」と言ったことについて、その場に居合わせたCさんは利害関係がない人物であることが認定されているものの、裁判官らは警官がそうした言動をするのは「いささか唐突」「警察官の所為としては不自然」としている(つまりそうした警官の発言があったことは認定しなかった)。しかしCさんは、「警察官であるにもかかわらず、その言動があまりに不自然だったから」こそ記憶していたのだ。
判決では、B氏による「乱暴な言動」は認定されている。ところが、「AさんがB氏に個人情報を提供することに同意した」という警察の主張も採用されている。つまり、差別言動を繰り返す男性に、義務もないのに個人情報を提供したことに、警察の責任がないものと断じたのだ。
しかし差別言動を繰り返していたB氏を恐れ、この情報漏洩後、Aさんは引っ越しを余儀なくされている。Aさんが個人情報を渡すことに同意する理由はどこにもない。
高裁で違法とされたのは「情報漏洩」のみ
一方、賠償を命じた東京高裁で、違法性を認めたのは、この情報漏洩の点のみであった。差別意識をもって「乱暴な言動」に及んでいるB氏がAさんの個人情報を悪用し、「インターネット上の投稿やストーカーまがいの行為」「人種または人格に対する誹謗中傷」をする危険性は容易に認識できたはずだとし、Aさんによる承諾があったか否かにかかわらず、これを違法行為だとした。
弁護団の中島広勝弁護士は、「B氏の差別を警察が助長した点で、人種差別撤廃条約違反は認められるはずですが、その点への言及がなく、残念」と語る。
西山温子弁護士もこう指摘する。
「判決では警察の証言をベースにしているため、Aさんが情報提供に同意したことになっていますが、B氏のような人物への個人情報提供承諾こそ、不自然、不合理ではないでしょうか」
娘ひとりへの複数人の警官による聴取については、「必要性がなかったとまではいい難い」としているが、Aさんはその深刻な影響を改めて訴える。
「娘は3歳で酷い扱いを受け、不安、鬱、悪夢に苦しんでいます。今も精神的な治療を受け、投薬なしでは眠れません。なぜ罪のない私の娘が正義を得られないのが、私には理解できません」
警察官による差別発言があったという訴えについて判決では、「容易には想定し難い不自然なもの」としている。また、「(B氏の行為を警官が制止しないのは)通常の警察官の行動として明らかに不自然、不合理」とし、むしろB氏の乱暴な言動を控えるよう働きかけた、という警官側の主張を採用している。
B氏の発言について「差別的で決して許されるものではない」としながらも、警官らが「国籍に対する差別的意識や偏見に基づく対応をしたと認めるに足りる証拠はない」と判断している。
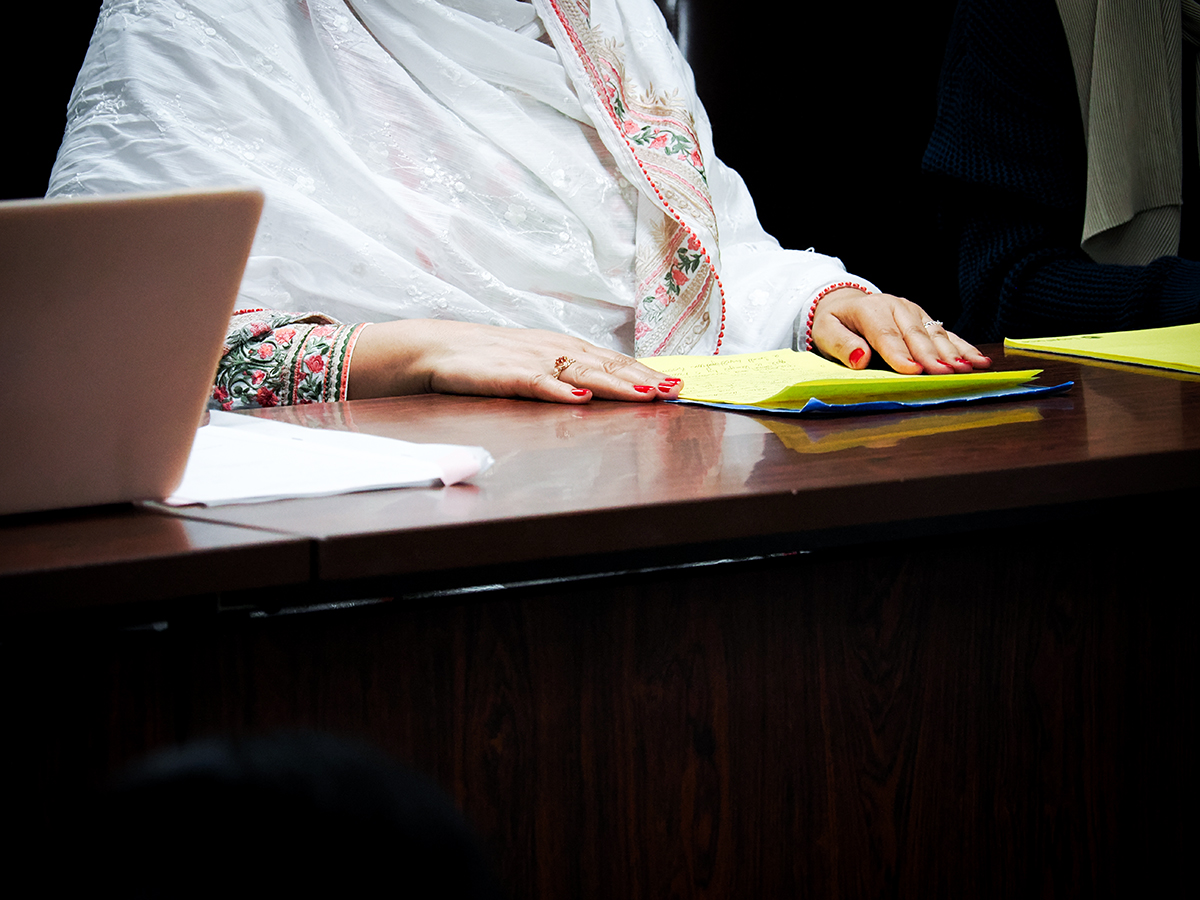
記者会見に出席するAさん。(安田菜津紀撮影)
警察による差別言動は「不自然」なのか
しかし、警官による差別言動は本当に「不自然」なものだろうか。差別や偏見に基づく職務質問など、「レイシャルプロファイリング」の問題を巡っては、訴訟も起きている。その裁判の過程で明らかになった愛知県警の内部資料《執務資料 若手警察官のための現場対応必携 〜君も今日からベテランだ!〜》には、こうある。
《一見して外国人と判明し、日本語を話さない者は、旅券不携帯、不法在留・不法残留、薬物所持・使用、けん銃・刀剣・ナイフ携帯等 必ず何らかの不法行為があるとの固い信念を持ち、徹底した追及、所持品検査を行う》
2024年2月には、埼玉県蕨市でクルド人の排除デモを警備していた警察官が、差別に反対する市民たちを「ザコども」と呼んだことが分かっている。
本件高裁判決では、B氏がAさんに対し「土人」という呼称を用いたことも認定されているが、2016年10月、沖縄県東村高江地区の米軍ヘリパッド建設に反対する市民に、大阪府警の機動隊員が「土人」と発言したこともあった。
「愛知県警の資料などを見ても、警察の法執行に無意識の偏見が生じうるのは否定できないのではないかと思っています。差別的対応をするはずがない、という逆の認定をしているのは、実態に反しているのではないでしょうか」と、中島弁護士は語る。

記者会見にて。右から西山温子弁護士、中島広勝弁護士、児玉晃一弁護士。(安田菜津紀撮影)
公権力による差別がもたらす影響
林純子弁護士は、近年の外国人排斥やヘイトスピーチ被害の実情を踏まえ、「政治家が言っているのだから、警察がやっているのだから、それくらい許される、という基準を作ってしまうのでは」と警鐘を鳴らした。
こうして公的機関が差別の主体となってしまう影響について、中島弁護士は指摘する。
「控訴審でも、公的機関が人種差別の廃止に毅然とのぞむべき理由をふたつ指摘しました。ひとつは、差別的な言動を行う人間にお墨付きを与え助長してしまう効果があること、そしてもうひとつは、被害者に対して“誰も助けてくれない”という絶望を与えてしまうということです」
人権侵害が起きたとき、日本の制度では司法が「最後の砦」とされている。しかしその司法に国際人権条約の観点が浸透せず、差別の問題が受け止められないのであれば、新たな制度の導入も必要になってくるのではないか。
「政府から独立した国内人権機関も求められていますし、本来、個人通報制度(※)が日本に導入されていれば、別の選択肢がありえたのではないかとも思います」
(※)個人通報制度:国際人権条約で保障された権利を侵害された際、条約機関に直接訴えることができる制度。
警察は国家権力の一部であり、その行使の仕方によっては、市民への暴力として働き、とりわけ社会的マイノリティの声を封じ込めてしまう。だからこそ警察組織は、「改めるべきは情報漏洩のみ」とあぐらをかくのではなく、ガイドラインの策定や、形式的ではない研修の実施など、自らが差別する主体とならないための具体的な措置をとる必要があるはずだ。そして国際条約機関から度々勧告されている、人権機関設立や個人通報制度導入は急務だろう。
Writerこの記事を書いたのは
Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda
1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。
あわせて読みたい・聴きたい
本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。
これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。
寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。