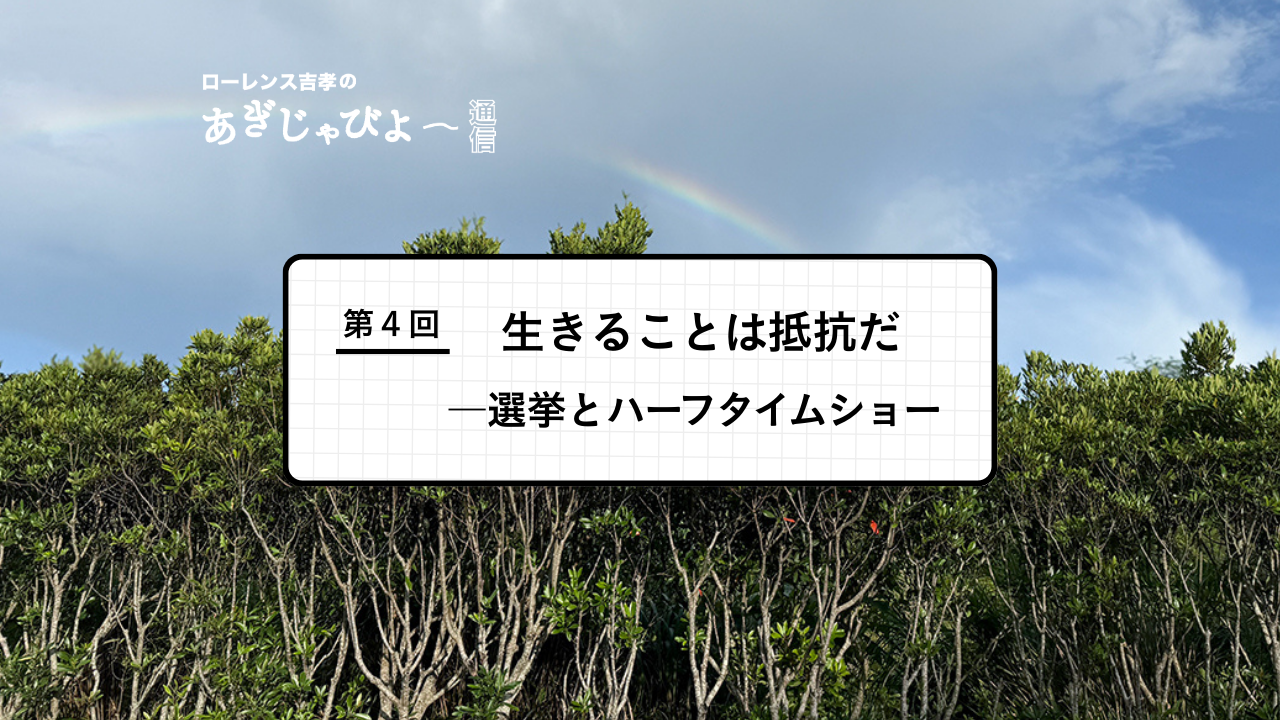国家暴力のトラウマと向き合う―光州民主化運動と関東大震災朝鮮人虐殺の視点から

2024年12月3日、尹錫悦大統領(当時)は「従北(北朝鮮に追従する)反国家勢力の撲滅」を口実に、突如戒厳を宣布し、一切の政治活動を禁止した。韓国メディアが配信する映像から流れてきたのは、民主化を成し遂げたはずの現代に、戒厳軍が再び市民の前に現れ、武装して国会に突入しようとしている様だった。光州で取材した人々は口々に、「45年前の記憶が呼び起こされた」と語った。
1980年5月、光州では、民主化を求め抗議の声をあげる市民たちが、戒厳軍による激しい弾圧を受けた。「アカの仕業」「北が介入した暴動」という当時の不当な“レッテル”は、今も根深く社会に巣くう。
被害を受けた人々のトラウマについて、民主化前から地道に調査、研究を重ねてきたオ・スソンさんらが、光州民主化運動(日付をとって「5.18」とも呼ばれる)と、関東大震災朝鮮人虐殺の、国家暴力としての共通性についての調査を進めている。
なぜ国家暴力のトラウマは社会に根深く残り続けるのか、なぜ関東大震災で起きた虐殺事件にも焦点を当てるのか、2025年10月、光州で取材した。

光州の旧道庁舎広場。(安田菜津紀撮影)
いまだ市民が背負うトラウマ
1980年5月21日、道庁広場へと続く錦南路では、国歌を「合図」に、軍が市民に向けて集団発砲した。
その錦南路に2015年に開館した「5.18民主化記録館」には、2011年にユネスコ「世界の記憶」に登録された、民主化運動の記録物などが展示されている。キム・ホギュン館長によると、『少年が来る』などの著者であるハン・ガンさんがノーベル文学賞を受賞したこと、さらには2024年12月に戒厳が宣布されたことを受けての社会的関心の高まりなどで、来館者は飛躍的に増え、海外からの来訪も目立つという。
記録館のガイド、チェ・ムンジョンさんは、展示を前に、いまだ市民が背負うトラウマについて語った。
「民主化運動から45年になりますが、大きな足音が聞こえると、『誰かが捕まえにくるのかもしれない』と怯えたり、髪を洗うとき、座って目をつぶることができないという人もいます」
チェさん自身は当時小学生だったが、今でも記憶に刻まれている光景があるという。
「夜中に誰かがドアをノックしました。ドアをあけると、真っ赤に染まったひとりの青年がそこに立っていました。最初は血かと思いましたが、赤い消毒液を全身に塗っていたんです。軍人に会ったら死んだふりをするために、そうしていたんだそうです。父が彼を安全なところに送っていったのを覚えています。何十年経っても、それが記憶から消えません。多くの光州市民が、直接的、間接的な経験によって痛みを抱えています」

記録館内でガイドするチェさん。(安田菜津紀撮影)
恐怖を感じながらも弾劾デモを
市内にある「5月母の家」は、秋でもなお青芝に覆われた小さな中庭を囲むように建てられた2階建ての施設だ。民主化運動で家族を亡くしたり、自身も被害を受けた女性たちの憩いの場となっている。
キム・ヒョンミ館長は、国家暴力によるトラウマを、「死ぬまで克服できないほど」深刻なものだと語る。
「私の兄は大学1年生の時に、学校の前で空挺部隊8人に集団暴行を受け、8年間、精神病院に入院した末に亡くなりました。母はその痛みを忘れられず、何を見ても兄のことを思い出して悲しんでいました。けれども亡くなる3ヵ月前、認知症になり、兄を失ったことを忘れてしまった様子でした。とても胸が痛むのですが、皮肉なことに、記憶を失ったことにより、かえって母の心は安らかになれたのだと思えました。ここに集うオモニ(母)たちは、みなそのような苦しみを抱えているのだと思います」
当時責任者だった全斗煥(チョン・ドファン)や盧泰愚(ノ・テウ)らは、誰も被害者に謝罪しなかった。だからこそ「5.18はまだ現在進行形」なのだ、とキム館長は語る。

光州市内の「5月母の家」。(安田菜津紀撮影)
それでもトラウマを少しでも癒そうと、絵を描いたり、ワークショップをしたり、様々な活動に取り組んできた。けれども民主化運動を歪曲する政治家らによって、その傷は度々えぐられてきた。そして2024年12月、尹氏による非常戒厳は、「全身が震えるような出来事」だったという。

「5月母の家」の館内を案内するキム館長。(安田菜津紀撮影)
非常戒厳の夜、恐怖を感じながらも「母の家」の関係者らは、すぐさま弾劾を求める集会を始める。「ここで集まらなければ、もっと恐ろしい事態になるのではないか」――そんな切迫した思いから、来る日も来る日も光州の広場には人々が集まってきた。ほかの地域からも、多くの支援が集まったという。「光州の人々を、“あの時”のように孤立させない」と。

白いチョゴリを着て、路上で声をあげ続けた女性たちの当時の写真。(安田菜津紀撮影)
国家暴力による「孤立」
かつて、国軍光州病院だった敷地には、オレンジ色のコスモスが鮮やかに咲いていた。その公園の先に、「国立トラウマ治癒センター」がある。2012年度に光州市のモデル事業として開始され、2024年、正式に国家事業となった。
利用者の最も多くを占めるのが、5.18民主化運動の被害者であり、そのほか、朝鮮戦争の民間人犠牲者や、軍に強制徴集された人々も対象に、全国規模のプロジェクトも展開している。被害者の心理的、精神的、社会的な治癒を促進し、「コミュニティ治癒」の一環として、一般市民を対象に、国家暴力トラウマとは何かを伝え、人権意識を高めてもらう啓発活動も行う。

光州市内の国立トラウマ治癒センター。(安田菜津紀撮影)
一方、国家暴力の被害者たちは、「国家事業」としてのプログラムに不信感を抱く場合もある。
教育リサーチ班のパク・イジェさんは、「無理にアプローチするのではなく、その方々がよく利用される福祉施設やその職員、あるいはつながりのある友人、知人を経由して接触し、警戒心を最大限に和らげようと努力します」と語る。
治癒リハビリ班のリム・ナムヨルさんによると、2024年12月の尹氏の戒厳宣布後、センターへの相談件数が増加したという。現地報道では、戒厳宣布からの約10日間で、センターには訪問相談84件、電話相談42件が寄せられたとある。
「『もう大丈夫になった』と言ってしばらくセンターに来ていなかった方、長期間安定した状態を維持していた方々も、再びあの戒厳がトリガーとなって、不安感を訴えました」
国家暴力被害の大きな特徴は、「孤立」だ。
民主化運動の後も軍事政権は続き、被害者らには「危険分子」のレッテルが貼られてきた。周囲の人々も、自身の安全のため沈黙する。ケアにつながれず、慢性化によって心の深いところにトラウマが植え付けられることで、行き場のない感情を周囲にぶつけ、家庭生活が破綻するケースもあるという。
こうした被害者の孤立を防ごうと、音楽を入口に参加できるプログラムや、「証言治癒」にも力を注ぐ。「証言治癒」とは、国家暴力の被害に遭った当事者が、被害体験や「その後」を人前で語る取り組みだ。
精神科医としてセンターの事業に携わるチョン・チャンニョン医師は、「証言治癒」の意味についてこう語る。
「記録や歴史を確認するのではなく、人々に受け止められることで、苦痛、トラウマ、悔しさ、鬱憤が治癒されることが目的です。1対1の対話で慰めになることもありますが、これまでの境遇を『自分の責任だ』『恥だ』と捉えていた被害者たちが、聴衆によって『あなたの過ちではない』と認められることで、悲しみを和らげることにつながります。そして証言したことが、共同体の記憶、社会の記憶になることで、新しい意味を作り出すことができるのです」

取材に答えるチョン医師。(安田菜津紀撮影)
取材した当日はちょうど、性暴力被害者らが集い、プログラムを行う日だった。プライバシーの観点から、取材することは叶わなかったが、事業に携わるチョン医師は、「性暴力の場合、より長い沈黙が強いられる」と語る。
「性暴力のほとんどは密室で行われるため、証拠となるものが乏しい上、相手は軍人、つまり国家です。『話してもこれを信じてくれるだろうか』、と被害者がためらったり、性暴力に対する理解そのものが社会に乏しいため、家族や身近な人からの支えを受けられないこともあるからです」
慢性化するPTSD
民主化運動当時、全南大学4年生だったキム・ソノクさんは、2018年、公の場で初めて、取り調べ捜査官から受けた性被害について語った。
2024年4月、「5.18民主化運動真相究明調査委員会」は、そうした被害に関する報告書を公表した。当初は補償要求のあったものなど52件が調査対象となっていたが、被害者がすでに死亡していたり、調査を望まないなどの理由で、実際に調査入りしたのは19件に留まった。そのうち、軍による性加害が立証されたと判断されたのは16件だった。被害者の一部は、国に賠償を求める訴訟を起こしている。

性暴力被害者たちの集いが予定されていた一室。(安田菜津紀撮影)
こうしていまだ、「現在進行形」の問題として社会に影を落とす国家暴力の問題を、関東大震災朝鮮人虐殺事件と重ねて調査をするチームがある。全南大学名誉教授で、光州トラウマセンター(現・国立トラウマ治癒センター)前所長のオ・スソンさん、心理健康研究所所長のキム・ソクウンさん、そして5.18記念財団研究委員のイ・ジェイさんらだ。彼らとは、2025年9月、調査で来日した際に知り合った。
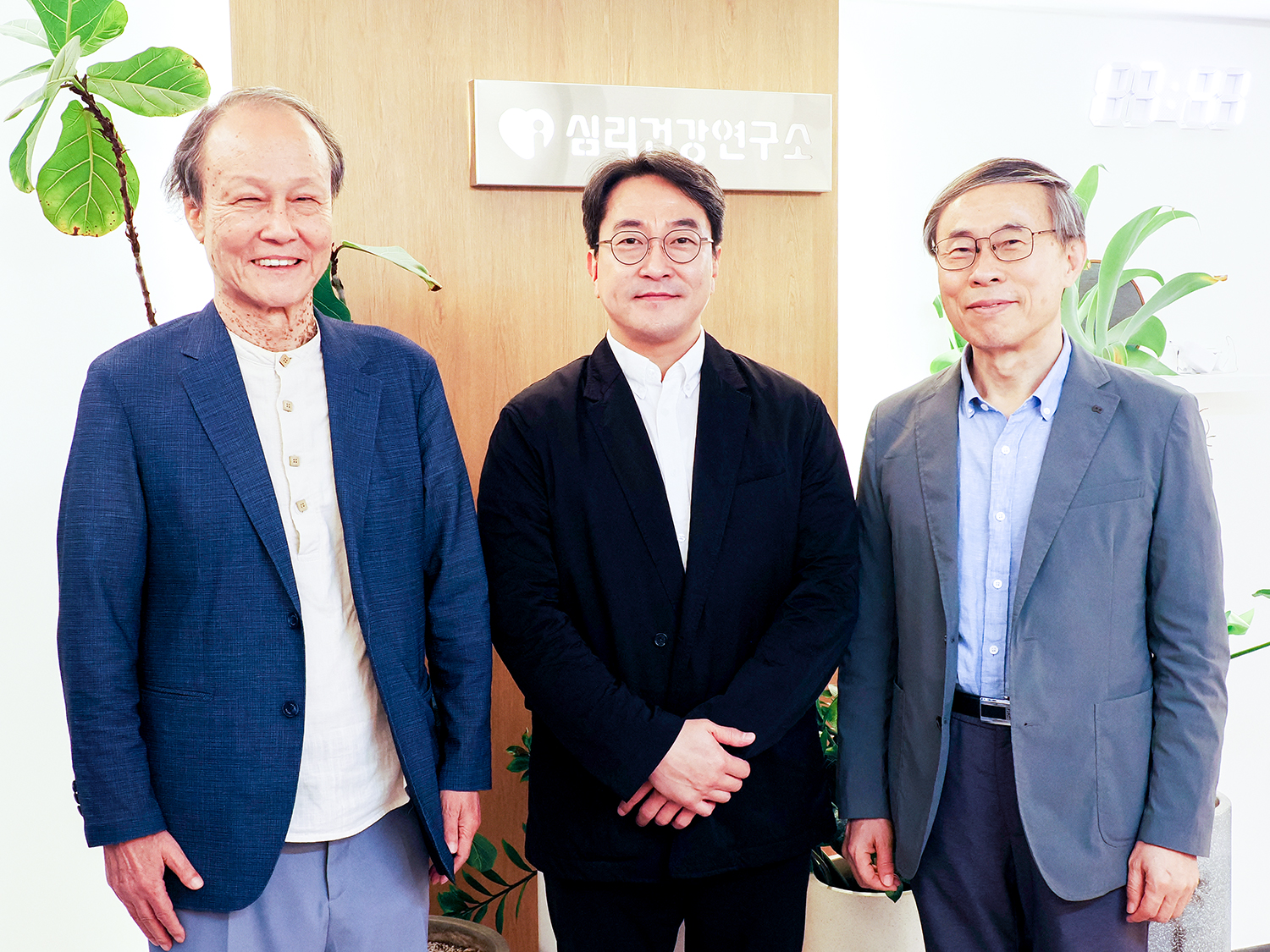
左から、オ・スソンさん、キム・ソクウンさん、イ・ジェイさん。(安田菜津紀撮影)
オさんはソウルの出身だが、光州民主化運動の前年1979年、全南大学心理学科教授に任用された。
「専攻は臨床心理学でしたが、軍人による虐殺の現場で何の役にも立たず、本当にショックを受け、無力感を覚えました。そして『生き残った』という罪悪感のようなものを抱き、私自身がうつ病に陥って、アルコールに依存しなければ生きられない時期がありました」
そんなオさんにとって契機となったのは、ある患者との出会いだった。
「あるとき病院の精神科で、40代の男性の心理評価を担当したとき、脳の損傷や、気質性、パーソナリティ障害など、複合的で特異な反応が見受けられました。『5.18』当時、忠壮路(中心地の路地のひとつ)で小さな店を出していた人で、その店に息子ほどの年齢の学生たちが逃げてきたんだそうです。追ってきた軍人たちに思わず抗議し、酷く殴打されました」
「診療当時はまだ、『5.18』について人々が公の場で話せるような状況ではありませんでした。その患者の症状が気になり深く話を聞いていくうちに、彼は初めてそうした記憶を語ったのです。この方の苦しみを目にし、『5.18』の影響を受けながらも、語れていない人たち、相談することもできない人たちが相当数いると考え、調査を始めることにしました」
沈黙を強いられる中で、回復の出発点にも立つことができない人々が確かにいた。しかし時代は依然として軍事政権下だ。民主化運動に関する調査を行うこと自体に危険が伴う。
「精神病院に行った翌日、公安がやってきて、『昨日どこへ行ったのか』と尋ねてきたり、講義室にも学生を装ってもぐりこんでくるような、非常に物騒な時代でした」

市民を殴打する戒厳軍の姿などをとらえた、記録館の展示の一部。(安田菜津紀撮影)
オさんが調査を公表したのは、韓国社会が「民主化」を果たした1987年から3年後、1990年のことだった。約150名の臨床資料を集め、「光州5月民衆抗争の心理的衝撃」という論文を発表した。
「当時はトラウマという言葉がほぼ知られておらず、『心理的衝撃』と翻訳し、初めて心的外傷後ストレス障害(PTSD)について発表しました。私が『五月症候群(メイ・シンドローム)』と呼んだ集団トラウマは、多くの人々が5月になると不安・憂鬱で不安定になる、という症状です」
被害を受けた日にちなどが近づくとトラウマ症状が出る、いわゆる「アニバーサリー反応」だ。
「実は私は2000年に一度、研究を止めました。そして『5月はこんなにも美しいものか』と気づかされました。研究をしている間は一度もそう感じたことがありませんでした。私自身が20年を経て、トラウマから解放されたのです。ところが2004年、私が面談したこともあるひとりを含む、複数人の被害者たちが自殺で亡くなります。20年経ってもPTSDが鎮まらなかったんです。国家暴力によるPTSDは、一般的なものとは全く異なる様相を見せ、慢性化し、複合的な状況が起こることが、その後の調査でも分かっていきました」
オさんは現在の国立トラウマ治癒センターの設立にも尽力してきた。「トラウマは医学的なモデルに依存せず、社会や環境の問題として向き合う必要がある」というオさんの観点は、センターの理念や活動にも活かされている。「国家暴力は国家が責任を負うことに意味がある」と指摘する。

トラウマセンターに展示された活動写真の一部。(安田菜津紀撮影)
持続する国家暴力と名誉回復
国家暴力の影響は、直接的な被害者や遺族だけに留まらない、とキム・ソクウンさんは語る。
「たとえば当時、現場で支援したりした人々、看護師や医師、教師たち、あるいは目撃した記者たちです。さらには当時を直接経験していなくても、関連した映像を見たり、情報に触れたことがトラウマ経験となる場合もあります。こうして被害者の範囲が拡張されるということは、国家暴力が持続していることを意味します。一時的な対応や賠償だけに留まるのではなく、トラウマの再発を防止することが非常に重要です」
こうしたトラウマが、世代間で受け継がれてしまうことがあるという。
「一般市民だった国家暴力の被害者の方々は、一夜にして“暴徒”、“アカ”という烙印を押されることになりました。一瞬にして本人が持っているアイデンティティが変わり、共同体からは周縁に押し出されていくしかなくなります。さらに被害経験によって感情調節ができなくなり、DVなど、暴力の再生産を生む場合があります」
「また、私が関わった遺族の中には、1980年(光州民主化運動が起きた年)に生まれた人がいます。その人の父親は『5.18』で死亡していて、本人は民主化運動に背を向けて生きていたと言いますが、実は生まれた時から『5.18』に束縛されていたのです。それは“父の喪失”ではなく、最初からいないという、“絶対的な不在”です。そして自分の子どもができた時、どう接し、どうケアしていいのか、深いところで分からない。その人は自分自身を“空っぽ”と表現していました」

「5月母の家」に飾られていた絵の1枚。戒厳軍の暴力を受けリヤカーで運ばれる夫を描いたもの。夫はその後、死亡した。(安田菜津紀撮影)
イ・ジェイさんは、体験者らの声を集めた『死を越え 時代の闇を越え』を1985年に出版したひとりだ。
「当時は非常に統制が厳しく、計画を知られれば、出版そのものが困難になったでしょう。それでも、民主化運動に関わった人々やその行動が、単に被害を被っただけでなく、“国家暴力に抵抗する”という、『正当性を持つ運動』だったということを知らせるために書きました」
取材対象となった人々には、例外なくある「共通点」があったとイさんは語る。
「みなが、やり場のなかった悔しさなどで泣くんです。そして崖から落ちてしまったかのように社会的に孤立し、口を閉ざすしかなかった人たちが、『話を聞いてもらえただけでも幸せだ』と言うのです」
1995年には、責任者処罰や被害者の名誉回復を目指す「5.18民主化運動等に関する特別法」が制定された。
「約15年で、『5.18』は“暴動”ではなく“民主化運動”だったという扱いに、劇的に変わる過程を経験しました。ところが関東大震災を取り巻く状況を知り、100年経ってもなお、歴史から消そうという力が働き、その力に抗う作業が非常に難しい側面があるのだと感じました。その被害は、私たちの国家においてさえも無視されており、二重、三重の困難が生じていると思います。まずは『5.18』を経験した私たちの視点から照らしてみようというのが、調査の趣旨です」

改修工事中の旧道庁舎を囲う壁には、孤立した光州市内で市民たちが一時的な「自治」を行っていた様子を示す写真が掲げられていた。(安田菜津紀撮影)
加害の歴史と向き合う責任
「朝鮮人が井戸に毒を入れている」「暴動を起こしている」――。1923年9月1日、関東大震災。発災直後から、恐怖を駆り立てる無根拠な「噂」が広がり、各地で「自警団」が結成された。警察をはじめ公権力までもがデマを扇動した。
9月2日には東京市と東京府下の5群(当時)に戒厳令を施行し、3日には東京府全域と神奈川に、4日には千葉県と埼玉県に拡大した。各地に投入された軍も当初、「朝鮮人暴動」を実在のものとして行動し、「自警団」や軍によって幾多もの虐殺が起きた。内閣府中央防災会議のまとめた報告書では、殺害された朝鮮人、中国人、あるいはそう見なされた日本人の犠牲者の人数を、推計で千~数千人としている。
オ・スソンさんは、戒厳令を敷いたこと、虐殺、それに伴うトラウマ、また歪曲やデマなど、関東大震災と光州民主化運動は、国家暴力という側面で非常に類似している点があると語る。
「しかし韓国でも、関東大震災について広くは知られていません。『5.18』も学術的には研究されてきましたが、一般の人々が詳細を知らないために、歪曲が多く起こっているのが実情です。両者をより知ることができるように、というのが研究の基本的な目的です」
光州では南北分断に加え、光州を含めた全羅道に対する地域的な差別も背景にあった。関東大震災においては、日本における朝鮮人に対する差別があり、その共通項にも着目しているという。
関東大震災当時、警察に自ら出向き、朝鮮人を殺害した「恩賞」を求めた者までいたという話も残っている。中央防災会議の報告書も、事件の背景に《無理解と民族的な差別意識もあったと考えられる》と指摘し、《過去の反省と民族差別の解消の努力が必要なのは改めて確認しておく》と記している。
韓国では2025年12月2日、関東大震災直後に起きた朝鮮人虐殺の真相究明や、被害者の名誉回復などを図る法案が可決し、真相究明委員会が立ち上がる。一方、日本はどうか。

2024年9月、歴史否定を繰り返す団体が追悼碑前での集会を開くことを阻止するため集まった市民ら。(安田菜津紀撮影)
毎年9月、墨田区の横網町公園にある朝鮮人犠牲者追悼碑の前で、日朝協会東京都連合会などでつくる実行委員会が追悼式典を行ってきた。オさんたちと出会ったのも、この式典だった。歴代の都知事はこの式典に追悼文を寄せてきたが、小池百合子知事は2017年から送付を取りやめている。朝鮮人虐殺については、「歴史家がひも解く」と曖昧な表現でかわし、史実として認識しているかさえ明言してこなかった。
関東大震災から100年の日を迎えようとしていた2023年8月30日、松野博一官房長官(当時)は会見で、虐殺について「政府内で記録が見当たらない」と答えている。だが、一部ではあるものの加害者は起訴され、虐殺に関連する公文書は複数確認されている。それでも調査・検証を行うどころか、政府自ら史実に背を向け続けている。
そもそも光州で残忍な弾圧を行ったかつての軍事政権は、日本の植民地支配と地続きのものだ。多大な犠牲を強いられながら民主化が成し遂げられてもなお昨年、戒厳軍が市民の前に現れた。一度植え付けられた構造的暴力を払拭することは容易ではない。日本の歴史と切り離して考えられる問題では、決してない。
日本政府こそ率先して、関東大震災時の虐殺を含めた加害の歴史と向き合い、検証し、これを繰り返さない未来を築く責任を負うべきではないだろうか。

ソウル市内の植民地歴史博物館では、尹氏に抗議する市民集会の映像や絵が展示されていた。(安田菜津紀撮影)
Writerこの記事を書いたのは
Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda
1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。
あわせて読みたい・聴きたい

D4Pメールマガジン登録者募集中!
新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。