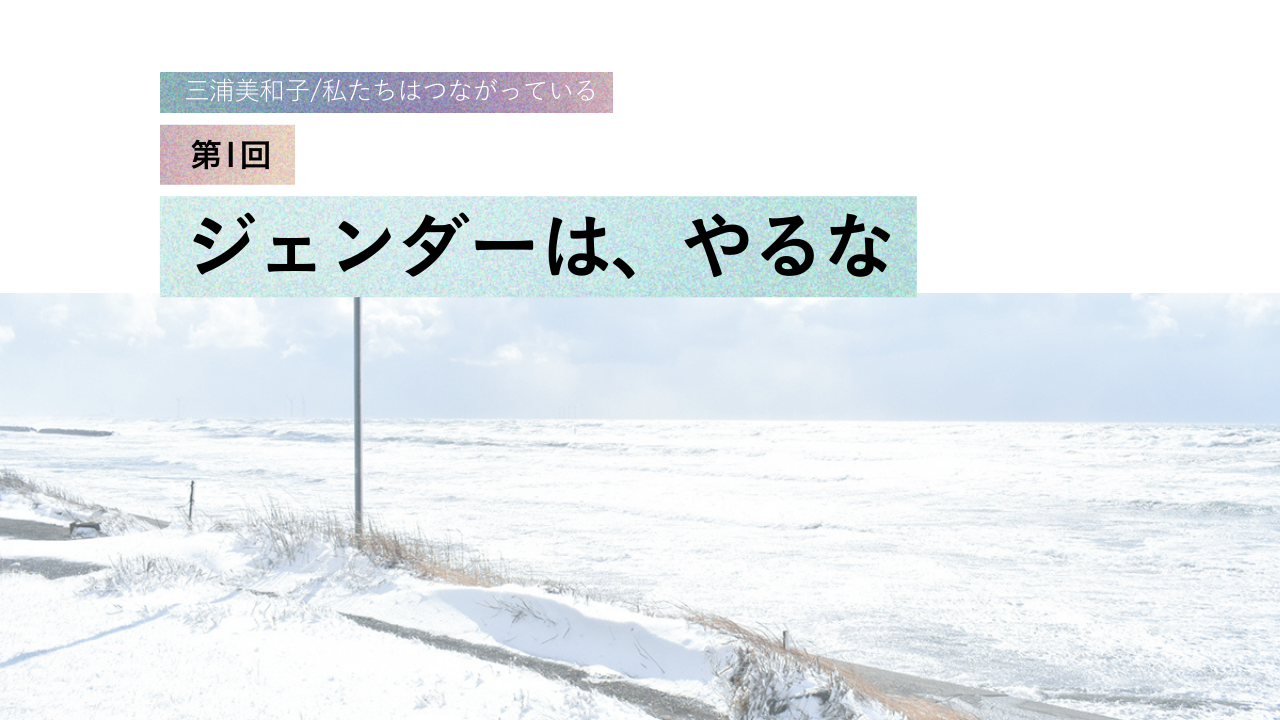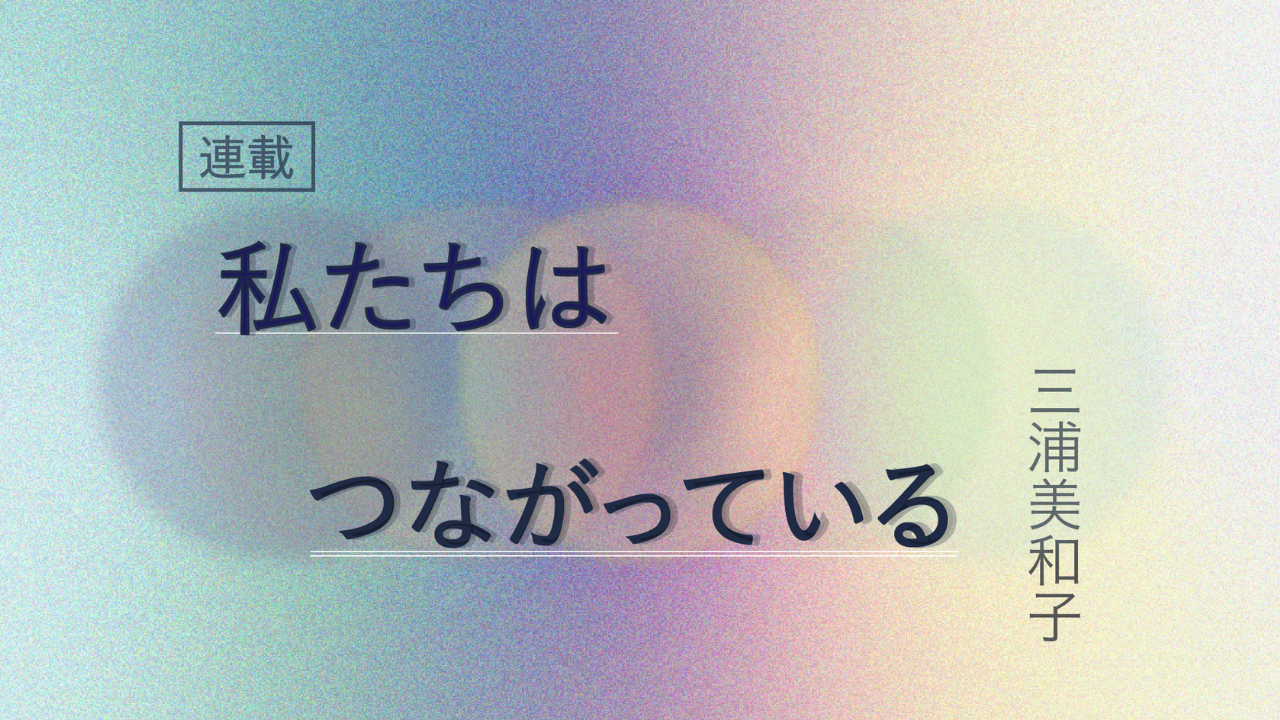2020年8月28日夕方、安倍首相が辞任を表明する会見を、私は食い入るように見ていた。
「在任中に成し遂げたレガシーは何ですか?」
会見が始まって間もなく、こんな質問が投げかけられた。けれども私が聴きたかったのはむしろ何を「成し遂げられなかった」と考えているのか、だった。
2020年までに指導的地位の女性を3割にすることを政府が先送りにし、具体的な期限のないふわりとした「目標」になってしまったのは先月のことだ。
これまで”女性の活躍”という言葉に、そもそも違和感を抱いてきた。そして政権下ではそれとは真逆の、尊厳を傷つけるような発言が政治家や大臣から繰り返されてきた。
「子どもを産まない方が幸せなんて勝手な考え」
「子どもを産まなかった方が問題」
「子どもを最低3人くらい産むようにお願いしてもらいたい」
「セクハラ罪なんて存在しない」
これはほんの一部に過ぎない。そして結局、会見では「女性」というワードは出てこなかった。けれどもこれは、政治側だけの問題ではない。記者の質問にも、この切り口のものがなかったのだ。時折画面に映る記者席も、ほとんどを男性記者が占めている。
ある時、メディアに携わる友人から相談を受けたことがある。
「モノ言う男性」と「聴く女性」という固定化したジェンダー観を、メディアが強めてしまっているのではないか、と。そのため彼女は、自身の関わる番組出演者のジェンダーバランスを見直していこう、という提案をしたそうだ。
”女性の活躍”が謳われ、”国会議員の女性の割合が少なすぎる”と報じる側のメディアが、同じく男性ばかりを起用しているようでは説得力がない。むしろ社会の価値観に大きな影響を与えるメディアこそ、率先して配慮すべきではないかと提案したという。前向きな返答が得られると思っていた。
ところが、スタッフ間の反応は鈍かったようだ。「いや、男女とかじゃなくて、その話題で一番話せる人を呼びたいから…」。
ただ、出演者に声をかける際に基準となるのも結局、「他のメディアで見たから」という場合が多い。男性の露出が元々多いのであれば、そのサイクルはずっと変わらないことになる。
ちなみにその番組のスタッフは全員、男性だそうだ。
問題の本質の「伝わらなさ」がやるせなかった、と彼女は悔しそうだった。私にも彼女と似たような経験があるので、痛いほど分かる。私もある企画で、「指導的地位の女性3割」を政府が先送りにした問題について取り上げたいと提案したところ、「取り上げるタイミングが今はない」と返答されてしまったことがあった。「取り上げるタイミングがない」と、「女性登用3割を実現するタイミングがない」は紙一重に思えた。
8月に放送される戦争の特集も、インタビューが男性に偏っていたり、男性のみだった、ということもある。誤解のないように付け加えると、一つひとつのインタビューの内容を否定したいのではない。どの証言も、大切な示唆を与えてくれる貴重なものだ。
ただ、ジェンダーの問題をはじめ、意思決定の過程や社会に響く声の多様性がなくなることも、「戦争」への一歩になりえてしまうのではないか。そんな教訓も私は、先人たちから受け取りたいと思っていた。
戦争報道だけではない。「コロナ後の世界」について識者が語る書籍や企画も、全員男性、というものが複数見受けられた。例えば下記の企画は、ひとりやふたりの発言を取り上げた企画ではない。にも関わらず、女性はひとりも選ばれなかった。この企画にはさすがに、「この世界に女性は存在しないのだろうか」と唖然としてしまった。
企画が成立するまでに、何人もの人々が関わったはずだ。ジェンダーバランスを懸念する声があがらなかったのだろうか、あがっても通らなかったのだろうか、とモヤモヤが止まらなかった。
たとえ女性がその場にいたとしても、どのように起用するかが気になることがある。民放の教養番組の審査を担当したときのことだ。例えば歴史番組で、「詳しい男性」出演者と、「素人の女性」という構図を作り上げてしまっているものも見受けられた。番組関係者には「まるで女性が”添え物のよう”」とはっきりお伝えした。
私たちDialogue for Peopleで制作している荻上チキ氏の動画の中で、【態度模倣効果(ミメーシス)】についての指摘がある。
態度模倣効果とは、身近なところやメディアで触れたある種の態度が、人々に広がっていくことだ。
例えばこの動画にもある通り、お笑い番組で芸人さんが披露した面白いギャグが、飲み会や家庭内で繰り返され、日常の中で模倣されていくことがある。
けれどもそれは必ずしも、ポジティブなものばかりではない。例えば見た目の「いじり」、というコミュニケーションがテレビで繰り返されることによって、「ルッキズム」=「見た目中心主義」が拡大してしまう恐れもある。実は広がっていくのは「態度」そのものだけではない。そこに含まれている様々な思想や考え方も、強力に伝播してしまうことがあるのだ。
ジェンダーバランスや、友人が言う「モノ言う男性」と「聴く女性」構図にも、同じことが言えるのではないかと私は思う。そしてその態度は、「モノ言う女性」が叩かれがちなことにも、確実につながっているだろう。だからこそメディア側からも変わらなければと思い、私なりに問題提起してきたつもりだった。
ところが、周囲が男性ばかりという環境だと、「自分がおかしなことを言っているのか」「自分が気にしすぎているのか」と段々と自信がなくなってくることもある。反発や、「Whataboutism」(そっちこそどうなんだ主義)の言葉が返ってくることが往々にしてあるからだ。
一方で、変わろうとしているメディアもある。昨年審査を務めた新聞労連のジャーナリズム大賞の審査員は、初めて男女比が半々となったそうだ。
メディアという大きな枠組みに限らず、私たちの「リアクション」で変えていくことも大切なことだろう。最近では女性登壇者がいない、少ないイベントには登壇しない、と意思表明する方々もいる。
先日、コロナと世界を考える、複数の執筆者が寄稿する書籍のお話を頂いたことがあった。執筆に参加する女性の割合はぎりぎり3割。そこに寄稿した文章の中で私は、こうしたコロナ禍のような事態の中で女性の声が届きにくい実態があること、そしてこの本に寄稿する女性の割合が少ないことも問題であることを記したところ、そのまま掲載されることになった。
大切なのは「ああ、またか」と受け流さず、その都度、「これはどうなの?」と問いかけていくことだろう。もちろん、冒頭で触れた友人の置かれた環境のように、問いかけること自体に労力や勇気がいることもある。でも、その輪は少しずつ、確実に広がってきているはずだ。
このジェンダーギャップについて相談した方から、「いつか、”あんな時代もあったよね”と笑える日がくるといいですね」と声をかけて下さった方がいた。その「笑える日」を、今目指している。
(写真・文 安田菜津紀 / 2020年8月29日)
※本記事はCOMEMOの記事を一部加筆修正し、転載したものです。
※一部内容を修正しました(2021年12月31日)
あわせて読みたい
■ ”誰もがメディアである”時代、荻上チキさんと学ぶ「メディア論」[2020.10.7/佐藤慧]
■ 安倍政権や総裁選、合流新党の方針を「女性活躍」の視点から読み解く[2020.9.13/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。