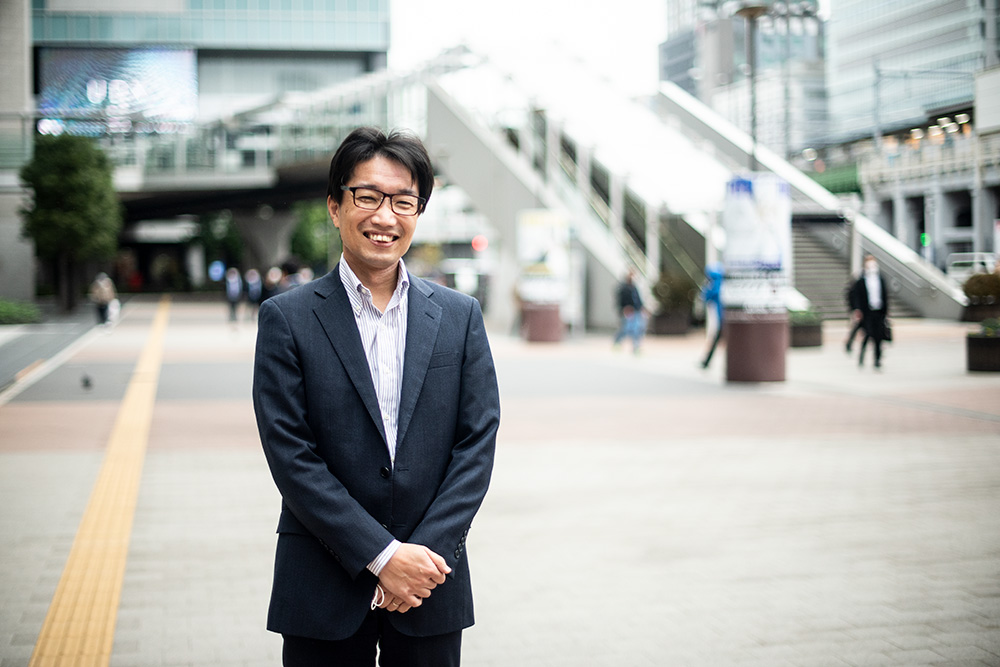あらゆる表現は政治と切り離せないもの

長らく戦闘下にあったシリア、ラッカの街が解放され、音楽を楽しむ人々。
2019年にグラミー賞を受賞したチャイルディッシュ・ガンビーノの「This Is America」のMVは、実際に起きた黒人への暴行、射殺事件を思い起こさせる、細部にわたって社会を風刺する映像だった。
このMVはその後、「This Is Nigeria」「This Is Iraq」とリメイクを繰り返され、各国で社会に鋭く切り込んでいる。
(一部衝撃的な映像もありますので、ご注意下さい。)
自分が大学生の時に何度も観てしまったMVはこれ、Kasabianの「Club Foot」だ。「プラハの春」など、当時の社会模様を描いたとされている。
衝撃的な映像を含む「This Is America」のMVが賞を受賞したということは、少なくともその衝撃を共に受け止める社会の土壌がそこにある、ということなのかもしれない。
ある時、洋楽が好きな高校生が、「戦争をテーマにしたMVや、アーティストの社会的活動を追っていくうちに、国際問題に興味を持つようになった」と話してくれたことがあった。
ひるがえって日本はどうだろう。アーティストが何か社会的な発言や表現をしようとすると、「音楽に政治を持ち込むな」とバッシングされる風潮が、いまだ根強いように思う。私も、「写真家がなぜ政治に発言するの?」という言葉を投げかけられたことがある。「ミュージシャンがなぜ?」「映画監督がなぜ?」…そんな言葉を、SNSなどで見かけたことのある方もいるかもしれない。ただ実は、政治的表現や発言をタブー視すること自体が、すでにとても政治性を帯びたことだということを考えたい。私たちの日常で、政治に無関係なことなどないのだから。
逆に表現者がもっと、活発に発信してもよいのでは、と思うことがある。振り返れば少なからず、芸術が戦争や弾圧を助長してきた歴史があるからだ。時には積極的に「プロパガンダ」を流布して、そしてときには「関与しない」という黙認で。沈黙をする、ということ自体もひとつの政治的なスタンスだとすれば、やはりどんな行動や営みも、政治とは切り離せないのではないか。
だからこそ「右でも左でもない」「思想がない」という言葉に触れると違和感を持ってしまう。人が何かを表現する限り、そこには必ず「視点」が存在し、それ自体に思想がにじむ。そうして自分が政治や思想から切り離された存在かのように振る舞うことで、逆に声の大きなイデオロギーの渦に、無自覚に吸収されてしまうこともあるかもしれない。
なにも、「みなが政治的なことをストレートに表現するべき」だと言いたいわけではない。すべてのことは政治につながる、という自覚を持ったうえで、それがどう表出してくるのかは表現者次第のはずだ。ダイレクトに響く言葉や写真もあれば、じんわりとにじむような歌や映像作品があるかもしれない。逆にそうした発信の応酬に疲れた時、心を休められる表現があってもいい。そのように活き活きとした多様性が、社会の呼吸につながるのではないだろうか。
(文・安田菜津紀 写真・佐藤慧 /2020年12月)
※本記事はCOMEMOの記事を一部加筆修正し、転載したものです。
あわせて読みたい
■ 2020年冬特集「それぞれの声が社会をつくる」[2020.6.3/安田菜津紀]
■ 僕たちは「誰かを見下ろす笑い」のままでいいのか 沖縄から社会問題を語る、せやろがいおじさんインタビュー[2020.6.22/安田菜津紀]
■ 後藤正文さんインタビュー『今という現在地から見る過去、未来』(前編)[2020.5.4/安田菜津紀、佐藤慧]
「それぞれの声が社会をつくる」
Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。2020年冬は「それぞれの声が社会をつくる」と題し、民主主義のアップデートをテーマとした特集を実施中です。一人一人の声を「伝える」ことから「共感」を育み、「対話」を生み出すこの取り組みを支えるため、あたたかなご支援・ご協力をよろしくお願いします。