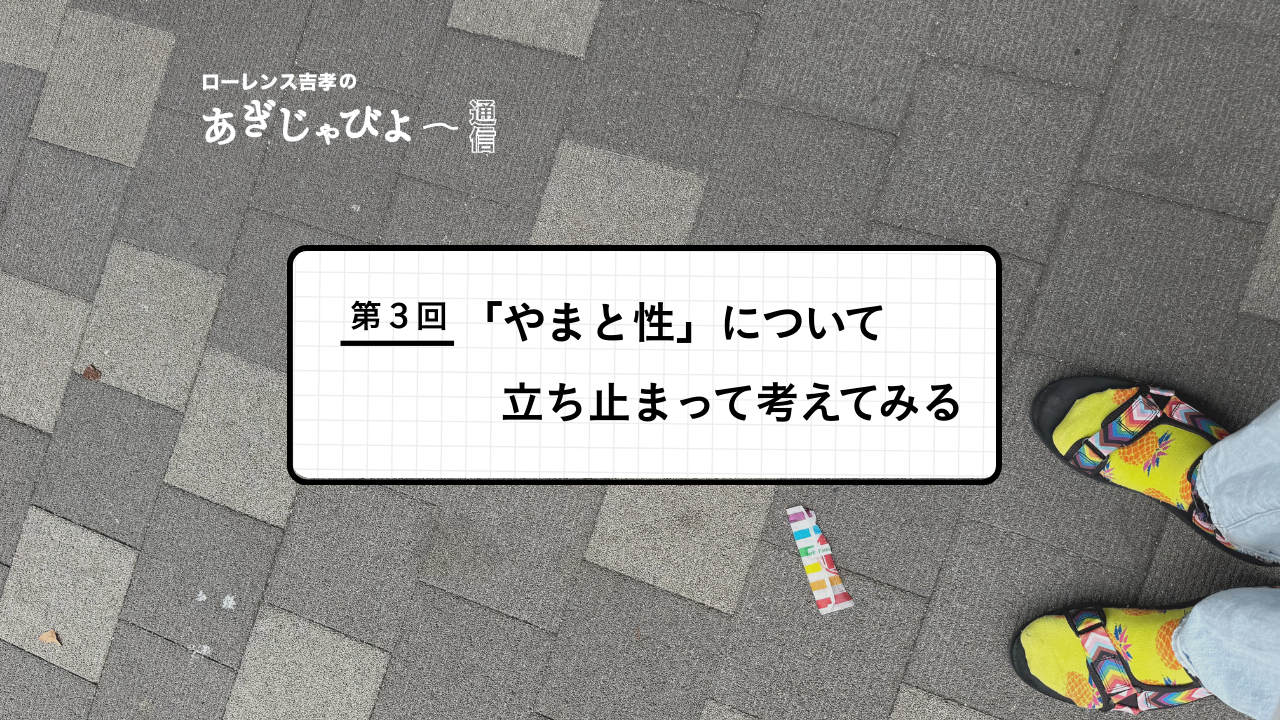「ねえ皆さん、どうしてトイレのマークは、男性が青で、女性が赤なんでしょう?」
高校時代、先生がクラスでそんな投げかけをしてくれたことがあった。それは私にとって、「はっとした」というよりも、「衝撃的」な言葉だったことを今でも覚えている。
「男性らしい色」、「女性らしい色」、とは一体誰が決めたものなのだろう…?でもこれまで一度も不思議に思わなかったのはなぜなのだろう…?自分の中の「当たり前」が、がらがらと崩れていく、目から鱗、の瞬間だった。その先生との出会いがなければ、「“らしさ”の呪縛」のようなものに何の疑問も持たずに過ごしていたかもしれない、と今でも思う。
高校卒業前、私の最後の担任の先生はベテランの女性で、保健体育を担当していた。学校自体は決して自由な校風とはいえず、保守的な空気が漂う場所だった。だからこそ、その先生は「異色」の存在だった。
ジェンダー問題や性的マイノリティーの方々のことに触れる授業を行い、ゲイであり、HIV陽性の男性を授業に招いてくれたこともあった。
私はその方への質問票の中に、不躾にも「どうして男性が好きなのですか?」と書いてしまった。その方が質問を読み上げて下さり、「例えば皆さんが女性として男性が好きだとします。ではなぜ、男性が好きか、理屈で説明できますか?」と問われ、言葉に詰まった。確かに答えられない、誰かを好きになるとはそういうことなのか、と。
その当時はまだ「LGBT」という言葉が今のように広く知られておらず、初めて学ぶことだらけだった。それまで友人同士の会話で、同性愛などを笑いのネタのように口にしていた自分を、「なんてことをしていたんだろう」と初めて省みた。
その先生はまた、性教育と真正面から向き合い、試験管を使って実際にコンドームのつけ方を教えてくれたこともある。その授業の中で「避妊をしっかりしない男性とは、性行為に同意しなくていい」とはっきり伝えてくれたことを今でもよく覚えている。
今でこそ「性的同意」という言葉が少しずつ広がり始めているものの、当時の私にはそんな概念さえなかった。拒否していい、でも言葉や態度で拒否ができないことがあったとしても、自分自身を責めなくていい、と丁寧に説いてくれたのだ。
▼「性的同意」とは?
恋愛をしている子たちは私を含め、クラスでも決して少なくなかった。ただ、付き合っている人との関係性や、性的なことで悩んでいても、デリケートな話題であるがために、なかなか友人にも相談しにくいものだった。けれども一人で抱え込んでいるうちに、益々自分の身を危険にさらしてしまうかもしれない。
最初は先生の投げかける性の問題に、茶化すような反応をしていたり、気まずそうにしていた私たちも、授業が進むにつれ、「これって話題にしてもいいんだ」と友人同士の空気感が少しずつ変わっていったように思う。
「実は今付き合っている人が、コンドームをつけてくれなくて悩んでる」と打ち明けてくれた友人と一緒に、「彼に伝えよう」、「言いにくかったら一緒に行こうか?」、「もしそれでも相手が納得しないんだったらきっとお別れした方がいいよ」と皆で真剣に話し合ったこともあった。
性被害が報道される度に、「なんでそんな服装していたんだ」「どうして付いていったんだ」と「被害者にも落ち度があったのではないか」というバッシングが飛び交う。けれども「どんな服装でも、二人で食事に行ったとしても、“落ち度”とレッテルを貼って責めるのはおかしい」とはっきりと言えるのは、早い段階で「性的同意」について学んでいたからだと思う。
先生は同時に、「優しそうに見える」=「性的同意を理解している」とは限らない、という現実も教えてくれた。授業で使った資料に、実際の大学のゼミでのやりとりが紹介されていた。性暴力、レイプについて話し合っている時、男子学生たちが「本当に嫌なの?」と、悪意なく、不思議そうに尋ねてくる場面が掲載されていた。
私は電車通学だったため、痴漢に遭ったこともあったし、帰り道に露出狂に遭遇したこともあった。性暴力は「分かりやすい悪意」で近づいてくるものだとばかり思っていた。けれどもそれは、「女性は喜ぶはずだ」「嫌がるはずがない」と、いつの間にか形作られてしまった「当たり前」の中にも潜んでいた。
そう思い返すと、改めて気が付く。その先生の授業は、単に「被害者」にならないための知識を得るためのものではなく、無意識に心ない言葉を吐いたり、「同意」をはき違える「加害者」にならないための教育でもあったのではないか、と。
いまだ自治体によっては「寝た子を起こすな」と性教育をタブー視しがちなところもある。それどころか、公権力が不当な批判をしてくることさえある。東京都立七生養護学校での独自の性教育が、都議らによって不当に批判された事件は、日本の性教育が委縮する引き金の一つだったといわれる。
けれどもジェンダーや性は、自分自身の「芯」ともいえる、存在の根幹だ。それが傷つけられることを避けるためだけではなく、傷つけるような大人にならないための教育は不可欠のはずだ。
だからこそ単純にその話題を遠ざけるのではなく、むしろどんなリスクがあるのかも含めて、正面から考える時間を築いていく必要があるのではないだろうか。
そんなテーマを日韓の生活実感からお話した動画を、最後にご紹介します。
(安田菜津紀/2021年2月)
※本記事はCOMEMOの記事を一部加筆修正し、転載したものです。
あわせて読みたい・知りたい
■ メディアが「再生産」していくいびつな「ジェンダーバランス」[2020.8.29/安田菜津紀]
■ 緊急避妊薬へのアクセスは人権の問題、それを阻んでいるものは? 「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」共同代表、遠見才希子さんインタビュー[2020.8.19/安田菜津紀]
■ 【取材レポート】伊藤詩織さんの意見陳述全文「同じ被害に苦しんでいる多くの人たちのために、この裁判を始めました」[2020.11.17/佐藤慧]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。