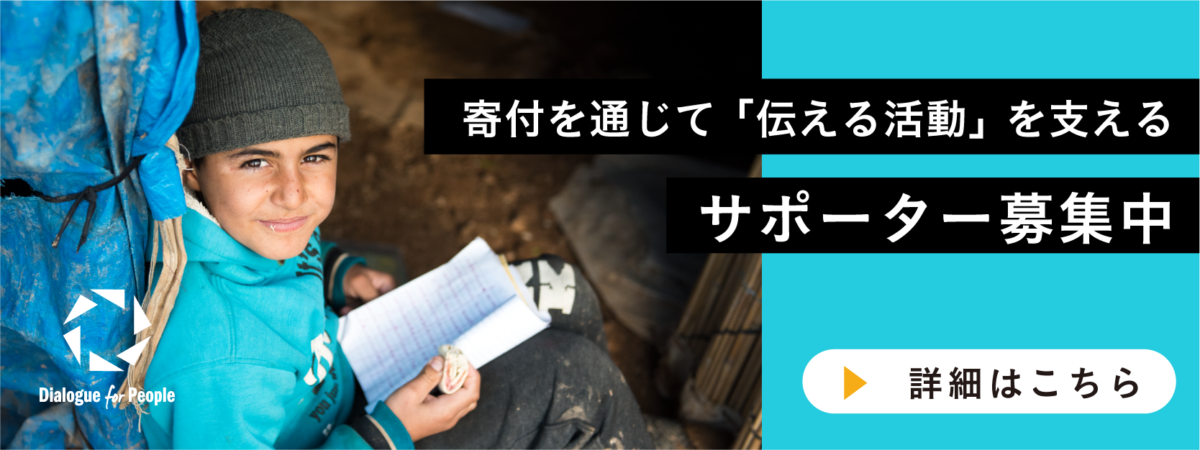よく晴れた日、地平線にはかすかに雪山の姿が見える。国境を越えたトルコ側にそびえたつ山々だ。シリア北部に位置するコバニはこの時期、氷点下まで冷えることも珍しくない。電気の供給が不安定な朝はとりわけ、寒さで目覚めることがあった。それでも窓の外から人々の生活の音が聞こえ始めると、どこか心が温まる。ここに人々の息吹が戻ってきているのだ、と。
この街の名前が世界に広く知られるようになったのは、2015年のISとの戦闘がきっかけだった。中でも果敢に前線へと向かっていくクルドの女性兵士たちの姿は、外国メディアでも頻回に取り上げられた。

米軍の支援を受けたクルド人部隊を主力とする「シリア民主軍」(SDF)の訓練に参加する女性兵士たち。
ISからコバニの街を守り抜いた後も、クルド人部隊を装ったISの兵士たちが巧みに検問を越え、市民を虐殺する事件が起きた。あまりに多くの人々が犠牲となった爪痕は、街にも、そして人々の心にもいまだ深く刻まれている。

街の入り口に築かれた、犠牲になった兵士や市民たちの墓地。

市街地の中でもとりわけ、破壊の爪痕が生々しく残る一角。
闘ってきたのは兵士たちだけではない。街へと戻ってきた人々が、もう一度尊厳の光を取り戻そうともがいている。そんな日常が少しずつ息を吹き返していく様子を、一人の女性の姿と共に見つめた映画が『ラジオ・コバニ』だった。
20歳の大学生ディロバンさんが、友人とラジオ局を立ち上げ、詩人たちや、店を再建した人々、そんな市政の人々の声を集め、それを「おはよう」の呼びかけと共に届けていく。「未来の我が子へ。戦争に勝者などいません。どちらも敗者です」。そんな彼女の鋭い言葉が胸を射る。そのディロバンさんに今回、会うことができた。まだ建設中の住宅が立ち並ぶ一角、完成したばかりの自宅を訪ねた。

自宅に招いてくれたディロバンさん。
今はラジオの仕事からは離れ、小さな頃からの夢だったという小学校の先生として教壇に立っている。映画の中で未来の“我が子”に呼びかけるように言葉を紡いでいたディロバンさんにとって、生徒たちも「我が子のように愛おしい」のだという。
「ISがコバニにやってくるまでは、何気なく街での日常を過ごしていました。けれどもそれが失われそうになって初めて、この街の存在がいかに愛おしいものだったのか分かったのです。私自身、この街の一部であるという実感も」。
人々の手で少しずつ進む復興に、彼女はこんな言葉を寄せてくれた。「人々はこの街の花だから、私たちの手で水を注ぎ続けるの」。

自宅のあるビルから、サッカーを楽しむ子どもたちを眺めるディロバンさん。
彼女が語るように、少しずつこの街にも、平穏な日々が戻りつつあるように思えた。それは彼女のように街を愛おしく思う人々が、力を持ち寄り合ってきたからだろう。

2017年秋にできたコバニ大学。物理の授業に熱心に耳を傾ける学生たち

夕方、街を見下ろす丘の上の自宅に戻る途中のおばあちゃんたち
けれども昨年末の米軍の撤退表明後、クルド勢力の拡大を恐れるトルコが再び越境攻撃をしかけるのではと、人々は懸念を強めている。昨年の3月には既に北西部の街アフリンが制圧され、事実上トルコの支配下にある。

トルコ国境沿いには今、壁が築かれている。多くの人々がISの手を逃れ避難していた頃にはまだ立ちはだかっていなかった壁だ。
再び彼女たちの日常が脅かされることのないよう、この地から目を逸らしたくない。再び街に緑が芽吹き、日常という花が咲き続けられるように。

“シャンゼリゼ”の愛称もあるコバニのバザールにて。
(2019.2.4/写真・文 安田菜津紀)
あわせて読みたい
■ 【取材レポート】そこに生きる人々を想像すること(クルディスタン/2018.9)[2018.10.2/佐藤慧]
■ 【レポート】 「最も醜いもの」 トルコの軍事作戦をうけて[2019.10.11/安田菜津紀]
■ 【お知らせ】「BABAGANOUJ PROJECT 2019」活動報告書[2020.1.31]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。