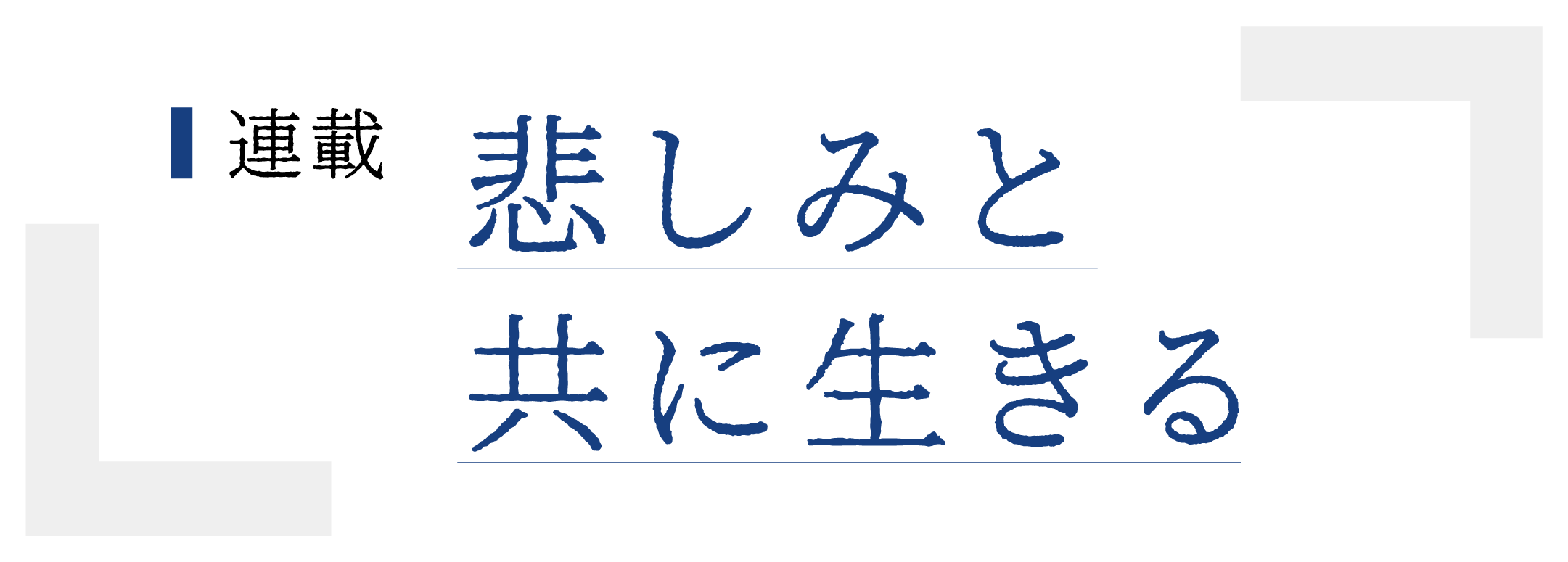本連載では、グリーフケアにまつわる人々へのインタビューを通し、喪失体験と共に生きる人々の姿をお伝えしていきます。第2回は、「一般社団法人 ここから未来」代表理事の、大貫隆志さんにお話を伺います。大貫さんは2000年、当時中学2年生だった次男、陵平さんを自殺で失い、その後「指導死」に関する調査や、自死遺族支援、講演活動などを行っています。
本文中には身近な人の死や、自死に関する記述がございます。そうした内容により、精神的なストレスを感じられる方がいらっしゃる可能性もありますので、ご無理のないようお願い致します。

Contents 目次
「指導死」という言葉を“死語”にしたい
―大貫さんは2000年、当時中学2年生だった息子の陵平さんを、「指導死」により亡くされています。この「指導死」という言葉自体、大貫さんご自身の経験を通して、また、同様のケースが多数存在することを知ったうえで作られた造語とのことですが、この死別からの20年とは、大貫さんにとってどのような時間でしたか?
「13歳の絶望 陵平はなぜ死を選んだのか」
http://www.2nd-gate.com/ryohei.html
何年経ったか…ということは、実はほとんど意識してないんですよね。このような機会に改めて振り返って、ああ、20年経ったんだなと気づきます。改めて振り返ってみると、月並みな言い方ですが、あっという間ですね。「指導死」という言葉を考えたのは、陵平が亡くなって7年後、2007年のことです。それから今まで指導死問題の解決のために活動し続けてきて、まだこれだけのことしかできていないんだという思いはあります。当時この言葉を考えたときには、自分の命がある間に「指導死」という言葉を“死語”にしようと思ってましたから。できていないことを考えてばかりでも自分を責めることにしかならないので、一定程度は進んできているんだと、そうした面も一緒に考えるようにはしてますけどね。

―「指導死」という概念を作られた当初、その言葉の定義はひとつだけでしたが、その後より具体的な項目が追記されましたね。
そうですね。新しい概念として言葉を作っているものですから、「それってどういうことなんですか?」と、よく尋ねられるわけです。「じゃあこういうケースは指導死なのでしょうか?」と、聞かれる中で、少しずつ概念を固めていきました。実は2013年刊行の書籍(『指導死』)に書いた定義は初期バージョンで、その後2~3度調整をしています。たとえば、直接的にその指導を受けていなくても、それを見聞きしたことによってショックを受ける、といったニュアンスなども足しています。多くの指導死遺族と出会う中で、問題のある指導が原因で亡くなった様々な子どもたちの事案を知りました。そうした子どもたちの身に起きたことを包括的に表現することのできる言葉として、今は4つの定義から成るものとなっています。
▶生徒指導をきっかけとした 子どもの自殺「指導死」の定義
①不適切な言動や暴力等を用いた「指導」を、教員から受けたり見聞きすることによって、児童生徒が精神的に追い詰められ死に至ること。
②妥当性、教育的配慮を欠く中で、教員から独断的、場当たり的な制裁が加えられ、結果として児童生徒が死に至ること。
③長時間の身体の拘束や、反省や謝罪、妥当性を欠いたペナルティー等が強要され、その精神的苦痛により児童生徒が死に至ること。
④「暴行罪」や「傷害罪」、児童虐待防止法での「虐待」に相当する教員の行為により、児童生徒が死に至ること。(「指導死」親の会 公式ブログhttp://41040.blog.fc2.com/より)
※筆者注
「指導死」という概念は、それが“教員だけの問題である”と指摘したいものではありません。そのような限られた意味での誤用は、むしろ「責任」の所在を一点に背負わせ、問題の本質を置き去りとした「切り捨て社会」をより助長させる危険性を孕んでいます。大貫さんらの提唱する概念はむしろ、「指導」という、誰かのためを思って行ったように見える行為が、実は思慮の足りない間違ったものである可能性や、ときに無意識の権力構造の中で暴力的な行為として発露する危険性があるのだと、学校という場だけではなく、この社会に生きる全ての人々に問いかけるものだと思います。誰もが被害者に、そして加害者になりえるのだということを、こうした構造的暴力について考える際には、意識する必要があります。
「指導死」の中には、DV(ドメスティック・バイオレンス)に相当するようなケースも見られるため、そうした面では、DVなどの概念の発展・拡張の影響も受けています。例えば、ある野球部の生徒が亡くなった事案では、部活動の副顧問に呼び出されたところまでは確認が取れても、その後実際に会ったのか、そこで何か言われたのかなどといったことは、当人たち以外には全くのブラックボックスで、外部から検証できないんです。その子に関する情報はそこで途絶えていて、そうした事実はわからないまま亡くなってしまいました。

不寛容な規則が他者への攻撃性を正当化する
―学校や教育に関する現場では、「ダークペダゴジー」と呼ばれるような、倫理的に問題のある手法を用いたものであっても、「お前のための教育・指導なんだ」と正当化されてしまう危険性が高いように思うのですが、そうした構造はこの20年で、どう変わってきたのでしょうか?
ダークペダゴジーに関しては、むしろ今の方が酷くなっていると思います。いわゆる「問題校則」と呼ばれるものも、より厳しく、増えているようです。一時期は減少していたのですが、それがまた復活してきている。しかもより細かく、ゼロ・トレランス方式的な、不寛容を前提とし、ひとつのルール違反に対して、それに相当するペナルティ・懲罰があらかじめ規定されており、それが問答無用で適用されるという世界になっています。
こうした現状となってしまった背景には、この間の政権の教育に対する姿勢といったものも色濃く反映されていると思いますが、それと同時に深刻なのが、保護者たちの意識です。「子どもとは厳しく指導しないと悪い方向に行ってしまう生き物なんだ」という価値観に、同調してしまっている保護者の方々が少なくないんですね。多少乱暴であっても、厳しい指導を通して導くことで、はじめて真っ当な人間になれるんだという。こうした傾向は、指導死問題を解決していくための大きなハードルのひとつとなっています。
例えば少年法の改正、厳罰化といったことが盛んに言われます。その背景にあるのはやはり、「人間は放っておくと、悪い道に進んでしまうんだ」という意識ですよね。厳しい懲罰を与えることがその人の更生に役立つんだ、というアイデアがあるわけです。そうした処遇が妥当である場合もゼロとは言いませんが、そうした意識に囲まれて育つ子どもたちは、より一層自分に対する肯定感が低下していったり、自己有用感を見失っていったりする可能性も孕んでいます。本来教育や指導に求められるものは、それと全く逆のことなのではないかと僕は思っているんですね。
―そうした大人の観方に対し、子どもたちはこの不寛容な社会をどう見ているのでしょうか?
平たく言うと、極めて息苦しい世の中なのではないでしょうか。本当に些細なことで注意をされ、「お前は間違っているんだ」という信号を出されるわけですよね。細かな校則の例でいうと、下駄箱に入れる靴の置き場所が決められていたりする。端から何ミリ以内という。でも教員はいちいち全てをチェックできないので、生徒同士でチェックさせるんですね。そして「靴がきちんと置かれていない」という報告が担任の耳に入ると、授業中であっても「靴を直してこい」と、玄関まで降りて直させるわけです。もっと酷いものになると、雨の日に傘を傘入れに入れますよね。その柄の向きを揃えなさいと言われる。形の乱れは心の乱れだと言って。冗談かと笑いたくなりますが、本当の話です。そうしたことを学校が真面目に指導しているし、嫌だと思う先生がいても、そこに加わらないと教員の中で吊るし上げられます。中には勇気を持って声を上げる教員の方もいらっしゃいますが、一生“平教員”であることを覚悟でやっているという方が多いですね。教員の中でも孤立してしまうので、果たしてどこまでその孤独に耐えられるのかということは、難しいところですよね。
そのような形で子どもに相互監視をさせていると、子どもたちもストレスが溜まり、「いじめが起きやすい環境」になっていきます。良かれと思ってやっている生徒指導が、いじめを誘発してしまうんですね。子どもの自己肯定感を低下させ、自分なんていなくてもいい存在なんだと思わせたり、「自分はちゃんとルールを守っているのに、あいつが守っていないから先生が怒る。あいつが悪いんだ」という、他者に対して攻撃的な感情を抱いてしまったりする。不寛容な規則による管理は、そうした感情を正当化させてしまいます。「だってルールを守っていないのはあいつの方なんだから。あいつのせいでみんな迷惑しているんだ。自分があいつを責めるのは正しいことなんだ」と。そうした環境を大人が用意してしまっているというのは、大きな問題だと思います。

生き方が現れていないと、死を照らし出せない
―大貫さんは「指導死」の起きてしまった学校で、第三者調査委員会としても多くの事案に関わってこられましたが、そこで作成される調査報告書とはどのようなものなのでしょうか?
「指導死」の真相を追求したいというご遺族の思いは、実は中々周囲の理解を得られないんです。「何を騒いでいるの」と他の保護者の方々に煙たがられたり、悪質なケースでは、学校側がそうしたご遺族を孤立させようとしたりすることもあります。ある事案では、追い込まれて自殺してしまった生徒に対し、学校側がPTAを通じ、「あの子はドラッグをやっていた」と、根も葉もない噂を故意に流していたことがわかっています。他にも、ご遺族に訴訟の意志があるかどうかを、学校側がPTA会長に「さりげなく調べて来てくれ」と、スパイのように使うということもありました。
ご遺族がスーパーで買い物をしていると、やれ「刺身を買った」、「オードブルセットを買った」、「お酒を買っているところを見た」だの、そうした様子が伝わり非難されることがあるんですね。「笑っていた」、ということまで言われます。まるで「被害者なら笑わないはずだ」という、偏見に満ちた言説が飛び交います。そのため、地元のスーパーでは買い物できず、隣町まで行くという話は何人もの方から聞いてきました。
なるべく穏便に済ませたい学校側と、真相を解明したいご遺族。その両者だけでは見えて来ない部分を調査するために組織されるのが、第三者調査委員会です。そこで作られる報告書は、遺族が事実を知りたいと思う気持ちに応えるとともに、学校関係者や教育委員会が真摯にその事案と向き合い、同じようなことを二度と発生させないための資料となるものです。ところが、そうした報告書を活用する仕組みはまだ十分とは言えず、ごく限定的に公開されるだけであったり、全く公開されないものもあります。もちろん、ご遺族の意向は最大限配慮されるべきですが、非常に重篤な被害を受けた子どもたちの代償として生まれた報告書なので、可能な限り広い範囲で公開をし、研究者に限らず、多くの人々がそこから様々な学びを得られることを願っています。また、第三者調査委員会そのものが、学校側の認識の追認のために組織されたものだったり、客観的・中立的なものではない場合もあるため、注意が必要です。
私が調査に関わった、2015年に奄美市で起きた中学生自死事案の調査報告書は、100ページを超えました。生徒指導を背景とした「指導死」と認定したうえで、再発防止策の提言も行い、そこに以下のような文言を入れてもらいました。
“本報告書は、Aさんという一人の人間の、生まれて、生きて、自殺へと追い込まれ生涯を終えた、命の記録である。” (調査報告書P104)
調査報告書[公表版] (奄美市ホームページ)https://www.city.amami.lg.jp/somu/daisansyaiinkai3.html
※この[公表版]は、遺族の意向を踏まえた上で、個人情報等の人権的配慮を行い作成されたものです。
こうした言葉が必要だと思ったんですね。単に誰が悪い、この仕組みが悪い、この教員が悪いと言っていても、「命」は見えない。こういう生き方をしていた子どもが、こういう言葉や行為で、命を絶たれたのだと。その子がどんな音楽を聴いて、どんな漫画を読んで、どんな価値観を持った人間だったのか。幸い、その調査委員会のメンバーは、「おかしいよね、こんなことで子どもが命を失うなんて」と、同じ意識を共有できる方々だったので、作文や手紙、友人からの寄せ書きなども丹念に集められました。生き方が現れていないと、死を照らし出せないんですよ。死んだこと、命を失ったことの重大さを。この報告書をお読みくださったご遺族から、「ここに自分たちの子どもが生きている」と言って頂けたことは、僕にとっても大切な経験でした。

「自分がうつになる」というイメージがなかった
―ここからは少し大貫さんご自身の悲嘆との向き合い方についてお伺いしたいのですが、はじめて陵平さんの訃報を聞いたときのことから、お話頂けますでしょうか?
当時僕は離婚をしていて、陵平と兄、彼らの母親とは別なところに住んでいたんですね。ある日母親から連絡があり、「陵平が死んじゃった」と。「何を言ってるんだ、冗談にもほどがあるだろう」と一瞬思ったのですが、声が本気だったんですね。すぐに病院に駆け付けると、診察台のようなものの上に陵平が横たわっていました。部屋の外には警察が待機していて、僕は陵平が病死したものだとばかり思っていたので訝しがっていたら、「自殺で亡くなりました」と。それを聴いた途端、崩れ落ちました。立っていられなかったんですね。
その後様々な背景がわかっていくことになります。中でも許せなかったのが学校側の態度でした。「全校集会を開いて、子どもたちに命の大切さを伝えたい」と言われたときに、「陵平は命を大切にしなかったのか?」と思いました。どんなことを話すのか、内容を聞いてからでないと判断できないので、「どんな内容を話すのでしょうか?」と聞いても、何も準備してきていない。その翌々日、「お父さん、お母さんが何を伝えたいのか教えてください。そのことを伝えますから」とやってきたので、「いや、そんな簡単に伝えられるものじゃないよ、私たちの気持ちは!」と思い、直接学校に行かせてもらうことにしました。その方がよっぽど自分たちの気持ちを伝えられるからと。
それで、実際に全校集会で話をして、壇上から下りたところで担任の先生が駆けてきて、「陵平くんは学校やクラスで何かあったのでしょうか?」と。さすがにその時は我慢できず、大きな声で「それを知りたいのは私だ!」と叫んでしまいました。校長は2年生(陵平さんの学年)の先生方から事案に関して聞き取り調査としたと言っていたのですが、その後全く何の調べもしていなかったことがわかったんです。その場、その場で取り繕うだけで、真剣に真相を解明しようとは思っていない。流石にこれでは埒が明かないと思い、市教育委員会に、学校側との話し合いの場をオブザーブしてもらうようお願いしました。その後月1回ぐらいのペースで3回そうした場を持った後、学校側に、「もう全て説明しました。もうこうした場は持ちません」と言われてしまったんです。
ちょうどその頃、学校への訴訟を起こすかどうか、弁護士の元まで相談に行っていたんですね。でも、その裁判のためには陵平と一緒に指導を受けた他の生徒さんの聞き取り調査が前提として必要でした。元妻は「陵平の友達に負担をかけるわけにはいかない」と抵抗を感じており、結局裁判に踏み切ることは断念しました。そのタイミングで、「あ、これはもう打つ手がなくなったな」と、力尽きてしまったんです。僕の場合、その頃になって初めて、悲しみに襲われました。
―精根尽き果ててしまったということですが、ご自身のそうした状態に関しては自覚してらっしゃったのでしょうか?
その後は父が亡くなったり、仕事が忙しかったりと、とにかく慌ただしく生きていたのですが、さすがにメンタルが疲弊してきて、ある朝布団から出られなくなってしまったんですね。まあ、うつ病ですよね。でも当時の自分には、「自分がうつになる」というイメージがない。なんとかご飯を食べることぐらいはできていたのですが、起きられない、布団から出られない日々が続きました。「これから先、どうなってしまうのだろう」と漠然とした不安を抱えていました。
そんなときに、たまたま新聞の広告でうつ病の人に投与する薬のモニター募集というものがあり、その広告内に「うつ病チェックリスト」のようなものが記載されていたんですね。それをなんとなく見ていたら、全ての項目にあてはまる。「あ!そうだったんだ!」と思い、数日の内には病院へと行きました。そこで、これこれこういうわけでと、離婚したこと、子どもを亡くして、父親も最近亡くなったことを伝えたら、「それは無理もないですよ」と言ってもらえたんですね。その言葉に、とても安堵したことを覚えています。
そのように「受け止めてもらえた」ということが、立ち直れるキッカケだったのではないかと思います。運よく薬との相性も良く、心身のバランスも変わっていくことを実感しました。同様に、学校との話し合いに関しても、僕自身は「まだこれだけのことしかできていない」と焦っていたのですが、ある方に「そこまでできる人、中々いないですよ」と言って頂けて、「ちゃんと“やってた”と思ってくれる人もいるんだ」と、救われるような思いでした。やっぱり、ずっと何もできていなくて、陵平に合わせる顔が無いと思っていましたから。
―その後、「悲しみ」との向き合い方は変わっていったのでしょうか?
悲しみそのものが無くなることはないんですよね。よくこうした取材を受ける中で、「どのようにして悲しみを“克服”したのでしょうか?」と聞かれることがありますが、「克服してねえよ!」と言い返したくなるときがあります(笑)。ただ、向き合い方というか、付き合い方は少しずつ変わってきているんですね。僕ら遺族の間では「地雷原」と呼んでいるのですが、日常の様々な所に、辛い気持ちを思い出させる場所だったり、物事だったりがあるわけです。子どもと一緒に行った場所とか、遊んだ記憶とか。ある状態のときに、そうした場所に不用意に踏み込んでしまうと、また一気に初期の頃のような喪失感や苦しみに引き戻されてしまうのですが、少しずつそんな時の自分との付き合い方もわかってきて、そうしたことが無くなるわけではないんですけど、地雷を踏んでも、わりと早くそのような感情が薄れていくというか、そういう風には変わってきてますね。

うつになって学んだこと
―そのような体験は、大貫さんの「死生観」にも変化を及ぼしたのでしょうか?
「人はすぐ死ぬものだ」「簡単に死ぬものだ」ということを痛感しました。それから、いずれ自分も死ぬのだと言うことも。そうであるならば、自分は生きている間に何をしよう、ということも考えるようになりましたね。元々、世の中のことなんてまるで興味がなくて、ずっと演劇、芝居をやってきて、その道に行き詰って広告の会社に入り、「適当に面白ければいいや」という風に生きていたんですね。それが、陵平との死別をきっかけに、社会学の本なども興味を持って読むようになったり、本棚の中身はガラリと変わりました。
僕ね、宗教に関しては極めて懐疑的な人間なんですよ(笑)。でも、「信仰心」のようなものは僕の中にもやっぱりあって。しんどくてもう耐えられないようなときに…その、アニミズムに近いものなのかもしれませんが、「自分の樹」というのを勝手に近所で決めておくんです。その樹に、声には出さないですが、「今日も来たぞ」とか声をかけたり、挨拶をしながら自分を勇気づける、といった感覚はありますね。
―その後「指導死」親の会や、NPO法人ジェントルハートプロジェクト、一般社団法人ここから未来など、多くの遺族の方々と関わられたり、指導死問題解決のための活動をされています。「グリーフケア」という言葉は、まだまだ社会的認知度の低いものですが、大貫さんご自身は、そうした方々のお話を伺う際に気を付けてらっしゃることなどありますか?
元々僕はそんなに人と接するのも好きではないし…好きじゃないといっても嫌いなわけでもないのですが…たくさんの人に囲まれているより、孤独でいる時間こそ一番いい時間だと思っているタイプなんですね。でも、被害を受けていらっしゃるご家族やご遺族、当事者の方々との接触に関しては、自分でも不思議なぐらいパワーが出てくるんです。初めの頃は、「なんでこの人こんなに話長いんだろう」とか思うこともありましたが、「いや、違う。この人は“今”話したいから話してるんだ」と思い直して、話を途中で切り上げないようにしています。また、ありがちなパターンとして「相談に答えを出してしまう」というものがあり、ついつい口を出したくなってしまうのですが、「いやいや、今は“聴く時間”だ」と、自分の役割を冷静に考えるようになりました。
でも、そうやって“聴く”ということができるようになったのも、ここ5年ぐらいの話だと思います。子どもを失って、どうしたらいいんだろうと途方に暮れているご遺族に対して、一定程度何か情報を提供できたり、お役に立てるようになったのは、最近のことですね。少しずつ、「ああ、自分にできることがあるな」と。だから、自分が勉強しないと適切な情報を提供できないし、不適切な対応をしてしまうと、相談しにきてくれた人を逆に苦しめてしまう。そんなことを思うようになりました。そうした実感が、生きるエネルギーに繋がってきたのかもしれません。
―最後に、陳腐な質問になってしまうのですが、陵平くんが亡くなられて、うつで倒れていた時期の自分に、もし今の自分が声をかけられるとしたら、どういう言葉をかけますか?
そうだなあ…。言葉をかけるかどうかはわからないけれど、違う答えになってしまうかもしれませんが、「自分にとって、うつの体験はとても多くの学びがあった」とは言えるかもしれません。もう亡くなってしまったのですが、僕より若い同僚にこんなことを言われたことがあります。まだ僕がうつで苦しんでいる頃だったのですが、「思い知ったか!」と。「どんなにやりたいと思っても、それができない人っているんだ。そういう人の気持ちをおまえは今までわからなかっただろう!」って。なんて酷いことを言うんだろうとそのときは思いましたが(笑)。それは大きな学びでした。別にそれまでだって何もかもできていたわけではないのですが、やりたくてもできない、弱っている人の気持ち・立場というものが、自分なりによくわかったんですね。あのときメンタルが壊れそうになっていなければ、気づけないことだったかもしれません。

【プロフィール】
大貫 隆志(おおぬき・たかし)
一般社団法人ここから未来、代表理事。1957年栃木県生まれ。2000年、当時中学2年生だった次男、陵平(りょうへい)を自殺で失う。以後、講演や自殺遺族の支援を行う。コピーライター(フリーランス)。▶︎一般社団法人 ここから未来 https://cocomirai.org/
(2020.7/インタビュー・写真 佐藤慧,安田菜津紀)
(記事素材書き起こし協力 落葉えりか,西田朋世)
【支援・相談窓口/参照リンク】
▶︎ 全国自死遺族総合支援センター
身近な人を自死(自殺)で亡くした方のつどいに関する情報や、相談先が記載されています。▶︎ 自殺対策支援センターライフリンク
「生き心地の良い社会」の実現をめざし、自殺対策、「いのちへの支援」に取り組んでいるNPOです。○ 相談先リンク
▶︎ 電話相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)
▶︎ SNS相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)○ グリーフケアについてもっと知りたい方へ
▶︎ 上智大学グリーフケア研究所
▶︎ 一般社団法人The Egg Tree House
あわせて読みたい
■ 連載「悲しみと共に生きる」 (※記事は順次更新して参ります)
■ 連載『悲しみと共に生きる』 第1回:物語を組み立てなおす [2020.9.10/佐藤慧]
■ 兄へ もう、死ぬために働くのはやめよう [2020.5.25/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の声の中には、これからを生きていく中で必要な「知恵」や忘れてはならない「想い」がたくさん詰まっています。共感をうみ、次の世代へこの「受け取り」「伝える」枠組みを残していくために。皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。