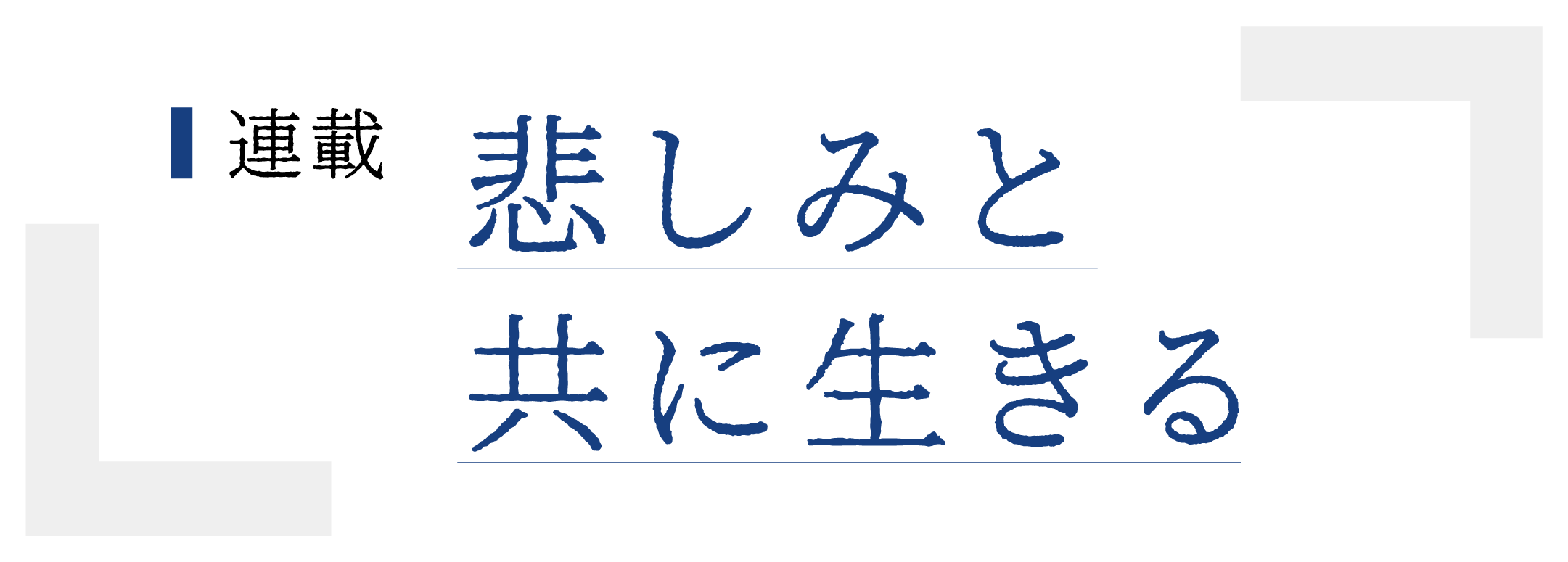本連載では、グリーフケアにまつわる人々へのインタビューを通し、喪失体験と共に生きる人々の姿をお伝えしていきます。第3回は、「一般社団法人 The Egg Tree House(エッグツリーハウス)」代表理事・公認心理師、臨床心理士の西尾温文さんにお話を伺います。西尾さんは1998年、当時5歳だった次女、百珠(ももみ)さんをがんで失いました。その後「遺族ケア」の必要性を感じ、51歳で臨床心理士の資格を取得、がん患者とその遺族の心のケアを始めました。現在は「たまごの家」を中心に、大切な人を亡くした子どもと大人のためのグリーフケアに取り組んでいます。
本文中には身近な人の死や、自死に関する記述がございます。そうした内容により、精神的なストレスを感じられる方がいらっしゃる可能性もありますので、ご無理のないようお願い致します。

悲嘆を抱えている人々の居場所を
―The Egg Tree Houseでは、様々なグリーフケアプログラムを開催されていますが、主な活動はどのようなものでしょうか?
The Egg Tree Houseを設立したのは2014年のことです。アメリカのポートランドに「ダギーセンター」という、子どものグリーフケアで世界的に有名な施設があるのですが、僕は2012年にそこの研修に参加しているんですね。是非そういった場所を日本にも作りたいと思い、The Egg Tree Houseを仲間たちと一緒に立ち上げました。ここでは家族や大切な人を亡くし、悲しみを抱えている子どもたちや若者、保護者らが、同じような経験をしている仲間と遊んだり、安心して語り合うことができる場所を提供しています。
ダギーセンター
ダギーセンターは1983年にアメリカ、オレゴン州ポートランドで大学病院小児科ナースをしていたベバリー・チャペル氏によって設立された、「大切な人を亡くした子どもとその家族のためのセンター」。名称は当時べバリー氏が担当していたダギー君という少年の名にちなむ。
The Dougy Center https://www.dougy.org/
最初は子どものグリーフに焦点をあてていたんですね。ところが蓋を開けてみると、子どもと一緒に保護者の方々も一緒にやってきます。なのでダギーセンターでもそうなんですけど、「子どものグループ」と「大人のグループ」に分けることにして、そうした集まりを「たまごの時間」と名付けました。
そこに今度は、そのどちらでもない、20代の若者がやってくるようになったんです。その時点では僕たちのプログラムには、子どもたちへのアートの時間とか公園で遊ぶとか、一緒に料理をするとか、そうしたものしかなかったんですね。そこで、若者には若者の居場所が必要なんじゃないかということで、そうした方々を対象にした「たまごカフェ」というグリーフカフェも開催することになりました。代田橋で行っている「たまごカフェ」は19歳以上どなたでも、小金井での「たまごカフェ」は19歳以上から、おおむね35歳までが対象です。

そうした場所に参加される方というのは、子どもやパートナー、伴侶を亡くされたという方が比較的多かったのですが、ある時から、自死遺族の方が訪ねて来るようになったんです。ところが自死遺族の方は、第一発見者が子どもであった場合を別として、自死だということを子どもに伝えてないことが多いんですね。僕らはそうした事実を「伝えなさい」とも言わないし、「伝えることが今後の課題」とも言いません。そうした方が、他の遺族の方と一緒にプログラムに参加する中で、例えば病気で死別された方は、「こういう闘病の末に・・・」とか、「突然大動脈破裂で亡くなりました」という話をするのですが、自死遺族の方は「突然死」というだけで、それ以上は説明されないわけです。もちろん、そうした方が「たまごカフェ」の場にいらっしゃることは構わないのですが、やっぱり自死遺族の方だけを対象にした時間を持った方がいいんじゃないかと、そのようなプログラムを「そっとたまご」と名付けて始めました。
その他にも、「生きづらさ」を抱える遺族を対象とした「ほっとたまご」、子どものグリーフケアに関心があり、ファシリテーターとしてThe Egg Tree Houseのプログラムに参加したい方向けの「ファシリテーター養成講座」も行っています。なんだか「たまごばっかりで分かりにくい」という意見も頂きますが(笑)。
The Egg Tree Houseの主な活動
http://eggtreehouse.org/program/index.html
子どもの抱えるグリーフ
―子どもの抱えるグリーフ(悲嘆)に特に焦点をあてて活動されているとのことですが、大人と比べて、子どものグリーフには何か特徴などあるのでしょうか?
グリーフケアキャンプというものを毎年行っているのですが、そこで子どもたちは2泊3日、保護者と別々に過ごすんですね。テントを張って、かまどを作って料理をしたり、自然の中で様々に遊んで過ごします。その2日目の夜にキャンドルトークの時間があり、蝋燭を灯しながら、静寂の中でそれぞれの悲嘆について話すんです。パスをしてもよくて、他の人々の話を聞くだけでも構わない。僕はその場にいなかったのですが、その時間の中で、ファシリテーターのひとりが他のファシリテーターに「(自身の死別体験を)みんなに話すの?」と聞いたんですね。するとその方は「自分は大事な人が亡くなったという話を、仲のいい友人にはできても、みんなにできるわけじゃない」と答えたんです。次に子どもたちに同じ質問をしたら、男の子のひとりが立ち上がって「学校でなんて、そんな話するわけないだろ!言ったってわかんねえじゃねえか!」と。つまり、「あの番組面白かったよね」とか、「〇〇食べておいしかった」とか、そういう話は子ども同士の日常会話の中で共有できるけれど、「きょうだいが亡くなった」「親が亡くなった」などという話は、学校や地域など、自分のコミュニティ内ではしてないことが多いんですね。高校生、大学生の参加者に聞いても、相手が自分の家族のことを知らないのであれば、あえてそうした話を自分からすることはない、という答えが多かったんです。そうした子は、たとえば恋人ができたり、就職したりというときに、家族のことを聞かれてどう答えるかといった壁に悩む場合もあります。
別な子の例ですが、その子の一番の悩みは「自分の父が病気で亡くなったということを親友に話せてない」ということだったんです。それがあるとき、「友達に言えた!」と報告してくれた。なぜ言えるようになったかというと、キャンプに参加している子どもたちはみな、「誰かを亡くしている」わけですよね。もちろん、パスをしてそうした自分の話をしない子もいるわけですが、中には言う子もいる。そうすると、「あれ?他の人も家族を亡くしていて、しかもその人はそれをスッと喋ることができている」と、そこから自分なりに何かを考えたり気づいたりするんじゃないかと思います。
子どもたちは、相手にそうした話をしたときに、相手が理解できないんじゃないか…あるいは自分も、そうした話をしたときに相手から返ってくる反応を、どう受け止めたらいいのかわからない。それならあえて言おうとは思わない。そういう傾向があるように思います。
また、たとえば親を亡くしたきょうだいがキャンプに参加して、上の子がその死別とうまく向き合うことができるようになったとしても、学齢前の下の子はそもそも記憶が曖昧で、「死別の話をする」という場所にいること自体に居心地の悪さを感じている場合もあります。同じ家族内の死別でも、それぞれ違った体験をしているんですね。

―そうしたグリーフを抱える人々に、周囲の人間ができること、気を付けた方がよいことなどありますでしょうか?
その方との関係性にもよりますが、友達やクラスメイトであれば、普段通りに、いつもと同じように関わってあげることが一番じゃないかなと思います。変に気を遣うと、「気を遣われている」ということが逆に苦しくなる場合もあります。もちろん、本人が「ちょっと聞いてよ」と声をかけてきた場合には、聞いてあげたらいいんじゃないかと思います。
あとは、時々詮索好きな方がいたりする場合がありますよね。「最近見ないけど〇〇さんどうしてるの?」とか、近所で噂をしたり。お子さんを亡くされたある親御さんの話ですが、その方は犬の散歩に行くにもマスクとサングラス、イヤホンで音楽を聴きながらじゃないと出られなかったと話していました。子どもを亡くしたことに触れられたくないし、顔も見られたくない。「元気になりました?」とか、そういう言葉も含めて声をかけられたくない。買い物に行くと誰かに会うかもしれないから、買い物にも行けない。死別から1年も経っていない方でしたが、そうした人の気持ちを慮ることも大切だと思います。
ただ、自分は人とは関わりたくないという方でも、「子どものために」とThe Egg Tree Houseのような場所を探していることがあります。子どもはどう、この悲嘆と向き合っていくのだろうかと、子どもの成長が心配になるんですね。どのようにしてこの記憶を整理していけるのだろうかと。悲しんでいるようには見えない、という心配も含めてですね。それで実際にプログラムに参加してみて、そこで大人同士の集まりもあったりして、少しずつご自身の悲嘆と向き合っていく方もいます。
たまごのある木
―西尾さんご自身、次女の百珠(ももみ)さんとの死別を経験していると伺いました。
三番目の子ども、次女の百珠(ももみ)は1992年生まれなのですが、1歳と5ヵ月のときに片目が腫れてきたんですね。でも何が原因かわからない。保育園に通っていたので、「ぶつけたの?転んだの?」って聞いていたんです。そうするうちに、もう一方の目も腫れてきて、近所の眼科に行ってもよくわからなかったのですが、知り合いの小児科医に見せたら、お腹を触診して、「ちょっと大きな病気かもしれないから、大きな病院に連れていきなさい」と。そこで採血をして検査をしたら、最終的に神経芽細胞腫だと言われた。要するにがんですよね。その病院から紹介された小児専門病院の主治医は、変に希望を持たせたり、不確かなことをいう先生じゃなかったので、今でも覚えてるんですが、「家には帰れるようになる」っておっしゃったんですね。先生の言う通り、お兄ちゃんの骨髄を移植して、8か月で退院、無事にももちゃん(百珠さん)は家に帰ってくることができたんです。
当時僕は塾を経営していたんですけど、病気の子どもを看ていくためには、なるべく家のそばで仕事をした方がいいだろうということで、家の隣に塾の分校をつくって、そこで働き始めたんですね。退院してしばらくの間はももちゃんも元気で、また保育園に通い始めて、一緒に遊んだり、旅行にも行ったりと、どんどん活動範囲が広がっていく。大きな病気を患わっていたなんて、忘れていくような時期でした。今思えば、そのときすでに病気が再発していたのだと思いますが、それに親は気づかない。ちょっと体調を崩していても、「あれ?インフルエンザかな?」とか。お腹が膨れて、ちょっと歩きにくそうにしてても、「なんでちゃんと歩かないの?」と言ってたぐらいです。でもやっぱり何かおかしいなということで再度病院に言ったら、「あと一か月かもしれません」と、再発を知らされたんですね。ここからはもう、病気に圧倒されていくような毎日でした。
一回目の入院のときは、ももちゃんが元気になるという希望を持っていたんですね。ところが今回は、様々な治療法を提案されても、ことごとく病気の勢いがそれを上回って行ったんです。「もう一度骨髄移植をしましょう」ということで検査をしてみると、腎臓が片方機能していないことがわかり、手術はできないと。それならということで、放射線をあてて腫瘍を取り除きましょう、大元の腫瘍を引き剥がしましょうということになっても、うまくいかない。そのうち腸も癒着してしまって・・・。新たな治療の提案に希望を感じては、それが砕かれていくという日々でした。
そんな入院中のある日、ももちゃんがこんな絵を描いたんです。

「この絵はね・・・」って、説明してくれた。「あのね、イエローはたまごでね、グリーンは木なんだよ。オレンジはたまごを大事にするカーテンなんだ」と。ももちゃん、がん性腹膜炎でお腹が膨れてたので、お腹をさすりながら「もうすぐ赤ちゃん産まれるかも」と言っていたんですね。それがこの「たまご」というイメージになったのかもしれません。ももちゃんの病室のカーテンはオレンジ色で、窓を開けると外には緑の自然が広がっていた。ももちゃんなりの、自分の命というものを支えてくれる周囲への感謝とか、命の希望を描いたものなのかもしれない。
その後病状が悪化して、いよいよ希望を持てなくなっていく。まだ本人が目の前にいるので、絶望というとまたちょっと違う感じなのですが、「もうお別れなんだな」「諦めなきゃいけないんだ」と、自分の居場所がないような、どこに行っても落ち着かない気持ちでした。お医者さんは、「もうこの子は亡くなりますよ」と伝えてくれているわけじゃないですか。それを何とか理解しようとする。対処しようとしますよね。でも人って、亡くなっても遺体が目の前に存在するじゃないですか。ももちゃんが亡くなって僕が一番辛かったのは、火葬場なんですね。子どもの体が無くなる、骨になるっていうのは、頭では理解してますよ。でも、実際に焼かれる、骨になってしまう。それはもう、僕は身のよじれるような感じだった。
悲しみの通奏低音
―その後どのように自身のグリーフと向き合い、グリーフケアへと繋がっていったのでしょうか?
ももちゃんが元気だったときは親子5人家族だったんです。妻にとっては子ども、子どもたちにとっては妹が亡くなった。それをそれぞれがどう感じているかとか、どの様に悲しさを抱いているかなんてことを想像する余裕は、まったくありませんでした。自分のことで精いっぱい。決まっていることは何とかこなせたので、淡々と仕事をこなしていく。当時塾で教えていて、元気いっぱいの子どもたちといると、自分も元気にしてなきゃと思うわけですよね。でもその時間が過ぎると、元気ではいられない。なんでこんなことしてるのかなあ、とか。辛いのに無理してるなあって、そんな思いでした。
その後塾の経営が傾き、ちょうど臨床心理士の資格が国家資格になるというブームがあり、元々勉強も好きだったので、子どもの心理領域に関わる仕事が何かできないかなと、塾を閉じる準備を進めながら資格をとったんですね。資格取得後、スクールカウンセラーを何年か経験したあと、都内の大学病院で、がん患者とその家族、子どもたちに関わる緩和ケアチームの一員として働き始めました。僕は病院で働くにあたって、週に1度は小児病棟に行かせてほしいという条件を出していたんですね。自分自身の経験もあり、闘病中に親はどんなことを心配に思っているか、わかる部分があったんです。その仕事を通じて、2011年にある女の子と出会いました。その子との出会いによって、僕は初めてグリーフケアというものを意識するようになったんですね。
その女の子とは、呼吸器内科の病棟で会いました。お母さんが肺がんで亡くなり、お母さんが亡くなるのに間に合わず、家族が医師に別室で死亡の経過説明を受けている時に、お母さんが横たわるベッドサイドにひとり立っていたんです。それから月に1回はその女の子と面談させてもらうようになりました。7ヵ月目くらいかな、その子が、「お母さんは天国で神様になる勉強をしている」と言ったんです。それで僕は「ああ、ちゃんと亡くなった人の居場所ができたんだな」と。想像上ではありますが、時々お母さんとお話できてるのかなと思い、それでもう、この子のグリーフケアは終わりだなと感じました。
その時に気づいたことがあるんです。病院は様々な診療科がありますが、「遺族に対する窓口」というものを持っていない。たとえば、遺族の方で「眠れない」という方がいたら、メンタルクリニックに行く。つまり「個人的苦悩」として扱われてしまい、家族や大切な人との死別という、「悲嘆との向き合い方」という視点にはならない。ましてや、家族を亡くした子どもをケアする窓口なんて存在しない。現在の日本でも、そうした窓口を備えている病院は数えるほどです。
その後ダギーセンターに研修に行き、日本にもそういう場所を作りたいと思い、仲間と一緒に設立準備を進めました。そこで名前をどうするかと考えているときに、「他のグリーフケアの団体と違って、西尾さんは自分自身が子どもを亡くしているでしょ。ももちゃんの描いた“たまごのある木”、あれを名前にしたらいいんじゃない?」と言われ、The Egg Tree Houseが始まりました。

そのようにしてグリーフケアの場を開催するようになると、子どもを亡くした親も、ある程度の比率で参加しているわけですよ。先ほどもお話しましたが、キャンプにいくとキャンドルトークという時間があるんですね。そこで参加者がひとりひとり、自身の悲嘆について言葉にしていく。僕はファシリテーターなので、みなさんが話すのを聴いている立場なわけですが、あるとき自分自身の中から、感情がぶわー!っと噴き出してきて、制御が効かない状態になったことがありました。僕は自分の死別体験というのは、もう随分と昔のことだとどこかで思っていたんですね。その後仕事にも励み、小児がんで亡くなる子を見送ったり、遺族の話も聞いたりしながら、「僕自身の感情」というものはずっと表には出してこなかった。それがそのキャンドルトークのときに、同じ境遇、似たような想い、そうした人の感情が順番にぶわー!っと出てくると、自分も参加者のひとりのように、普段では気づかない悲嘆感情というものが浮かび上がってきたんですね。ももちゃんが焼かれて、骨になってしまう・・・あのときの、体がよじれるような感覚を思い出した。
後にある時友人がこんなことを言ったんです。その方は音楽の好きな人だったんですが、「西尾さん、音楽ってね、耳に聞こえる音だけじゃなくて、聞こえない音もあるんだよ。西尾さんにとって、子どもを亡くした経験というのは、音楽に例えると通奏低音。普段の西尾さんには聞こえてない音がずっと流れてるってことなんじゃないのかなあ」って。
僕が認識しているかどうかは別として、その悲しみって消えるわけじゃなくて、ずっと流れているものなんじゃないのっていうことですよね。それを聞いて「なるほどなあ」と思った。The Egg Tree Houseの参加者の方には申し訳ないのですが、この場所というのは、僕自身が悲嘆感情を表す場所でもあったんだなと、その時思いました。

あるがままでいられる居場所
―西尾さんはグリーフケアに「野口体操」という、故・野口三千三氏の体操を用いてますが、それはどのような思いからなのでしょうか?
野口三千三(のぐち・みちぞう)
1914‐98年。群馬県生まれ。群馬師範学校・東京体育専門学校助教授を経て、東京芸術大学教授、のち名誉教授。野口体操教室を長年にわたり主宰。主著『原初生命体としての人間―野口体操の理論』(岩波現代文庫)では、身体的思考にもとづく独創的な人間論、運動・感覚・言葉論を展開する。トラウマと身体の関係については、べッセル・ヴァン・デア・コーク氏の『身体はトラウマを記録する――脳・心・体のつながりと回復のための手法』(紀伊國屋書店)などにより現代でも深く研究されている。
野口体操そのものは、実際に野口三千三先生に10年間師事していたこともあり、昔から知っていました。野口先生はももちゃんと同じ年に亡くなったのですが、その教えというのは非常に強く僕の中に残っているんですね。野口先生が凄いなあと思ったのは、「一番大事なのは個の自由だよ」と言い続けていたことなんです。「僕は本気で、体操による人間革命を考えてるんだ。動きから変えるんだ」って。もうね、痺れたね。個の自由って…決して「好き勝手やる」ということではなく、あるがままである。それを認め合う。徹底して自分を大事にする。自分を大事にする人しか、人を大事にできないんだよって。「そうだよなぁ~」と思うんですよ。だって他の人は、自分じゃない「自分」を持ってるわけですから。自分を大事にしていれば、その人の「自分」というのも尊重できるだろうって言うんです。深く考えるということの意味を教えてくれたと思うんですよね。
体操を教えるといっても、唯一無二の正解があるわけではないんです。教義があったり、偉い人がいて、その人に従ってこうするとか、そういうものじゃない。「それぞれでいいんだよ」と。だから、障害をもっている人も病人も、自分らしい動きってあるだろう?それでいいんだよっていうのが野口先生の体操なんです。それがなんか、僕にはすごい救いだった。
先生の遺した言葉で、「感覚こそ力である」というものがあるのですが、それは「自分の感覚が第一で、他の人も同じように感じている」ということではないんですね。「あなたが感じていることから始めるしかない」ということなんです。それは孤独な作業かもしれません。僕が感じている悲しさとか、意味とか、それはやっぱり僕個人のものでしかない。家族とか、非常に身近な人とですら、共有できているかというとそうではないかもしれない。家族が寝静まっている中ふと夜に目覚めて、ももちゃんがいないという現実が急に襲ってきて、いたたまれなくなるときが何度かあったのですが、それは僕自身の悲しみなんですね。でもそれは単にネガティブなものかというとそうではなくて、僕にとってはとても大事な、大切なものを感じているときだと思うんです。
グリーフケアキャンプに行くじゃないですか。そうすると、蝶々が飛んでくるんですね。野口先生は、「人間も地球物質じゃないか」って言うわけです。中々僕は「岩石も自分と一緒だ」とまで思えているわけではないんですけど、「繋がってるよなあ!」という感覚はあるわけです。それで、その蝶々を僕はももちゃんだと思ってて、「ああ、今年も来てくれたねえ」って。だから子どもがキャンプで蝶々つかまえると苦しいんですよ。それ、僕の子どもだから!とは言えないけど…(笑)。「早く逃がしてあげようよ~」と(笑)。「ああ、これって、僕の感覚だよなあ」って思うんですよね。自分の内面でその蝶々に話しかけるんです。そういう感覚を持っているのは確か。それを誰かに「あなたもそう感じなさい!」なんて言うつもりはないけど、「それでいいんだ」っていうのが野口先生の教えですね。正解があって評価するのではなく、「君はそれで気持ちいいのかい?」ということを、問い続けていたのだと思います。
だから「たまごの時間」とか、The Egg Tree Houseでの活動も、その子自身が自分に素直になって人に話せる、安心して過ごせる時間になって欲しい。「自分の家族はこうで、相手はこうで、お前の悲嘆はこうで…」とかっていう、比較しようっていう話じゃないんだから。

―西尾さんにとってグリーフケアとは?
昔僕が幼い頃、田舎の祖父の葬儀に参加したことがあるのですが、村ぐるみで葬儀を行うわけですよね。それはそれで煩わしいこともたくさんあったのだと思いますが、そうした人との近さ、コミュニティの関係性というのは、その時代におけるグリーフケアを担っていたと思うんです。今は環境も関係も当時とは違うので、単純に比較できるものではないと思うのですが、なんというか…人生における重大な悲嘆感情を「個人で」引き受けられるかというと、そうではない。やっぱり見守ってくれる誰かというのが必要だと思うんですよね。それは本来、お寺とか教会とか、地域独自のコミュニティが担っていたものかもしれませんが、そうしたものが希薄な現代に、ダギーセンターのような、死別を経験した人が安心して集まれる場所って必要なんじゃないかなあと思うんです。なので僕にとってのグリーフケアとは、「場所」なんじゃないかな。ここに来ると、人がいて、話を聞いてくれるというか。言語化する機会があって、時間がかかってもいいから、ずっと待ってくれるというか。The Egg Tree Houseもそうした場所であってほしいなと思います。
【プロフィール】
西尾 温文(にしお・あつふみ)
1977年丹誠塾設立、経営。2001年よりNPO 法人遊学会理事長、2007 年より順天堂医院がん治療センター心理士、2011年立教大学大学院現代心理学研究科博士課程単位取得退学。2012年3月ダギーセンター(米国オレゴン州)で研修、2012 年Kids Hurt Too(ハワイ)で3ヶ月間研修。2013年7月International Summer Institute(ダギーセンター)で研修。※2021年6月、西尾温文さんがご逝去されました。優しく温かな言葉をお預かりできたことに感謝申し上げるとともに、氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
(2020.10/インタビュー・写真 佐藤慧)
(記事素材書き起こし協力 西田朋世)
【支援・相談窓口/参照リンク】
▶︎ 全国自死遺族総合支援センター
身近な人を自死(自殺)で亡くした方のつどいに関する情報や、相談先が記載されています。▶︎ 自殺対策支援センターライフリンク
「生き心地の良い社会」の実現をめざし、自殺対策、「いのちへの支援」に取り組んでいるNPOです。○ 相談先リンク
▶︎ 電話相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)
▶︎ SNS相談等を行っている団体一覧(厚生労働省HP)○ グリーフケアについてもっと知りたい方へ
▶︎ 上智大学グリーフケア研究所
▶︎ 一般社団法人The Egg Tree House
あわせて読みたい
■ 連載「悲しみと共に生きる」 (※記事は順次更新して参ります)
■ 連載『悲しみと共に生きる』 第2回:死を照らし出すために(大貫隆志さん) [2020.9.26/佐藤慧,安田菜津紀]
■ 兄へ もう、死ぬために働くのはやめよう [2020.5.25/安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。