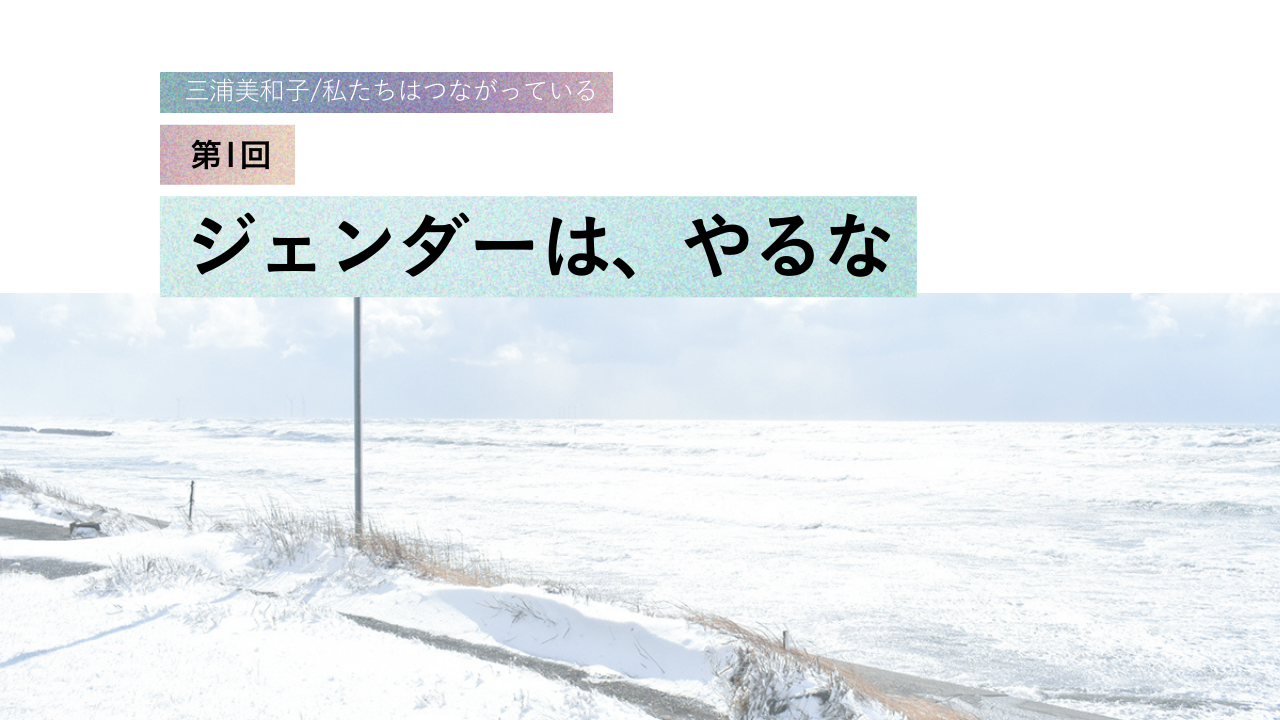被害者に沈黙を強いる社会のアップデートを―伊藤詩織さん意見陳述全文(9月21日 東京高裁)
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBSワシントン支局長の山口敬之氏による性暴力被害を受けたとして、損害賠償を求めて起こした民事訴訟の控訴審が、9月21日、東京高裁で開かれました。そこで行われた伊藤さんの意見陳述全文を掲載します。

控訴審を終えるにあたり、以下のように陳述させていただきます。
事件が起きてから、6年が過ぎました。この裁判を始めてからは約4年が経ちます。
2015年、事件当時の私は、必死でバイトで貯めたお金で海外の学校に通い、ずっと夢を見ていたジャーナリストの仕事がスタートし、毎日ワクワクしながら仕事に出かけていた25歳でした。当時はその後の20代を裁判に費やすとは想像もしていませんでした。
事件と向き合う中で、自分の身に起こったことを、司法や社会がどう判断するのかを目の当たりにしてきました。精神的に痛めつけられ、攻撃されることの繰り返しでした。しかし「真実と向き合った」という事実は私の人生でとても大切なことだったのだと思います。
この4年間、裁判で訴えたかったことは、そう多くはありません。まず、私の身に起きた出来事に対して、司法の適切な判断が下されることでした。そしてもうひとつ、判決を通じて、私が経験したような、性被害、および被害者バッシングという二次加害が、決して許されないものなのだというメッセージが広がることで、新たに被害者が泣き寝入りしなくてよい社会になることです。
私は警察に届け出た段階で、刑事司法で裁いてもらうことを望んでいましたが、逮捕は直前で取り消しとなり、それはかないませんでした。刑事司法の不透明な対応に左右され、確かに存在していた性被害が、なかったことにされてしまうことに危機感を抱き、自分の顔を出し、そして名前を出して発信することを決意しました。
「売名」「被害者ビジネス」「ハニートラップ」……。名乗り出てから、本当にさまざまな言葉が投げかけられました。刑事司法が適切に対応してくれていれば、私が被害者であることを、公に名乗り出る必要はありませんでした。また、名乗り出ることで傷つくことや失うことがあることも想像できたので、本当に悩みました。それでもこうして名乗り出たのは、被害を否定してはいけないと思ったためです。
私は山口氏(以下、控訴人)に性暴力を受けてから、PTSD によるフラッシュバック、うつ状態を経験し、何度も死を考えました。街を歩くことにさえも恐怖を抱くようになり、一時期は日本を離れました。さまざまな誹謗中傷に触れたことで、現在でも自分でネットを閲覧することが難しい状態が続いており、仕事で必要なネットでの対応は、第三者にすべてお願いしています。
裁判の過程は、とても苦しいものでした。被害と向き合い続けたことや、ネットなどでの二次加害だけが理由ではありません。裁判の内外で、控訴人側が正当な反論を超えた中傷、そして二次加害の扇動を行い続けたためです。
控訴人の第一審担当の北口弁護士は、ブログや記者会見で繰り返し、「妄想」「虚構」「虚偽」など私を嘘つき扱いし、病人扱いしてきました。北口弁護士は懲戒処分になりましたが、私は裁判自体に向き合う恐怖を深めました。
今回の控訴審で控訴人側は、いかに私が信用のおけない人物であるかを示すことにエネルギーを費やしました。例えば私が事件当時住んでいた住居は、当時の私の収入では払えないはず、そしてそのマンションのオーナーは実は愛人をたくさん囲っていた、とあたかも私がオーナーに部屋を貸してもらう等の親しい間柄にあったような印象を与えるための無根拠な主張を重ねました。実際は、マンションの部屋をシェアハウスに改造したものであり、全く高額な家賃でなく、自分で働いたお金で支払っていたのにも関わらず。
他にも私の身の回りを詮索され、邪推され、事実ではないことを発信され続けました。
また、この控訴審で、「真の性被害者」という言葉が、控訴人側の主張として繰り返し使われました。これは、被害者のステレオタイプを一方的に作り出し、そのイメージとズレているから、あの人は偽の告発者・性被害者なのだ、とする主張です。
第一審の判決直後、控訴人側が開いた記者会見で控訴人は「『被害者は、あのような笑い方はしない』と性被害を受けた女性からきいた」という主張を行いました。控訴人は「引用である」と釈明しましたが、これも典型的なステレオタイプだと思います。この件にとどまらず、今回の裁判の中で、性被害者や女性全般に対するステレオタイプ的な見方が繰り返し持ち出され続けました。
例えば、私が早くその場を去りたかったために、シャワーを浴びずに朝5時にホテルを出たことについて、控訴人はこう主張しました。「偶発的な経過から初めて性交に至ったにすぎない相手の男性が宿泊するホテルの居室で、当該相手の男性も使用しているであろうバスルームのシャワーを共有することなど、女性の心理として性交の合意があろうがなかろうが抵抗感、不潔感、羞恥心といった、ないし消極的な感情を覚えるほうが当然といえる(※筆者注:なので、性被害にあった故の行動とはいえない)」などという主張をしました。もちろん、そのような「女性の心理」が、この社会に存在している根拠は示されていません。
また、ホテルから出る際に、私の髪型が前夜と違って結ばれていたことについても、「心理的な余裕が明確にあったからできた」はずだとも主張しました。性被害にあった人であっても被害にあったことを周囲にわからないように行動をとる、ということもあるかと思います。何ごともなかったかのように。
冷静に振舞おうとする被害者が多くいることを説明してもなお、「本当の被害者なら他の行動をとるだろう」という勝手な論理にすがり続け、私を非難し続けました。こうした文面がふんだんに記された準備書面や書証などの攻撃的な資料が届くたび、また新たな加害が行われているように感じ、苦痛の日々を過ごしてきました。
事件直後、被害届を出そうとした私に対し、捜査員が「君の人生が水の泡になってしまうからやめなさい」と言いました。どんな事件でも、「被害者側に沈黙させる方が、被害者のために良いのだ」とされてしまう社会の仕組みの下では、これからも誰かを長期間苦しめてしまうでしょう。被害者が司法できちんと守られること、そしてこれ以上「真の被害者」という勝手なステレオタイプによって、誰かを貶めるような出来事がおきないことを願ってます。
この控訴審は新型コロナウイルスの影響により期日が延期されました。そのような大変な時期にもかかわらず、ここまで丁寧に審理していただき、本当にありがとうございました。
こうした伊藤さんの意見陳述に対し山口氏は「本人が記憶がないと言っていることに対して、第三者がその主張を覆すのは非常に難しい。けれど記憶をなくす前後についての伊藤さんの証言にはたくさんの嘘や矛盾がある」と陳述を行いました。
裁判はこの日で結審となり、判決は2022年1月25日に言い渡される見通しです。
その後の報道陣による取材の中で伊藤さんは、個人の尊厳の問題に留まらず、社会の構造的な欠陥、そしてそのアップデートの必要性について語りました。不透明な刑事司法、被害者に対するステレオタイプ、ネット上で拡散されていく誹謗中傷、被害者に沈黙を強いる社会構造……。
この社会は何を「正しい」とする価値観に向かっていくのか――そこに唯一無二の答えはありません。けれど、沈黙を強いられてきた側の声に耳を傾けることこそが、一人ひとりの尊厳を土台とする社会を築いていくために、何よりも欠かせないことなのではないでしょうか。

(2021.9.22/写真・文 佐藤慧)
あわせて読みたい
■ 【インタビュー】性被害報道、記者は何を心がけるべきなのか?「性暴力被害取材のためのガイドブック」から考える[2021.3.30/佐藤慧・安田菜津紀]
■ ”誰もがメディアである”時代、荻上チキさんと学ぶ「メディア論」[2020.10.7/佐藤慧]
■【取材レポート】伊藤詩織さんの意見陳述全文「同じ被害に苦しんでいる多くの人たちのために、この裁判を始めました」[2020.11.17/安田菜津紀]
■ 【取材レポート】伊藤詩織さんの記者会見からネット上での誹謗中傷について考える ―言葉を凶器にしないための「Rethink」を―[2020.6.10/佐藤慧・安田菜津紀]
Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。